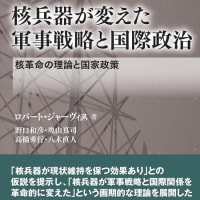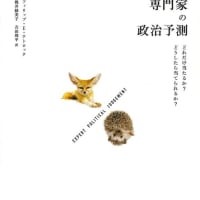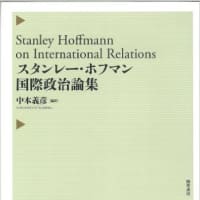私が専門とする政治学/国際関係論の学界では、猪口孝氏は、まさに「知の巨人」です。猪口氏は、これまで数え切れないほどの著作や論文など日本語のみならず英語や各国語で発表しており、私にとっては雲の上の存在です。
『実証政治学構築への道』は、その猪口氏が、御自身の来歴と学問を振り返った「自叙伝」です。同じ学問分野を専攻する私としては、猪口氏がかくも膨大な業績をどうやって作ってきたのか、かねてからたいへん興味がありました。ですので、本書は一気に読んでしまいました。
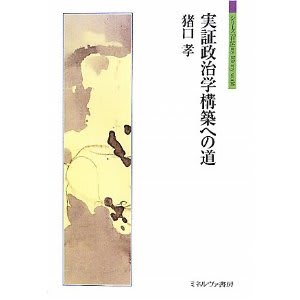
同書には、刺激に満ちた様々な記述があるのですが、その中でも、私が興味深く感じた部分を独断的にピックアップしたいと思います。
「私をその後も悩まし続けるジレンマ…つまり、英語でいいところに刊行できないと日本語の刊行が増え続け、日本列島のなかでだけ回り続ける。英語でいいところに刊行しようとし始めると、だいたいすぐには刊行できず、改定や拒否が続きやすい。同じ論文の原稿を二年も三年も弄り続けることになりかねない」(30ページ)。
こんなのは朝飯前のごとく、画期的で厖大な研究論文や学術図書を英語で量産している猪口氏でさえ、このようなジレンマに悩まれていたことを知って、少し驚いた次第です。
「日本社会では学術研究で文科系と理科系を分け、血液型と関連させたりする愚かな考えもあるが、実証主義でいく限り、文科も理科もない。すべて真実を究明することを目的としている。…それが元気良く恒常的になされる仕組みのない社会では、怪しげな迷信や偏見が幅をきかせたりする」(62-63ページ)。
まったくその通りです!文学などの人文学系は別として、日本における文系・理系という学問の分け方は、私も常におかしいと思っていました。社会科学であれ自然科学であれ、科学は科学であるはずです。にもかかわらず、こうした当たり前の考えは、日本では非常に弱く、科学=理科系という等式が一般的な通念となっているようです。そうであれば、社会科学とは、一体、何なのでしょうか?
私が奉職している国際学科は、「国際学」を専門に掲げる研究教育組織であり、「国際学」は社会科学に分類されると言ってよいでしょう。ところが、国際学科に入学してくる学生のほぼ全員が、「国際学」は社会科学であるという認識を全く持っていません。国際学=国際問題の「時事評論」だと勘違いしているのです。もっとも、若い学生たちが、そう勘違いするのも仕方ないかもしれません。なぜなら、日本社会において、文系は科学ではないといった観念が幅を利かしているのですから…。
「国家の違いを超えて説明できるような理論的枠組は、ほとんど米国にしか生まれなかった。…米国以外で国際政治学をやろうとすると、非米国の様式を意識せざるを得ないが、母国で評価されても様式の違う米国ではあまり流布しない。逆も逆で米国流でやっても母国では評価されにくい。そこで私のアドバイスは両方を身につけることである。具体的には、分析的な実証主義的な方法を身につけることと歴史地域的な経路依存的説明も身につけることである」(142ページ)。
これは非常に重要な方法論上の指摘だと思います。未熟ながらも、私も同じようなことを考えながら、拙著『パワー・シフトと戦争』を執筆しました。もちろん、上記の両方の方法を身につけるまでには至っていませんが、理論と歴史・地域の両方を意識して研究したことは確かです。
最後に、以下を引用して締めくくります。
「私は…シラバスの充実や講義方法の改善などを図った。だが、その帰結は学生が極端に少なくなることだった」(151ページ)。
笑うに笑えない話です。同じような経験をした大学教員も多いのではないでしょうか?私もその一人です。私は、いくつかの大学で「国際政治学」に類する科目を長年にわたり担当しています。「グローバル・スタンダードの国際政治学」の授業をしようと意気込んで、同科目の授業を組み立てる際、国際政治学で高い評価を受けている、北米の著名な大学の「スター教授」のシラバスを入手して、それを真似た授業を行ったこともありましたが、結果は、受講生の激減でした(苦笑)。もっとも、その最大の原因は、「平凡教授」の私が、愚かにも「スター教授」をまねたことにあったのでしょう。くわえて、読書課題やレポート・論文などの課題の出し方にも問題があったと反省しています。
本書『実証政治学構築への道』は、「執筆を職業、趣味、習慣の三位一体としている」猪口氏の知的バイタリティとタフネスが表れ、学問上のエピソードがちりばめられた、とりわけ政治学徒にとっては、刺激的な自伝だと思います。
『実証政治学構築への道』は、その猪口氏が、御自身の来歴と学問を振り返った「自叙伝」です。同じ学問分野を専攻する私としては、猪口氏がかくも膨大な業績をどうやって作ってきたのか、かねてからたいへん興味がありました。ですので、本書は一気に読んでしまいました。
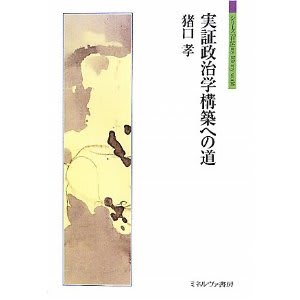
同書には、刺激に満ちた様々な記述があるのですが、その中でも、私が興味深く感じた部分を独断的にピックアップしたいと思います。
「私をその後も悩まし続けるジレンマ…つまり、英語でいいところに刊行できないと日本語の刊行が増え続け、日本列島のなかでだけ回り続ける。英語でいいところに刊行しようとし始めると、だいたいすぐには刊行できず、改定や拒否が続きやすい。同じ論文の原稿を二年も三年も弄り続けることになりかねない」(30ページ)。
こんなのは朝飯前のごとく、画期的で厖大な研究論文や学術図書を英語で量産している猪口氏でさえ、このようなジレンマに悩まれていたことを知って、少し驚いた次第です。
「日本社会では学術研究で文科系と理科系を分け、血液型と関連させたりする愚かな考えもあるが、実証主義でいく限り、文科も理科もない。すべて真実を究明することを目的としている。…それが元気良く恒常的になされる仕組みのない社会では、怪しげな迷信や偏見が幅をきかせたりする」(62-63ページ)。
まったくその通りです!文学などの人文学系は別として、日本における文系・理系という学問の分け方は、私も常におかしいと思っていました。社会科学であれ自然科学であれ、科学は科学であるはずです。にもかかわらず、こうした当たり前の考えは、日本では非常に弱く、科学=理科系という等式が一般的な通念となっているようです。そうであれば、社会科学とは、一体、何なのでしょうか?
私が奉職している国際学科は、「国際学」を専門に掲げる研究教育組織であり、「国際学」は社会科学に分類されると言ってよいでしょう。ところが、国際学科に入学してくる学生のほぼ全員が、「国際学」は社会科学であるという認識を全く持っていません。国際学=国際問題の「時事評論」だと勘違いしているのです。もっとも、若い学生たちが、そう勘違いするのも仕方ないかもしれません。なぜなら、日本社会において、文系は科学ではないといった観念が幅を利かしているのですから…。
「国家の違いを超えて説明できるような理論的枠組は、ほとんど米国にしか生まれなかった。…米国以外で国際政治学をやろうとすると、非米国の様式を意識せざるを得ないが、母国で評価されても様式の違う米国ではあまり流布しない。逆も逆で米国流でやっても母国では評価されにくい。そこで私のアドバイスは両方を身につけることである。具体的には、分析的な実証主義的な方法を身につけることと歴史地域的な経路依存的説明も身につけることである」(142ページ)。
これは非常に重要な方法論上の指摘だと思います。未熟ながらも、私も同じようなことを考えながら、拙著『パワー・シフトと戦争』を執筆しました。もちろん、上記の両方の方法を身につけるまでには至っていませんが、理論と歴史・地域の両方を意識して研究したことは確かです。
最後に、以下を引用して締めくくります。
「私は…シラバスの充実や講義方法の改善などを図った。だが、その帰結は学生が極端に少なくなることだった」(151ページ)。
笑うに笑えない話です。同じような経験をした大学教員も多いのではないでしょうか?私もその一人です。私は、いくつかの大学で「国際政治学」に類する科目を長年にわたり担当しています。「グローバル・スタンダードの国際政治学」の授業をしようと意気込んで、同科目の授業を組み立てる際、国際政治学で高い評価を受けている、北米の著名な大学の「スター教授」のシラバスを入手して、それを真似た授業を行ったこともありましたが、結果は、受講生の激減でした(苦笑)。もっとも、その最大の原因は、「平凡教授」の私が、愚かにも「スター教授」をまねたことにあったのでしょう。くわえて、読書課題やレポート・論文などの課題の出し方にも問題があったと反省しています。
本書『実証政治学構築への道』は、「執筆を職業、趣味、習慣の三位一体としている」猪口氏の知的バイタリティとタフネスが表れ、学問上のエピソードがちりばめられた、とりわけ政治学徒にとっては、刺激的な自伝だと思います。