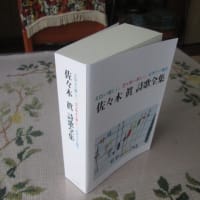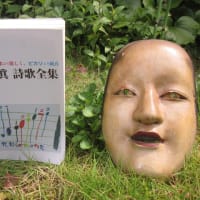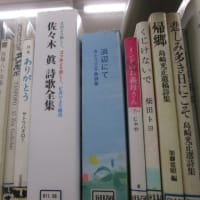照る日曇る日第1627回

子規が28歳から29歳にかけて「日本」紙上で連載したコラムからの抜粋である。
彼は28歳の頃は、まだ上野の森まで出かけて展覧会の絵を見たり論じたりすることもできたようだが、その翌年には早すぎた晩年の寝たきり生活に突入することになる。
内容はお得意の俳句の紹介だけでなく、文芸、美術、哲学全般に及び、特に当時悪評嘖々の森鴎外を擁護したり、最晩年の樋口一葉を激賞したり、西園寺公の文学者パーティをやっつけたり、西鶴、近松、芭蕉の3名の長短を論じたりしていて面白い。
さりながらが、最後の項目で近松の「曽根崎心中」の道行を論理的に事挙げして「阿保陀羅調」と悪罵しているが、あにはからんや、あそこは文辞は2の次3の次で、775調のアホダラ経だからこそいいのである。恐らく子規はこれを文楽でも歌舞伎でも見物しなかったのだろう。
漱石は、後年友を偲んで「悪い意味ではないが、すれっからし」と評したが、近松論ではその「すれっからしのいやらしさ」が少し滲み出ているように思う。
打って変わって興味深いのは「ベースボール」紹介文で、この時点ではまだ「野球」という訳語は使われていないものの、図を使い、「打者」「走者」「直球」などの用語を駆使してこれでもか、これでもかと延々と続くのであるが、子規が夢中で書けば書くほどゲームの実体が謎に包まれていくのが妙におかしい。
なお表題について一言。
子規は最後のコラム「松蘿玉液子を祭る」において、松蘿玉液とは清国徽州の産で陳玄子松蘿玉液と号し年齢不詳、30余年前に渡来した風来坊のような知己としているが、実際は生誕以来現在まで子規にとり付いて無数の作品を生みだした詩神の象徴であろう。
凄まじき騒音に耐え家に居る次は我が家が音を出す番 蝶人