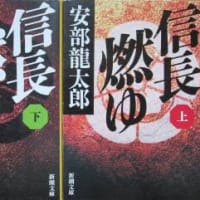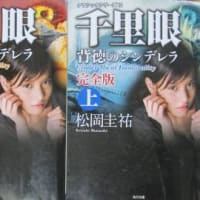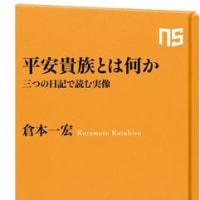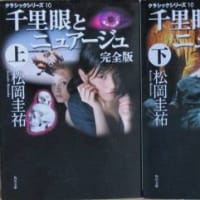英雄8人をプロファイリング!
今年、2024年3月に刊行されたエッセイ集。
本書は、1章1武将で、8章構成。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、武田信玄、上杉謙信、伊達政宗、松永久秀、石田三成が取り上げられている。「英雄」という言葉から、松永久秀、石田三成を即座にカウントする人はそれほど多くはないかもしれない。私は思い浮かばなかった。
著者はこの8人を選んでいる。まず、それがおもしろい。なぜ、この8人をとりあげたのかはエッセイの中で語られている。
「はじめに」において、著者は、史料に拠る実証主義の歴史学者に比べて作家は気楽なものと言いながら、「突飛な話にし過ぎては、読者が興醒めしてしまうかもしれない。そのためには対象となる人物や時代を良く知らねば、こうではないかという想像すら思い浮かばないのだ」と記す。人物や時代を知るために、著者が小説を生み出す舞台裏でどのようなことをしているかの様子をこのエッセイ集で垣間見ることができる。
それを、次の文でさらりと抽象化して語っている。「仮に物証はなくとも、行動パターン、過去の経歴、身体的特徴などさまざまなものから人物像の輪郭を限りなく明確にしていく。いわば、それは歴史上の人物のプロファイリングである。私は小説を書く過程において意識して、あるいは無意識にでも必ずしている」と。
「そういった意味では、本書は創作しているときの私の頭の中を、余すところなく語り尽くし、文章に書き起こしたものといえるかもしれない」と記す。
章を読み進めていくと、人物プロファイリングを行うために、著者が相当に史料を渉猟し、時代と人物を明確に想像するための下準備を重ねている様がよくわかる。日本史研究における歴史解釈の変化や動向が語られたり、戦国武将の行動事象についてその解釈に様々な仮説があることを列挙してくれている。そのうえで、時代小説作家として己の解釈、仮説を語っていく。おもしろいのは、著者が己の小説の中でどのような人物造形をしたかについて、随所で触れている点である。これは著者自身の作品PRにもなっていて一石二鳥という感じ。著者の作品群で知らなかったものに気づく機会にもなった。
本書は読みやすい。ここに登場する人物の行動や思考法を語る際に、現代社会において誰しもが見聞あるいは経験している事象や行動、用語などを譬えに使って語られている箇所が多いからである。身近に感じられ、ピンとくるところがある。
「第1章 織田信長」を例にとるだけでも、流通革命、ジャイアントキリング、ランナーズハイ、スティーブ・ジョブス、ファストファッション、ヘッドハンティング、燃え尽き症候群、大河ドラマや映画での信長役を引き合いに出す、などを譬えに利用している。すんなりとイメージしやすくなるのは、この語り口に一因があるようだ。
他章でも、会社の合併・子会社化などで権力構造を譬える例がある。「後輩ムーブ」「親ガチャ」「コミュ力オ化け」「無理ゲー」などという語句も使われていて、おもしろい。
各章は、戦国武将の人物像を推理し、プロファイリングしていく叙述である。そのエッセンスの一端が各章の見出しに副題として付されている。それをご紹介しておこう。後は本書を楽しんでいただきたい。
第1章 織田信長 - 合理精神の権化
第2章 豊臣秀吉 - 陽キャの陰
第3章 徳川家康 - 絶えざる変化の人
第4章 武田信玄 - 厳しい条件をいかに生きるか
第5章 上杉謙信 - 軍神の栄光と心痛
第6章 伊達政宗 - 成熟への歩み
第7章 松永久秀 - なぜ梟雄(キョウユウ)とされてきたか
第8章 石田三成 - 義を貫く生き方
各章末には、ここに取り上げられた戦国武将の簡略な系図と、武将本人の略年表が収載されている。
各章に2ページの分量でコラムが載っている。本文は戦国武将という英雄を扱うのに対し、こちらは戦国時代の縁の下の力持ち的な、黒子的役割を担った一群の人々を取り上げている。英雄は本人一人で生まれるものではないという側面をこれらの人々で代表させているのかもしれない。
穴太衆/国友衆/雑賀衆・根来衆/伊賀衆・甲賀衆/黒鍬衆/金山衆・金堀衆/海賊集衆/会合衆、を語っている。
これらの名称を読み、即座にイメージが浮かぶなら、あなたはかなりの歴史小説愛読者なのだろう。だが、さらに一歩踏み込んだ知識を得られるコラムになっていると思う。
私の読書遍歴からは、ここに取り上げられた8人の武将の中で、戦国時代の三大梟雄の一人と言われる松永久秀が相対的に一番遠い存在だった。本書では松永久秀のポジティブな側面をかなり推理している。著者の視点と語り口を興味深く受け止めた。著者は松永久秀を主人公にした小説『じんかん』に触れている。私には気づいていなかった一冊。また、一つ読書目標ができた。
ご一読ありがとうございます。
今年、2024年3月に刊行されたエッセイ集。
本書は、1章1武将で、8章構成。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、武田信玄、上杉謙信、伊達政宗、松永久秀、石田三成が取り上げられている。「英雄」という言葉から、松永久秀、石田三成を即座にカウントする人はそれほど多くはないかもしれない。私は思い浮かばなかった。
著者はこの8人を選んでいる。まず、それがおもしろい。なぜ、この8人をとりあげたのかはエッセイの中で語られている。
「はじめに」において、著者は、史料に拠る実証主義の歴史学者に比べて作家は気楽なものと言いながら、「突飛な話にし過ぎては、読者が興醒めしてしまうかもしれない。そのためには対象となる人物や時代を良く知らねば、こうではないかという想像すら思い浮かばないのだ」と記す。人物や時代を知るために、著者が小説を生み出す舞台裏でどのようなことをしているかの様子をこのエッセイ集で垣間見ることができる。
それを、次の文でさらりと抽象化して語っている。「仮に物証はなくとも、行動パターン、過去の経歴、身体的特徴などさまざまなものから人物像の輪郭を限りなく明確にしていく。いわば、それは歴史上の人物のプロファイリングである。私は小説を書く過程において意識して、あるいは無意識にでも必ずしている」と。
「そういった意味では、本書は創作しているときの私の頭の中を、余すところなく語り尽くし、文章に書き起こしたものといえるかもしれない」と記す。
章を読み進めていくと、人物プロファイリングを行うために、著者が相当に史料を渉猟し、時代と人物を明確に想像するための下準備を重ねている様がよくわかる。日本史研究における歴史解釈の変化や動向が語られたり、戦国武将の行動事象についてその解釈に様々な仮説があることを列挙してくれている。そのうえで、時代小説作家として己の解釈、仮説を語っていく。おもしろいのは、著者が己の小説の中でどのような人物造形をしたかについて、随所で触れている点である。これは著者自身の作品PRにもなっていて一石二鳥という感じ。著者の作品群で知らなかったものに気づく機会にもなった。
本書は読みやすい。ここに登場する人物の行動や思考法を語る際に、現代社会において誰しもが見聞あるいは経験している事象や行動、用語などを譬えに使って語られている箇所が多いからである。身近に感じられ、ピンとくるところがある。
「第1章 織田信長」を例にとるだけでも、流通革命、ジャイアントキリング、ランナーズハイ、スティーブ・ジョブス、ファストファッション、ヘッドハンティング、燃え尽き症候群、大河ドラマや映画での信長役を引き合いに出す、などを譬えに利用している。すんなりとイメージしやすくなるのは、この語り口に一因があるようだ。
他章でも、会社の合併・子会社化などで権力構造を譬える例がある。「後輩ムーブ」「親ガチャ」「コミュ力オ化け」「無理ゲー」などという語句も使われていて、おもしろい。
各章は、戦国武将の人物像を推理し、プロファイリングしていく叙述である。そのエッセンスの一端が各章の見出しに副題として付されている。それをご紹介しておこう。後は本書を楽しんでいただきたい。
第1章 織田信長 - 合理精神の権化
第2章 豊臣秀吉 - 陽キャの陰
第3章 徳川家康 - 絶えざる変化の人
第4章 武田信玄 - 厳しい条件をいかに生きるか
第5章 上杉謙信 - 軍神の栄光と心痛
第6章 伊達政宗 - 成熟への歩み
第7章 松永久秀 - なぜ梟雄(キョウユウ)とされてきたか
第8章 石田三成 - 義を貫く生き方
各章末には、ここに取り上げられた戦国武将の簡略な系図と、武将本人の略年表が収載されている。
各章に2ページの分量でコラムが載っている。本文は戦国武将という英雄を扱うのに対し、こちらは戦国時代の縁の下の力持ち的な、黒子的役割を担った一群の人々を取り上げている。英雄は本人一人で生まれるものではないという側面をこれらの人々で代表させているのかもしれない。
穴太衆/国友衆/雑賀衆・根来衆/伊賀衆・甲賀衆/黒鍬衆/金山衆・金堀衆/海賊集衆/会合衆、を語っている。
これらの名称を読み、即座にイメージが浮かぶなら、あなたはかなりの歴史小説愛読者なのだろう。だが、さらに一歩踏み込んだ知識を得られるコラムになっていると思う。
私の読書遍歴からは、ここに取り上げられた8人の武将の中で、戦国時代の三大梟雄の一人と言われる松永久秀が相対的に一番遠い存在だった。本書では松永久秀のポジティブな側面をかなり推理している。著者の視点と語り口を興味深く受け止めた。著者は松永久秀を主人公にした小説『じんかん』に触れている。私には気づいていなかった一冊。また、一つ読書目標ができた。
ご一読ありがとうございます。