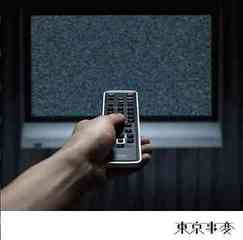興味深いテキストを読んだので、その感想というか実感込みで。
とは言うものの、めんどくさい文章なのでテキトーに読んでさらっと流してください。
Type A
事実→解析→意見→感情
Type B
感情→意見→解析→事実
この2つのパターンは何かというと、とある大学の先生が教え子について良く感じることだそうです。
出典は
こちら。
この先生が仰っていることに対して、明後日の方向から思ったことをずらずらと書き連ねようと思います。
前者が本来あるべき理論的思考プロセスであって、後者が若い学生の思考というか、思考に至るまでのプロセスとのこと。
ほほぅ・・・、と膝を打った訳ですよ。
この考え方はあらゆる学問の入門編としては大事だと思います。
でも、あるレベルを超えた学者とかは「自分はこう思うからきっと真実はこうなんだ」という思いがあるはず。
それがなければ「真実」に到達することはできないでしょう。
Type Bからある時期にType Aにシフトするものの、結局、Type Bの思考に戻るんだと思います。
そのType B方式で導き出した「事実」が自分の思惑と違っていたか、合っていたかは突き詰めて行けば最終的には分かることで、最初に「事実」ありきで考えてしまうのはつまらないと思うのです。
その「想い」が無ければそこまで考えない。
その途中で放棄するのであれば、中途半端なところで投げ出すのであれば、思いついたことだけを胸に秘めておけ、と思うのです。
このところ、公私問わずで、あらゆることが動く動く。
で、その全てに於いて「人」が関わっているのは間違いなく、その、人間関係に翻弄され、翻弄することもあり、人に悩まされ、人を悩まし、幸か不幸か、根が浅いのか深いのかも分からない状態であるわけです。
こんなこと言っていると、オマエは大きめの病院にでも行った方が良いんじゃないか?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
そうかもしれません。
30も過ぎるとどうやら結構な部分を諦観できるものだなぁ、と自分でも驚きます。
諦観している部分が、自分にとってもの凄く大きなことであっても、その相手のために自分を曲げる、もしくは隠す、という芸当が表面上できてしまうことがあります。
これ、Type Bの思考です。
で、根本的には何も解決しない。
そんなこと出来てる訳ねぇだろ。
冒頭のフリは何だったのかというと、このType Aというのがもの凄く曲者だといこと。
本来正しいはずの思考プロセスに足をすくわれることがあるということです。
事実を客観的に受け入れるなんてことが出来るわけねぇだろ。バカヤロウ。
感情が伴わないことが、その本人にとっての事実に成りうることなんてあるわけねぇだろ。
感情で起こっている出来事でそんな真似出来るわけねぇだろ。
馬鹿なこと言うんじゃないよ。
私以外の方は、事実から感情という自分自身の「事実」を導き出すということが出来るんでしょうか。
もしそうだとしたら、なんと自分は未熟なのか。わがままなのか。
吐き出し口が常に無いとAKIRA(大友克洋)の覚醒した状態の様な内側の世界に押しつぶされかねない。
もしかして、大友氏はそういう内側で完結しようとした世界の虚無を描いたのかもしれない。
しかし、最後は新しい世界をを作るために不確定要素達が見えないところに向かって行く。
こうやって思考をとんでもない方向へ巡らせてみて、どこかにあるかもしれない脱出口を探しまくる。
その小さな脱出口に向かって行ったものの後ろを振り返った瞬間にずるずると引き戻される。
古典の引用って便利だなぁ。
でも、その通りだったりとか思って、その古典の中に本質らしきものを見いだしてみようとすると、結局未練がましいばかりで、泥の中をもがきまくって結局深く、生暖かい泥に包み込まれ、しかもその泥が暖かいもんだから生きている実感を得た様な気分になったりして、相当タチが悪い。
どんな状況であろうと、人はその状況に置かれた自分のことを正当化できる様です。
脳って便利だなぁ。
是か非ではなく、こうありたいと思うのはType Bですね。
感情→意見→解析→事実
事実らしきものからの帰納法で導き出した感情なんてモンは理屈で固めた殻みたいなモンで、そこに核は無い、と思うのです。
まず、感情ありきで物事の事実まで突き進めることが、最も幸せなことではないでしょうか。