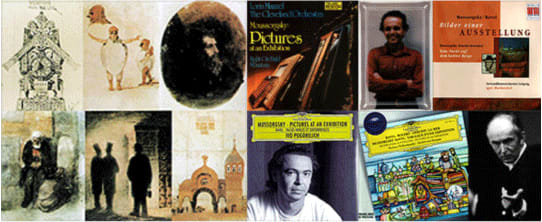
2006年6月7日投稿分__
「展覧会の絵 Pitures at an Exhibition」は、ムソルグスキー Moussorgsky のピアノ独奏曲がオリジナルですが、ラヴェルによる管弦楽編曲版が一般には有名です。 普通の人は、オーケストラ演奏を聞いてから 原曲のピアノ曲に親しみますね。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
組曲「展覧会の絵」はロシアの作曲家、モデスト・ムソルグスキーによって、1874年に作曲されたピアノ組曲。 ハルトマンという友人の遺作展を歩きながら、そこで見た10枚の絵の印象を音楽に仕立てたもので、ロシアにとどまらずフランスやローマ、ポーランドなどさまざまな国の風物が描かれている。 また これらの10枚の絵がただ無秩序に並ぶのではなく、プロムナードという短い間奏曲が5回繰り返して挿入されるのが特徴的で、このプロムナードはムソルグスキー自身の歩く姿を表現しているという。 プロムナード / 古城/雛の踊り / ビドロ / バーバー・ヤーガの小屋 / キエフの大門 など覚えやすいメロディーと緩急自在の構成 (ユーモラスな曲/優雅な曲/重々しい曲/おどろおどろしい曲など) から、ムソルグスキーの作品の中でも最も知られた作品である (Wikipedia)。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
マゼール Lorin Maazel 指揮クリーヴランド管による優秀デジタル録音 (‘78年 Telarc 30分) LP には圧倒されましたね。 フィルアップ曲の「禿げ山の一夜 A Night on the Bare Mountain」も同様に大いに楽しめます。 大体この組合わせが定番ですね。「禿げ山」はムソルグスキーのオリジナル / リムスキー=コルサコフによる改訂版。 どちらも音楽による描写がよくできていて、クラシック音楽の初心者でもすんなり楽しめます。
「展覧会の絵」オリジナルのピアノ版は色々な人の演奏で聞きましたが、ユーゴ出身のポゴレリッチ Ivo Pogorelich の演奏 (‘95年 DG 42分) にはびっくりしました__先ず遅い、録音が鮮明、タッチは明確。
~~~~~~~~~~~~~
ムソルグスキーはロシア出身ですから、ロシア人による演奏がいいかというと、必ずしもそうではありません。 マルケヴィッチ指揮ゲヴァントハウス管による「展覧会の絵」「禿げ山の一夜」(‘73年 Berlin Classics 33分) は、魅力に今ひとつ欠けますね。 もっとも この東独のオケラ演奏にはそれほど期待していませんでしたが、やっぱりというものでした。 演奏自体はいいと思うのですが、これといった特徴がなく 古いモノクロ写真を見るような感覚です。
~~~~~~~~~~~~~
ラヴェルはフランス人だから、フランスの指揮者によるものが良さそうにも思いますが、これといった CD が思い浮かびません。 もう世界のオーケストラ・コンサートの定番曲となっていますから、特定国に限定して考えなくてもいいのかも。 カラヤン / ベルリン・フィル絶頂期の録音 (‘64~’66年 DG 36分) もお気に入りの一つです。
以上
「展覧会の絵 Pitures at an Exhibition」は、ムソルグスキー Moussorgsky のピアノ独奏曲がオリジナルですが、ラヴェルによる管弦楽編曲版が一般には有名です。 普通の人は、オーケストラ演奏を聞いてから 原曲のピアノ曲に親しみますね。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
組曲「展覧会の絵」はロシアの作曲家、モデスト・ムソルグスキーによって、1874年に作曲されたピアノ組曲。 ハルトマンという友人の遺作展を歩きながら、そこで見た10枚の絵の印象を音楽に仕立てたもので、ロシアにとどまらずフランスやローマ、ポーランドなどさまざまな国の風物が描かれている。 また これらの10枚の絵がただ無秩序に並ぶのではなく、プロムナードという短い間奏曲が5回繰り返して挿入されるのが特徴的で、このプロムナードはムソルグスキー自身の歩く姿を表現しているという。 プロムナード / 古城/雛の踊り / ビドロ / バーバー・ヤーガの小屋 / キエフの大門 など覚えやすいメロディーと緩急自在の構成 (ユーモラスな曲/優雅な曲/重々しい曲/おどろおどろしい曲など) から、ムソルグスキーの作品の中でも最も知られた作品である (Wikipedia)。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
マゼール Lorin Maazel 指揮クリーヴランド管による優秀デジタル録音 (‘78年 Telarc 30分) LP には圧倒されましたね。 フィルアップ曲の「禿げ山の一夜 A Night on the Bare Mountain」も同様に大いに楽しめます。 大体この組合わせが定番ですね。「禿げ山」はムソルグスキーのオリジナル / リムスキー=コルサコフによる改訂版。 どちらも音楽による描写がよくできていて、クラシック音楽の初心者でもすんなり楽しめます。
「展覧会の絵」オリジナルのピアノ版は色々な人の演奏で聞きましたが、ユーゴ出身のポゴレリッチ Ivo Pogorelich の演奏 (‘95年 DG 42分) にはびっくりしました__先ず遅い、録音が鮮明、タッチは明確。
~~~~~~~~~~~~~
ムソルグスキーはロシア出身ですから、ロシア人による演奏がいいかというと、必ずしもそうではありません。 マルケヴィッチ指揮ゲヴァントハウス管による「展覧会の絵」「禿げ山の一夜」(‘73年 Berlin Classics 33分) は、魅力に今ひとつ欠けますね。 もっとも この東独のオケラ演奏にはそれほど期待していませんでしたが、やっぱりというものでした。 演奏自体はいいと思うのですが、これといった特徴がなく 古いモノクロ写真を見るような感覚です。
~~~~~~~~~~~~~
ラヴェルはフランス人だから、フランスの指揮者によるものが良さそうにも思いますが、これといった CD が思い浮かびません。 もう世界のオーケストラ・コンサートの定番曲となっていますから、特定国に限定して考えなくてもいいのかも。 カラヤン / ベルリン・フィル絶頂期の録音 (‘64~’66年 DG 36分) もお気に入りの一つです。
以上









