 ルール違反を黙認
ルール違反を黙認
2014年6月20日
ワールドカップ(W杯)ブラジル大会で、日本は上位のギリシャ戦で善戦し、来週のコロンビア戦 にもし勝てれば、決勝進出もないではない位置にいます。普段はサッカーに興味を持たないわたしもW杯となると、特に日本戦はテレビの前に座ります。以前からの「サッカーはルール無視を奨励しており、子供の教育に悪い」という感じを今回も持ちました。ルール違反をみとめるのもルールですか。そこに人気があるのですかね。妙なスポーツですね。
ルール違反の判定が曖昧なところが面白いのだという人もいるでしょう。ラフなところがいいという人もいるでしょう。そうでしょうか。スロービデオの高感度映像をみますと、目にあまる違反があまりにも多いことに腹が立ってきます。違反がバレなければいい、違反が試合の進行に重大な影響を及ぼしていなければ、おとがめなしのようですね。
社会的ルール、法律は守らなければならないと、子供の時から教育しています。スポーツを通じて、健全な精神と身体をつくり、特にフェアプレー精神を体で覚えこませるのがスポーツの目的のひとつです。そういうことを心がけ、貫いているスポーツはいくらでもあります。それに比べ、世界でもっとも人気のあるスポーツの王様のサッカーは、スポーツの中ではフェアプレー精神ともっとも縁遠いのですね。縁遠いところに人気の源泉があるのですかね。
頭の固い人間の繰言と思わないでください。スポーツの中で並みはずれて、サッカーはフェアとかけ離れていると考える人は少ないないはずです。わたしは新聞社に長くおり、編集部門にスポーツ論としてのサッカーを書いてはどうだ、と頼んだことが何度もあります。運動部記者はサッカーはそういうものだと刷り込まれ、あまり問題意識を持っていないのでしょうか、当社は無反応でした。目にあまるプレーが多かった2010年の南アフリカ大会の時、経済紙の日経が違反プレーを鋭く批判する解説コラムを載せておりました。新聞社および系列のテレビ局は、広告収入と読者獲得を目当てに、サッカー大会のスポンサーなっていることが多く、それでサッカーの批判記事を載せないとしたら、残念なことです。
他のスポーツの例をあげましょう。今年の大相撲5月場所の千秋楽で、横綱日馬富士が大関稀勢の里の髷をつかみ、倒した取り組みでは、「頭髪を故意につかむことは違反が決まり」として、反則負けにしました。せっているうちに、うっかり手を髷に入れてしまったのでは、という同情論もあることはありました。故意、偶然、うっかりとは関係なく、厳正に判定を下したのです。
1986年、アルゼンチンの英雄マラドーナが飛んできたボールに手を出してゴールに押し込んだ時、審判はヘッディングと見て、得点を認めました。マラドーナはインタビューで「ただ神の手が触れた」といい、手(ハンド)を使ったことを否定しませんでした。瞬間的、本能的に手が出てしまうことはあるでしょう。映像をみると、まず故意に手を使ったと思われます。ともかくルールは故意か偶然かを問わず、違反は違反にすべきです。それがルールです。
プロ野球では、投手が打者の頭部にボールをぶつけると、危険球とみなされ違反になるばかりでなく、直ちに退場処分を受け、投手交代です。意図的な危険球が一時、目立ったので、ルールが強化されたのです。野球ではもっとも重い処分でしょう。これも故意か偶然かを問いません。退場処分が重いので、故意に危険球を投げる投手はまずいません。突然の投手交代で、試合の流れが相手方に一気に傾くことが多いからです。
ブラジル大会の開幕戦、ブラジル対クロアチア戦の審判は3人の日本人が務め、話題になりました。主審が試合を左右する決定的なPK(ペナルティー・キック)の判定を下し、これが得点につながりました。わたしもテレビを見ていました。ゴール前という極めて重要なエリアで、あきらかにクロアチアの選手は手を使い、相手選手の背後から押すか引っ掛けるかして、押し倒していました。映像はそれを否定できないほど正直です。
この判定に抗議が相次ぎました。「簡単に押し倒される選手ではない」、「他の審判ならPKの判定はなかった」、「審判の助けを借りて、ブラジルは勝った」。ひどい抗議は、試合に負けたクロアチアの監督が「こんなことでは、今大会は1000回ものペナルティー・キックが行われるぞ」とわめいていたことです。ルール違反をなくすには、厳しい判定をどしどしだして、結局、高いコストを払わせていけばいいのです。そうはしないのは、審判がジャッジを曖昧にして、違反を黙認し、それが試合を面白くしていると考えているからでしょう。もともと不正、違反が試合を盛り上げるという暗黙の了解があるのでしょう。
日本戦に触れますと、初戦のコートジボワール戦、次のギリシャ戦では、日本側を含め、手を使って、ボールに接近している相手選手の腕、袖を引っ張り、押しのけたり、倒したりしていました。足をだし、相手がつまづいて、倒れるシーンも多くありました。悪質の程度に応じて、イエローカード(2枚でレッドカードで出場停止)、ペナルティー・キックとかいろいろ差はつけてはいますがね。映像をみると、明らかに意図して違反をしているのに、指摘された選手は手を広げ「オーノー」のゼスチャーです。よくやりますよね。
野球ではどうでしょう。キャッチャーのミットが打者のバットに触れただけで打撃妨害をとられ、進塁が認められます。走塁妨害、ボークなども故意か偶然かを問わず、ペナルティーをとられます。高校野球の甲子園大会で、相手投手を疲れさそうと、ファウルを故意に何度も打つ選手の打法がバントの亜種とみなされ、スリーバント・アウト(バントで3回、ファウルを打つとアウト)と認定されました。練習を重ね、亜種打法に磨きをかけてきたその選手は、得意技を封じられ、号泣しました。厳しいのですね。
日本のサッカー選手はきまじめすぎる、つまりフェアプレーに徹する傾向が他国の選手に比べると強いと、いわれます。「選手を温室育ちにすると、激しい当たりが多い国際試合に勝てなくなる」という解説を読んだことがあります。きっとそうなのでしょう。
最後にもうひとつ、現実の社会では、法律の網の目をくぐり、違反をしてでも、いかに相手をだますか、いかに裁判で重い罪から逃げおおせるかに達者な人が多いことは間違いありません。性悪説で成り立っている人間社会を生き抜くには、サッカーで訓練をつむのもいいのかもしれません。サッカーはそうしたことを暗黙の前提としているとすれば、社会的効用はないでもありませんね。










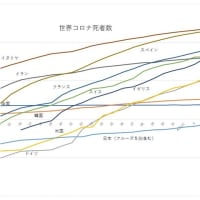









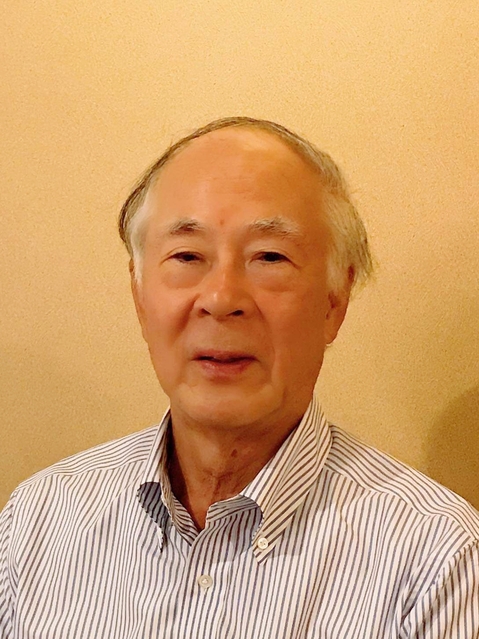

サッカーにもスポーツマンシップがあれば息子に習わせたいのですが、トップの人たちがあれでは、二の足を踏んでしまいます