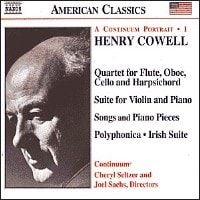『沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)』は坪内逍遥(1859 - 1935)作の歌舞伎劇。
この出し物が、現在歌舞伎座「四月大歌舞伎」(六世中村歌右衛門五年祭) で演じられています。
淀君が「自尊心を独り異様に高ぶらせて、錯乱に陥」る場面は、明らかに、オペラにある〈狂乱の場〉の影響(たとえば、ドニゼッティ『ランメルモーアのルチア』における「ルチア狂乱の場」(ただし、こちらは恋愛感情によるものだが)。
オペラにおける〈狂乱の場〉も、伝統的な1つの「型」となっており、ヘンデルの『オルランド』には、珍しい男性による狂乱シーンも見られます。
それでは、世の東西を問わず、舞台芸術や音楽、そして文学などの藝術にはなぜ「型」があるのか(あるいは「あったのか」)。
というのが、本日のお題。
「叙情」には人によってばらつきがあったとしても、「型」には原則的にそのようなことはありません。
なぜなら、「型」には、長い時間を経ての、多くの人々の体験が凝縮されているからです。だから「型」のよって立つ淵源は、個人よりも共同体にあります。
例えば日本の場合、「和歌」を支えていたのは、女房を中心とした「宮廷」であり、「俳句」を支えていたのは、上層町人階級だった。
藝術における個性や新規性を重視する傾向も(最も高唱されたのは、ロマン主義の世紀である19世紀)、たかだか200~300年の歴史しかないけれど、「型」の古いものになると、ヨーロッパの場合で言えば、ギリシア時代にまで遡ることも可能です(演劇での「三一致の法則」なるものは、誤解があったにせよ、アリストテレスに始まるとされ、ラシーヌ、モリエールなどフランス古典劇の基本原則となった)。
音楽で言えば、古典派といわれる、機能和声とソナタ形式を柱とした様式ね。
それはそれで、「型」という共通認識があるから、一度なじんでしまえば、後は理解が早い。
「型」はある種の制約ではあるけれど、どのような制約があろうとも、新しいものを盛り込むことは不可能ではない。
しかし、新しく盛り込むものが大きくなり過ぎると、あるいは「型」を支えていた共同体が力を失うと、今度は、その「型」を崩そうとする動きも表れてくるのは、必然的なことでしょう。
このような「型」は、伝統芸能の場合、口伝として次世代へと引き継がれてきました。
ちょうど、本日夕刊の能楽評で、世阿弥作『頼政』の主人公の性根を伝えることばが、
「演じすぎず、リアルにやらないで老将の気骨を見せよ」
と紹介されていました。
「型」のまったくない藝術は、考えられません。
すべての藝術は(あるいは表現行為は)「型」を模倣するところから出発するからです(現代藝術を言うならば、ミニマル音楽における、作曲家相互の影響関係を思い浮かべてもいい)。
その点で、「藝術における個性や新規性」をあまりにも重視するロマン主義的な発想は、もう一度検討されるべきでありましょう。
この出し物が、現在歌舞伎座「四月大歌舞伎」(六世中村歌右衛門五年祭) で演じられています。
淀君が「自尊心を独り異様に高ぶらせて、錯乱に陥」る場面は、明らかに、オペラにある〈狂乱の場〉の影響(たとえば、ドニゼッティ『ランメルモーアのルチア』における「ルチア狂乱の場」(ただし、こちらは恋愛感情によるものだが)。
オペラにおける〈狂乱の場〉も、伝統的な1つの「型」となっており、ヘンデルの『オルランド』には、珍しい男性による狂乱シーンも見られます。
それでは、世の東西を問わず、舞台芸術や音楽、そして文学などの藝術にはなぜ「型」があるのか(あるいは「あったのか」)。
というのが、本日のお題。
「叙情」には人によってばらつきがあったとしても、「型」には原則的にそのようなことはありません。
なぜなら、「型」には、長い時間を経ての、多くの人々の体験が凝縮されているからです。だから「型」のよって立つ淵源は、個人よりも共同体にあります。
例えば日本の場合、「和歌」を支えていたのは、女房を中心とした「宮廷」であり、「俳句」を支えていたのは、上層町人階級だった。
藝術における個性や新規性を重視する傾向も(最も高唱されたのは、ロマン主義の世紀である19世紀)、たかだか200~300年の歴史しかないけれど、「型」の古いものになると、ヨーロッパの場合で言えば、ギリシア時代にまで遡ることも可能です(演劇での「三一致の法則」なるものは、誤解があったにせよ、アリストテレスに始まるとされ、ラシーヌ、モリエールなどフランス古典劇の基本原則となった)。
音楽で言えば、古典派といわれる、機能和声とソナタ形式を柱とした様式ね。
それはそれで、「型」という共通認識があるから、一度なじんでしまえば、後は理解が早い。
「型」はある種の制約ではあるけれど、どのような制約があろうとも、新しいものを盛り込むことは不可能ではない。
しかし、新しく盛り込むものが大きくなり過ぎると、あるいは「型」を支えていた共同体が力を失うと、今度は、その「型」を崩そうとする動きも表れてくるのは、必然的なことでしょう。
このような「型」は、伝統芸能の場合、口伝として次世代へと引き継がれてきました。
ちょうど、本日夕刊の能楽評で、世阿弥作『頼政』の主人公の性根を伝えることばが、
「演じすぎず、リアルにやらないで老将の気骨を見せよ」
と紹介されていました。
「型」のまったくない藝術は、考えられません。
すべての藝術は(あるいは表現行為は)「型」を模倣するところから出発するからです(現代藝術を言うならば、ミニマル音楽における、作曲家相互の影響関係を思い浮かべてもいい)。
その点で、「藝術における個性や新規性」をあまりにも重視するロマン主義的な発想は、もう一度検討されるべきでありましょう。