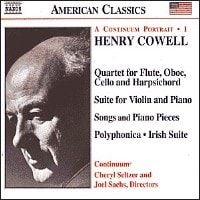前回述べた武満徹とは異なった方法論で、「世界音楽」を目指そうとして作曲家がいます。
高橋悠治(たかはし・ゆうじ、1938 - )です。
ここでは、彼が主宰した「水牛楽団」を通じて、世界各国の音楽との「連帯」について考えてみたいと思います。
「水牛楽団」というのは、1978年から1985年まで活躍していた音楽グループで、
一方、演奏を聴いている側にとっては、その音楽は次のようなものに受け取られたようです。
しかし、今現在、「水牛楽団」のCDを聴いてみると、その「素人じみたこなれない演奏」や「へんてこな音楽」が、かえって意味を持ってきているように思えます。
一つは、高橋悠治がこの楽団を作った時に感じていた、悪しき状況が変わらないどころか、より変な形(広告代理店やマスコミによる、音楽家の「物語」づくり。一例として、フジ子・ヘミングや大江光が挙げられるでしょう)になってきているから。
当時、高橋の問題意識の一つは、「世界中で『名人芸を披露する』国際コンクール上がりの演奏家が、生産的な音楽家でない」ことにあったようです。
このような「非生産的な音楽家」に対して素人による音楽を対峙させる。
もう一つには、鑑賞されるような「民族音楽」が、本当に民族や民衆に根ざしているものなのか、という疑問があったのではないか。
現在も「ワールド・ミュージック」としてCD化されているものは数多くあり、それらは「癒し」の音楽として多くの人びとに受け取られています。
しかし、それらの演奏のほとんどは、アマチュアによるものではなく、音楽を聴かせて商売にしている人々によるもの(アイルランド音楽でのチーフタンズや、中国音楽での女子十二坊など)。
「水牛楽団」がそれに対して、
水牛楽団
高橋悠治―大正琴・ハルモニウム・トイピアノ
西沢幸彦―ケーナ・シーク
福山敦夫―歌・三線・ピン・チャランゴ
福山伊都子―ハルモニウム・大正琴・歌
八巻美恵―タイコ・トイピアノ・歌
ゲスト―モンコン・ウトック―如月小春―矢川澄子
(水牛)
高橋悠治(たかはし・ゆうじ、1938 - )です。
ここでは、彼が主宰した「水牛楽団」を通じて、世界各国の音楽との「連帯」について考えてみたいと思います。
「水牛楽団」というのは、1978年から1985年まで活躍していた音楽グループで、
「それまでの生活も音楽もすて、人々と対話し、手づくりの雑誌『水牛通信』で反体制の声をくみとり、発言しつづけた。(中略)
西洋音楽を操るような洗練された技術はそこにない。ないというより、あえてそういう技術を否定したところに水牛楽団はあった。不慣れな楽器にふりまわされた手と手のあいだから、楽譜には書きあらわせない音の厚みや綾がうまれる。」(CD説明書より)
一方、演奏を聴いている側にとっては、その音楽は次のようなものに受け取られたようです。
「水牛楽団をきいたのは二十年くらいまえ、それも一度きりだ。そのころ高橋悠治はぼくにとって、バッハやサティ、クセナキスを弾くすぐれたピアニストであり、「現代音楽」の有名な作曲家だった。そういう高橋悠治を期待して水牛楽団のコンサートに足をはこんだ。でもコンサートは失望でしかなかった。
はっきりとしたことは覚えていない。薄暗いちいさな会場にまばらな客。曲はなんだったか。たぶんオリジナル曲やプロテスト・ソングだっただろう。素人じみたこなれない演奏。ヨーロッパに向けられた自分の視線の向こうにいるはずの高橋悠治もいなかったし、「現代音楽」もなかった。あったのはどこか不慣れな手つきで大正琴を弾いている高橋悠治とへんてこな音楽だった。」(三橋圭介「いま、水牛」)
しかし、今現在、「水牛楽団」のCDを聴いてみると、その「素人じみたこなれない演奏」や「へんてこな音楽」が、かえって意味を持ってきているように思えます。
一つは、高橋悠治がこの楽団を作った時に感じていた、悪しき状況が変わらないどころか、より変な形(広告代理店やマスコミによる、音楽家の「物語」づくり。一例として、フジ子・ヘミングや大江光が挙げられるでしょう)になってきているから。
当時、高橋の問題意識の一つは、「世界中で『名人芸を披露する』国際コンクール上がりの演奏家が、生産的な音楽家でない」ことにあったようです。
このような「非生産的な音楽家」に対して素人による音楽を対峙させる。
もう一つには、鑑賞されるような「民族音楽」が、本当に民族や民衆に根ざしているものなのか、という疑問があったのではないか。
現在も「ワールド・ミュージック」としてCD化されているものは数多くあり、それらは「癒し」の音楽として多くの人びとに受け取られています。
しかし、それらの演奏のほとんどは、アマチュアによるものではなく、音楽を聴かせて商売にしている人々によるもの(アイルランド音楽でのチーフタンズや、中国音楽での女子十二坊など)。
「水牛楽団」がそれに対して、
「完成もなく、そのときその場に吹きすぎる風のような音楽。フォークでも、民謡でも、またどこかにあるような日本の歌でもない。日本からアジア、ヨーロッパの民衆の音楽に通じる根源に根ざした歌。かつて水牛楽団がタイのカラワン楽団と交流したように、歌の道は文化を超え、目に見えない通路によって民衆の根につながっている。」(CD説明書より)としていたのは、方向性としては間違ってはいないでしょう(楽団としての失敗は、政治的党派性に関わり過ぎたからか?)。
この項、つづく
水牛楽団
高橋悠治―大正琴・ハルモニウム・トイピアノ
西沢幸彦―ケーナ・シーク
福山敦夫―歌・三線・ピン・チャランゴ
福山伊都子―ハルモニウム・大正琴・歌
八巻美恵―タイコ・トイピアノ・歌
ゲスト―モンコン・ウトック―如月小春―矢川澄子
(水牛)