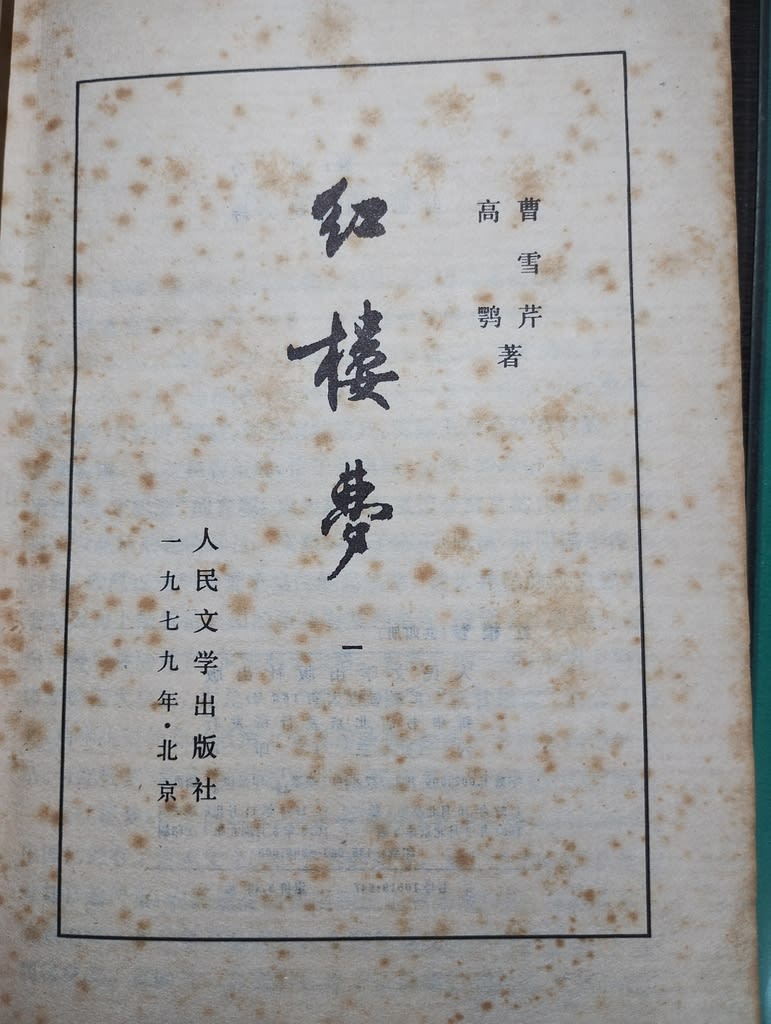
今回は、鳳姐に横恋慕した賈瑞に対して、鳳姐が策略を講じ、賈瑞を懲らしめる様子が描かれます。この事件を契機に病を得、寝たきりとなった賈瑞が、この物語で時々登場する僧侶と道士の片割れからもらった不思議な鏡を覗いてみると……。『紅楼夢』第十二回の始まりです。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
王熙鳳は毒もて相思の一局を設け
賈天祥は正に風月の鑑(かがみ)を照らす
(「王熙鳳」は、本文ではあだ名の「鳳姐」と書かれています。「相思」は男女が互いに思慕すること。「賈天祥」は賈瑞の別名です。)
さて鳳姐がちょうど平兒と話をしていると、取り次ぎをする者の声が聞こえた。「瑞旦那様がお越しになりました。」鳳姐は「お入りになってもらって。」と命じた。賈瑞は面会を請求し、心の中では密かに嬉しく思っていた。鳳姐に会うと、満面笑みを浮かべ、続けて何度も挨拶をした。鳳姐もわざと慇懃に賈瑞を座らせ、お茶を勧めた。賈瑞は鳳姐がこのように身繕いしているのを見て、益々メロメロに倒れそうになり、それでとろんとした眼になって尋ねた。「璉兄さんはどうしてまだ帰ってないの。」鳳姐は言った。「どうしてか知らないの。」賈瑞は笑って言った。「どうせ途中で誰かに捕まってしまい、帰って来れなくなったんじゃないか。」鳳姐は言った。「男性というのは、たまたま見かけた方を好きになってしまうということが、おありになると知りました。」賈瑞は笑って言った。「ねえさん、それは間違っています。わたしはそんな男じゃないですよ。」鳳姐は笑って言った。「あなたのような人が何人もいるものですか。十の内にひとりもいないわ。」
賈瑞はそう聞いて、気持ちが押さえきれない程嬉しくなった。また言った。「ねえさんは毎日ストレスが溜まって大変ですね。」鳳姐は言った。「本当にそうなの。だから誰か来てくれて、お話しして憂さを晴らせるといいんだけど。」賈瑞は笑って言った。「わたしは逆に毎日閑にしています。もし毎日こちらに来て、ねえさんの憂さを晴らしてさしあげれば、いいんじゃない。」鳳姐は笑って言った。「あなた、わたしをからかってるの。あなたのとこから、わたしのとこに来たいとでも言われるの。」賈瑞は言った。「わたしがねえさんの面前で、もし一言でも嘘をついたら、天から雷に打たれて死んでしまいますよ。ただ日頃人の話で、ねえさんはおっかない人で、ねえさんの前では少しも間違いは許されないと聞いていたので、びくびくしていたんです。今ねえさんにお会いして、とてもやさしくて親しみやすい人だと分かりました。どうして来ないもんですか。たとえ死んでも会いに来たいと思います。」鳳姐は笑って言った。「道理であなたはものの分かった人で、蓉ちゃん、薔ちゃん兄弟よりずっと世事に長けているのね。わたしはあの子たちは見かけは綺麗で、もう少しものの分かった人たちだと思っていたけど、実際はふたりともぼんくらで、少しも他人の気持ちを理解してくれないのよ。」
賈瑞はこの話を聞いて、益々心の内に強く響くものがあり、知らず知らずのうちにまた一歩前に近寄り、こっそり鳳姐の荷包(香包とも言う。良い香りのする香料やお菓子などを入れた小さな飾り袋)を盗み見て(「偷香窃色(偷香窃玉)」。男女が密かに通じること。他人の奥さんである鳳姐に横恋慕する意味)、また尋ねた。「どんな指輪をつけているの。」鳳姐はこっそりと言った。「もう少しきちんとなさって。小間使いたちに見られるといけないわ。」賈瑞は服従せざるを得ない話(綸音佛語 lún yīn fó yǔ)を聞いたかのように、慌てて後退すると、鳳姐が笑って言った。「あなた、もう行かないといけないわ。」賈瑞は言った。「わたしはもう少し座っていたい、――本当に容赦の無いねえさんなんだから。」鳳姐はまたこっそり言った。「昼日向は人の往来が多いから、あなたがここにいるのも都合が悪いわ。あんた、とりあえずお行きなさい、夜になって、宵の口(起更)にお越しになって、こっそり西側の穿堂(通り抜けができるようになった部屋)でわたしをお待ちになって。」賈瑞はそう聞くと、珍宝を得たかのように、急いで尋ねた。「わたしを騙さないでよ。でも、あそこは人通りが多いから、どうしたらうまく隠れられるだろう。」鳳姐は言った。「ご安心なさい。わたし、夜勤の小者たちに皆暇を取らせるから、両側の入口を閉じれば、もう誰も来ないわ。」
賈瑞はそう聞くと、嬉しくてたまらなくなり、慌ただしく別れを告げて出て行ったが、心の内ではうまくいったと思った。夜になるのを待ちかね、果たして真っ暗闇の中を栄国府に手探りで入り込み、門を押すやいなや、穿堂の中に潜り込んだ。果たして漆黒の中に誰一人往き来する者も無く、賈のお婆様のお宅の方の門は既に鍵を閉めて閉ざされ、ただ東向きの門だけが閉まっていなかった。賈瑞は耳をそばだてて聞いていたが、しばらくの間誰もやって来なかった。ふと「ガタン」という音がして、東側の門にも鍵が掛けられた。賈瑞は慌てたが声を上げる勇気が無く、こっそり出て行かざるを得ず、門をゆすってみたが、鉄の桶のように固く閉ざされていた。この時外に出ようとしても、不可能であった。南北はどちらも高い壁で、乗り越えようにもよじ登ることができなかった。この部屋の中は風が吹き抜け、がらんとしていた。今は師走の気候であり、夜も長く、冷たい北風が吹き、肌に染み通り骨を砕くようで、一晩でほぼ凍え死にしかる程であった。なんとか早朝になるのを待ちかねていると、ひとりの老婆が先に東門を開けて入って来て、西門の方を呼ばわったので、賈瑞は老婆の背後から覗き込み、素早く飛び出した。幸いまだ早朝で、人々もまだ起き出していなかったので、裏門(后門)からまっしぐらに家に走って帰った。
元々賈瑞の両親は早く亡くなり、彼の祖父の代儒により教育や養育を受けていた。かの代儒は平素たいへん厳しく教育し、賈瑞があちこち歩き回るのを許さず、彼が外で酒を飲んだり博打をしたりしやしないか、またそれで学業を怠けるのではないかと心配した。今ふと一晩帰って来なかったのを見て、賈瑞がきっと外で酒を飲んでいたのでなければ博打を打つか、女郎を買って一夜共にしているに違いないと思い、鳳姐に騙されて穿堂の中に閉じ込められているなど夢にも思わなかった。そのため、一晩中腹を立てていた。賈瑞も怒られるのを恐れて冷や汗をかき、嘘の言い訳を言わざるを得なくなり、こう言った。「叔父さんの家に行きましたところ、暗くなってしまったので、一晩泊めていただいたのです。」代儒は言った。「元々わたしの許しを得ず勝手に出かけるなど許されないのに、どうして昨日は勝手に出かけたんだ。このことだけでも罰しないといけないのに、ましてや嘘をつくとは。」このため意を決して棒で三四十回叩き、更に飯を食べるのを許さず、彼を中庭に跪かせて文章を読ませ、十日分の宿題を追加でやるように命じ、それが終わってようやく許された。賈瑞は先ず一晩寒さに凍え、また棒で叩かれ、また腹を空かせ、風の吹き抜ける地面に跪いて文章を読まされた。それは筆舌に尽くしがたい苦しみであった。
それでも賈瑞の邪(よこしま)な心は改まらず、また鳳姐が自分のことをからかっているとは思わなかった。二日経って、時間ができたので、また鳳姐を訪ねた。鳳姐はわざと賈瑞が約束を破ったと不満を言ったので、賈瑞は慌てて今度は約束通りにすると誓った。鳳姐は賈瑞が自ら網に飛び込んで来たので、また別の計略で賈瑞に思い知らせてやらないといけないと思い、それでまた賈瑞と約束して言った。「今日の晩、あなた、前の場所に行ってはだめよ、わたしの家の後ろの狭い通路の中の空き家の中で待っていて。――でも出し抜けに頭をぶつけちゃだめよ。」賈瑞は言った。「それは本当なの。」鳳姐は言った。「あなた、信じないなら、来なくていいわ。」賈瑞は言った。「必ず行くから。死んでも行くよ。」鳳姐は言った。「今度はあなたが先にお行きなさい。」賈瑞は夜には全てがうまく行くと確信し、今回は先に帰って行った。鳳姐はここで今晩の布陣を考え、計略を仕掛けた。
かの賈瑞は夜になるのを待ちかねたが、あいにく家には親戚が来るわ、晩飯を食べてからようやく帰られるわで、その日は既に火点し頃となった。更にお爺様がお休みになるのを待って、ようやく栄国府に潜り込み、その路地の中の家に来て待っていたが、まるで熱い鍋の上の蟻のように、そわそわして居ても立ってもいられなかった。ただ、左で待てど人の影が見えず、右で聞き耳を立てても人の声が聞こえず、心中不安になり、絶えず猜疑にかられながら言った。「きっとこれは来ないんじゃないか。またわたしを一晩凍えさせないとだめなのか。……」
ちょうど自らあれこれ猜疑にかられていると、ふと真っ黒の中に人がひとり入って来たので、賈瑞は鳳姐に違いないと思い、黒白構わず、その人が目の前に来るや否や、飢えた虎が食べ物に飛びつき、猫が鼠を捕えるかのように、抱きついて叫んだ。「愛するねえさん、死ぬほどお待ちしていました。」そう言うや、抱きかかえて部屋の中のオンドルの上に行き、キスをしてズボンを引っ張って下ろし、やたらと「愛しいひと」と叫び出した。相手の人はただ声を立てず、賈瑞は自分のズボンを引っ張って下ろすと、硬いものを挿し入れようとした。突然ランプの灯りがきらめき、賈薔が燭台を持ち上げているのが見え、それで照らしながら言った。「誰がこの家の中にいるんだ。」するとオンドルの上のその人が、笑って言った。「瑞叔父さんがわたしを犯そうとしたんだ。」
賈瑞は見えなければそれで済んだのだが、見てしまうと、恥ずかしさの余り、穴があれば入りたいほどであった。――その人は誰あろう、賈蓉であった。賈瑞は身を翻して逃げようとしたが、賈薔にぎゅっと掴まれ、言った。「逃げるな。今、璉叔父さんの奥さん(鳳姐)がもう奥様の前でご報告されているが、おまえがあの方をからかったので、あの方はとりあえずおまえをここにおらせたんだ。奥様はこのことを聞いて激怒され、今回わたしにおまえを捕まえに来させられたんだ。早くわたしと一緒に行くんだ。」賈瑞はこれを聞いて、魂の無い抜け殻のようになり、ただこう言った。「兄さん、お願いだ。わたしが居なかったと言ってくれさえすれば、明日幾重にも重ねてあなたに感謝します。」賈薔は言った。「おまえを放っておいても何の値打ちも無いが、おまえさん、わたしにどれくらい感謝してくれるんだい。ましてや口で言うだけでは何の保証にもならないから、一枚証文を書いてくれないと、割りに合わないね。」賈瑞は言った。「それはどう書いたらいいんだ。」賈薔は言った。「こう書いてくれてもいいよ。博打で負けたので、銀子を若干両借りるものとする、と書けばしまいだ。」賈瑞は言った。「それなら簡単なことだ。」
賈薔は振り向いて出て行くと、紙や筆は有り合わせのものを持って来て、賈瑞に書かせた。彼らふたりは何だかんだ言いながら、ただ五十両の銀子と書き、花押を描くと、賈薔が受け取った。それから賈蓉と片を付けた。賈蓉は最初は歯を食いしばって承知せず、ただこう言った。「明日、一族の人に判断してもらいましょう。」賈瑞は焦って遂には地面に頭をぶつけて(磕頭)謝った。賈薔は何だかんだ言っていたが、五十両の借用証書を書かせて終わりにしてしまった。
賈薔がまた言った。「今おまえを放免したら、わたしは悪事に加担したことになる。お婆様のお宅の方の門はとっくに閉まっている。旦那様はちょうど広間で南京から来たものを見られているので、あちらの通路は通るのが難しい。今は裏門を通るしかない。こう行って、もし人と出逢ったら、わたしも具合が悪い。わたしが先に行って見て来て、それからおまえを連れに来るよ。この家の中は、隠れていられない。しばらくしたらものを積みに来るから、わたしが隠れる場所を捜すのを待ってくれ。」言い終わると、賈瑞を引っ張り、灯りを消したままで、敷地の外に出ると、入口のところの石段の下を手で探り、こう言った。「この窪みの中がいい。じっとしゃがんでいて、声を立てるんじゃないぞ。わたしが戻って来たら、行こう。」そう言うと、ふたりは立ち去った。
賈瑞はこの時、身体の自由が効かず、ただその石段の下にしゃがんでいた。ちょうど頭の中で段取りをつけていると、頭の上の方で「えいやっ」という声が聞こえ、ザザーッと桶一杯の糞尿が頭の上からぶちまけられ、ちょうど賈瑞の全身に注ぎかけられた。賈瑞は我慢できなくなって「ひゃあっ」と声を上げ、慌てて口を塞ぎ、これから敢えて声を出す勇気も無く、頭から顔から糞尿まみれになり、体中が冷たく冷やされブルブル震えた。ふと賈薔が走って来て叫んだ。「早く逃げろ、早く逃げろ。」賈瑞はようやく命拾いしたような気持ちで、急いで裏門から家に走った。時間は既に三更(夜中の12時から2時)を過ぎており、門番を呼んで門を開けてもらうしかなかった。
家人は賈瑞のこの様子を見て、尋ねた。「どうされたんですか。」賈瑞はうそを言わざるを得なかった。「暗くなって、足をすべらせて肥溜めの中に落ちてしまったんだ。」そう言いながら、すぐに自分の部屋に行って着替えて身体を洗ったが、心の中ではようやく鳳姐が彼をからかったのだと分かり、このため一度は彼女を恨んだ。しかしまた鳳姐の容姿の美しさを思うと、またしばらくの間欲しくてたまらないものが手に入らない思いが胸いっぱいに広がり、あれこれ考えていると、一晩中眠りにつくことができなかった。これ以降、鳳姐のことは思っても、栄国府に行く勇気は無かった。

賈蓉たちふたりはしばしばやって来て銀子を要求したが、賈瑞もまたこのことが祖父に知られるのを恐れた。正に鳳姐への思いがなお断ち切れず、おまけに借金をこしらえてしまい、昼間は勉強の課題も厳しくなった。彼は二十歳過ぎであったが、まだ結婚しておらず、鳳姐のことを思うも、思い通りにならないので、自ずと「指先で自慰行為」をすることとなった。しかも二回の凍える寒さと駆けずり回らせる困難に遭い、このように四方八方から攻められ、知らず知らずのうちに病を患うこととなった。――心臓が膨張し、口の味覚を失い、足の下が綿を踏むように力が入らなくなり、眼がチカチカし、夜は熱っぽく、昼間はいつも身体がだるくなった。夢精をしてしまい、痰を吐くと血が混じった。こうした症状が、一年もしないうちに、全て現れた。そして身体を支えることができず、ばったり床に倒れてしまい、精神に異常をきたし、口では常に意味の分からぬことを言い、恐怖心は異常な程だった。なんとかして医者にお願いして治療しようとし、肉桂、付子(トリカブトの根の周囲に付いた小さな塊上のもの)、すっぽんの甲羅、麦冬(ジャノヒゲ)、玉竹(アマドコロ)などの薬を、何十斤も飲んだが、何の効き目も見られなかった。
瞬く間に農暦十二月が終わり新年がやって来たが、この病は益々重くなった。代儒も急いで、あちこちで医者を頼み治療してもらったが、皆効き目が無かった。それでこれから「独産湯」(朝鮮ニンジンと三温糖で作ったスープ)を飲まそうにも、代儒にそんな経済力は無く、栄国府に行ってお願いせざるを得なかった。王夫人は鳳姐に命じて人参を二両量って代儒に与えるよう言った。鳳姐は答えて言った。「先日お婆様のために薬を配合したばかりで、あの人参丸々一本は、楊提督の奥様のお薬として取ってあったのが、あいにく昨日もう人に頼んで持って行かせました。」王夫人は言った。「うちに無いのだったら、人を遣ってあなたのお姑(しゅうとめ)さんのところに行って聞いてあげて。それか珍兄さんのところに有るかもしれないわ。方々尋ねてあげて、それらを合わせて差し上げなさい。ちゃんと飲ませて、人の命を救えば、これもあなたがたの功徳になるわ。」鳳姐は「はい」と答え、しかし人を遣って尋ねには行かせず、ただ少しばかり人参の屑のところを何銭か集め、人に命じて持って行かせた。そしてただこう言わせた。「奥様に命じられて持ってきました。もう他にありません。」それから王夫人にはこう言った。「皆尋ねて来ました。全部合わせて二両余りになりましたので、持って行きました。」
かの賈瑞はこの時何とか生きながらえようと、飲まぬ薬は無く、ただ無駄に金を使うばかりで、効き目は見えなかった。ふとある日びっこの道士(跛足道人 )がやって来て托鉢をし、口では専ら前世からの悪因で起きる病気を治すと称していた。賈瑞は聞かなくてよいものを、あいにく部屋でそれを聞いてしまったので、道士に直に声をかけて言った。「早くその菩薩さまに入って来ていただいて、命を救ってください。」そう言いながらベッドの上で額ずいた。召使たちは道士を連れて来ざるを得なかった。賈瑞はしっかり道士を掴むと、何度も「菩薩様、お助けを。」と叫んだ。かの道士はため息をついて言った。「あなたの病は薬では治すことができません。わたしが持っている宝をあなたに差し上げます。あなたが毎日これを見れば、あなたの命を保つことができます。」そう言うと、袋の中から正面も裏面も人を映すことのできる鏡を取り出し、――背面に「風月宝鑑」の四文字が彫られていた――これを賈瑞に渡して言った。「この鏡は太虚幻境空霊殿から出たもので、警幻仙子が作られ、専ら淫らな性欲や妄想が引き起こす病気の症状を治し、世の中の人々を救済し、生命を保つ効き目があります。それゆえこの鏡が世の中にもたらされたのは、主に聡明で気力に満ち、才能のある人物がこれで映し見て、彼らが淫らな考えや妄想に走るのを防ぐためのものです。くれぐれも鏡の正面を映してはなりません。裏面で映してください。くれぐれもご注意あれ。三日したら、わたしが取りに来ます。あなたの病が良くなること請け合いです。」そう言うと、ぶらぶら歩いて行ってしまった。召使たちはなんとか引き留めようとしたが、適わなかった。
賈瑞は鏡を受け取ると、こう思った。「あの道士は面白いやつだ。早速試しに顔を映してみよう。」そしてかの「宝鑑」を持って来て、鏡の裏面を映して見ると、ひとりの骸骨が中に立っていた。賈瑞は慌てて蓋をし、かの道士を罵った。「このろくでなしめ。わたしを驚かせやがって。――それなら、鏡の正面で映すとどうだろう。」そう思いながら、鏡の正面を映すと、鳳姐が中に立って、彼を手招きしているのが見えた。賈瑞は心の中で大いに喜び、ふわふわと空中に浮いているような気になり、鏡の中に入って行き、鳳姐と男女の営みを行い、鳳姐が彼を送って出て来た。ベッドの上に着くと、「うわっ」と一声発し、眼を開くと、鏡はもう一度向きを変え、相変わらず鏡の裏面ではひとりの骸骨が立っていた。賈瑞は自ら汗びっしょりになるのを感じ、下の方には大量の精液が残っていた。心の中ではそれでも満足できず、また鏡の正面にひっくり返すと、鳳姐がまた手招きして彼を呼ぶので、賈瑞はまた入って行った。このようなことが三四回続いた。最後には、ちょうど鏡から出て来ると、ふたりの男がやって来て、鉄の鎖で賈瑞をくくると、引っ張って行こうとした。賈瑞は叫んだ。「わたしに鏡を取らせて、それから行ってくれ……」これだけ言うと、もはや口をきくことができなくなった。

横で世話をしていた召使が見ると、賈瑞は先にまた鏡を映し見ていたが、鏡を下に落とし、それでもなお眼を見開いて鏡を手で拾ったが、最後には鏡を下に落とし、もう身体が動かなくなった。召使たちが集まって来て様子を見ると、賈瑞はもうこと切れて、身体の下の方は冷たく湿り気で染み通り、大量の精液が残っていた。こうなってから急いで衣裳を着させてベッドから移動させた。代儒夫婦は正気を失うほど泣きぬれ、道士を大声で罵った。「なんといかがわしい道術じゃっ。」遂に人に命じて火を起こしてその鏡を燃やさせた。ふと空中でこう叫ぶのが聞こえた。「誰がやつに正面で映し見させたのか。おまえたち自身がうそを真としていながら、なぜわたしという鏡を燃やすのか。」ふとその鏡が部屋の中から飛び出すのが見えた。代儒が門を出て見ると、やはりあのびっこの道士であり、大声でこう叫んだ。「わたしの「風月宝鑑」を返してくれ。」そう言いながら、鏡を奪い取ると、見る間にふらりと行ってしまった。
当座は代儒はなす術が無く、葬儀の事を執り行うことしかできず、各所にそれを伝えに行った。三日の間お経を読んでもらい、七日目に棺を担ぎ(「發引」。葬送する)、鉄檻寺にお棺を預けた。その後しばらくして、賈家の人々が一斉に弔問に訪れた。栄国府の賈赦は銀二十両を贈り、賈政も二十両、寧国府の賈珍もまた二十両贈った。それ以外の一族の人々は、貧富様々で、ある者は一二両、ある者は三四両と、皆異なった。それ以外にも同じ家塾に通う者の中にも香典を出す者がいて、それらを集めると二三十両になった。代儒の暮らし向きは貧しく質素であったが、これらの香典をもらったお陰で、却って金持ちとなって賈瑞の葬儀を終えた。
思いがけずこの年の冬の終わりに、林如海が伝染病に罹って重体となり、手紙を書いて、特に黛玉に帰宅するよう迎えを寄越した。賈のお婆様はこのことを聞いて、また悲しまれるのを免れなかったが、急いで黛玉に出発する準備をさせざるを得なかった。宝玉は面白くなかったが、父と娘の情愛は如何ともし難く、それを妨げることはできなかった。そして賈のお婆様は賈璉に黛玉を送って行かせると決められ、また事が終われば彼女を連れて帰るよう命じた。土産物や路銀のことなど一切については、くどくど喋るまでもなく、自然と穏当に準備が為された。速やかに日時を選び、賈璉が黛玉と共に人々に別れを告げ、召使たちを連れて、船に乗り揚州に向かった。そして果たしてどうなったか、次回に解説いたします。
次回第十三回では、秦可卿が亡くなり、その葬儀にまつわる話が展開されます。次回をお楽しみに。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます