A.鈴木瑞穂、渡辺美佐子
戦争体験といっても、人により場所により、あるいは年齢によりさまざまなのは当然で、中国大陸や南方での戦場体験、兵士としての軍隊体験だけでなく、戦争末期の空襲体験、疎開体験、さらに戦後の食糧も乏しい生活などまで含めればそれこそ無数の体験が語られ書かれている。なかでも広島と長崎への原爆体験は、一瞬の閃光で亡くなってしまった人はそれを言葉にすることもできなかったわけだが、生き残った人たちは、あまりに悲惨であるゆえにそれをあえて語らなかった、あるいは語ることができなかった人も多い。ただ、爆心地からの距離で原爆体験というものも、語られ方、語り方が変わってくる。
「今年で九十三歳になる鈴木瑞穂は、新劇の大ベテランである。いまから三年前、トークショーで聞いたエピソードが忘れられない。2017(平成29)年1月22日、東京の池袋で開かれた「現代社会とチェーホフ」という会に、九十歳を前にした鈴木が登壇した。さっそく駆けつけた。いまから考えても、ぜいたくなイベントだった。
この日、ベテラン俳優はなにを語ったか――。
1945(昭和20)年8月6日、江田島にある海軍兵学校の生徒(第75期生)だった鈴木は、朝食を終え、モールス信号の授業の準備をしていた。江田島と広島の中心地はおよそ11キロ離れている。
午前8時15分、「ピィーッ」と音を立てたようにまわりが真っ白になり、、地鳴りとともに校舎が揺れた。鈴木はあわてて裏の古鷹山に登った。真北を向くと、向かって左奥に広がる広島湾の空の色がおかしい。声優としても活躍した渋い声で、このように語った(以下は当日の公式記録動画より筆者が活字化した)。
ダークオレンジの、カルメ焼きのような、下から「グーーッ」と盛り上がって、それがもう「スーーッ」と上のほうへのぼっていくんですね。見る間に一万二千メートルくらいの上までいって、上のほうは冷えているんで真っ白になって、きのこ雲ができた。それしか僕らは見なかったんですけど。実際に原爆が落とされた真ん中にいたわけじゃない。十一キロくらい離れていますから。ちょうど、ちょうど、言い方は悪いけれども、見ごろだったですね。ただ、海軍ではそれがわかっていたようで、「生徒は外に出るな。いっさい雨にうたれちゃいかん」、それから「空から降ってきたものに触るな」と言うんで、僕らは外に出られなかったんですけど……。
(劇団銅鑼創立四十五周年記念公演第一弾『彼の町――チェーホフ短編集より―ー』プレイベント「現代社会とチェーホフ」2017年1月22日、ワーカーズコープ会議室)
海から救出に向かった水兵たちは、なすすべもなく江田島に戻ってきた。「広島湾は死体の筏で、すべて埋まっています。オールがききません」。水兵たちから状況を知らされ、若き日の鈴木は言葉をうしなう。そのうち甘酸っぱい、なんと形容していいのかわからない、吸うと吐き気をもよおす死臭が、北から風にのってきた。
その日の日記に鈴木は、こう怒りをぶつけた。「人間が、ここまで人間を貶めることが出来るのか」。
その鮮烈な記憶を目の前で語られると、臨場感がすごい。しかも、あの声でだ。言い方は悪いけれど、ただただ聞き惚れてしまった。この日のトークは、鈴木が出演した劇団銅鑼公演『彼の町――チェーホフ短編集より―ー』のパンフレットに、再構成(抜粋)のかたちで載っている。8月6日の体験が、活字として記録されたことになる。
終戦となった。秋田にいる叔父のもとで暮らした鈴木は、京都大学に入学する。京都での三つの出会いが、その後の人生を決めた。『日本国憲法』、河上肇の「貧乏物語」、そして、チェーホフの『かもめ』。
今日との華頂会館で観た『かもめ』は、劇団民藝の第一回公演である(1950年12月27,28日)。「人間というのは1人ひとり、こんなに多彩な生き方ができるものなのか」戦争しかなかったわが身をかえりみた鈴木は、楽屋を訪ねた。そこに宇野重吉がいたので、芝居で受けた感動を伝えた。「それがきっかけで京大を中退、劇団民藝に入団した。それから今日までずっと、新劇の世界で生きている。
鈴木へのインタビュー記事やエッセイはあるけれど、単著としての自伝、聞き書きの類は、いまのところ一冊も出ていない。お元気なうちに、と思うのは無責任だろうか。
渡邉美佐子は、朗読劇を通じて原爆を語りついでいる。デビューは俳優座で、昭和三十年代の日活映画にたくさん出た。それから今日まで、印象的な舞台、映画、テレビの仕事は数知れない。
全国各地をまわり、手弁当で原爆朗読劇をつづける「夏の会」は、メディアでよく取り上げられてきた。メンバーは、渡辺美佐子、高田敏江、寺田路恵、大原ますみ、岩本多代、日色ともゑ、小山内美那子、柳川慶子、山口果林、大橋芳枝らベテランの女優たちばかり。「夏の会」は、木村光一主宰の地人会(2007年解散)による「この子たちの夏」を受けついで生まれた。毎年夏になると「夏の会」の女優たちが、原爆朗読劇「夏の雲は忘れない」を上演する。あの日の広島と長崎を、それぞれが語る。
2019(令和元)年4月には、ドキュメンタリー映画『誰がために憲法はある』(「誰がために憲法はある」製作運動体)が封切られた。井上淳一監督の本作では、「夏の会」の女優たちを追うとともに、冒頭で渡辺美佐子が『憲法くん』をひとり語りする。『憲法くん』は、政治風刺やパントマイムを得意とする松本ヒロが、「日本国憲法」を擬人化して書いた。およそ十二分間、渡辺が『憲法くん』を語るさまは圧巻だった。
筆者は十年以上、生活協同組合の雑誌で、編集兼ライターの仕事をしている。その連載インタビューで「反戦と平和」がテーマに立ち上がったとき、まっさきに渡辺の名前を挙げた。『誰がために憲法はある』のプロモーションを兼ねて、インタビューできることになった。映画の封切を控えた4月4日の夕方である。
1932(昭和7)年、東京・麻布に生まれた渡辺は、小学生のとき、転校してきた同級生に淡い恋ごころを抱く。「水瀧くん」と呼んだその同級生は、一年もしないうちに姿を消してしまう。渡辺はその消息を、戦後三十五年もたってから知った。
1980(昭和55)年、『小川宏ショー』(フジテレビ)の人気コーナー「初恋談義」に、渡辺が出演することになる。事前にスタッフに挙げた名が「水瀧くん」であった。放送当日スタジオにあらわれたのは、「水瀧くん」ではなく、その両親であった。渡辺はそこで、「水瀧龍男」という本名と、広島の原爆で行方不明になったことを聞かされる。
8月6日の朝、爆心地近くで勤労動員していた旧制広島県立広島第二中学校(現・広島県立広島観音高等学校)一年生(三百二十一名)が犠牲となる。そのひとりに「水瀧くん」がいた。広島二中の悲劇は、1969(昭和44)年に広島テレビがドキュメンタリー化し、『いしぶみ 広島二中一年生 全滅の記録』(ポプラ社、1970年)として出版された。映画『誰がために憲法はある』には、雨のなか、渡辺がひとり「広島二中原爆慰霊碑」に花をたむける姿が映されている。
生協の雑誌インタビューでは、「水瀧くん」のことを訊いた。フジテレビのスタジオでのことを、渡辺はこう話してくれた。
どこか遠い出来事だった原爆が、急に、ドーンと、すごい近いものになりました。広島で二十万人、そうやって数でしか伝えられてこなかったものが、ひじょうにもっと、顔、かたちをもって、近くなったんです。
ご両親は当時、外地にいらしたそうです。せっかく疎開させた広島で、息子が消えてしまった。ご両親は三十五年間、そのつらさを背負っていらした。私が「会いたいな」と思ったばっかりに、悲しいことを思い出させてしまった。「本当に申し訳ありません」とその時申し上げたんです。
ご両親は、こうおっしゃいました。「私たちは各地を転々としていたので、龍男には友だちができる暇もありませんでした。あの子が生きていたことを知るのは、私たち家族と親戚だけです。三十五年も覚えていただいて、本当にありがとうございます」と。本当につらかったです。 (「のんびるインタビュー『戦争を知る私たちが語り、撒く、平和の種』」『のんびる』2019年7月号、パルシステム生活協同組合連合会)
これまでに本や雑誌を通して、いろいろな俳優の戦争体験に接してきた。しかし、取材のかたちで話を聞くことが出来たのは、渡辺美佐子ただひとりである。「水瀧くん」のエピソードは、渡辺の自伝エッセイ『ひとり旅 一人芝居』(講談社、1987年)に書かれている。インタビューなどでも、たびたび語られてきた。
でも、こうして目の前で語られると、重く、せつない。凛とした佇まいをくずさず、言葉をえらぶようにして語る姿に、緊張というか、気おくれしてしまった。
原爆朗読劇を続けてきた私たちは、戦争を経験しています。戦争を知らない世代が語る「平和」という響きと、戦争を知る世代が語る「平和」という響きは、中身がかなり違っているはずです。若い方たちにとっては、「平和」と言っても比べようがないですよね。私たちは、比べるものをもっています。平和がどんなにすばらしくて、大事なものか、わかっています。 (前掲書)
この日の取材時間は二十五分しかなかった。果たしてこのボリュームで記事にまとめることができるのか。不安しかなかった。「一つひとつの言葉を、大切に語るかたでしたね」、取材後、撮影をお願いした若い写真家が言った。
翌日、一言一句ていねいに、録音を活字に起こした。すると、カットできるところがない。血のかよった言葉はすごい、と痛感した。
原爆朗読劇「夏の雲は忘れない」は、2019年の夏をもって公演を終えた。「夏の会」の女優たちには、変わらぬ反戦への意志、平和への祈りがある。とはいえ、企画、台本の準備、告知、稽古、チケットの販売にいたるまで、自分たちですべておこなうため、大きな負担になっていた。それでやむなく、「夏の会」に終止符をうったのである。
「夏の会」の活動は、映画『誰がために憲法はある』と、NHK・BS1のドキュメンタリー「女優たちの終らない夏 終われない夏」(2019年11月10日放送)にまとめられた。朗読を通して反戦と平和を訴えた、女優たちの貴重な記録となる。
「ずっとつづけている朗読の会では、原爆朗読劇のいくつかを、レパートリーに加えたい」取材の最後、渡辺はそう言った。」濱田研吾『俳優と戦争と活字と』ちくま文庫、2020年、pp.342―350.
戦争体験は、その時代を生きていた自分の「当事者としての視点」で振り返っているか、自分も生きていた時代だが、犠牲になった人びとへの「生き残った自分から犠牲者への視点」で眺めるかで、かなり色合いが違ってくる。鈴木瑞穂さんの広島原爆体験は、あくまで11キロ離れた距離にいた視点である。しかし、それは忘れることのできない、しかも何もできなかったという体験である。なぜ原爆が落とされたか、その死者たちはなぜ無残な死を引き受けさせられたのか、それは語ることによって、体験していないわれわれにも重大な意味をもつ。そして、渡辺美佐子さんの体験は、なんと戦後35年経って、たまたま小学校の同級生が広島で亡くなったことを知ったことから、原爆を語
る朗読を始める、という活動になる。それまでは、広島原爆はごく一般的な歴史のお話しとしてしか考えていなかったことが、具体的な個人の体験として、自分の戦争体験に蘇ったというわけだ。こういうことは、おそらくいろいろ他にもあるのだろう。

B.死に立ち会うこと
ぼくは両親の死を少し間をおいて十年ほど前までに体験した。その前後に、親しかった同年代の友人の死も相次いで経験した。母の死は、直前まで普通に暮らしていて、ある夜風呂場で眠るように亡くなってしまったので、心の準備も動揺も感じる暇がなく、ただ救急車に一緒に乗って病院で死を確認しただけだった。あっけにとられて、涙も出ず、ただ残された父のことだけ心配しながら葬式の手配をしなければと考えていた。逆に父の死は、だんだん身体が衰えてきて、2年位かかって寝たきりになり、最後はぼくと弟で交代で胃ろうを一日2回点滴しながら、意識もしだいにあいまいになっていったので、いわば「死」への緩慢なプロセスを毎日見ていたから、最後に病院で臨終となっても、ほぼ予想された通りのこととして、これもまったく平常に遺体を寺まで運び、葬式をすませて悲しみはなかった。ぼくにとって、両親の死は比較的平穏に、つまり母はあまりに突然ぽっくりであり、父は時間をかけた想定の範囲内で、ぼくにとって特別なこととは思わなかった。それはたぶん、父母への追悼や慰霊というものを別の形でやろうと決めていたからだ。
でも、親しい死者との別れがじゅうぶんにできなかった人の場合は、そのような精神の落ち着き方は難しいのだろう。ぼくたちは、ふだん自分が生きるのに忙しく、親しく大事な他者とゆっくり話をする余裕がない。急にこの世から消えた人と、もっと話しておくこと、もっと一緒に過ごしておきたかった時間、というものは失われてからつた身をともなって迫ってくる。
「インタビュー 今考える「死」とは ノンフィクション作家 柳田邦男 さん
コロナ患者の最期 さよなら言えずに 家族の残る喪失感 ;年間150万人以上が死ぬと予測される「多死社会」を前に、日本は新型コロナという予想せぬ災禍にも襲われた。私たちは今、死の意味が変わりつつある時代の中にいるのだろうか。事故や災害、病気などによる人間の生死の問題を、60年も現場から描き続けてきたノンフィクション作家の柳田邦男さん(84)に聞いた。
――月刊誌に発表したルポで、新型コロナによる死を「さよならのない死」と意味づけました。「コロナでは、入院した患者が家族と一度も会えないまま、亡くなった例が多くありました。『さよなら』を言えなかった死別は、残された家族の心に複雑なトラウマを生じさせることがあります。そんな問題意識を持ちつつ、コロナ患者を受け入れた病院関係者を中心に取材を始めました」
――志村けんさんも発症から約2週間で亡くなりました。みとれなかった肉親は遺骨の入った箱でやっと再会できた、と。
「志村さんの死は衝撃的で、コロナ氏の特異性を痛感しました。入院後、すぐ重症化し死に至るという点では突然死に近く、災害や事故、事件で突然、身近な人間を失ってしまう死別に近いです。米国のミネソタ大学のポーリン・ボス名誉教授の言う「あいまいな喪失」(ambiguous loss)に該当します。生きているか死んでいるかわからない別れという意味です。みとれずに遺骨だけが戻っても、華族はあいまいな喪失感を抱えたまま、葛藤に苦しむことがあります」
< 中 略 >
―ー「共存性」で思い出すのは、柳田さんの作品「犠牲(サクリファイス)」です。脳死になった次男洋二郎さんと11日間、病室で時間を過ごしながら、気持ちを通わせる様子が描かれています。
「27年前です。25歳の息子が脳死状態になって死亡診断が下るまで11日間ありました。表情の変化は全くなく、人工呼吸器の力で生きている。医学的な見方では『死』になるのです。ただ私たち親子には、共有した人生の数限りない記憶があります。ベッドの息子を医学的には『死者』だと、割り切れるものではありません。2人で無言の会話をしていました」
―ー脳死状態でも、それは「会話」と感じ取られたのですね。
「息子は『おやじは作家だというなら、人の心の苦しみがわかっているのか』などと再現なく語りかけてきました。科学的には妄想と片付けられるかもしれません。でも、だから意味がないわけではないし、人間の生死や生きる力は、医学や科学の実証主義でつかみきれるものではありません」
――事実を丹念に突き上げ、事件や事故の全体像を浮かび上がらせる。そうした柳田さんの事実に対する姿勢がこの出来事を契機に変わっていったのでしょうか。
「私はノンフィクション作家として事実にこだわり続け、『事実の時代に』や『事実の読み方』などの作品も書きました。事件や事故取材で、実証主義に基づき証拠を積み上げ、全体の構造をつかんで問題点を指摘する。そこで重要なのは根拠となる事実です。ただ、早くから『事実と事実主義は違う』とも書いてきました。科学と化学主義も違う。とりわけ人間の命や心に関しては、証拠で実証しなければ真実ではないとする事実主義や化学主義の外に、重要な真実があると思います」
――どういうことでしょうか。
「コロナ患者を受け入れた病院が感染防止だけを考えるなら、患者と会いたい家族は邪魔になる。化学主義を突き詰めればそれが結論です。でもたとえ重症化した人でも、ウイルスと治療の拮抗関係の中にだけ生命があるわけではない。医学的な命とは別に、家族や恋人など人間関係による心の営みが生きる上で不可欠です。それは証明が必要な話ではありません」
――戦後ずっと「死は無意味である」という考え方が、支配的だったように思えます。
「時代傾向ですね。1988年に元検事総長が書いた『人は死ねばゴミになる』という本が出版され、ずいぶん読まれました。この題は象徴的で、私には一つの戦後遺産のように思えました」
―ー「戦後遺産」ですか。
「日本は戦後、米国の工業生産力と科学技術との圧倒的な差で戦争に負けたと認識し、科学技術への信仰が生まれました。次第に魂や精神性は軽んじられ、『人は死んだらゴミ同然』といった時代思潮が支配的になったのです。しかし、80年代になると、医療の中で、生と死を二元論的に分けず、死を生の中でとらえなおす『死の臨床』という取り組みが広がり始めました。死にゆく人と残された家族の双方にとって何が大切なのか、という観点が重視されるようになったのです」
―ー「死の臨床」の考え方は現在の医療に、どんな形で反映されているのでしょうか。
「95年の阪神・淡路大震災では、救急隊が死傷者を区別なく病院に搬送した結果、重傷者が後回しになる事態が起きました。この反省から搬送に優先順位をつける『トリアージ』が導入され、2005年のJR福知山線脱線転覆事故では救える重傷者を優先した。ところが死亡を示す黒タグをつけられて安置所に運ばれた犠牲者の肉親が何の治療も去れなかった無念でトラウマになった事例が報告され、その後、死者の遺族のケアにあたる『災害死亡者家族支援チーム』(DMORT)が発足しました。医療が『死ねばゴミ同然』で生のみを対象にするならば、扱わない問題でしょう」
――テクノロジーの急激な進歩が死の意味を変えないでしょうか。死者をVR(仮想現実)でよみがえらせて「再会」させる技術が進んでいると聞きます。
「それは『再会』とは違う。津波で子供が行方不明になった親が、海岸でよく子供の幻影を見ました。『幽霊を見ました』と本人は言いますが、そうして現れる行方不明者の幻影を見る方が、テクノロジーで作り上げた精巧な映像よりも『再会』に近いと思います。詩人の長田弘さんは『記憶とは現在だ』と詩に書いています。相手を思い返す現在の自分の中に、亡き人は生きているのです」
――たとえ技術的な幻影だとしてももう一度会いたい、という気持ちをもつ人もいるのでは。
「僭越なので人の気持ちまで論評したくはありません。映画「鬼滅の刃」は見ましたか」
―ーはい、見ました。
「あの映画では、何度か登場人物の亡くなったお母さんの幻影が現れ、語りかけてきます。単なる回想場面とは違い、生々しく目の前に現れて話をするのですね。私の瞼の裏にもいまも亡き息子が出てきます。人工的に作った仮想現実とは違います」
―ーぶしつけな質問をさせてください。テクノロジーが人工的な洋二郎さんを完璧に再現しても、「再会」に興味はありませんか。
「気持ち悪いですね。ただ、仮想現実と現実が区別できない時代がいずれ来るかも知れない。小学校4年生の孫はうちに来ると、スマホを使って30分で短編小説を書いてしまう。文脈に乱れがなく、落ちもあって面白いんです。机で原稿用紙に向かう私とは危機との関係性が全然違う。テクノロジーが人間の五感を変える時代がやって来て、死の受け止め方まで変えてしまうかもしれません」 (聞き手・中島鉄郎)」朝日新聞2020年12月3日朝刊13面オピニオン欄。
ぼくも、ヴァーチャルな仮想現実、テクノロジーで作り出す死者の幻影など、気持ち悪いとしか思えない。かけがえのない死者の悼み方というものは、その人の意きた生の全体を、想像してみる必要があると思う。それは写真や映像の一瞬の姿ではなく、ある長い生を生きていた人間そのもののリアリティに、たとえ手が届かなくても、想像力で思いを馳せる以外に、生き残っている者にとって死というものの意味はありえない。
















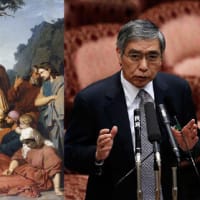









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます