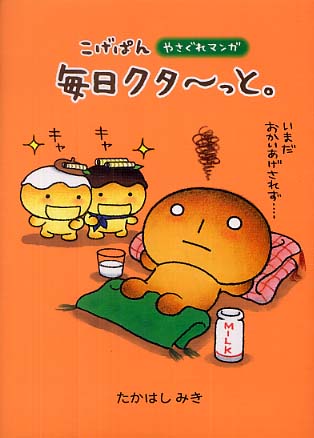どなたのブログで知ったのか、今では忘れてしまったのですが「国マニア」という本があります。

Amazonだったか、楽天だったか期限付きポイントの利用案内メールに乗せられて、一月ほど前に急遽購入してありました。
まぁ、お話の引き出しが増えるかなとあまり期待していませんでしたが、パラパラと読んでみると、意外にこれが面白いんです。(著者には失礼な物言いですが…)
独立国がすべて、軍隊を持っているかというと、外交・防衛を近隣大国にすべて任せてしまってある国が紹介されていたりして、思わず腕組みをしてしまいます。
「国って何なのだろうか…」
サブタイトルに
「世界の珍国、奇妙な地域へ!」とあるように
政治向き、社会問題に興味を持っていない方でも、「ねぇねぇ知ってる~」ってなノリで知人に紹介できるので、幅広い層に読後の満足感があるような気がします。
腹を抱えて笑ってしまう「国のかたち」(当該国には失礼)もあれば、
小国ながらも、したたかな戦略に感心させられる「国のかたち」もあって、
その意味では、深い取材力と巧い文章構成力は、さすがマスコミ関係者(だったはず)ですね。
そういえば、先日NHKの3点ドキュメントで話題となった「ツバル」についても、触れられていました。
こんな状態でも国家として成り立ち得るという、あまりにも多様な「国のかたち」を紹介されると、我々が如何に既成概念に囚われて国家・地域を語っているか反省至極です。
行政関係の方、地域振興を考える立場の方には「必読の書」に近いのではないでしょうか。
さて、珍妙な国と地域のお話は「国マニア」を読んで頂くことにして、ここではちょいと違う角度から、思ったことをご紹介させて頂きます。
ディズニー映画の「ナルニア国物語」と勘違いしてしまった(…(^^;ゞ…)「ナウル共和国」のお話です。
章のサブタイトルには、「国がまるごと音信不通になった、とんでもない島」とあります。(以降、「」内引用部分、数字・単位などブログに合うよう引用者加筆)
「南太平洋に浮かぶナウル共和国は、面積わずか21Km^2で、島一つだけの国。バチカン、モナコに次ぐ世界で三番目に小さい国だ。人口13,000人弱のうちナウル人は58%で、残りは出稼ぎの外国人。町と呼べるような場所もなく、世界で唯一、公式の首都すらない国…」とくると、一体全体国の体をなしているのか…と不思議な気がしてきます。
ナウルがこんな状態でも成立したのは「島全体が燐鉱石の山」だったからで、貴重な肥料となるその輸出でナウル人一人当たりのGDPはアメリカやドイツ並みだったとか。
かつては、素朴な漁民の島だったようですが、植民地支配などの時代を経て、独立後は鉱山会社からの収入で「税金や教育費がタダなのはもちろん、国民には年金が支給されて何もしなくてもお金がもらえる。ナウル人は魚も捕らなくなり、三度の食事すらも中国人が経営するレストランですませて料理さえも作らないようになり、行政はすべて西サモアなどから雇ってきた外国人に任せ、『働いている国民は、18人の国会議員くらい』とまでいわれる国になった。」そうです。
ところが、自分たちが拠って立っている地面を掘り返して食いつぶしているのですから、資源はいつか枯渇します。
ついに、その時がやってきて、2003年。
労働者への賃金未払いが発端となって暴動が発生。1台だけあった「国際通話が可能な電話機が壊れたため」サブタイトルのような事態に。
「見かねたオーストラリア政府が『ナウル人全員にオーストラリアの市民権をプレゼント』」という申し出を民族自立を理由に断り、「世界各国からの援助に頼って取りあえず生き延びている。」状態なのだそうです。(日本からも1億円の無償援助が決まっているとか)
ところが、この期に及んでもまだ国民は働こうとしていないようで、「100年近く遊び暮らし、糖尿病に罹った国民の比率が世界一高いといわれるナウル人たちが、『体を動かさないと生活できない』と悟る日は来るのだろうか?」と著者は締めくくっています。
かつて働いたことがある世代の人は、昔を思い出しながら何とかできるかも知れません。
しかし、生まれてこの方、一度も働いたことがない人は、果たして「働いて生活する」ということが肌感覚で理解できるものなのでしょうか?
しかも、この状態が100年以上ということは、ほぼ全員が産まれて以来働いた経験を持たない人々…
このブログと交流をさせて頂いている「ぜん」さんが「なぜ働くのか(2006.06.05~)」シリーズ最後の「番外編(2006.06.14)」で、いみじくも
「自らの務めとして働く」
と示されています。
ナウル共和国の国民の暮らしぶりと、この国での暮らしぶりを眺めると、この指摘の深さを感じずには、おられません。
中国には労働を善とする価値観が伝統的にあると、何方かから伺ったことがあります。それが儒教や中国での仏教の発展に沁み込み東アジア全体に流れているとしたら、いまさらながら途方もない時間と、その間を往来した人々の膨大な数や暮らしに、想いを寄せてしまいます。
独断と偏見かも知れませんが西洋文明はどうも「労働は忌避すべきもの」と考えていたような気がしてなりません。
この考え方だと「遊ぶ(ために必要なお金を稼ぐ)ために働く」ことになります。
目的と手段が正反対。
これでは、「働いている時間は苦役以外の何者でもなく、当然その時間は幸福なはずがない」と思うのは、考えすぎ。
でしょうか。
働くことと、幸福であることが矛盾しないような「暮らしのかたち」と「世の中のかたち」。
実現できたらいいなぁ~と、素朴に思うのです。
まだ、全部読んではいませんが、ちょっとした時間が空いたときに、気楽に読めるので(ナウルの章は気楽に読めませんでしたが…(^^;)いつも鞄に入れて持ち歩き、長~い時間を掛けて拾い読みする本になりそうです。

Amazonだったか、楽天だったか期限付きポイントの利用案内メールに乗せられて、一月ほど前に急遽購入してありました。
まぁ、お話の引き出しが増えるかなとあまり期待していませんでしたが、パラパラと読んでみると、意外にこれが面白いんです。(著者には失礼な物言いですが…)
独立国がすべて、軍隊を持っているかというと、外交・防衛を近隣大国にすべて任せてしまってある国が紹介されていたりして、思わず腕組みをしてしまいます。
「国って何なのだろうか…」
サブタイトルに
「世界の珍国、奇妙な地域へ!」とあるように
政治向き、社会問題に興味を持っていない方でも、「ねぇねぇ知ってる~」ってなノリで知人に紹介できるので、幅広い層に読後の満足感があるような気がします。
腹を抱えて笑ってしまう「国のかたち」(当該国には失礼)もあれば、
小国ながらも、したたかな戦略に感心させられる「国のかたち」もあって、
その意味では、深い取材力と巧い文章構成力は、さすがマスコミ関係者(だったはず)ですね。
そういえば、先日NHKの3点ドキュメントで話題となった「ツバル」についても、触れられていました。
こんな状態でも国家として成り立ち得るという、あまりにも多様な「国のかたち」を紹介されると、我々が如何に既成概念に囚われて国家・地域を語っているか反省至極です。
行政関係の方、地域振興を考える立場の方には「必読の書」に近いのではないでしょうか。
さて、珍妙な国と地域のお話は「国マニア」を読んで頂くことにして、ここではちょいと違う角度から、思ったことをご紹介させて頂きます。
ディズニー映画の「ナルニア国物語」と勘違いしてしまった(…(^^;ゞ…)「ナウル共和国」のお話です。
章のサブタイトルには、「国がまるごと音信不通になった、とんでもない島」とあります。(以降、「」内引用部分、数字・単位などブログに合うよう引用者加筆)
「南太平洋に浮かぶナウル共和国は、面積わずか21Km^2で、島一つだけの国。バチカン、モナコに次ぐ世界で三番目に小さい国だ。人口13,000人弱のうちナウル人は58%で、残りは出稼ぎの外国人。町と呼べるような場所もなく、世界で唯一、公式の首都すらない国…」とくると、一体全体国の体をなしているのか…と不思議な気がしてきます。
ナウルがこんな状態でも成立したのは「島全体が燐鉱石の山」だったからで、貴重な肥料となるその輸出でナウル人一人当たりのGDPはアメリカやドイツ並みだったとか。
かつては、素朴な漁民の島だったようですが、植民地支配などの時代を経て、独立後は鉱山会社からの収入で「税金や教育費がタダなのはもちろん、国民には年金が支給されて何もしなくてもお金がもらえる。ナウル人は魚も捕らなくなり、三度の食事すらも中国人が経営するレストランですませて料理さえも作らないようになり、行政はすべて西サモアなどから雇ってきた外国人に任せ、『働いている国民は、18人の国会議員くらい』とまでいわれる国になった。」そうです。
ところが、自分たちが拠って立っている地面を掘り返して食いつぶしているのですから、資源はいつか枯渇します。
ついに、その時がやってきて、2003年。
労働者への賃金未払いが発端となって暴動が発生。1台だけあった「国際通話が可能な電話機が壊れたため」サブタイトルのような事態に。
「見かねたオーストラリア政府が『ナウル人全員にオーストラリアの市民権をプレゼント』」という申し出を民族自立を理由に断り、「世界各国からの援助に頼って取りあえず生き延びている。」状態なのだそうです。(日本からも1億円の無償援助が決まっているとか)
ところが、この期に及んでもまだ国民は働こうとしていないようで、「100年近く遊び暮らし、糖尿病に罹った国民の比率が世界一高いといわれるナウル人たちが、『体を動かさないと生活できない』と悟る日は来るのだろうか?」と著者は締めくくっています。
かつて働いたことがある世代の人は、昔を思い出しながら何とかできるかも知れません。
しかし、生まれてこの方、一度も働いたことがない人は、果たして「働いて生活する」ということが肌感覚で理解できるものなのでしょうか?
しかも、この状態が100年以上ということは、ほぼ全員が産まれて以来働いた経験を持たない人々…
このブログと交流をさせて頂いている「ぜん」さんが「なぜ働くのか(2006.06.05~)」シリーズ最後の「番外編(2006.06.14)」で、いみじくも
「自らの務めとして働く」
と示されています。
ナウル共和国の国民の暮らしぶりと、この国での暮らしぶりを眺めると、この指摘の深さを感じずには、おられません。
中国には労働を善とする価値観が伝統的にあると、何方かから伺ったことがあります。それが儒教や中国での仏教の発展に沁み込み東アジア全体に流れているとしたら、いまさらながら途方もない時間と、その間を往来した人々の膨大な数や暮らしに、想いを寄せてしまいます。
独断と偏見かも知れませんが西洋文明はどうも「労働は忌避すべきもの」と考えていたような気がしてなりません。
この考え方だと「遊ぶ(ために必要なお金を稼ぐ)ために働く」ことになります。
目的と手段が正反対。
これでは、「働いている時間は苦役以外の何者でもなく、当然その時間は幸福なはずがない」と思うのは、考えすぎ。
でしょうか。
働くことと、幸福であることが矛盾しないような「暮らしのかたち」と「世の中のかたち」。
実現できたらいいなぁ~と、素朴に思うのです。
まだ、全部読んではいませんが、ちょっとした時間が空いたときに、気楽に読めるので(ナウルの章は気楽に読めませんでしたが…(^^;)いつも鞄に入れて持ち歩き、長~い時間を掛けて拾い読みする本になりそうです。