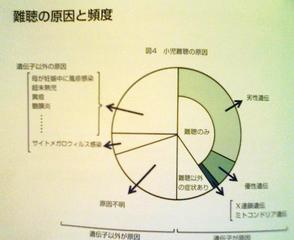昨日は、協会のクリスマス例会だった。ゲストから難聴者の手話について誤解の甚だしいことを思い知らされた。
一人は、手話落語で有名な方らしいが、難聴者に対して手話が分からない人は表情でイメージしてくれと言う。いくら何でも仲間と声と身振りに近い手話で会話している会員には手話だけでは無理だ。磁気ループ用のピンマイクのワイヤレスマイクをつけて声を出してもらったが当初は声も出さない予定だったらしい。
さらに要約筆記者がいるにも関わらず、要約筆記はするなと言って使わせなかった。
難聴者協会の会員、難聴者対象の手話講習会を受講中の人々は2年学んで手話だけでコミュニケーション出来る人はまだ少ない。
みな声と口型、手話でコミュニケーションしている。相手が怪訝な素振りをすればもう一度ゆっくり話したり、筆談、指文字で表す。自然とそうするのだ。難聴者のコミュニケーションは。
もう一つのボランティアグループは長いことろう者と接してきたかもしれないが、難聴者との交流は少ないのか、手話で歌う時に最初マイクをつけてくれなかった。難聴者が手話を使うというのは音声、口型と必ず一緒だと言うことが理解されない。
ナレーションはマイクに話してもらったが効果音のCDラジカセの音が大きい。マイクを離してもらったがこれでは聞こえないのでは口が動いているのが読みとれる。難聴者は声を聞いている時に他の音や声が重なるととたんに聞こえが悪くなることが理解されていない。
ろう者に対して演じる時は音が大きくてもかまわない。健聴者はナレーションと効果音が重なっても聞き分けることが出来る。難聴者はそれが出来ないのだ。
会場の何人かに聞いてみた。やはりあのしゃべりの早さでは磁気ループがあっても落語は難しかったようだ。
例会実行委員会は、難聴者に「理解」があって出演してくれた人たちに、そこまで難聴者のコミュニケーションを理解してもらうのに多少遠慮もあったのだろう。時間があればもっと関わってあげたかった。
今年最後の例会に寂しい思いをさせてすまなかった。
難聴者も「絆」を大切にすること、ここに一緒にいることになった「きっかけ」を皆と分かち合うことを前ロールに書いて話した。
来年も「絆」を強め、広げよう。たくさんの出会いの「きっかけ」を作ろう。
ラビット 記
※写真は、膝のリハビリに使っている高周波の機械。
一人は、手話落語で有名な方らしいが、難聴者に対して手話が分からない人は表情でイメージしてくれと言う。いくら何でも仲間と声と身振りに近い手話で会話している会員には手話だけでは無理だ。磁気ループ用のピンマイクのワイヤレスマイクをつけて声を出してもらったが当初は声も出さない予定だったらしい。
さらに要約筆記者がいるにも関わらず、要約筆記はするなと言って使わせなかった。
難聴者協会の会員、難聴者対象の手話講習会を受講中の人々は2年学んで手話だけでコミュニケーション出来る人はまだ少ない。
みな声と口型、手話でコミュニケーションしている。相手が怪訝な素振りをすればもう一度ゆっくり話したり、筆談、指文字で表す。自然とそうするのだ。難聴者のコミュニケーションは。
もう一つのボランティアグループは長いことろう者と接してきたかもしれないが、難聴者との交流は少ないのか、手話で歌う時に最初マイクをつけてくれなかった。難聴者が手話を使うというのは音声、口型と必ず一緒だと言うことが理解されない。
ナレーションはマイクに話してもらったが効果音のCDラジカセの音が大きい。マイクを離してもらったがこれでは聞こえないのでは口が動いているのが読みとれる。難聴者は声を聞いている時に他の音や声が重なるととたんに聞こえが悪くなることが理解されていない。
ろう者に対して演じる時は音が大きくてもかまわない。健聴者はナレーションと効果音が重なっても聞き分けることが出来る。難聴者はそれが出来ないのだ。
会場の何人かに聞いてみた。やはりあのしゃべりの早さでは磁気ループがあっても落語は難しかったようだ。
例会実行委員会は、難聴者に「理解」があって出演してくれた人たちに、そこまで難聴者のコミュニケーションを理解してもらうのに多少遠慮もあったのだろう。時間があればもっと関わってあげたかった。
今年最後の例会に寂しい思いをさせてすまなかった。
難聴者も「絆」を大切にすること、ここに一緒にいることになった「きっかけ」を皆と分かち合うことを前ロールに書いて話した。
来年も「絆」を強め、広げよう。たくさんの出会いの「きっかけ」を作ろう。
ラビット 記
※写真は、膝のリハビリに使っている高周波の機械。