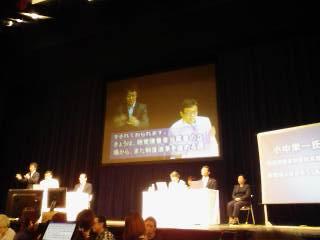自公民による障害者基本法改正案の内容はまた紹介するが、管首相おろしの陰の狙いが大増税による社会福祉の切り下げ、国民生活の破壊、TPPの強行、普天間基地の存続などの大連立にあることが透けて見えるだけに、その条文の裏を見通したい。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆1◆ 民主・自民・公明、「障害者基本法改正案の修正案」を合意
添付したPDF(ラビット:省略)は、民主・自民・公明党で合意した障害者基本法改正案の修正案です。
6月15日(水)に衆議院内閣委員会で審議入りが濃厚とのことですが、国会の会期末は22日(水)で終了の方向が強くなっているそうです。
民主党は会期内成立をと考えているので、即日審議・採決の可能性もあるとの見方も聞いています。
━━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2011.6.10 第130号(通巻238)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━━
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆1◆ 民主・自民・公明、「障害者基本法改正案の修正案」を合意
添付したPDF(ラビット:省略)は、民主・自民・公明党で合意した障害者基本法改正案の修正案です。
6月15日(水)に衆議院内閣委員会で審議入りが濃厚とのことですが、国会の会期末は22日(水)で終了の方向が強くなっているそうです。
民主党は会期内成立をと考えているので、即日審議・採決の可能性もあるとの見方も聞いています。
━━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2011.6.10 第130号(通巻238)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━━