高擶地区は、天童市役所の南西約5kmのところ
県道24号線の北側に八幡神社が南向き参道で鎮座します
前の県道の側道に 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました



参道入口です

郷社 八幡神社です
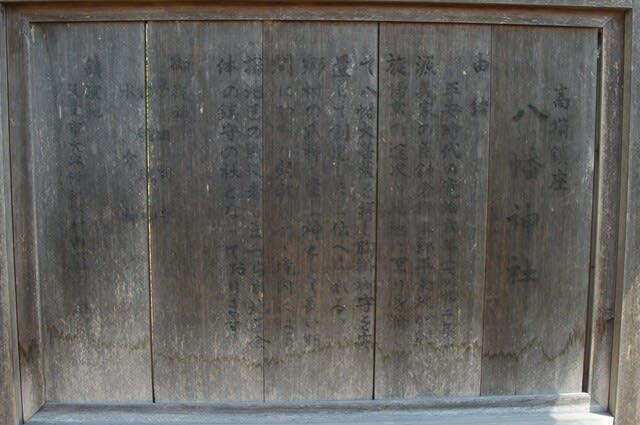
説明板です
高擶鎮座
八幡神社
由緒書ですが良く見えません・・・

後利益表皮板です

高擶(たかだま)地区、清池(しょうげ)の地名由来版です




鳥居脇にはケヤキの大木です





南側道路から

杉とケヤキの並木の参道です

説明板です
八幡神社社叢
天童市指定天然記念物
平成10年3月26日指定
八幡神社境内5091.9㎡の社叢は、樹目が鬱蒼と茂っていて、地域の何処から見ても一際目立つ社である。この社叢を構成している植物は、目通し幹周り5.64m、5.53m、5.42mなど12本のケヤキの巨木群をはじめ、目通し幹周り2.74m、2.59m、2.51mの杉の巨木群や、八幡神社の御神木となっている目通し幹周り3.74mのイチョウの巨木、そしてエノキ、コブシ、ケンポナシ、クヌギ、アベマキ、モミ、カシノキなど数多くの高木があり、いずれも見事に育っている。なかでもコブシの高木群は珍しい。また、アオキ、ガマズミ、マユミ、ヤマブキ、ムクゲ、カエデ、などの低木や下草なども良く育っている。
八幡神社は、寛治6年(1092)、源義家の臣相模の住人・鎌倉権五郎平景政の創建によると伝えられる。本殿の裏側に、清池の地名の源となったといわれる、目を射られた景政が矢を抜き、目を洗った御手洗池がある。御神木のイチョウの木は、天正の昔、天童家家臣土屋某氏が武運長久祈願のため当八幡神社に参詣の折りにお手植えしたものと伝えられている。
境内は、神域としてよく保護、維持されてきたことから、多様な植物が豊富に、しかも昔の姿のままに保たれており、市内に例の無い極めて貴重な社叢である。
平成25年1月31日
天童市教育委員会
高擶地域づくり委員会

手水舎です

手水舎の脇には由緒ある石神様が在ります

石神様です

説明板です


狛犬です

拝殿です

本殿です

本殿裏側に御手洗池です

御手洗池の石碑です



ケヤキの巨木です



かなり斜めに成っています



側から




北側から




境内のケヤキです




北側から





社殿脇のケヤキです
では、次へ行きましょう

県道24号線の北側に八幡神社が南向き参道で鎮座します
前の県道の側道に
 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました


参道入口です


郷社 八幡神社です

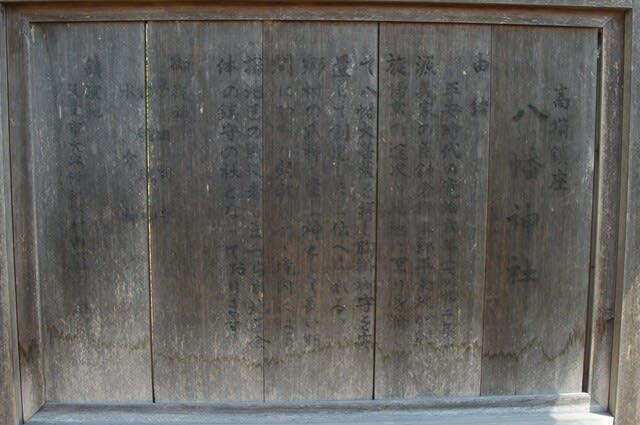
説明板です
高擶鎮座
八幡神社
由緒書ですが良く見えません・・・

後利益表皮板です


高擶(たかだま)地区、清池(しょうげ)の地名由来版です





鳥居脇にはケヤキの大木です






南側道路から


杉とケヤキの並木の参道です


説明板です
八幡神社社叢
天童市指定天然記念物
平成10年3月26日指定
八幡神社境内5091.9㎡の社叢は、樹目が鬱蒼と茂っていて、地域の何処から見ても一際目立つ社である。この社叢を構成している植物は、目通し幹周り5.64m、5.53m、5.42mなど12本のケヤキの巨木群をはじめ、目通し幹周り2.74m、2.59m、2.51mの杉の巨木群や、八幡神社の御神木となっている目通し幹周り3.74mのイチョウの巨木、そしてエノキ、コブシ、ケンポナシ、クヌギ、アベマキ、モミ、カシノキなど数多くの高木があり、いずれも見事に育っている。なかでもコブシの高木群は珍しい。また、アオキ、ガマズミ、マユミ、ヤマブキ、ムクゲ、カエデ、などの低木や下草なども良く育っている。
八幡神社は、寛治6年(1092)、源義家の臣相模の住人・鎌倉権五郎平景政の創建によると伝えられる。本殿の裏側に、清池の地名の源となったといわれる、目を射られた景政が矢を抜き、目を洗った御手洗池がある。御神木のイチョウの木は、天正の昔、天童家家臣土屋某氏が武運長久祈願のため当八幡神社に参詣の折りにお手植えしたものと伝えられている。
境内は、神域としてよく保護、維持されてきたことから、多様な植物が豊富に、しかも昔の姿のままに保たれており、市内に例の無い極めて貴重な社叢である。
平成25年1月31日
天童市教育委員会
高擶地域づくり委員会

手水舎です


手水舎の脇には由緒ある石神様が在ります


石神様です

説明板です


狛犬です


拝殿です


本殿です


本殿裏側に御手洗池です


御手洗池の石碑です



ケヤキの巨木です




かなり斜めに成っています




側から





北側から





境内のケヤキです





北側から






社殿脇のケヤキです

では、次へ行きましょう





















































































