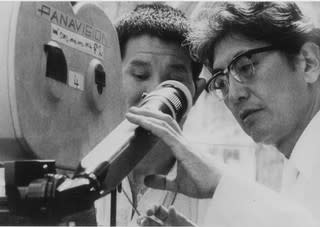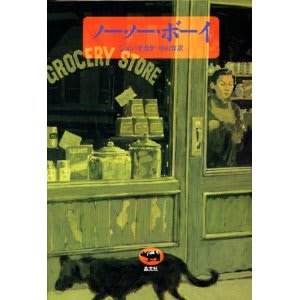岡山駅で降りると、市電が走っている。残してるんだ、
いいなぁと思って乗り込む。岡山城や後楽園、官庁街と
いったエリアへは3駅ほど行った「城山駅」で降りる。
目指すは「岡山市立オリエント美術館」。岡山へ向かう
新幹線のなかでどんなところかネットで見てたら、俄然
行きたくなる。
☆
「オリエント」は「日が昇るところ」という意味だそう
で、古代ギリシャ・ローマ人が東方に位置する先進文明
の地を畏敬の念をこめて読んだ言葉だとか。
日本という言葉も中国からみた「日出づる国」だという
話だったことを思い起こす。

受付を入ると、高い吹き抜け空間。広くはないんだけど、
天窓から光が差し込んできて、やわらかく照らす。縦線
と横線による建築構成。

壁にはモザイク。5世紀のシリアの豹。虎や兎なども。こ
んな文明を生み出したところが、戦火で苦しんでいると
思いをはせる。建築物の床に組み込まれていたもの。

展示に入って行くと、狩猟採集時代の壷、大きな角ヤギが
描かれている。紀元前3200年頃、イラン北東部。よくこ
んな形で残っていると感心する。
農耕が始まり、都市国家が成立しはじめた頃、文字が誕生。
楔形文字を目の当たりにして感動。粘土板に描かれた文書
は取引のことから、歴史の記述まであらゆることが記述さ
れ、巨大な書庫も設置されたとか。再現したらさぞ面白い
だろうなぁ。

前2400年頃のメソポタミア。受験で勉強したころは無味
乾燥だったけど、こうして実物をみると感無量。写真は、
美術館の検索から。使い勝手がいい。タブレット型の音
声ガイドは機械による語りなので、すぐに返却。無料だ
けど。
いいなぁと思って乗り込む。岡山城や後楽園、官庁街と
いったエリアへは3駅ほど行った「城山駅」で降りる。
目指すは「岡山市立オリエント美術館」。岡山へ向かう
新幹線のなかでどんなところかネットで見てたら、俄然
行きたくなる。
☆
「オリエント」は「日が昇るところ」という意味だそう
で、古代ギリシャ・ローマ人が東方に位置する先進文明
の地を畏敬の念をこめて読んだ言葉だとか。
日本という言葉も中国からみた「日出づる国」だという
話だったことを思い起こす。

受付を入ると、高い吹き抜け空間。広くはないんだけど、
天窓から光が差し込んできて、やわらかく照らす。縦線
と横線による建築構成。

壁にはモザイク。5世紀のシリアの豹。虎や兎なども。こ
んな文明を生み出したところが、戦火で苦しんでいると
思いをはせる。建築物の床に組み込まれていたもの。

展示に入って行くと、狩猟採集時代の壷、大きな角ヤギが
描かれている。紀元前3200年頃、イラン北東部。よくこ
んな形で残っていると感心する。
農耕が始まり、都市国家が成立しはじめた頃、文字が誕生。
楔形文字を目の当たりにして感動。粘土板に描かれた文書
は取引のことから、歴史の記述まであらゆることが記述さ
れ、巨大な書庫も設置されたとか。再現したらさぞ面白い
だろうなぁ。

前2400年頃のメソポタミア。受験で勉強したころは無味
乾燥だったけど、こうして実物をみると感無量。写真は、
美術館の検索から。使い勝手がいい。タブレット型の音
声ガイドは機械による語りなので、すぐに返却。無料だ
けど。