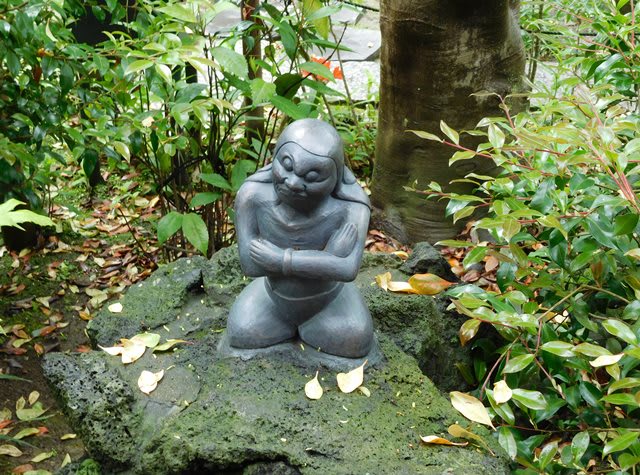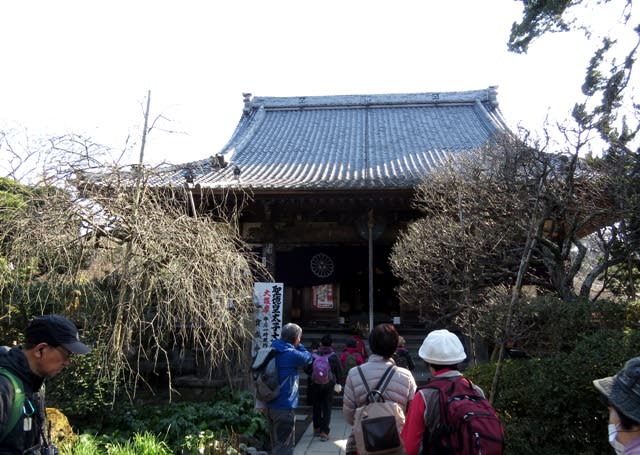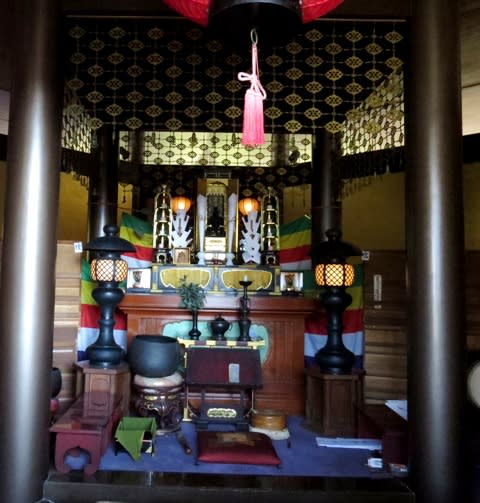6月10日 クラブの仲間と「日光の自然・寺社を歩く 第7回」に参加した。今回のテーマは”湖畔のハイキングと千手ヶ浜のクリンソウを尋ねて”で、千葉から乗ったバスから赤沼車庫で低公害のハイブリッドバスに乗り換えて、西ノ湖入口まで行き、西の湖まで森林浴しながら歩いた。
・赤沼車庫でハイブリッドバスに乗る。排ガスによる動植物への被害に配慮して1993年4月より運行開始

・西ノ湖への案内板

・好天の中ルンルン気分でカラマツの林を通り西ノ湖へ向かって進む

・物凄く揺れる吊り橋を通る

・西ノ湖畔に到着、今年は雨が少ないのか水辺が遠い。「21世紀に残したい日本の自然100選」に選ばれている

・クリンソウが見られた

・木陰でランチタイム。小学生の遠足気分だ

・岸辺にミズナラの巨木が。幹回りは4-5人が手を伸ばしても届かない

・西ノ湖を後にして2km離れた千手が浜へ向かう

・中禅寺湖の西端の千手ヶ浜へ到着。遠くに日光のシンボル男体山が聳えたつ

・今回のハイライト”クリンソウ鑑賞”。色とりどりのクリンソウに出会う。個人(伊藤さん)の敷地に植えられている





・小川に映るクリンソウ


・見事なクリンソウ群生だ

・遊覧船に20分ほど乗り菖蒲ヶ浜へ向かう

・遊覧船の航跡を見ているとロマンチックな気分になる

・遊覧船からの男体山。数年前に登ったことを懐かしく思い出す

次回は「長野 入笠山に登る(6/16)」をアップします