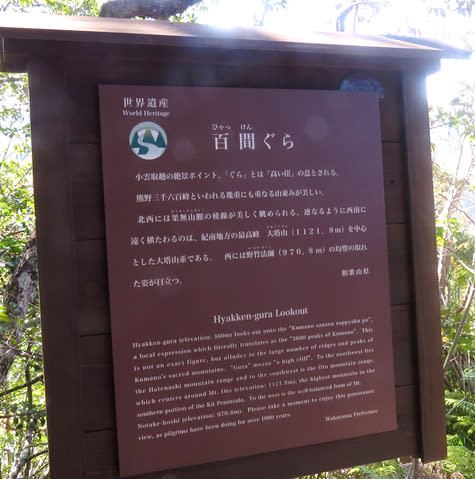12月21日クラブの仲間と矢倉岳(876m)に登った。神奈川県西部の箱根山地と丹沢山地の間に広がる足柄山地にある山で、金太郎伝説で知られる金時山(1,213m)の北側に位置する。おにぎりを立てたような特徴的な山容をしており、足柄平野から足柄山地の山々を眺めた際にひときわ目立つため、一目でそれと分かる。
・山北町 矢倉沢の集落でバスを降り、準備体操して出発。2日前の天気予報が嘘のような青空

・綺麗に刈り込まれた茶畑の脇を通る

・少し上ると茶畑の彼方に集落が見えた

・登山道に入ると登りがきつくなって来た。歩くとカサカサと枯葉の音がして気持ちがよい


・山頂に近づくと辺りが霧に覆われ50m先が見えない

・歩き始めから1.5時間で山頂(876m)に到着。先着組が昼食の真っ最中

・天気が良ければススキの向こうに冠雪の富士山が望めるのだが 残念!!

・昼食後に下山開始したが山道が前日の雨で泥土と化して滑りやすい。用心!用心!

・下山途中で見えた矢倉岳はおにぎりを立てたような山容だ

・よく手入れされ万葉公園の脇を通る。もうすぐ足柄峠だ

・足柄峠で小休止。足柄関所跡を通り富士山の見える展望台へ向かう

・霧が晴れ富士山が見えてきた。山頂付近は雲に覆われている


・富士山を見て満足した後、足柄古道を通りゴールに向かう


・途中で5回ほど国道を横切る

・ゴールの地蔵堂で無事歩き終えたことに感謝しお参り

次回は「鎌倉の森と寺社を歩く 第8回(12月23日)」をアップします