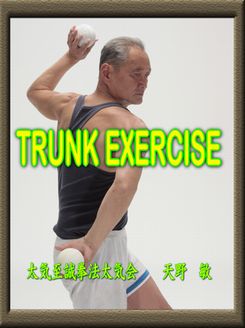人間には、主観的な世界が存在します。
例えば、小学生と社会人の世界に対する認識は当然違います。
また、僕のような中卒の人間と、博士号を取るまで学術に専念してきた人でも、世界観はまるで異なっているはずです。
世界そのものは同じです。ただ、どこまでを現実の世界として実感しているかは、実は人によって異なっているのです。だから、海外にいったときなどは、多大なカルチャーショックを受けます。
海外生活の経験がある方なら実感していると思いますが、生活文化が異なると、言語だけでなく生理的な許容範囲や善悪の概念まで、全く異なってくるのです。その違いは、同じ文化内での個人差よりはるかに大きい。まさしく、別の星の住人と呼ぶにふさわしいものがあります。
例えば、世界の8割以上の文化圏では、一夫多妻が社会的に認められています。客人に対する貸し妻の慣例も、いまだ各地に残っています。フランスでは、不倫が半ば社会的に容認され、高校生が親公認で週末同棲するのは珍しくありません。イギリスでは、「結婚は時代遅れの制度か」ということが何十年も前から議論されています。
世界のトイレ事情も面白いのですが、お食事中のゲストに配慮して、ここでは略します。
ともかく、こうしたことが日本社会で堂々と実行されれば、その人はとんでもない異端者扱いされるでしょう。そこの文化であれば、誰もが当然に認めることであっても、です。
これはどれが正しいかという問題ではなく、単なる世界の多様性の一例です。にもかかわらず、異文化の慣例を生理的に嫌悪することは珍しくありません。
つまり、世界が狭い人ほど頭が硬くなっていて、時には異文化を生理的に拒絶してしまうのです。ここに、独善的愛国心の土壌があります。健全な世界観育成のためには、できる限り世界を広げていく努力が不可欠です。世界がいかに広く、多様性に満ちたものであるかを実感することです。
今の日本の教育を考えるときにも、こうした落とし穴の存在は知っておくべきではないでしょうか。日本に限らず、世界の多様性に視野を広げるのは当然のことで、そこからより優れた教育システムを吟味していくことが、より高度なシステムの構築につながります。
そうした意味では、帰国子女はもとより、海外からの留学生や在留外国人、さらにフリースクールなど、多様な教育システムを体験してきた人々の意見を集約することが必要です。いくら日本中の優秀な人々が集まっても、同じような教育環境の中だけで育ってきた人々だけでは、どうしても視野が狭くなってしまうでしょう。
日本の教育界には、多様なバックボーンを持つ人材が不足しているように思われます。つまり、全体として教育システムについての視野が狭い。そのために、現代日本の教育方法、あるいは自分のやり方を冷静に客観視することが困難になっています。
例えば悪名高い英語教育ですが、教諭への採用条件を「一定期間以上英語圏で生活してきた者に限る」としてはどうでしょう。
英語圏といっても、カナダやアメリカもあればイギリスもオーストラリアもある。インドも広い意味では英語圏です。そうした社会で学んできた人々が、その体験を日本で活かしていけば、日本の教育文化も大きく変わっていくでしょう。
また、学術的に古今東西の教育システムを研究していくことも大切です。特に、過去の教育システムには留学することができませんから、残された資料などの研究が頼みになります。もちろん、留学機会が得られなかった教育関係者が、様々なシステムを教養として知っておくことも大切でしょう。
僕は、古今東西の教育システムを集大成した、いわば『世界教育全集』の発刊を目指しています。寡聞にも、僕はこうした資料集の存在を知りません。地域別とか、義務教育だけとかならまだしも、全てを網羅しているものは皆無です。本来ならば、民官の教育界を挙げて最初に編集すべき資料集でしょうが、現に見当たらない以上、ひとりででもやるしかありません。
国際化、情報化が進んでいるといわれながらも、海外の教育についての情報は、驚くほど浸透していません。アメリカの義務教育が何年か知っている人が、日本にどれだけいるでしょうか?
アメリカの場合、義務教育の期間は州によって異なり、6年間の州もあれば12年間の州もあります。
6・3・3制だけでなく、6・6制や8・4制を採っている州もあるのです。日本のように、単純に小学校とか、高校といった分類は通用しないのです。
8・4制のケンタッキー州では、公立高校への進学に受験はありません。
アメリカの教育では地域参加が重視され、大学に進学するには、ボランティア活動の経験と、そのリーダーによる推薦が不可欠です。
日本が最も影響を受けているアメリカについての情報でさえ、十分に浸透しているとは言い難い。まして、アメリカ以外の地域の教育については、教育関係者でさえ、ほとんど予備知識がないのが実情ではないでしょうか。
これでは、教育改革についての国民的論議といっても、規制概念に囚われた、小手先の改革案に終始する恐れが大きい。まずは、子どもに教育する前に、世界の教育システムを大人が学習しなければならないでしょう。
中国に義務教育はないのですが、働く児童のために「半労半学学校」があります。これは文字通り、半日働いて、半日学ぶというスタイルの学校です。インドでは、そもそも小学校(5年制)は半日しか授業をやりません。宿題も出ません。
世界では、2部ないし3部制の義務教育が一般的です。それはゆとり教育などという理想からではなく、児童労働の必然性から確立されたスタイルなのです。
こういったケースを発展途上国の遅れたシステムとして軽蔑し、参考にできることなど何もないと考えるのが、先進国の高慢さでしょう。労働経験は人格形成上も大切なことですし、親に頼らずに自分で学費を捻出するという姿勢は、全ての先進国の学生が見習うべき模範であるとも考えられるのではないでしょうか。
さらに、学校制度が確立する以前の過去の教育法や、自然界の教育法などを知っておくことも、当然参考になるはずです。あるいは歴史上の偉人の特殊な学習ケースにも、一般化できる部分が隠されているはずです。それらの全てが役に立つわけではないとしても、全く知らないよりは一応知っておいたほうがいい。大切なのは、人類、さらにそれ以前の動物において、次世代育成のためにどのような試行錯誤を重ねてきたのか、その歴史を受け継ぐことです。
ランキング参加中(^^)/ ←クリック
例えば、小学生と社会人の世界に対する認識は当然違います。
また、僕のような中卒の人間と、博士号を取るまで学術に専念してきた人でも、世界観はまるで異なっているはずです。
世界そのものは同じです。ただ、どこまでを現実の世界として実感しているかは、実は人によって異なっているのです。だから、海外にいったときなどは、多大なカルチャーショックを受けます。
海外生活の経験がある方なら実感していると思いますが、生活文化が異なると、言語だけでなく生理的な許容範囲や善悪の概念まで、全く異なってくるのです。その違いは、同じ文化内での個人差よりはるかに大きい。まさしく、別の星の住人と呼ぶにふさわしいものがあります。
例えば、世界の8割以上の文化圏では、一夫多妻が社会的に認められています。客人に対する貸し妻の慣例も、いまだ各地に残っています。フランスでは、不倫が半ば社会的に容認され、高校生が親公認で週末同棲するのは珍しくありません。イギリスでは、「結婚は時代遅れの制度か」ということが何十年も前から議論されています。
世界のトイレ事情も面白いのですが、お食事中のゲストに配慮して、ここでは略します。
ともかく、こうしたことが日本社会で堂々と実行されれば、その人はとんでもない異端者扱いされるでしょう。そこの文化であれば、誰もが当然に認めることであっても、です。
これはどれが正しいかという問題ではなく、単なる世界の多様性の一例です。にもかかわらず、異文化の慣例を生理的に嫌悪することは珍しくありません。
つまり、世界が狭い人ほど頭が硬くなっていて、時には異文化を生理的に拒絶してしまうのです。ここに、独善的愛国心の土壌があります。健全な世界観育成のためには、できる限り世界を広げていく努力が不可欠です。世界がいかに広く、多様性に満ちたものであるかを実感することです。
今の日本の教育を考えるときにも、こうした落とし穴の存在は知っておくべきではないでしょうか。日本に限らず、世界の多様性に視野を広げるのは当然のことで、そこからより優れた教育システムを吟味していくことが、より高度なシステムの構築につながります。
そうした意味では、帰国子女はもとより、海外からの留学生や在留外国人、さらにフリースクールなど、多様な教育システムを体験してきた人々の意見を集約することが必要です。いくら日本中の優秀な人々が集まっても、同じような教育環境の中だけで育ってきた人々だけでは、どうしても視野が狭くなってしまうでしょう。
日本の教育界には、多様なバックボーンを持つ人材が不足しているように思われます。つまり、全体として教育システムについての視野が狭い。そのために、現代日本の教育方法、あるいは自分のやり方を冷静に客観視することが困難になっています。
例えば悪名高い英語教育ですが、教諭への採用条件を「一定期間以上英語圏で生活してきた者に限る」としてはどうでしょう。
英語圏といっても、カナダやアメリカもあればイギリスもオーストラリアもある。インドも広い意味では英語圏です。そうした社会で学んできた人々が、その体験を日本で活かしていけば、日本の教育文化も大きく変わっていくでしょう。
また、学術的に古今東西の教育システムを研究していくことも大切です。特に、過去の教育システムには留学することができませんから、残された資料などの研究が頼みになります。もちろん、留学機会が得られなかった教育関係者が、様々なシステムを教養として知っておくことも大切でしょう。
僕は、古今東西の教育システムを集大成した、いわば『世界教育全集』の発刊を目指しています。寡聞にも、僕はこうした資料集の存在を知りません。地域別とか、義務教育だけとかならまだしも、全てを網羅しているものは皆無です。本来ならば、民官の教育界を挙げて最初に編集すべき資料集でしょうが、現に見当たらない以上、ひとりででもやるしかありません。
国際化、情報化が進んでいるといわれながらも、海外の教育についての情報は、驚くほど浸透していません。アメリカの義務教育が何年か知っている人が、日本にどれだけいるでしょうか?
アメリカの場合、義務教育の期間は州によって異なり、6年間の州もあれば12年間の州もあります。
6・3・3制だけでなく、6・6制や8・4制を採っている州もあるのです。日本のように、単純に小学校とか、高校といった分類は通用しないのです。
8・4制のケンタッキー州では、公立高校への進学に受験はありません。
アメリカの教育では地域参加が重視され、大学に進学するには、ボランティア活動の経験と、そのリーダーによる推薦が不可欠です。
日本が最も影響を受けているアメリカについての情報でさえ、十分に浸透しているとは言い難い。まして、アメリカ以外の地域の教育については、教育関係者でさえ、ほとんど予備知識がないのが実情ではないでしょうか。
これでは、教育改革についての国民的論議といっても、規制概念に囚われた、小手先の改革案に終始する恐れが大きい。まずは、子どもに教育する前に、世界の教育システムを大人が学習しなければならないでしょう。
中国に義務教育はないのですが、働く児童のために「半労半学学校」があります。これは文字通り、半日働いて、半日学ぶというスタイルの学校です。インドでは、そもそも小学校(5年制)は半日しか授業をやりません。宿題も出ません。
世界では、2部ないし3部制の義務教育が一般的です。それはゆとり教育などという理想からではなく、児童労働の必然性から確立されたスタイルなのです。
こういったケースを発展途上国の遅れたシステムとして軽蔑し、参考にできることなど何もないと考えるのが、先進国の高慢さでしょう。労働経験は人格形成上も大切なことですし、親に頼らずに自分で学費を捻出するという姿勢は、全ての先進国の学生が見習うべき模範であるとも考えられるのではないでしょうか。
さらに、学校制度が確立する以前の過去の教育法や、自然界の教育法などを知っておくことも、当然参考になるはずです。あるいは歴史上の偉人の特殊な学習ケースにも、一般化できる部分が隠されているはずです。それらの全てが役に立つわけではないとしても、全く知らないよりは一応知っておいたほうがいい。大切なのは、人類、さらにそれ以前の動物において、次世代育成のためにどのような試行錯誤を重ねてきたのか、その歴史を受け継ぐことです。
ランキング参加中(^^)/ ←クリック