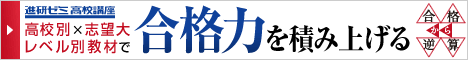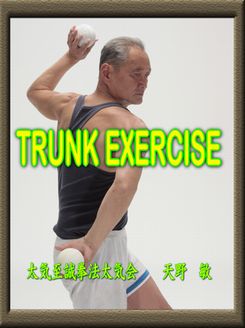われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(教育の目的)第1条
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)第2条
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)第3条
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
(義務教育)第4条
国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
(男女共学)第5条
男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
(学校教育)第6条
法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
(社会教育)第7条
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
(政治教育)第8条
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)第9条
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
(教育行政)第10条
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
(補則)第11条
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
最新ニュースランキングを見る
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(教育の目的)第1条
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)第2条
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)第3条
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
(義務教育)第4条
国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
(男女共学)第5条
男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
(学校教育)第6条
法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
(社会教育)第7条
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
(政治教育)第8条
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)第9条
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
(教育行政)第10条
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
(補則)第11条
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
最新ニュースランキングを見る