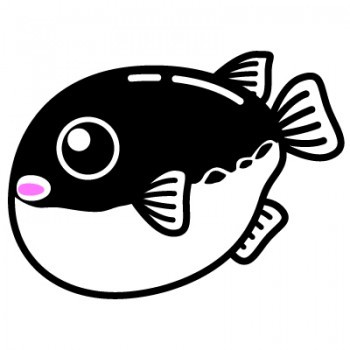1. まえがき
前回より複雑な事例を述べる。
2. 問題
図のように、水平な床上に質量Mの台Qがある。台Qの水平な上面にはばね定数kのばねを、左
側に、ばね定数2kのゴムひもを右側につけた質量mの物体Pがある。ばねとゴムひもの他端は
台Qに固定されてる。このとき、ばねとゴム紐は自然長である。
ばねが自然長の時の物体Pの位置を原点x=0として、台Qに固定した右向きのx軸をとる。はじ
め物体Pはx=2dの位置でつりあっていた。装置各部の摩擦や空気抵抗、物体Pの大きさ、ばね
とゴムひもの質量は無視でき、たるんだゴムひもがPや台Qの運動を妨げることはないとする。
(1) 台Qを床に固定したまま物体Pをx=3dの位置までずらして静かに放すと、Pはつりあいの位
置を中心とする振幅dの単振動を行なった。この単振動の周期をもとめよ。
(2) 台Qを床に固定したまま物体Pをx=0の位置までずらして静かに放すと、Pは往復運動を行な
った。
(a) 物体Pの速さの最大値を求めよ。
(b) 物体Pのx座標の最大値を求めよ。
(c) 物体Pが再びx=0の位置に戻ってくるまでの時間を求めよ。
(3) 台Qを自由に動けるようにした。台Qが静止してる時、x=2dの位置にある物体Pに右向きの
初速を与えた所、PはQに対して周期運動をおこない、Pのx座標の最大値はx=4dとなった。
(a) 物体Pに与えた初速を求めよ。
(b) 物体Pのx座標の最小値を求めよ。
(c) 物体Pに与えた初速をv₀、運動の周期をT₀とする。一周期間での台Qの右向きの変位を
v₀、T₀を用いて表せ。
3. 解
(1) ゴムひもが自然長の時、その左端の位置(x=0からの)をLとすると、釣合の式から
k2d=2k(L-2d)、したがって、
L=3d ・・・・・①
Pの運動方程式は
mx''=-kx+2k(L-x)=-3kx+6kd (x<L=3d)・・・・②
mx''=-kx (x>L=3d) ・・・・③
設定から、振動は x<L=3d なので➁を満たす。この解はよく知られており角周波数は
w=√(3k/m) ・・・・・④
となる。したがって、周期は
T=2π/w=2π√(m/3k)
となる。
(2)(a)
②は mx''=-3k(x-2d) と変形できて、これを解くと、x=2d+Acoswt+Bsinwt となる。
x(0)=x'(0)=0 として
x=2d(1-coswt) , v=x'=2dw sinwt ・・・・・⑤
を得る。
Pの最大速度v₁は、wt=π/2の時で、⑤から x=2d (<L=3d)
v₁=2dw={2√(3k/m)}d
を得る。
(b)
最大の座標 x₂は ⑤から、x=4d となる。つまり、ゴムひもは垂るみ、②の条件を満たさ
ず、③を解かねばならない。そこで、境界、x=3dの速度v₂は⑤から
3d=2d(1-coswt) → coswt=-1/2 → wt=π/3・・・・⑥
v₂=2dwsin(π/3)=dw√3={3√(k/m)}d
となる。
時刻をt=0にして、③を解くと
x=Acosw't+Bsinw't , w'=√(k/m)
となるが、⑥の結果の初期条件
x(0)=3d , x'(0)=v₂={3√(k/m)}d
から、A=B=3d となり
x=3d(cosw't+sinw't)=(3√2)d cos(w't-π/4) ・・・・⑦
を得る。したがって、最大座標は x₂=(3√2)d , w' t=π/4 となる。
(c)
ゴム紐がたるんだ時、x≧L=3dでの往復時間は、⑦で、x≧3d となる時間だから、
w' t=π/4 を挟んだ w' t=0~π/2 の間である。つまり、その時間T'は
T'=π/(2w')=(π/2)√(m/k)
となる。
つぎに、ゴム紐がたるんでいないときの⑤の 0≦x≦L=3d の運動時間は⑥から
t=(π/3)/w=(π/3)√(m/3k)となる。原点に戻る時間を加えるとこの2倍になるから、
上のT'を足して、求める時間T₃は
T₃=(π/2)√(m/k)+2(π/3)√(m/3k)=(π/2)√(m/k){1+4/(3√3)}
となる。
(3)(a)
初速をv₀とする。始めのバネとゴムのエネルギーは k(2d)²/2=2kd², 2k(L-2d)²/2=kd²
また、mが 4dで停止したとき(ゴムはたるんでいる)、Mとmの速度は同じだから、運動
量保存により
(M+m)v=mv₀ → v=mv₀/(M+m)・・・・・・⑧
となる。エネルギー保存から
2kd²+kd²+mv₀²/2=k(4d)²/2+(M+m)v²/2=8kd²+{m²/(M+m)}v₀²/2・・・⑨
v₀=[√{10k(M+m)/mM}]d={√(10k/μ)}d・・・・⑩
ここで、μは換算質量
μ=mM/(m+M)
である。
(b)
Pの最小座標xは反対方向で、M,mの速度が等しくなったところだから、エネルギー保存は
⑨の右辺を変更して
2kd²+kd²+mv₀²/2=kx²/2+2k(3d-x)²/2+(M+m)v²/2
⑧⑩を使って整理すると
(3/2)x²-6dx+d²=0 → x={2-√(10/3)}d (小さい方を取る)
となる。
(c)
地べたの慣性系を基準にすると、mと台の座標をそれぞれx,yとする。すると運動量保存に
より、
mx'+My'=mv₀、積分して、mx+My=mv₀t → (mx+My)/(m+M)=mv₀t/(m+M)
この左辺はm,Mの重心の座標と等距離にある座標である。つまり、重心の座標は等速運動
をする。mの運動の1周期T₀をとれば、その分の変位は合計0となる。したがって、T₀の間
に台が移動する距離は
mv₀T₀/(m+M)
となる。
以上