
MIT教授であるトマス・W・マローンの『フューチャー・オブ・ワーク』を読んだ。ネットワーク社会における組織について考察した本である。
テクノロジーの進展に伴うコミュニケーション・コストの低下に焦点を当て、社会が孤立した群れから、中央集権化された王国へ、そして最後は権力が分散化された民主制へと移行したように、企業も孤立した商店から、階層構造を持つ企業へ、そしてネットワーク型企業へと進化すると説明する。
そして、分散化にも、「ゆるやかな階層制」、「民主制」、「マーケット」の三種類があるとして、それぞれの長所・短所を議論している。その中でいろいろな組織の事例が引かれていて面白い。社内でブログを活用するGoogle、リナックスの開発形態、Wikipediaの編集方法、ゴア社の意思決定方式、イーベイの顧客民主制などなど。
そこから更に議論が急進的な方向(分散化の究極の姿)へ進む方思ったが、本書はここでより現実的な議論へと方向転換する。分散化は個人の自由や創造力をより開放する方向へ向かうが、本書は「全員が自立を望んでいるわけではない。また、自立を望んでいる者すべてが、うまくやれる能力を持っているわけではない」という。従って、仕事が必要とする自主性と人間が求める自主性が重なるポイントを目指すことが重要だとする。そして議論は分散化が必要とされるケース、されないケースの分析へ進む。ここまでが前半。
後半は、分散化された組織におけるマネージメント論が展開される。その中心となる主張は、「<命令と管理>から<調整と育成>へ」である。その議論自体はそれほどの新鮮味を覚えるものではないが、ITにおけるインターフェースの標準化になぞらえつつ、組織における分散化の方法を議論しているあたりは面白い。以降、分散化環境で求められるリーダーシップ、ビジネスの目標と個人の価値観の一致などが議論されるが、やや抽象的で面白みに欠ける。
全体としては、前半部分の分散化された組織の可能性に関する議論の方が面白い。多少非現実的であっても、それを突き詰めた将来の可能性を追求すると更に面白かったかもしれない。分散化環境のマネージメントは、まだまだ身の回りでは未成熟な状況にあるだけに勉強になるが、具体的な事例が少ないのがやや物足りないか。
-----
たまたま今日の郁次郎(日経新聞のコラム「やさしい経済学」)は、「知識を創造する主体として組織を見るとき、これまでとは異なる人間観・組織観」が必要となると論じている。つまり、階層型の組織は、人間を情報処理の部品としか見ていないというのだ。その新しい組織観は、どうも明日の話題のようで、今日は触れられていない。きっとマローンの論ずるところの分散化された組織、あるいはそれに近い話題が登場するのではなかろうか。
テクノロジーの進展に伴うコミュニケーション・コストの低下に焦点を当て、社会が孤立した群れから、中央集権化された王国へ、そして最後は権力が分散化された民主制へと移行したように、企業も孤立した商店から、階層構造を持つ企業へ、そしてネットワーク型企業へと進化すると説明する。
そして、分散化にも、「ゆるやかな階層制」、「民主制」、「マーケット」の三種類があるとして、それぞれの長所・短所を議論している。その中でいろいろな組織の事例が引かれていて面白い。社内でブログを活用するGoogle、リナックスの開発形態、Wikipediaの編集方法、ゴア社の意思決定方式、イーベイの顧客民主制などなど。
そこから更に議論が急進的な方向(分散化の究極の姿)へ進む方思ったが、本書はここでより現実的な議論へと方向転換する。分散化は個人の自由や創造力をより開放する方向へ向かうが、本書は「全員が自立を望んでいるわけではない。また、自立を望んでいる者すべてが、うまくやれる能力を持っているわけではない」という。従って、仕事が必要とする自主性と人間が求める自主性が重なるポイントを目指すことが重要だとする。そして議論は分散化が必要とされるケース、されないケースの分析へ進む。ここまでが前半。
後半は、分散化された組織におけるマネージメント論が展開される。その中心となる主張は、「<命令と管理>から<調整と育成>へ」である。その議論自体はそれほどの新鮮味を覚えるものではないが、ITにおけるインターフェースの標準化になぞらえつつ、組織における分散化の方法を議論しているあたりは面白い。以降、分散化環境で求められるリーダーシップ、ビジネスの目標と個人の価値観の一致などが議論されるが、やや抽象的で面白みに欠ける。
全体としては、前半部分の分散化された組織の可能性に関する議論の方が面白い。多少非現実的であっても、それを突き詰めた将来の可能性を追求すると更に面白かったかもしれない。分散化環境のマネージメントは、まだまだ身の回りでは未成熟な状況にあるだけに勉強になるが、具体的な事例が少ないのがやや物足りないか。
-----
たまたま今日の郁次郎(日経新聞のコラム「やさしい経済学」)は、「知識を創造する主体として組織を見るとき、これまでとは異なる人間観・組織観」が必要となると論じている。つまり、階層型の組織は、人間を情報処理の部品としか見ていないというのだ。その新しい組織観は、どうも明日の話題のようで、今日は触れられていない。きっとマローンの論ずるところの分散化された組織、あるいはそれに近い話題が登場するのではなかろうか。











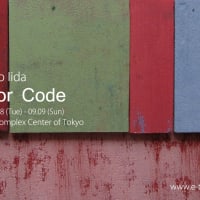
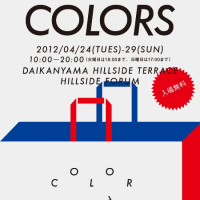

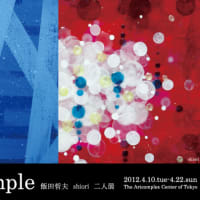



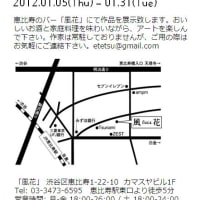

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます