元IBJの大垣尚司氏の「金融アンバンドリング戦略」を読んでいる。まだ斜め読みしかしてないが、それだけでも刺激的な箇所があったので書いておきたい。
これは著者がIBJの後に外資系金融機関に勤務していた時のトピックとして紹介されている。著者は本社のシステム担当者から「協力会社のSEを一度全員返してインドのシステム会社を利用することを含めて、体制を組み直せと指示された」という。人ががらりと変わってしまえばシステム仕様が把握できなくなるので当然反対したそうだが、本社からはこのように言われたという。
「システム経費の大部分は人件費だ。自社社員の給料を先に切るのか、システム会社の従業員を切るのか経営者として判断しろ」
よくあるストーリーは、インドに外注したが、やっぱりうまくいかないねぇというものだが、大垣氏のケースは、なんとかなってしまったという。また、これが実際に必要な要員とそうでない要因の判断にも役立ったという。うまくいったのには、大垣氏の手腕によるところも大きいのだろうが、こうした経営判断が実行に移されているという話は興味深い。
本書によると、アメリカの金融業界は80年代中盤から90年代にかけて、上記のような経験を業界ぐるみで経験している。つまり経費削減のためにオフショア開発を徹底し、それはインド系ベンダーの台頭を許したが、米系ITベンダーもその変化に応じてインドでのオペレーションを急拡大させた。
著者は日本の現状に対しては、ITベンダーと金融機関の相互依存が高く、米国のような改革が進んでいないという。つまり、株式の持合と、ITベンダーが大口貸出先であるという事実が、改革を阻害していると。結果的に大手金融機関のシステム統合も、効率性よりも政治的要素を重視した辻褄合わせとなるのだろう。
しかし、株式持合いは減少傾向にあり、インド系ベンダーも日本での営業活動を活発化している。また、繰り返された統合により、金融機関はグループ会社も含めると大量のシステム要員を自社の中に抱えていることになる。多いところでは数千人規模である。
こうした状況は単価の下落としてITベンダーへ既に重くのしかかって来ているが、それが単なるITバブルの崩壊によるものでなく、上記のような構造的な変化によるものであることに留意する必要がある。つまり、景気が良くなっても単価が大きく戻る可能性は低い。
むしろ、金融機関が日系ベンダーの利用をやめて、一気にオフショアリングへ移行する可能性も捨てきれない。これは単価の下落としてではなく、仕事そのものがなくなるという形で基幹系に食い込めていないベンダーを直撃する可能性がある。最も被害が大きいのは非メーカー系のSIベンダーである。
結局は差別化、もしくはオフショアリングも含めた規模拡大が必要だが、非メーカー系は金融機関へビジネスモデルを提案できるくらいにまで専門分野を強化するか、あるいは自らが新しいビジネスモデルを作り上げるところまでいかないと、生き残れないのではないかと危惧する。大垣氏のエピソードを読んでその危機感が更に強まったのである。
『金融アンバンドリング戦略』 大垣尚司 日本経済新聞社
これは著者がIBJの後に外資系金融機関に勤務していた時のトピックとして紹介されている。著者は本社のシステム担当者から「協力会社のSEを一度全員返してインドのシステム会社を利用することを含めて、体制を組み直せと指示された」という。人ががらりと変わってしまえばシステム仕様が把握できなくなるので当然反対したそうだが、本社からはこのように言われたという。
「システム経費の大部分は人件費だ。自社社員の給料を先に切るのか、システム会社の従業員を切るのか経営者として判断しろ」
よくあるストーリーは、インドに外注したが、やっぱりうまくいかないねぇというものだが、大垣氏のケースは、なんとかなってしまったという。また、これが実際に必要な要員とそうでない要因の判断にも役立ったという。うまくいったのには、大垣氏の手腕によるところも大きいのだろうが、こうした経営判断が実行に移されているという話は興味深い。
本書によると、アメリカの金融業界は80年代中盤から90年代にかけて、上記のような経験を業界ぐるみで経験している。つまり経費削減のためにオフショア開発を徹底し、それはインド系ベンダーの台頭を許したが、米系ITベンダーもその変化に応じてインドでのオペレーションを急拡大させた。
著者は日本の現状に対しては、ITベンダーと金融機関の相互依存が高く、米国のような改革が進んでいないという。つまり、株式の持合と、ITベンダーが大口貸出先であるという事実が、改革を阻害していると。結果的に大手金融機関のシステム統合も、効率性よりも政治的要素を重視した辻褄合わせとなるのだろう。
しかし、株式持合いは減少傾向にあり、インド系ベンダーも日本での営業活動を活発化している。また、繰り返された統合により、金融機関はグループ会社も含めると大量のシステム要員を自社の中に抱えていることになる。多いところでは数千人規模である。
こうした状況は単価の下落としてITベンダーへ既に重くのしかかって来ているが、それが単なるITバブルの崩壊によるものでなく、上記のような構造的な変化によるものであることに留意する必要がある。つまり、景気が良くなっても単価が大きく戻る可能性は低い。
むしろ、金融機関が日系ベンダーの利用をやめて、一気にオフショアリングへ移行する可能性も捨てきれない。これは単価の下落としてではなく、仕事そのものがなくなるという形で基幹系に食い込めていないベンダーを直撃する可能性がある。最も被害が大きいのは非メーカー系のSIベンダーである。
結局は差別化、もしくはオフショアリングも含めた規模拡大が必要だが、非メーカー系は金融機関へビジネスモデルを提案できるくらいにまで専門分野を強化するか、あるいは自らが新しいビジネスモデルを作り上げるところまでいかないと、生き残れないのではないかと危惧する。大垣氏のエピソードを読んでその危機感が更に強まったのである。
『金融アンバンドリング戦略』 大垣尚司 日本経済新聞社











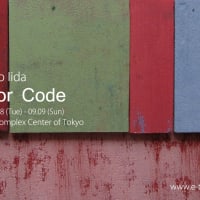
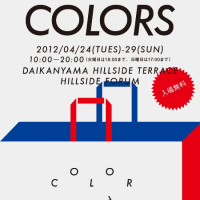

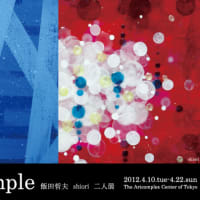



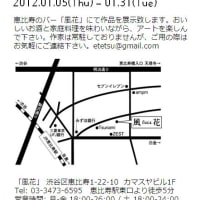

(日本の顧客に対して日本滞在SEがフェイスした上でインドでの開発を行うスキーム)
の為、金融業界向けSE経験者の採用を活発化させて
いる姿を目にしました。
既存の日本滞在スタッフとほぼ同数を採用し、
規模を倍増させようということで、かなり積極的な
展開と思います。
ご指摘の危惧、かなりリアルに感じてしまいます。
インド系企業がコンペ先になるケースはまだそれほど多くないものの、でも着実に増えてきているような気がしますね。こちらが先に取り込まなければ、むこうに取り込まれることになりかねないですね。