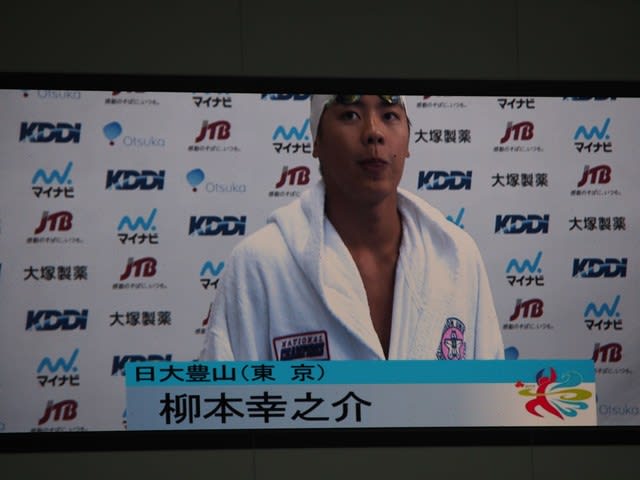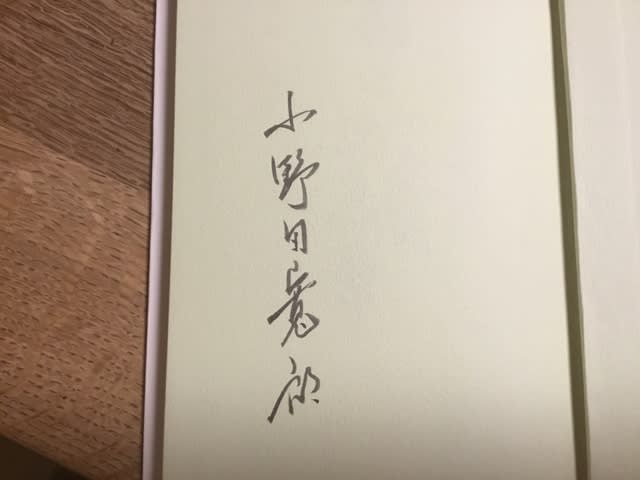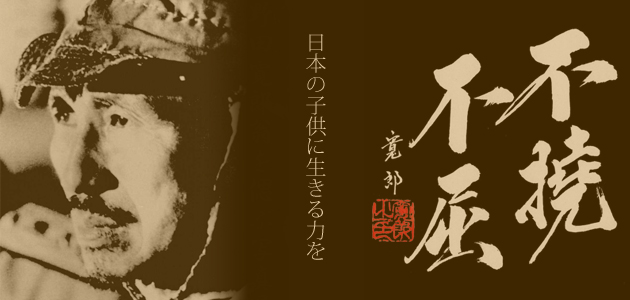今年から全国中学校大会に民間クラブチームの参加が認められるようになりました。
得点を集計しての学校対抗が廃止され、個人・リレーで順位が出るだけの大会となりました。
私は全国中学大会に行っておりましたので、これまでの大会との違いについて感じたことをまとめてみます。
まず最初に感じたことは、メドレーリレー参加チームの減少です。
特に女子のメドレーリレーの参加チームは、9チームだけでした。
組数は2組で決勝進出チームは8チームですから、予選落ちするのは1チームだけです。
コロナ前の2019年の大会に参加していた女子メドレーリレーのチームは、4組で35チームでした。
今年の女子メドレーリレーの参加チームは激減しています。
男子のメドレーリレーは2019年が39チーム、今年が23チームで、これも大幅に減少しています。
一方、女子のフリーリレーは今年50チームが参加しており、以前よりも増加しています(2019年の参加チームは、31チーム)。
男子フリーリレーは2019年チームと今年はともに25チームでした。
2019年と今年は競技順序の違いもあり単純に比較はできませんが、フリーリレーに比べてメドレーリレーの参加チームが減少していることは男女ともに共通しています。
これの意味することを考えると、やはり学校対抗を廃止した影響が出ているものと想像できます。
フリーリレーは大会初日で個人種目が少ない日に予選があるのですが、メドレーリレーの予選は二日目の昼頃に設定されており、個人種目の予選と決勝の間にあります。
つまり、個人種目に参加する選手がメドレーリレーの予選に出場することで、身体の負担が大きくなるわけです。
これまでは学校対抗があれば多少の無理をしてでもメドレーリレーに参加していたチームも、個人種目に集中したいという理由で都道府県大会の段階から参加していないケースが考えられます。
来年以降、さらに参加チームが減少し8チーム以下になれば、予選のないタイム決勝となることでしょう。
次に感じたことは、チームとして参加することの意識の低下です。
これも私たちのように学校対抗で勝利することを目標にしていた学校だからこそ、それを強く感じるのかもしれません。
リレーに参加するということは競技日程がタイトになり、身体もきついのですが、チームという意識がそれを支えているといえます。
そのきつさに耐えるために練習するという意識も生まれてきます。
今後予想されることは、個人主義的な意識がますます強くなり、個人種目に参加する選手がいるチームはリレーに出なくなるのではないかということです。
個人種目に参加しない選手だけでリレーを組むことになれば、リレーのレベルは下がる一方でしょう。
そもそもリレーの全国大会の参加標準記録が切れなくなることも考えられます。
このままではいずれ、全国中学はリレー種目のない個人種目だけの大会となり、ますますチームとしての取り組みが失われていくことでしょう。
このような流れが高校にも及ぶことを想像したくはありませんが、いずれその時が訪れることも考えなければならないと思います。
水泳は基本的に個人スポーツですが、チームとして取り組むことによって練習にも活気が出て、大会への意気込みも増すものですが、それも失われていく可能性があります。
これから日本のスポーツはどのような変化を遂げていくのでしょうか。

竹村知洋