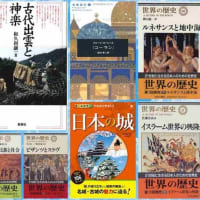-表象の森- 多折法、筆触のひろがり
石川九楊編「書の宇宙」シリーズ-二玄社刊-、№14「北宋三大家」より
宋代-960~1127(北宋)-、蘇軾-ソショク-・黄庭堅-コウテイケン-・米芾-ベイフツ-の、いわゆる北宋の三大家の書によって、書の書きぶりはがらりと一変し、書史の軸はいっきに移動する。
王羲之の書-古法、いわゆる晋唐書-の書と比較すると、三者の書に共通する特徴は、筆蝕が波立つように揺れ、字形が歪み、文字が倒れ、行が傾く。これらの書は、「蚕頭燕尾-サントウエンビ-」とよばれる筆蝕段階の顔真卿の書をふまえ、拡張することによって生じ、王羲之の表現と、顔真卿の表現と、さらにつけ加えれば李邕-リヨウ-の表現-この二者ないし三者の函数である。
王羲之と顔真卿の両者を二つながらにふまえながら、顔真卿の書の「蚕頭燕尾」に隠れた、抑揚の大きな筆蝕を拡張したのが蘇軾であり、顔真卿の「蚕頭燕尾」の、筆尖を立てる垂直筆にアクセントを置き、これを拡張し、多折法という新たな筆法段階に導いたのが黄庭堅である。この二者に対し米芾の場合、蜀素帖などにおいては、顔真卿の「蚕頭燕尾」の影響は背後に隠れ、前面に李邕の不均等比例均衡の姿が現れ、あるいはまた草書四帖や行書三帖などでは、翻って王羲之の姿が直截に露岩してくる。
三折法の段階の草書である狂草の影響下に生まれた顔真卿の「蚕頭燕尾」、その拡張によって生まれた多折法段階の書は、字形や字画、筆触において自在に伸縮するという表現の拡張をもたらすとともに、俄然、表現密度を高め、演劇的展開性までをも孕むことになった。
黄庭堅「伏波神詞詩巻」より

園辞石柱。/筋力盡炎

洲。一以巧名/累。飜思馬
「見るたびに新しい」とは、伏波神詞詩巻に対する高村光太郎の感想である。
垂直筆と多折法から、きわめて複雑な表現が展開されている。
余裕と余力をもった伸び伸びとした筆触と、長かった王羲之-唐・太宗的な「一対一」「左右対称」の基準均衡とでもいうべき構成法を打ち破って登場した、おおらかな構成こそが最大の魅力であり、また後世の範ともなったものである。
字画が比較的均質な太さで現れているのは、筆尖と紙-対象-とが垂直に近い状態、垂直筆を基調に書かれているからである。
新たに生まれた多折法は、表現の幅を広げ、横画を長く伸ばし、左ハライ、右ハライを長く伸ばし、また逆に、筆触が凝縮する大きな「点」の表現ももたらし、偏と旁が落差をもった大胆な構成も可能にし、さらに渇筆の表現も出現している。
―山頭火の一句― 行乞記再び -03-
12月24日、晴、徒歩8里、福島、中尾屋
8時過ぎて出立、途中ところどころ行乞しつつ、漸く県界を越した、暫らく歩かなかつたので、さすがに、足が痛い。
山鹿の宿もこの宿も悪くない、20銭か30銭でこれだけ待遇されては勿体ないやうな気がする。
同宿の坊さん、籠屋のお内儀さん、周旋屋さん、女の浪花節語りさん、みんなとりどりに人間味たつぷりだ。
※表題句は、同前、12月31日付記載の句