
山頭火ゆかりの種田酒造場跡地付近
<行き交う人々-ひと曼荼羅>
<名代の蕎麦処「凡愚」を営む真野夫妻のこと>
大阪の西端、澱江と別称された淀川の支流木津川と尻無川に挟まれた下町界隈で、沖縄出身者が多いことでも知られる大正区。
その東西に伸びる幹線大正通りを横断する43号線(阪神高速西大阪)を過ぎた一つ目の信号を右に入ると、’90年代、蕎麦屋のニューウェーブとして全国に名を馳せた、そば切り「凡愚」がある。
古いしもた屋風情の家なのだが、その昔彼らは此処をアトリエとしていた時期もあって、当時の面影を残したままだから、一見蕎麦屋にはとても見えない奇妙な店構え。
なんと週の内の4日間しか開業せず、それも午前11時からで、売り切りで夕刻前には店仕舞いするという、悠々自適?の店。子どものいない店主夫婦のライフスタイルを前面に出した遊び感覚に満ちたものだ。
この店主夫婦が真野竜彦・恒代さんなのだが、この二人と私の間には因縁浅からぬものがある。
彼ら夫婦がこの蕎麦屋を始めたのは’91年(H2)のことというから、今年で15年目ということになるが、私との縁はさらにぐっと遡る。
夫君竜彦さんとは細君恒代さんを通して知己となった。
恒代さんは旧姓宮本、高校の同期生。在校時、同じクラスになることはなかったから、当時はまあ顔見知りという程度で、とくに交わりがあった訳ではない。
彼女と再会し、後にこの夫婦とそれこそ結ぼれの如き仲となる発端は卒業後4.5年を経た頃ではなかったか。
記録を紐解けば、‘68年(S43)の神澤茂子・天津善昭そして私との三人によるジョイントリサイタル「FITO-ひと」で衣裳デザインを担当したデザイナーH女史のアシスタントとしてH女史の後ろに畏まって付いて来ていたのが彼女で、ヤァ、ヤァとなった次第だ。
この会は、三人のジョイントながら、私にとっては舞踊作家デビューの記念すべきものであった。
三人が各々三つの作品を制作し、神澤和夫師の「Blues1.2.3」を加え、上演のプログラムとした。
公演は‘68年(S43)6月22日、大阪森之宮の厚生会館文化ホール(現・青少年会館文化ホール)にて。
因みに、私の作品タイトルは「吼えろ、吼えろ、ふくろう党」「蝕」「灰の水曜日」。
デザイナーのH女史は当時の阪神百貨店のデザインルームのチーフだったかで、打合せなどで私も何回か通ったのだろう、その部屋で彼女と話したりした記憶がいま微かに蘇ってくる。
この頃の私はすでに世帯(一度目の)をもって丸二年が経過、’75(S50)年春に泉北の晴美台に転居するまでの8年を大正区の三軒家枦町 (現・泉尾1丁目) に長屋住まいをしていたのだが、前述の再会からどれほどの時を経てか、家近くの街中で昼日中偶然にも彼女とバッタリ出くわしたのだった。聞けば結婚してこの辺りに住居しているという。昔から彼女は人懐っこい性格だからか、またしてもヤァ、ヤァだ。「旦那は写真をやっているから、是非紹介したいし、家に寄っていきませんか」とノリよくお誘い戴いたので、私も偶々閑だったのだろう、そのまま新居にお邪魔をして、竜彦さんと初のお目文字となった。
夫君は少し繊細な感じがするものの人の好さは一目瞭然、お世辞にも話し上手とはいえない人見知りするタイプ、人見知りの強いのは私もご同様だが。彼女はとても気散じで決して相手を逸らさない饒舌家だったから、これはこれで対照の妙。
仕事は写真の撮影のほうではなく、大判の紙焼きを主とする技術屋さんで、当時としてはちょっとした大型の機械を持っていて、そんな話題に興じたものだった。
それ以来、家が近いこともあって互いに行き来をするような付き合いが続いたのだが、私が自前の舞踊公演を打つようになって、細君に衣裳デザインを依頼してからいよいよ深くなる。夫君の竜彦氏も稽古や舞台の写真撮影を引き受けて、夫婦揃ってのスタッフ付き合いとなったものだ。
‘75年(S50)の芝居と踊りのジョイントシアター「風が立つ」にはじまり、翌年の劇「挑戦者たち」、舞踊の「螺旋の河をゆく阿呆船」と続き、以後も私の企画公演には欠かせぬスタッフとして付き合いは深まってゆく。
その付き合いが嵩じてか、‘80年(S55)2月には「ダンスとブルースによる真野恒代のファッション・ショー」まで致すことと相成る。遊び感覚に溢れた劇場型ファッショショーというわけだ。会場を芦屋のルナ・ホールとした。ここは円形型劇場だから企画に相応しかろう。出演者は真野夫妻と親交深いブルース・ミュージシャンたちと私のほうのダンサーたち。題してFashion, Dance&Blues「遊びにいけるさ土曜日に」。無名の服飾デザイナー真野恒代が、業界などというものとはまったく無縁の世界で歩み出した晴れの舞台だった。
すでにこの頃には、真野夫妻には自宅を改造してアトリエをやりたいという望みがどんどん膨らんでいた。夫君の写真と細君の服飾デザインというお互いの職能をそのまま活かした形のものをという願いだ。当初は、細君の服飾デザインを前面に押し出したものとなってオープンさせた。「アトリエ・シャンソニエ」の誕生である。
このシャンソニエの誕生とファッションショーのどちらが先行したのだったかは、残念ながら私の記憶は定かではない。ひとまず相前後して、としておこう。
’80年代、二人の工房であるアトリエ・シャンソニエのありようは、その二人、真野夫妻のありようを映して変貌していく。
子どもを持たぬ夫婦が、お互いにかけがえのない他者として、同伴者として生きてゆくことの変遷の歴史がここにも固有のかたちである。相剋と和合の螺旋のような繰り返しが。
まるでシテと脇の交代劇の如く、細君の服飾デザインを主体にしていたアトリエの様相が一変して、夫君のフォトアトリエ兼イベント空間へと変貌するのである。
数年前から撮影対象をアングラ系劇団や暗黒舞踏系へと足場を移していっていた夫君は、その交友関係のなかでいろんなパフォーマーたちに空間を提供し、アトリエ・シャンソニエを彩っていくこととなる。
私もまた、オープニングイベントの一つとして、店先の路上でのダンスパフォーマンスをしている。’84年(S59)12月のことだから、この時がGalleryシャンソニエへと転身した始まりであったのだろう。
イベント空間へと変身したGalleryシャンソニエがどれほど続いたかは、どうもはっきりしないのだが2年位ではなかったろうか。
夜もずいぶん遅い時間だったと記憶するが、ある日、突然、夫妻が泉北の我が家を訪ねてきた。
二人は「アメリカへ行く」というのである。「半年になるか、一年になるか。とにかく自分たちをそれぞれ見つめなおしたい」などと言い残して数日後旅立っていったのだ。
すでに40歳を過ぎた夫婦者が手を携えてアメリカ大陸へヒッピーさながらに放浪の旅へと、勇躍という形容が相応しいかどうか疑問だが、とにかく二人はアメリカ行きを敢行したのである。
帰ってきたのは丸一年後だった。
二人の家を訪ねていろいろ話し込んだが、心なしか細君のほうに一年の放浪のためだけではなかろうやつれを感じた。
私のほうにもいろいろあって、その後はお互い訪ねあうこともなく打ち過ぎていたのだが、そういえば夫君が蕎麦打ち修業をしているという話を聞く機会もあったのだが、それがいつの頃だったかは失念してしまっている。
兎に角、私にとっての彼らの記憶は、冒頭のそば切り「凡愚」の誕生となるのである。
一風変わったというより、かなり破天荒な蕎麦屋である「凡愚」はオープン以来、グルメ雑誌などにたびたび紹介され、話題が話題を呼び、全国から旅の寄る辺にわざわざ立ち寄る客が後を絶たないようだ。
結構なことではある。結構このうえないのだが、私の胸の内では、この夫婦、まだもう一度は大きく転身をはかるのだろうな、という予感がする。それがどういう形をとるものかは予想もつきがたいし、彼らの思いの内が語らずとも伝わりくるほど身近に接してはいない昨今は手がかりとてないというものだが。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。















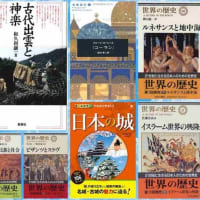




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます