
-表象の森- 紫色の火花と芥川の自殺
昭和2(1927)年の今日、7月24日未明、「僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」なる言葉を遺して自殺したのは芥川龍之介。薬物による服毒自殺だが、35歳というまだ若い死であった。
芥川の忌日を「河童忌」というようだが、もちろん晩年の作品「河童」に因んでのこと。
龍之介の実母は、彼の生後7ヶ月頃、精神に異常をきたしたといわれ、それ故に乳飲み子の彼は、母の実家である芥川家に引き取られ、育てられたというが、そのことが龍之介の内面深くどれほどの影を落としたかは想像も及ばないが、彼の憂鬱の根源にどうしても強く関わらざるを得ないものであったろう。
久米正雄に託されたという遺作「或阿呆の一生」は彼の自伝とも目される掌編だが、いくらか脈絡の辿りにくい51のごく短い断章がコラージュの如く配列されている。
例えば「八、火花」と題された断章、
「彼は雨に濡れたまま、アスフアルトの上を踏んで行つた。雨は可也烈しかつた。彼は水沫の満ちた中にゴム引の外套の匂を感じた。
すると目の前の架空線が一本、紫いろの火花を発してゐた。彼は妙に感動した。彼の上着のポケツトは彼等の同人雑誌へ発表する彼の原稿を隠してゐた。彼は雨の中を歩きながら、もう一度後ろの架空線を見上げた。
架空線は相変わらず鋭い火花を放つてゐた。彼は人生を見渡しても、何も特に欲しいものはなかつた。が、この紫色の火花だけは、――凄まじい空中の火花だけは命と取り換へてもつかまへたかつた。」
彼の命と取り換えてでも掴みたかったという、「紫色の火花-凄まじい空中の火花」が何であったかはいかようにも喩えられようが、同人雑誌に発表するという懐に抱いた彼の原稿が、その一瞬に輝いた閃光に照射されるという僥倖が、ここで自覚されていることはまちがいあるまい。
だが、彼を生の根源から揺さぶる憂鬱は、その僥倖さへなおも生き続けることへの力と成さしめなかったようで、「四十四、死」では、
「彼はひとり寝てゐるのを幸ひ、窓格子に帯をかけて縊死しようとした。が、帯に頸を入れて見ると、俄かに死を恐れ出した。それは何も死ぬ刹那の苦しみの為に恐れたのではなかつた。彼は二度目には懐中時計を持ち、試みに縊死を計ることにした。するとちよつと苦しかつた後、何も彼もぼんやりなりはじめた。そこを一度通り越しさへすれば、死にはひつてしまふのに違ひなかつた。彼は時計の針を検べ、彼の苦しみを感じたのは一分二十何秒かだつたのを発見した。窓格子の外はまつ暗だつた。しかしその暗の中に荒あらしい鶏の声もしてゐた。」
と書かしめ、最終章の「五十五、敗北」へとたどりゆく。
「彼はペンを執る手も震へ出した。のみならず涎さへ流れ出した。彼の頭は〇・八のヴエロナアルを用ひて覚めた後の外は一度もはつきりしたことはなかつた。しかもはつきりしてゐるのはやつと半時間か一時間だつた。彼は唯薄暗い中にその日暮らしの生活をしてゐた。言はば刃のこぼれてしまつた、細い剣を杖にしながら。」
この稿了は昭和2年6月と打たれているが、すでに久しく彼の生と死はまだら模様を描き、ただその淵を彷徨いつづけているのみ、とみえる。
7月24日の龍之介の自殺が、早期の発見を自身想定した狂言自殺だったとの説もあるようだが、よしんば事実がそうであったにせよ、この遺稿を読みたどれば、その真相の詮索にはあまり意味があるとも思えないし、後人が狂言説を喧しく言挙げしないのも納得のいくところだ。
<歌詠みの世界-「清唱千首」塚本邦雄選より>
<恋-32>
見し人の面影とめよ清見潟袖に関守る波の通ひ路 飛鳥井雅経
新古今集、恋四、水無瀬の恋十五首歌合に。
邦雄曰く、歌合での題は「関路恋」、本歌は詞花・恋上、平祐挙の「胸は富士袖は清見が関なれや煙も波も立たぬ日ぞなき」。袖の波とは、流す涙の海の波。番(つがい)、左は家隆「忘らるる浮名をすすげ清見潟関の岩越す波の月影」で、持(じ)。いずれも命令形二句切れの清見潟ながら、右の本歌取りの巧さは比類がない。この歌のほうが新古今集に採られたのも当然か、と。
わが袖は潮干に見えぬ沖の石の人こそ知らね乾く間ぞなき
二条院讃岐
千載集、恋二、寄石恋といへる心を。
邦雄曰く、源三位頼政の女、讃岐は、この代表作をもって「沖の石の讃岐」の雅称を得た。家集に「わが恋は」として見え、千載集選入の際、選者俊成が手を加えたものか。「わが恋は」のほうが、より強く、しかも「乾く間」に即き過ぎずあはれは勝る。父の歌にも、「ともすれば涙に沈む枕かな潮満つ磯の石ならなくに」があり、併誦するとひとしおゆかしい、と。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。















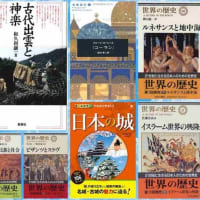




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます