……苦行はつづく……
<一茶と山頭火>
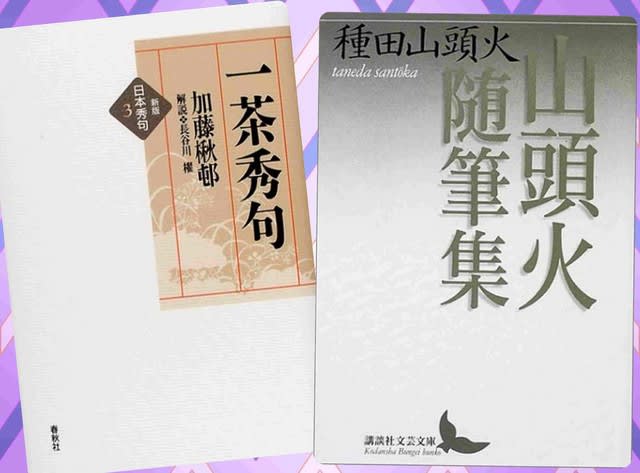
-表象の森- 愚にかへる -2006.05.06記
春立つや愚の上にまた愚にかへる
文政6(1823)年、数えて61歳の還暦を迎えた歳旦の句である。
前書に「からき命を拾ひつつ、くるしき月日おくるうちに、ふと諧々たる夷(ヒナ)ぶりの俳諧を囀りおぼゆ。-略-今迄にともかくも成るべき身を、ふしぎにことし六十一の春を迎へるとは、げにげに盲亀の浮木に逢へるよろこびにまさりなん。されば無能無才も、なかなか齢を延ぶる薬になんありける」と。自分の還暦に達したことを素直に喜びながら、それも「無能無才」ゆえだと述懐している。
また文政5(1822)年の正月、「御仏は暁の星の光に、四十九年の非をさとり給ふとかや。荒凡夫のおのれのごとき、五十九年が間、闇きよりくらきに迷ひて、はるかに照らす月影さへたのむ程の力なく、たまたま非を改めんとすれば、暗々然として盲の書を読み、あしなへの踊らんとするにひとしく、ますます迷ひに迷ひをかさねぬ。げにげに諺にいふとほり、愚につける薬もあらざれば、なほ行末も愚にして、愚のかはらぬ世を経ることをねがふのみ」とあり、ここにも愚の上に愚をかさねていこうという覚悟は表れているが、その胸底には、非を改めようとしても改めきれない業のごときものへの嘆きが、切実に洩らされているのだともいえようか。
類句に「鶯も愚にかへるかよ黙つてる」-文政8(1825)年作-がある。
山頭火もまた「愚にかえれ、愚をまもれ」と折につけ繰り返したが、その山頭火が一茶に触れた掌編があるので併せて紹介しよう。
大の字に寝て涼しさよ淋しさよ
一茶の句である。いつごろの作であるかは、手許に参考書が一冊もないから解らないけれど、多分放浪時代の句であろうと思う。
一茶は不幸な人間であった。幼にして慈母を失い、継母に苛められ、東漂西泊するより外はなかった。彼は幸か不幸か俳人であった。恐らくは俳句を作るより外には能力のない彼であったろう。彼は句を作った。悲しみも歓びも憤りも、すべても俳句として表現した。彼の句が人間臭ふんぷんたる所以である。煩悩無尽、煩悩そのものが彼の句となったのである。
しかし、この句には、彼独特の反感と皮肉がなくて、のんびりとしてそしてしんみりとしたものがある。
「大の字に寝て涼しさよ」はさすがに一茶的である。いつもの一茶が出ているが、つづけて、「淋しさよ」とうたったところに、ひねくれていない正直な、すなおな一茶の涙が滲んでいるではないか。
切っても切れない、断とうとしても断てない執着の絆を思い、孤独地獄の苦悩を痛感したのであろう。一茶の作品は極めて無造作に投げ出したようであるが、その底に潜んでいる苦労は恐らく作家でなければ味読することができまい。
いうまでもなく、一茶には芭蕉的の深さはない。蕪村的な美しさもない。しかし彼には一茶の鋭さがあり、一茶的な飄逸味がある。
ちなみに「大の字に寝て」の句が詠まれたのは、文化10(1813)年、一茶51歳の時。人生五十年の大半を、江戸に旅にと、異郷に暮らし、しかも義母弟との長い相剋辛苦の末に得た故郷信濃の「終の栖」に、「これがまあつひの栖か雪五尺」と詠んだ翌年のこと。
この点は山頭火の記憶違いである。
―――参照 加藤楸邨「一茶秀句」、種田山頭火「山頭火随筆集」

<今月の購入本>2013年02月
◇吉岡 忍「墜落の夏―日航123便事故全記録」新潮文庫
◇飯塚 訓「墜落の村-御巣鷹山日航機墜落事故をめぐる人びと」河出書房新社
◇河 信基「代議士の自決―新井将敬の真実」三一書房
◇栗原 俊雄「20世紀遺跡-帝国の記憶を歩く」角川学芸出版
◇帚木 蓬生「閉鎖病棟」新潮文庫
◇帚木 蓬生「安楽病棟」新潮文庫
◇檜垣 立哉「子供の哲学-産まれるものとしての身体」講談社選書メチエ
<一茶と山頭火>
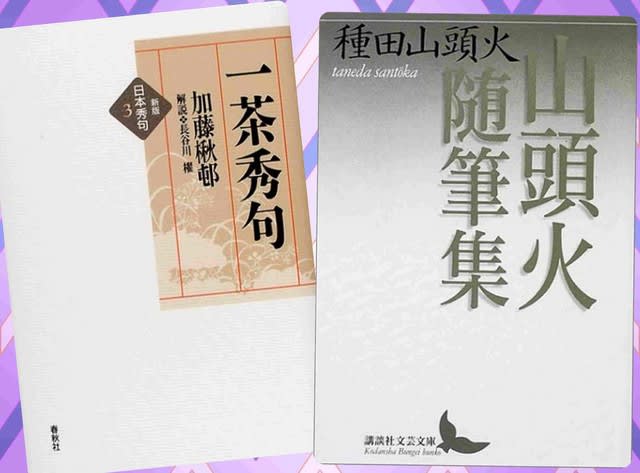
-表象の森- 愚にかへる -2006.05.06記
春立つや愚の上にまた愚にかへる
文政6(1823)年、数えて61歳の還暦を迎えた歳旦の句である。
前書に「からき命を拾ひつつ、くるしき月日おくるうちに、ふと諧々たる夷(ヒナ)ぶりの俳諧を囀りおぼゆ。-略-今迄にともかくも成るべき身を、ふしぎにことし六十一の春を迎へるとは、げにげに盲亀の浮木に逢へるよろこびにまさりなん。されば無能無才も、なかなか齢を延ぶる薬になんありける」と。自分の還暦に達したことを素直に喜びながら、それも「無能無才」ゆえだと述懐している。
また文政5(1822)年の正月、「御仏は暁の星の光に、四十九年の非をさとり給ふとかや。荒凡夫のおのれのごとき、五十九年が間、闇きよりくらきに迷ひて、はるかに照らす月影さへたのむ程の力なく、たまたま非を改めんとすれば、暗々然として盲の書を読み、あしなへの踊らんとするにひとしく、ますます迷ひに迷ひをかさねぬ。げにげに諺にいふとほり、愚につける薬もあらざれば、なほ行末も愚にして、愚のかはらぬ世を経ることをねがふのみ」とあり、ここにも愚の上に愚をかさねていこうという覚悟は表れているが、その胸底には、非を改めようとしても改めきれない業のごときものへの嘆きが、切実に洩らされているのだともいえようか。
類句に「鶯も愚にかへるかよ黙つてる」-文政8(1825)年作-がある。
山頭火もまた「愚にかえれ、愚をまもれ」と折につけ繰り返したが、その山頭火が一茶に触れた掌編があるので併せて紹介しよう。
大の字に寝て涼しさよ淋しさよ
一茶の句である。いつごろの作であるかは、手許に参考書が一冊もないから解らないけれど、多分放浪時代の句であろうと思う。
一茶は不幸な人間であった。幼にして慈母を失い、継母に苛められ、東漂西泊するより外はなかった。彼は幸か不幸か俳人であった。恐らくは俳句を作るより外には能力のない彼であったろう。彼は句を作った。悲しみも歓びも憤りも、すべても俳句として表現した。彼の句が人間臭ふんぷんたる所以である。煩悩無尽、煩悩そのものが彼の句となったのである。
しかし、この句には、彼独特の反感と皮肉がなくて、のんびりとしてそしてしんみりとしたものがある。
「大の字に寝て涼しさよ」はさすがに一茶的である。いつもの一茶が出ているが、つづけて、「淋しさよ」とうたったところに、ひねくれていない正直な、すなおな一茶の涙が滲んでいるではないか。
切っても切れない、断とうとしても断てない執着の絆を思い、孤独地獄の苦悩を痛感したのであろう。一茶の作品は極めて無造作に投げ出したようであるが、その底に潜んでいる苦労は恐らく作家でなければ味読することができまい。
いうまでもなく、一茶には芭蕉的の深さはない。蕪村的な美しさもない。しかし彼には一茶の鋭さがあり、一茶的な飄逸味がある。
ちなみに「大の字に寝て」の句が詠まれたのは、文化10(1813)年、一茶51歳の時。人生五十年の大半を、江戸に旅にと、異郷に暮らし、しかも義母弟との長い相剋辛苦の末に得た故郷信濃の「終の栖」に、「これがまあつひの栖か雪五尺」と詠んだ翌年のこと。
この点は山頭火の記憶違いである。
―――参照 加藤楸邨「一茶秀句」、種田山頭火「山頭火随筆集」

<今月の購入本>2013年02月
◇吉岡 忍「墜落の夏―日航123便事故全記録」新潮文庫
◇飯塚 訓「墜落の村-御巣鷹山日航機墜落事故をめぐる人びと」河出書房新社
◇河 信基「代議士の自決―新井将敬の真実」三一書房
◇栗原 俊雄「20世紀遺跡-帝国の記憶を歩く」角川学芸出版
◇帚木 蓬生「閉鎖病棟」新潮文庫
◇帚木 蓬生「安楽病棟」新潮文庫
◇檜垣 立哉「子供の哲学-産まれるものとしての身体」講談社選書メチエ









