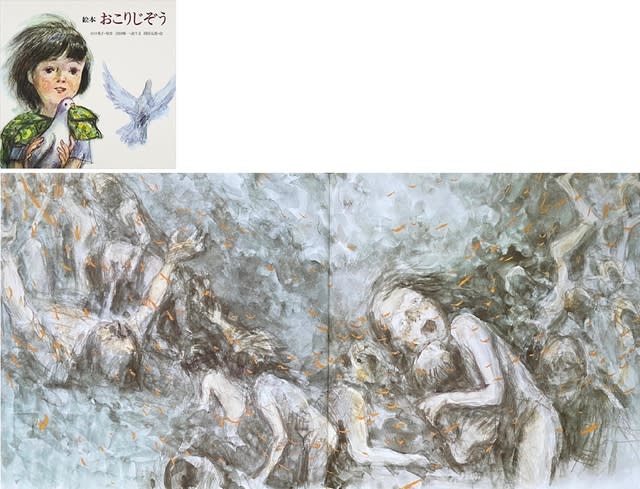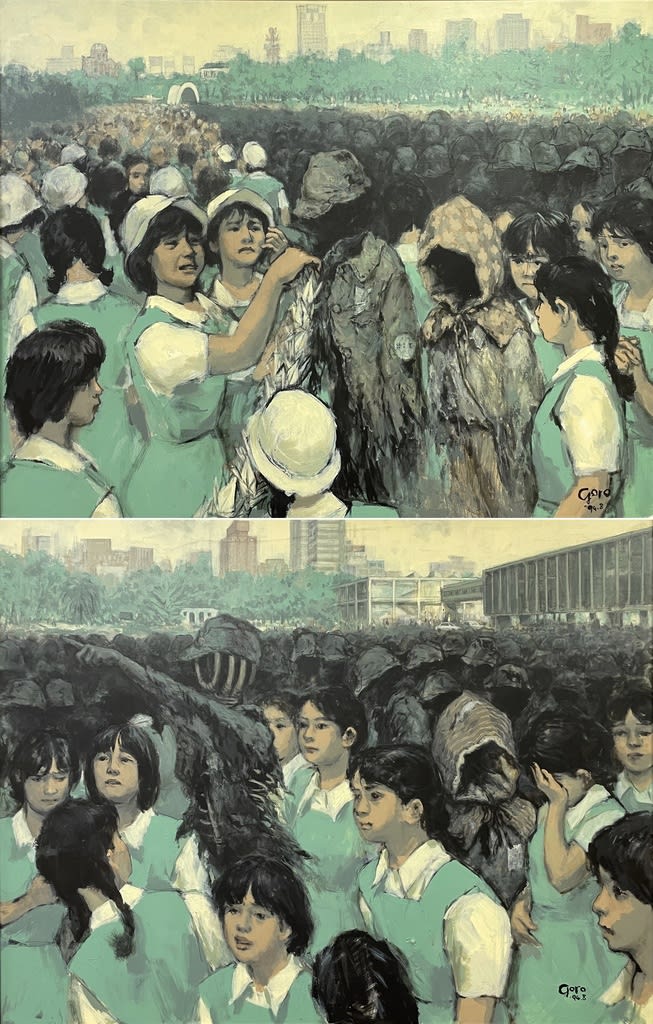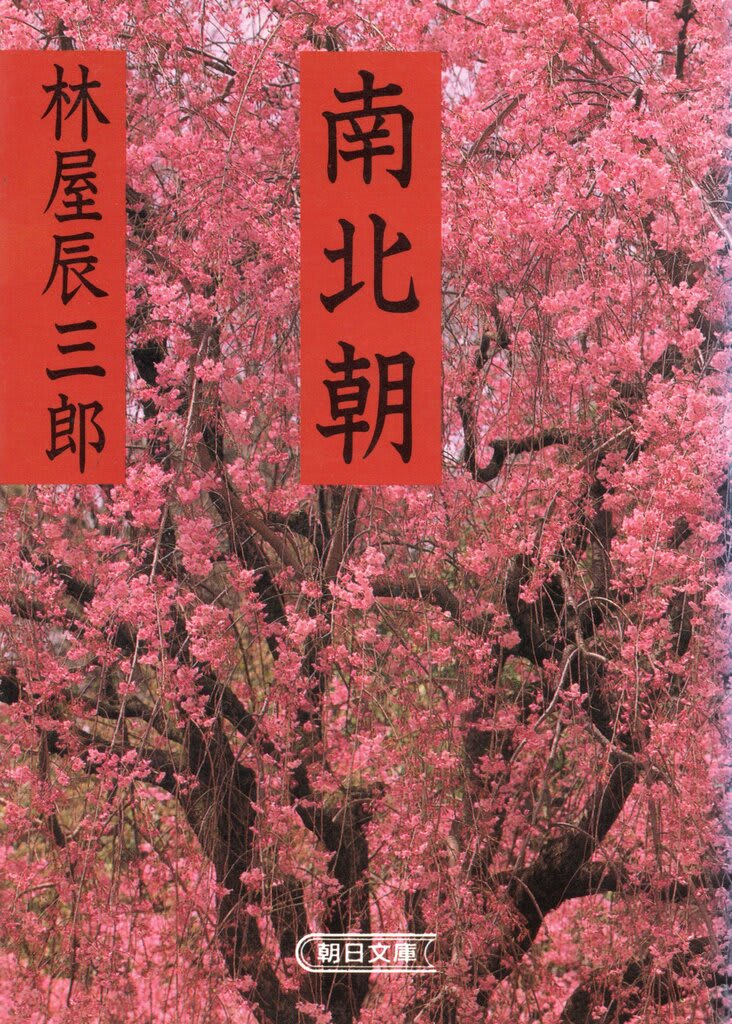真鍋 淑郎, アンソニー・J・ブロッコリー, 阿部 彩子・増田 耕一 (翻訳, 監修), 宮本 寿代 (翻訳)「地球温暖化はなぜ起こるのか - 気候モデルで探る 過去・現在・未来の地球」講談社 (ブルーバックス 2022/6).
序文には「(著者のひとり)真鍋がプリンストン大学大気海洋科学プログラムで教えた大学院課程の講義ノートをもとにしている」とあるが,大学院レベルの教科書をイメージすると勝手が違う.数式を使えばすっきりすると思われる部分もほとんどコトバで説明するので,まどろしく分かりにくい.フラックス調整とか湿潤対流調整とかも,この厚さの本では無理かもしれないが,数式に数値を入れて定量的に示していただきたいところだ.
翻訳は悪くないと思う.
学術図書並みに図版目次,文献リスト,索引完備.勉強したければ文献を当たりなさい...ということか.2010 年代後半以降の文献はあまりないが,大した進歩がなかったのでしょう.カラー図版が参照すべき位置に挿入されず,巻頭にまとめられているのは不満.
数式なしだからポピュラーサイエンス本ということ ? それにしては口当たりが悪すぎ ! ブルーバックス化は最初は念頭になかったように思う.講談社の編集担当はひとことも口を挟んでいないのではないか.
監訳者あとがきには「読む方は第1章の後半から内容が急に高度になったと感じるかもしれない.それは「悟り」がここに書かれているからである」.だから「第1章を難しく感じた方も,気にせずその先へと進んでほしい」とある.仰せの通り,かなりの斜め読みではあったが,読み進んだら最後まで行ってしまった.
深く狭い分野ではなし,シュレディンガー方程式・マックスウェル方程式に匹敵する予備知識は不要だから,なんとかついて行けた,というところ.
講談社 BOOK 倶楽部のホームページに詳細な目次があるが,章のタイトルだけをあげると以下のようになる.n) という表記は第 n 章のことである.
1) はじめに / 2) 初期の研究 / 3)1次元モデル / 4)大循環モデル / 5)初期の数値実験 / 6)気候感度 / 7) 氷期・間氷期の比較 / 8) 気候変化における海洋の役割 / 9) 寒冷な気候と海洋深層水の形成 / 10) 地球の水循環はどう変わるか?
まず観測を再現するプログラムを作り,そこで CO2 量のようなパラメータを振るのはどの分野のシミュレーションでもおなじこと.16 トンにとって馴染みが深いのはプラズマのシミュレーションで,それと本質的には変わらないのだが,実験室プラズマの構成要素や境界条件に比べると,地球は生き物であり,ずっと複雑だということは実感できた.おもしろかったのは 7)-9) だった.
6) のタイトルとされている「気候感度」は平衡応答のことである.この 6) では珍しく数式が登場し,フィードバックについて記述される.ここは大学初年級の制御工学の説明を取り入れればずっとスマートに行けそうだ.7) までは平衡応答,すなわち熱を強制的に与えたとき,長い時間をかけて気候が落ち着く先を調べているが,8) 以下では過渡応答が問題にされる.
「コントロール実験」という耳慣れない言葉も頻出するが,これは標準的なパラメータを用いた試行の結果で,パラメータを振った結果と比べるときのスタンダードというほどの意味らしい.
この春の第77回物理学会年次大会領域13には林 弘文氏 (この7月にご逝去) による「真鍋論文に学べ」という,語呂合わせのようなタイトルのチュートリアル講演があったそうだ.