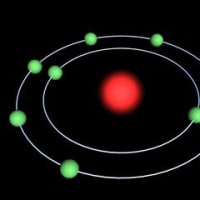時間がなかったので、以前、書いたことを再掲します。
川端康成の『雪国』の描写に主語がない、ということを通して、「私」の位置を考えてみたものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
よく知られるように、川端康成の「雪国」は、
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」
という文章で始まっている。
この文には主語がない。いったい何が、あるいは誰が、長いトンネルを抜けたのか、肝心なそのことが描かれていない。
国境の長いトンネルを抜けるのは、筆者ではない。島村(主人公)という人物が、そういう経験をした、と述べているのでもない。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」とは、ある人物がたまたま持った経験を述べている文ではないのだ。もし強いて「私」という語を使うなら、国境の長いトンネルを抜けると雪国であったという、そのことそれ自体が「私」なのである。だから、その経験をする主体は、その世界内の一部として存在しているわけではない。西田幾多郎の用語を使うなら、これは主体と客体が分かれる以前の「純粋経験」の描写である。
(典拠:西田幾多郎 絶対無とは何か 永井均著 NHK出版)
後半部は何を言いたいのかよく分からないかもしれない。
だから『雪国』の原文をもう少し引用してみよう。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。
向側の座席から娘が立って来て、島村の前のガラス窓を落した。雪の冷気が流れこんだ。娘は窓いっぱいに乗り出して、遠くへ叫ぶように、
『駅長さあん、駅長さあん。』
明りをさげてゆっくり雪を踏んで来た男は、襟巻で鼻の上まで包み、耳に帽子の毛皮を垂れていた。
もうそんな寒さかと島村は外を眺めると、鉄道の官舎らしいバラックが山裾に寒々と散らばっているだけで、雪の色はそこまで行かぬうちに闇に呑まれていた」
この「島村」(主人公の名前)の部分を、「私」と置き換えれば、首尾一貫した一人称の小説としてすんなり読める。ところがこの小説は、一人称のような表現が使われながら、あくまで島村を主人公とした三人称の小説なのだ。だから私はここを読むと、あたかも私自身がカメラとなって、このシーンと私が一体化しているような感覚に陥るのである。
英語だとこういう表現にはならないそうだ。
川端作品の翻訳を多くを手掛けたE.サイデンステッカー氏は、この文を
「The train came out of the long tunnel into the snow country.」
と訳している。ここには原文にはなかった「train(汽車)」という主語が入っている。
こうなると視点が変わってしまう。
この文から思い浮かぶ情景を英語圏の人に描かせたところ、汽車の中からの情景を描いたものは皆無で、全員が上方から見下ろしたアングルでトンネルを描いていたらしい。明らかに話者の視点は汽車の外にある。トンネルからは列車の頭が顔を出しており、列車内に主人公らしい人物を配した者もいたそうだ。
この文では、私はあくまでカメラマンで、カメラを手に持って、高いところからトンネルを抜けていく汽車を撮影している感じとなり、原文のような奇妙な感覚は受けない。
この違いが、「私」という常識的な概念を破る、一つのきっかけになるかもしれないと思っている。
川端康成の『雪国』の描写に主語がない、ということを通して、「私」の位置を考えてみたものです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
よく知られるように、川端康成の「雪国」は、
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」
という文章で始まっている。
この文には主語がない。いったい何が、あるいは誰が、長いトンネルを抜けたのか、肝心なそのことが描かれていない。
国境の長いトンネルを抜けるのは、筆者ではない。島村(主人公)という人物が、そういう経験をした、と述べているのでもない。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」とは、ある人物がたまたま持った経験を述べている文ではないのだ。もし強いて「私」という語を使うなら、国境の長いトンネルを抜けると雪国であったという、そのことそれ自体が「私」なのである。だから、その経験をする主体は、その世界内の一部として存在しているわけではない。西田幾多郎の用語を使うなら、これは主体と客体が分かれる以前の「純粋経験」の描写である。
(典拠:西田幾多郎 絶対無とは何か 永井均著 NHK出版)
後半部は何を言いたいのかよく分からないかもしれない。
だから『雪国』の原文をもう少し引用してみよう。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。
向側の座席から娘が立って来て、島村の前のガラス窓を落した。雪の冷気が流れこんだ。娘は窓いっぱいに乗り出して、遠くへ叫ぶように、
『駅長さあん、駅長さあん。』
明りをさげてゆっくり雪を踏んで来た男は、襟巻で鼻の上まで包み、耳に帽子の毛皮を垂れていた。
もうそんな寒さかと島村は外を眺めると、鉄道の官舎らしいバラックが山裾に寒々と散らばっているだけで、雪の色はそこまで行かぬうちに闇に呑まれていた」
この「島村」(主人公の名前)の部分を、「私」と置き換えれば、首尾一貫した一人称の小説としてすんなり読める。ところがこの小説は、一人称のような表現が使われながら、あくまで島村を主人公とした三人称の小説なのだ。だから私はここを読むと、あたかも私自身がカメラとなって、このシーンと私が一体化しているような感覚に陥るのである。
英語だとこういう表現にはならないそうだ。
川端作品の翻訳を多くを手掛けたE.サイデンステッカー氏は、この文を
「The train came out of the long tunnel into the snow country.」
と訳している。ここには原文にはなかった「train(汽車)」という主語が入っている。
こうなると視点が変わってしまう。
この文から思い浮かぶ情景を英語圏の人に描かせたところ、汽車の中からの情景を描いたものは皆無で、全員が上方から見下ろしたアングルでトンネルを描いていたらしい。明らかに話者の視点は汽車の外にある。トンネルからは列車の頭が顔を出しており、列車内に主人公らしい人物を配した者もいたそうだ。
この文では、私はあくまでカメラマンで、カメラを手に持って、高いところからトンネルを抜けていく汽車を撮影している感じとなり、原文のような奇妙な感覚は受けない。
この違いが、「私」という常識的な概念を破る、一つのきっかけになるかもしれないと思っている。