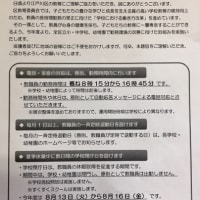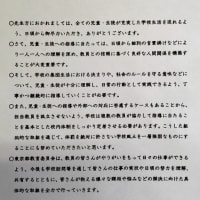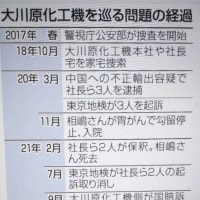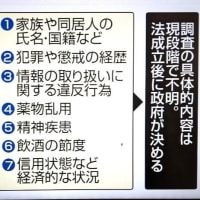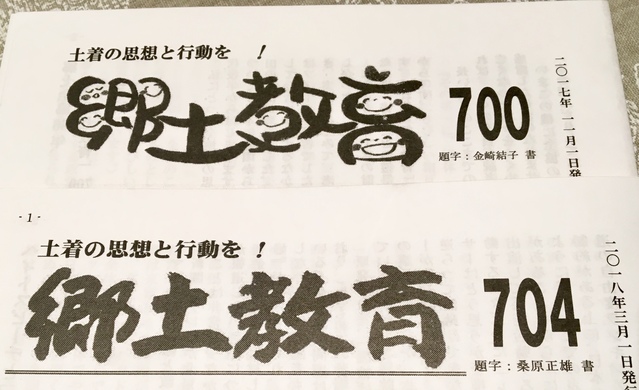04月13日(日)朝10時、テレビ朝日のテレメンタリーPlus「独白 引きこもり40年、それから・・・」を見ました。

山口県宇部市に暮らす国近斉さん、1962年生まれ。
子どもの時から、内気で、内向的なタイプ、中学時代、仲の良い友人がいた、同じ高校を受験したが、友人は不合格だった。
入学した高校は屈指の進学校、国近さんは、周りのみんな優秀で自分は劣等生、授業がわからない、高校2年で中退。
その後アルバイトしたが、うまくいかず、家に引きこもってしまう。
(まだ、17歳、経済的に厳しいわけでもないのだから、まずは定時制の高校にいくとか、専門学校にいくとか、整備工とか一人でやっていく職業に就く道を探せなかったのか・・・どこでつまずいたか原因は分かっているのだから…本人はどうしていいか分からなくても、祖父母、親戚、周りの人で、声を掛けたり、遊びに連れだしたり、悩みを聞き一緒に考えてくれる人はいなかったのか)。
彼は成人式には、スーツを新調し参加している。
彼はどう社会に踏み出していいのかわからない、社会と接点がもてず、いきどころがなくて家にこもっているだけなのに。
「家にいても社会に出ても自分の居場所がない感じ」「ぼーっとすごしていた」当時のことを振り返ります。
登校拒否・不登校が社会問題になったのは、80年後半以降、引きこもりが社会問題になってきたのは、2000年以降。
国近さんは言う「自分はひきこもりの先駆けだった」
両親は一人息子の将来を心配し悩んでいたでしょうが、斉さんを責めたり、追い詰めたりすることもなく、淡々と引きこもりの息子を受け入れ、親子3人、地域とも親類ともかかわらず、平穏に暮らしていたのでしょう。
だから斉さんは昼夜逆転もなることもなく、普通に近所のスーパーに買い物に行っていたし、自分で掃除洗濯をし、時には家族の夕飯を作っていたかもしれない。
10年20年30年が過ぎ、母親が病気に倒れ入院、数か月後亡くなる、2,3年して父親も亡くなる。
50代半ばで一人残された国近さん、この頃から毎日、ノートに日記を書き始める。
親が残した預貯金を毎月6万ずつ下ろして暮らす。
通帳の残高を見て、このままでは行き詰まると焦り始める。
市の広報紙で、ひきこもりのNPO法人「ふらっとコミュニティ」を見つけ、連絡を取る。
理事の山根俊恵さんに、週2回、通うように誘われる。
イベント、おしゃべり会、学習会などに参加、「家に一人いてもやることないし…孤独死した時、早く、見つけてもらいたいし・・・」。
この頃、山口朝日放送の制作班は、「ふらっとコミュニティ」を取材し撮影する中で、国近さんに出会い、彼を中心に撮り始めた。
彼らは撮影のためとはいえ、国近さんのアパートにやって来て、国近さん話を聞き、相談にものった、友人のような付き合いだったでしょう。
2年後、「働きたい」と国近さんは山根理事長に相談。
「どんな仕事がいいですか?」と聞かれて、「人とかかわらない仕事、人の中に入るのが苦手だから」。
国近さんが就いた仕事はハウスクリーニング、上司の指示に従ってチームで清掃をする。
体力的にきつい、現場の上司は、威張って横柄だったり、細かなことをうるさく言ったりするけれど・・・
5年目に上司のパワハラに頭にきた彼は「やめます」。
しかし、5年間の経験があり、別の会社のハウスクリーニングに就く。
もう一つ国近さんを悩ませた難題は、住まい。
親が契約し親と共に住んでいた市営住宅は、両親が亡くなったら、居住契約は切れる。子が60歳以上、又は障碍者の場合を除いて、同居していた子に移譲されない。
国近さんは不正居住のかたちで、罰則として、2倍の家賃を払ってきた。
60歳になったので、名義を変更、更新となり、書類を作ることになった。
そのためには連帯保証人、又は身元引受人が必要だが、親戚とは疎遠、頼む人がいない。
国近さんは市役所の市営アパート担当者に相談に行った。
製作スタッフは、市役所まで同伴し、外の縁石で待っていた。
スタッフは、国近さんが担当者から渡された書類を見て、「『親戚は疎遠で、頼めない』とはっきり言った方がいい」と助言。
国近さんは、もう一度市役所に戻り、担当者との話し合い。
「身元引受人(死んだときの身柄引き取り人)は、空欄で契約更新ができました」と市役所から出てきて、ホッとしたように語る国近さん。
家賃は本来の料金に戻り、約1万円下がった。よかった!
でも、スタッフのアドバイスに、担当者に粘って交渉できた。
決まりは決まりとしても、引きこもりで収入もない、他に住むところもない50代後半の息子に居住権移譲は認められないのだろうか。
親戚に「連帯保証人にはなれません」の一筆を書かせるような書類を渡すなんて、制作スタッフの助言がなかったら、どうなっただろう。
山口朝日放送の制作者スタッフは、撮る人と撮られる人という関係だけど、国近さんの思い、不安、悩み、これまでの日々のことなど親身になって聞き、共感してくれたでしょう、国近さんは、他者に自分の思いを伝えることに慣れ、心を開いて人と付き合うことに馴染んでいったのでしょう。
山根理事に「仕事も5年続きましたね、がんばりましたね、最近はどうですか?」と聞かれて、「不安はいっぱいです。この先ずっと健康でいられるか…怪我でもしたどうなるか…」
「困ったときは、言ってね。大丈夫、何とかなるから・・・何とかするから・・・」と山根理事。
この言葉を待っている人が、どんなに多くいるだろう。
自己責任論に縛られ、他人とかかわらない、孤立、無縁社会は、物価高に困窮し、底なしに深化する。
「働いても不安、働かなくても不安。ただ、生きていてもいいと思えるようになったかな、社会の一員として、底辺でもいいから、引っかかっていたい」とつぶやく国近さん。
引きこもり40年、それから・・・NPO[ふらっとコミュニティ」にかかわり、ハウスクリーニングのバイトを続け、山口朝日放送の制作スタッフと向き合い、語り合う中で、国近さんの今現在の心境、あまりに謙虚な独白に、切なく、社会の冷めたさが胸に迫りました。
-Ka.M-

山口県宇部市に暮らす国近斉さん、1962年生まれ。
子どもの時から、内気で、内向的なタイプ、中学時代、仲の良い友人がいた、同じ高校を受験したが、友人は不合格だった。
入学した高校は屈指の進学校、国近さんは、周りのみんな優秀で自分は劣等生、授業がわからない、高校2年で中退。
その後アルバイトしたが、うまくいかず、家に引きこもってしまう。
(まだ、17歳、経済的に厳しいわけでもないのだから、まずは定時制の高校にいくとか、専門学校にいくとか、整備工とか一人でやっていく職業に就く道を探せなかったのか・・・どこでつまずいたか原因は分かっているのだから…本人はどうしていいか分からなくても、祖父母、親戚、周りの人で、声を掛けたり、遊びに連れだしたり、悩みを聞き一緒に考えてくれる人はいなかったのか)。
彼は成人式には、スーツを新調し参加している。
彼はどう社会に踏み出していいのかわからない、社会と接点がもてず、いきどころがなくて家にこもっているだけなのに。
「家にいても社会に出ても自分の居場所がない感じ」「ぼーっとすごしていた」当時のことを振り返ります。
登校拒否・不登校が社会問題になったのは、80年後半以降、引きこもりが社会問題になってきたのは、2000年以降。
国近さんは言う「自分はひきこもりの先駆けだった」
両親は一人息子の将来を心配し悩んでいたでしょうが、斉さんを責めたり、追い詰めたりすることもなく、淡々と引きこもりの息子を受け入れ、親子3人、地域とも親類ともかかわらず、平穏に暮らしていたのでしょう。
だから斉さんは昼夜逆転もなることもなく、普通に近所のスーパーに買い物に行っていたし、自分で掃除洗濯をし、時には家族の夕飯を作っていたかもしれない。
10年20年30年が過ぎ、母親が病気に倒れ入院、数か月後亡くなる、2,3年して父親も亡くなる。
50代半ばで一人残された国近さん、この頃から毎日、ノートに日記を書き始める。
親が残した預貯金を毎月6万ずつ下ろして暮らす。
通帳の残高を見て、このままでは行き詰まると焦り始める。
市の広報紙で、ひきこもりのNPO法人「ふらっとコミュニティ」を見つけ、連絡を取る。
理事の山根俊恵さんに、週2回、通うように誘われる。
イベント、おしゃべり会、学習会などに参加、「家に一人いてもやることないし…孤独死した時、早く、見つけてもらいたいし・・・」。
この頃、山口朝日放送の制作班は、「ふらっとコミュニティ」を取材し撮影する中で、国近さんに出会い、彼を中心に撮り始めた。
彼らは撮影のためとはいえ、国近さんのアパートにやって来て、国近さん話を聞き、相談にものった、友人のような付き合いだったでしょう。
2年後、「働きたい」と国近さんは山根理事長に相談。
「どんな仕事がいいですか?」と聞かれて、「人とかかわらない仕事、人の中に入るのが苦手だから」。
国近さんが就いた仕事はハウスクリーニング、上司の指示に従ってチームで清掃をする。
体力的にきつい、現場の上司は、威張って横柄だったり、細かなことをうるさく言ったりするけれど・・・
5年目に上司のパワハラに頭にきた彼は「やめます」。
しかし、5年間の経験があり、別の会社のハウスクリーニングに就く。
もう一つ国近さんを悩ませた難題は、住まい。
親が契約し親と共に住んでいた市営住宅は、両親が亡くなったら、居住契約は切れる。子が60歳以上、又は障碍者の場合を除いて、同居していた子に移譲されない。
国近さんは不正居住のかたちで、罰則として、2倍の家賃を払ってきた。
60歳になったので、名義を変更、更新となり、書類を作ることになった。
そのためには連帯保証人、又は身元引受人が必要だが、親戚とは疎遠、頼む人がいない。
国近さんは市役所の市営アパート担当者に相談に行った。
製作スタッフは、市役所まで同伴し、外の縁石で待っていた。
スタッフは、国近さんが担当者から渡された書類を見て、「『親戚は疎遠で、頼めない』とはっきり言った方がいい」と助言。
国近さんは、もう一度市役所に戻り、担当者との話し合い。
「身元引受人(死んだときの身柄引き取り人)は、空欄で契約更新ができました」と市役所から出てきて、ホッとしたように語る国近さん。
家賃は本来の料金に戻り、約1万円下がった。よかった!
でも、スタッフのアドバイスに、担当者に粘って交渉できた。
決まりは決まりとしても、引きこもりで収入もない、他に住むところもない50代後半の息子に居住権移譲は認められないのだろうか。
親戚に「連帯保証人にはなれません」の一筆を書かせるような書類を渡すなんて、制作スタッフの助言がなかったら、どうなっただろう。
山口朝日放送の制作者スタッフは、撮る人と撮られる人という関係だけど、国近さんの思い、不安、悩み、これまでの日々のことなど親身になって聞き、共感してくれたでしょう、国近さんは、他者に自分の思いを伝えることに慣れ、心を開いて人と付き合うことに馴染んでいったのでしょう。
山根理事に「仕事も5年続きましたね、がんばりましたね、最近はどうですか?」と聞かれて、「不安はいっぱいです。この先ずっと健康でいられるか…怪我でもしたどうなるか…」
「困ったときは、言ってね。大丈夫、何とかなるから・・・何とかするから・・・」と山根理事。
この言葉を待っている人が、どんなに多くいるだろう。
自己責任論に縛られ、他人とかかわらない、孤立、無縁社会は、物価高に困窮し、底なしに深化する。
「働いても不安、働かなくても不安。ただ、生きていてもいいと思えるようになったかな、社会の一員として、底辺でもいいから、引っかかっていたい」とつぶやく国近さん。
引きこもり40年、それから・・・NPO[ふらっとコミュニティ」にかかわり、ハウスクリーニングのバイトを続け、山口朝日放送の制作スタッフと向き合い、語り合う中で、国近さんの今現在の心境、あまりに謙虚な独白に、切なく、社会の冷めたさが胸に迫りました。
-Ka.M-