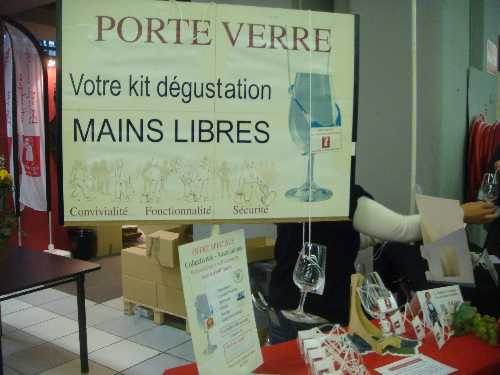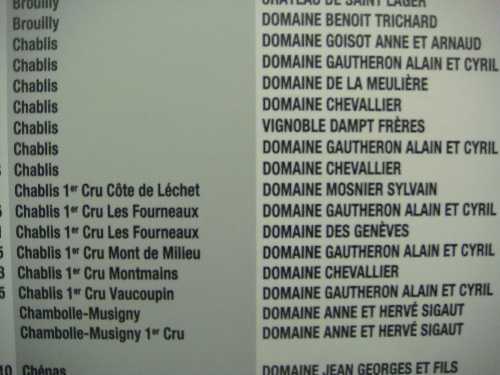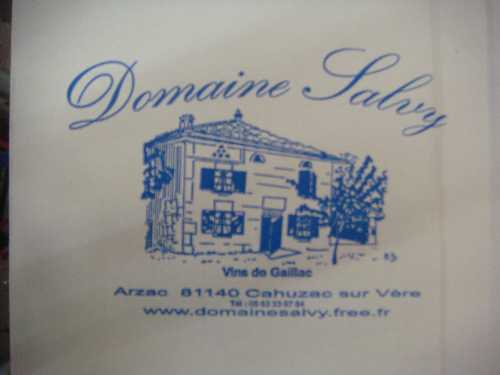三週間ぶりの今回、がらりと趣向を変えて「アフリカの食文化」を、カメルーンからご紹介いたしましょう。

密林の一角にそびえる「バウバオ」の木
アメルーンでは、同じバウバオの木も、繁り方が違って、枝葉が多く実も沢山なるのです。

西アフリカの一角を占めるカメルーン共和国
面積は日本の13倍程(475平方キロ)で、人工は2000万人を切るくらいです。
人口密度が、平方キロ当たり(たった)34人。
280以上の部族からなる「アフリカのライオン」は、南北に渡って非常に文化が異なります。
北部の三分の二の国土は「サバンナ」で、数世紀に渡って続いたイスラムの侵略の影響で、イスラム教圏です。
その最南部が800メートル級の山岳地。
馬で遠征していたイスラムは、馬がその山地を越えられず、イスラム文化の侵入はそこで止まりました。
そこから南の大西洋までは、大航海時代以来西洋人がもたらしたキリスト教の文化圏となり、熱帯雨林の密林地帯も残っています。
10州のうち8州が旧フランス植民地であるため、フランス語でパンも「フランスパン」。
2州は旧イギリス植民地であったため、英語で、パンも「食パン」。
都会は、行政首都『ヤウンデ』と、最大の都市で経済の中心の『ドウアラ』。
どちらもフランス語圏にあります。
残りの町は、三階建て以上の建物が(ほとんど)有りません。。。
経済は、原油と農産物の輸出で成り立っていて、国民一人当たりのGDPは、年間2000ユーロ程。
農産物は、コーヒーと綿花でした。
しかし、中国からの安価な繊維製品の洪水的流入により、原綿の価格が暴落してしまった為に、最近では各地で収穫されずに放置されている綿花畑を、散見する様になりました。

綿花の集積(買い付け業者のところに収穫した綿花が集う)
地域経済は、総てが『市場』を中心に回っています。
どこの町にも村にも、必ず市場があり、食料品から日常雑貨まで「ありとあらゆる物」が取引されています。
早速、その市場で食材を見てみましょう。

市場の一隅

村の市場
彼等の食事は、地方は伝統的な民族料理で、ヤムイモや名称不明の植物を使って、主に「でんぷん」を摂取します。

ヤムイモの一種
それらを、蒸してすり潰し、いろんな「正体不明」の香辛料で作ったソースを絡めるのです。

唐辛子売り(ニンニクも)

香辛料(ディテール)
肉も食べますが、所得が低いのでやはりチキンが中心となり、魚は殆どが干し魚。

魚や

魚や(ナマズ)
ナマズや、草魚、雷魚の様な淡水魚ですが、最近は地方の小さなの隅々まで「冷凍庫」が普及し、大西洋の「キャピテーヌ」という大型の白身の魚が好まれています。

肉や

何やら豆の様な木の実を売る子供

食材の植物のカバーの上には、トカゲも(売り物に有らず)

塩売り(岩塩)

水売りまで出ています
ちなみに、都会以外の地方の市は、週に決まった曜日しか起っていません。

店が出ていないときの「ブース」
さあ、いよいよ調理に取りかかりましょう。

ヤムイモを茹でてすり潰す

サトウキビの様にも見える不思議な植物

不思議な植物(ハーブ)の皮を剥く

それらを「石臼」ですり潰す

石臼

オクラの様にネバネバになった、サトウキビみたいな植物

これも何かの植物のピューレ

ヤギはご馳走です

ローストされたヤギ

何やら煮えてる鍋

すり潰してネバネバの食材を葉っぱでチマキに

サフランの様なハーブを使って作る黄色いソース

既に挽いてパウダー状になったソースの元

名物料理『アシュウム』(ヤムイモのピューレに黄色いソース)
この「アシューム」は、チキンの入った黄色いソースを、お皿の周りのヤムイモのピューレで絡めて食します。
街角のレストラン『メシ屋』では、チキンの腿のローストに付け合わせはバナナのフリッターが、定番。

調理用の特別なバナナ『プランタン・バナナ』

レストランで「プランタン・バナナ」を刻む調理係

揚げられているバナナのフリッター
大西洋で取れる、大型の舌平目のムニエルが、絶品です。
厚みが3センチ以上も有りそうな、目の下60センチなどはザラ。
限られたレストランでしか出て来ません。

本日のヒラメはやや小型でした…

チキンのグリル
街角には、露天の焼き肉屋が、必ず店を出しています。
ドラム缶の輪切りの中に炭を熾して、牛肉の大きな塊を焼くのです。
表面に「塩とクミン・パウダー」を塗り付けて。
お客がくれば、塊を細切れに切って、一掴みを「新聞紙」でくるんでくれて 100円くらい。
クミン・パウダー入りの塩を振って食べます。
『ソーヤ』と言って、ナイジェリア辺りから南部カメルーンにかけての、庶民のファーストフードです。

街角のソーヤ売り

ソーヤ売り
ここでは、ご馳走の『瘤』の部分を焼いていました。

瘤牛の瘤の部分の細切れ

瘤牛
北部の都会『ウンガウンデレ』では、毎週木曜日に「牛市」が起ちます。

周辺から牛市のたつンガウンデレに向かう牛の群れ

牛市に向かう牛の群れ
ところで、カメルーンの人たちは、熱いアフリカの常で「コカコーラ」の類いを良く飲みます。
カメルーン独特の、カーヒー味のコーラという、不思議な物も有ります。
それとは別に、アルコール飲料は、野生の『野麦』で<ビール>を作るのです。

野麦

集めた野麦を脱穀する人々

野麦ビールを売る女性
ビールと呼んでいる物の、当然皆さんが日夜飲んでいらっしゃるビールとは、全く違います。
いわば「どぶろく」。
微かに、舌にぴりっと発泡感が感じられる程度の、3度か4度くらいのアルコール飲料ですが、全国で飲まれています。
都会では、「アムステル」とか「33」とか、フランスの大衆ビールが幅を利かせていて、街角のカフェやメシ屋では、みなその「ヨーロッパ」のビール(現地生産ですが)を飲みますが、都会を一歩出ると未だに「野麦(ミール)のビール」が欠かせません。
その他、伝統的な食べ物に、「ピスタッチオのチマキ」が有ります。
先程の写真の物とは違うのですが、レストラン等でも人気のサイドメニューです。

ピスタッチオのチマキ
北部都市ンガウンデレと首都ヤウンデを結ぶ、唯一の鉄道が走っています。
夜行の寝台列車が毎晩走っているのですが、保線状態が悪いので時々脱線が起こり、その度に7~8時間遅れたりしますが、重要な交通の動脈となっています。
その列車が止まる度に、各駅では「チマキ売り」が群がって来るのです。

停止した列車に急ぐ「チマキ」売り達

車窓越しに、やり取りするチマキ売り
大した味がついている訳でもなく、お世辞にも美味しいとは言えないのですが、彼の国の人達は大好きなのです。
一本1円くらい。
言ってみれば、私たちにとっての「おにぎり」みたいな物なのでしょう。

密林特急
デザートには、是非フルーツを。
パイナップルも、完熟でとても美味しいですが、マンゴーやパパイアもお勧めです。
現地では、レモンをふって食します。

ラグビーボール程も有るパパイア
カメルーン。
なじみの無い国ですね。
2002年サッカーの日韓ワールドカップに、遅れて来たチーム、と言う事で話題になりました。
しかし、子供達の教育は周辺アフリカ諸国にまして、国が熱心に取り組んでいます。
日本がODAで全国に200校以上の小学校を建てた事も有って、現地での日本のイメージは良好です。
見かけ以上に清潔で、お腹を壊す事も有りません。
木彫りの彫刻や、伝統的な布地等、素晴らしい物にも事欠きません。

伝統的な柄の布地
是非、お出かけになってみませんか?

実がたわわになったバウバオの木