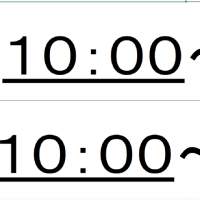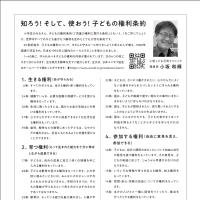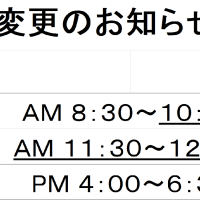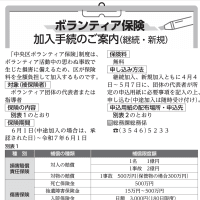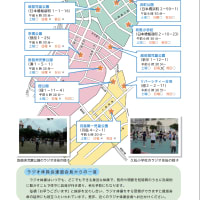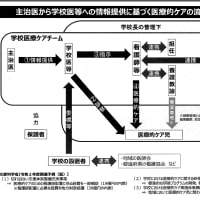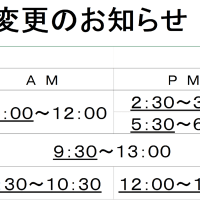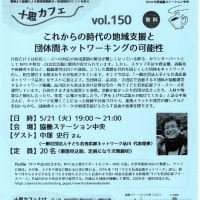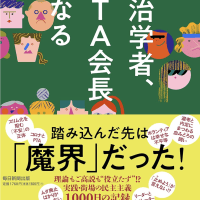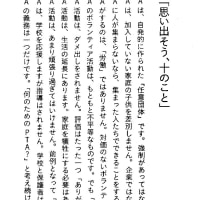以下、横浜市衛生研究所が、わかりやすくまとめられていました。
(情報提供は、聖路加看護大学 堀先生に感謝。)
************************************
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/ninshin1.html
健康な妊娠・出産のために注意したい感染症について
妊娠・出産と感染症
私たちの周囲には、目には見えませんが、細菌やウイルスといった微生物が無数に存在します。人に感染症を引き起こす微生物である病原体も存在します。これらの病原体の中には、妊娠中の女性が感染すると、妊娠の経過やおなかの赤ちゃんに悪い影響を与える病原体もあることが知られています。ここでは、健康な妊娠・出産のために、そのような病原体に対する対策を考えて見ましょう。
食品からの病原体
リステリアは、ある種のチーズや、滅菌消毒されていない乳製品の中に見出されることがある細菌です。また、ニワトリ・アヒル・ガチョウ・七面鳥などの肉にも見られることがあります。妊娠中にこのリステリアに感染した場合、新生児に命にかかわる敗血症や髄膜炎を起こすことがあります。
トキソプラズマは、加熱不十分な肉や、洗っていない果実や野菜で見出されることがある原虫です。妊娠中にこのトキソプラズマに感染した場合、生まれてくる赤ちゃんが目や耳が不自由になったり、精神的発達の遅れが見られたりすることがあります。生まれた直後は問題がないように見えても、後になってこどもに目や脳の問題が出現してくることがあります。
妊娠中は、食品からのリステリアやトキソプラズマの感染を防ぐために、食品について、以下のことに注意しましょう。
食べる前に、肉などの食品を十分に加熱すること。
食べる前に、果実や野菜の皮をむいたり、水で十分に徹底的に洗うこと。
生の肉や、果実・野菜に触れた手や台所用品、まな板や流しなどを、洗剤と水とで十分に洗うこと。
フェタチーズ、ブリーチーズ、カマンベールチーズ、ロクフォーチーズは、食べるのを控えましょう。
滅菌消毒していない生のミルクや、その生のミルクから作ったソフトチーズのような食物を飲食するのは、控えましょう。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「リステリア症について」および「トキソプラズマ症について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
ペットからの病原体
トキソプラズマに感染したネコがトイレにしている場所との接触によって、私たちはトキソプラズマに感染する可能性があります。ネコは、トキソプラズマに感染した小動物や生肉を食べることにより感染することがあります。トキソプラズマに感染してもネコは無症状のこともあり、そのような場合には、ネコがトキソプラズマに感染しているかどうか、外見からは知ることができません。妊娠中にこのトキソプラズマに感染した場合、生まれてくる赤ちゃんが目や耳が不自由になったり、精神的発達の遅れが見られたりすることがあります。生まれた直後は問題がないように見えても、後になってこどもに目や脳の問題が出現してくることがあります。
妊娠中は、ネコからのトキソプラズマの感染を防ぐために、ネコについて、以下のことに注意しましょう。
ネコとの接触はできるだけ避けましょう。
ネコの排泄物が混入している可能性がある土や砂には触れないようにしましょう。土や砂に触れるときは手袋などをして、直接触れないようにして、触れた後ですぐに手をよく洗いましょう。
ネコのトイレは、毎日、他の人に掃除してもらいましょう。
ネコは屋内で飼いましょう。
屋外にいたり、生の肉を食べていたようなネコを、新しく家の中で飼うのは止めましょう。
加熱が不十分な肉や生の肉は、生きている病原体(トキソプラズマのシスト)を含んでいる可能性があります。十分に加熱して病原体を殺すことが大切です。ネコに与える場合でも、人が食べる場合でも、肉は十分に加熱しましょう。また、缶詰や箱詰めのキャットフードをネコのエサにしましょう。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「トキソプラズマ症について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
また、オウム・インコなど私たちの身の回りにいる鳥などが、一見健康に見えても、オウム病に感染していることがあります。オウム病に感染している鳥などとの接触によって私たちはオウム病に感染することがあります。妊婦が感染して、早産・流産・死産になるような場合もあります。オウム病が心配されるような鳥などが身近にいる場合には、獣医に相談しましょう。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「オウム病について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
こどもたちからの病原体
こどもたちは、いろいろな感染症に感染しますが、軽い症状のものが多いです。しかし、それらの感染症の中には、妊娠中に感染すると、おなかの中のこどもが悪影響を受ける場合があるものも知られています。妊娠中には、学校・幼稚園・保育園・託児所・小児科医療機関等のようなこどもたちとの接触が多い職場に勤めているような場合、あるいは家族に小さなこどもがいるような場合には、こどもたちからそのような感染症の病原体を受け取って感染してしまうようなことは、避けるように注意する必要があります。
風疹(三日はしか)や水痘(みずぼうそう)に対しての免疫のない人が、妊娠中に風疹や水痘にかかったりすると、おなかの中のこどもの、目や耳が不自由になったり、精神的発達に遅れが出たり、流産・早産になったりすることがあります。また、妊娠中に、伝染性紅斑(リンゴ病)にかかった場合には、流産・早産・死産になることがあります。また、妊娠中にサイトメガロウイルス(CMV)に感染すると、誕生後にこどもに学習面での問題が生じることがあります。
妊娠中に母親が麻疹(はしか)にかかると、早産、自然流産、低体重児出産の確率を高めます。但し、麻疹が原因の先天奇形はまれとされています。
妊娠中のムンプス(流行性耳下腺炎、おたふくかぜ)の罹患は、先天性奇形と関係ないとされています。しかし、妊娠初期の場合には、流産の確率が高まります。
妊娠中のエンテロウイルスの感染は、流産、死産や先天性奇形と関係ないとされています。しかし、出産の直前の時期に妊婦が感染すると、新生児がエンテロウイルスに感染する恐れがあります。感染した新生児は、通常は軽い症状を起こすだけですが、まれに、肝臓・心臓を含む多くの臓器に感染を起こし死亡する場合もあります。
妊娠中には、風疹、水痘、麻疹(はしか)、ムンプス(流行性耳下腺炎、おたふくかぜ)、サイトメガロウイルス感染症、エンテロウイルス感染症のこどもたちあるいは伝染性紅斑に感染の疑いのこどもたちとは、できるだけ接触しないようにしましょう。接触があったときには、すぐに医師に相談しましょう。
サイトメガロウイルス(CMV)に感染していても、無症状のこどももいます。無症状でもつばや尿の中にサイトメガロウイルス(CMV)が出て来るので、こどもたちのオシメを替えたようなときは、すぐによく手を洗いましょう。
風疹、水痘、麻疹(はしか)とムンプス(流行性耳下腺炎、おたふくかぜ)には予防接種(ワクチン)があります。将来の妊娠を考えている女性は、早めに血液検査(風疹、水痘、麻疹とムンプスに対する抗体検査)を受けて風疹、水痘、麻疹とムンプスに対する免疫の有無を確認し、免疫がない場合には、早めに予防接種(ワクチン)を受けましょう。風疹、水痘、麻疹とムンプスの予防接種(ワクチン)については、妊娠中は接種することができませんし、接種後3ヶ月間は妊娠するのを避ける必要があります。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「風疹について」、「水痘について」、「麻疹(はしか)について」、「ムンプス(流行性耳下腺炎、おたふくかぜ)について」、「伝染性紅斑について」、「サイトメガロウイルス感染症について」、「エンテロウイルスについて」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
性交渉からの病原体
多くの病気が性交渉によって広がります。性交渉によって広がることのある感染症をまとめて、性感染症(STD)ということがあります。性感染症(STD)としては、クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、淋菌感染症(淋病)、梅毒、トリコモナス感染症、B型肝炎、HIV感染症などがあります。妊娠中に性感染症(STD)に感染すると、そのままではおなかの中のこどもが悪影響を受ける場合があります。性感染症(STD)に感染していても、母親が無症状の場合もあるので、まだ生まれて来ないこどものために、性感染症(STD)の検査を妊娠中の母親が受けることもあります。
コンドームは、妊娠を防ぐ目的もありますが、性感染症(STD)を防ぐ目的もあります。性交渉時は、毎回、最初から最後までコンドームを使用しましょう。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「性器クラミジア感染症」、「淋菌感染症(淋病)について」、「性器ヘルペス感染症について」、「梅毒について」、「トリコモナス感染症について」および「HIV感染症について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
その他の病原体
B群連鎖球菌(GBS)は、妊娠女性の5人に1人の割合で、腸や陰部に認められる細菌です。B群連鎖球菌(GBS)が認められても、通常、B群連鎖球菌(GBS)を持っている女性は無症状のことが多いです。しかし、生まれてくるこどもでは、血液・髄液・肺などで重症の感染症を起こすことがあります。B群連鎖球菌(GBS)の検査では、膣や直腸をこすって検体を採取します。妊娠35-37週で検査が行われます。この検査でB群連鎖球菌(GBS)を母親が持っていることが確認されたり、陣痛・分娩時の発熱などの場合に、このB群連鎖球菌(GBS)に赤ちゃんが感染しないように、ペニシリンのような抗生物質が母親に点滴投与されることがあります。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「B群連鎖球菌(GBS)感染症について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
2001年4月5日初掲載
2002年1月25日増補
2008年9月2日増補
2009年2月20日増補
2012年5月1日増補
(情報提供は、聖路加看護大学 堀先生に感謝。)
************************************
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/ninshin1.html
健康な妊娠・出産のために注意したい感染症について
妊娠・出産と感染症
私たちの周囲には、目には見えませんが、細菌やウイルスといった微生物が無数に存在します。人に感染症を引き起こす微生物である病原体も存在します。これらの病原体の中には、妊娠中の女性が感染すると、妊娠の経過やおなかの赤ちゃんに悪い影響を与える病原体もあることが知られています。ここでは、健康な妊娠・出産のために、そのような病原体に対する対策を考えて見ましょう。
食品からの病原体
リステリアは、ある種のチーズや、滅菌消毒されていない乳製品の中に見出されることがある細菌です。また、ニワトリ・アヒル・ガチョウ・七面鳥などの肉にも見られることがあります。妊娠中にこのリステリアに感染した場合、新生児に命にかかわる敗血症や髄膜炎を起こすことがあります。
トキソプラズマは、加熱不十分な肉や、洗っていない果実や野菜で見出されることがある原虫です。妊娠中にこのトキソプラズマに感染した場合、生まれてくる赤ちゃんが目や耳が不自由になったり、精神的発達の遅れが見られたりすることがあります。生まれた直後は問題がないように見えても、後になってこどもに目や脳の問題が出現してくることがあります。
妊娠中は、食品からのリステリアやトキソプラズマの感染を防ぐために、食品について、以下のことに注意しましょう。
食べる前に、肉などの食品を十分に加熱すること。
食べる前に、果実や野菜の皮をむいたり、水で十分に徹底的に洗うこと。
生の肉や、果実・野菜に触れた手や台所用品、まな板や流しなどを、洗剤と水とで十分に洗うこと。
フェタチーズ、ブリーチーズ、カマンベールチーズ、ロクフォーチーズは、食べるのを控えましょう。
滅菌消毒していない生のミルクや、その生のミルクから作ったソフトチーズのような食物を飲食するのは、控えましょう。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「リステリア症について」および「トキソプラズマ症について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
ペットからの病原体
トキソプラズマに感染したネコがトイレにしている場所との接触によって、私たちはトキソプラズマに感染する可能性があります。ネコは、トキソプラズマに感染した小動物や生肉を食べることにより感染することがあります。トキソプラズマに感染してもネコは無症状のこともあり、そのような場合には、ネコがトキソプラズマに感染しているかどうか、外見からは知ることができません。妊娠中にこのトキソプラズマに感染した場合、生まれてくる赤ちゃんが目や耳が不自由になったり、精神的発達の遅れが見られたりすることがあります。生まれた直後は問題がないように見えても、後になってこどもに目や脳の問題が出現してくることがあります。
妊娠中は、ネコからのトキソプラズマの感染を防ぐために、ネコについて、以下のことに注意しましょう。
ネコとの接触はできるだけ避けましょう。
ネコの排泄物が混入している可能性がある土や砂には触れないようにしましょう。土や砂に触れるときは手袋などをして、直接触れないようにして、触れた後ですぐに手をよく洗いましょう。
ネコのトイレは、毎日、他の人に掃除してもらいましょう。
ネコは屋内で飼いましょう。
屋外にいたり、生の肉を食べていたようなネコを、新しく家の中で飼うのは止めましょう。
加熱が不十分な肉や生の肉は、生きている病原体(トキソプラズマのシスト)を含んでいる可能性があります。十分に加熱して病原体を殺すことが大切です。ネコに与える場合でも、人が食べる場合でも、肉は十分に加熱しましょう。また、缶詰や箱詰めのキャットフードをネコのエサにしましょう。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「トキソプラズマ症について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
また、オウム・インコなど私たちの身の回りにいる鳥などが、一見健康に見えても、オウム病に感染していることがあります。オウム病に感染している鳥などとの接触によって私たちはオウム病に感染することがあります。妊婦が感染して、早産・流産・死産になるような場合もあります。オウム病が心配されるような鳥などが身近にいる場合には、獣医に相談しましょう。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「オウム病について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
こどもたちからの病原体
こどもたちは、いろいろな感染症に感染しますが、軽い症状のものが多いです。しかし、それらの感染症の中には、妊娠中に感染すると、おなかの中のこどもが悪影響を受ける場合があるものも知られています。妊娠中には、学校・幼稚園・保育園・託児所・小児科医療機関等のようなこどもたちとの接触が多い職場に勤めているような場合、あるいは家族に小さなこどもがいるような場合には、こどもたちからそのような感染症の病原体を受け取って感染してしまうようなことは、避けるように注意する必要があります。
風疹(三日はしか)や水痘(みずぼうそう)に対しての免疫のない人が、妊娠中に風疹や水痘にかかったりすると、おなかの中のこどもの、目や耳が不自由になったり、精神的発達に遅れが出たり、流産・早産になったりすることがあります。また、妊娠中に、伝染性紅斑(リンゴ病)にかかった場合には、流産・早産・死産になることがあります。また、妊娠中にサイトメガロウイルス(CMV)に感染すると、誕生後にこどもに学習面での問題が生じることがあります。
妊娠中に母親が麻疹(はしか)にかかると、早産、自然流産、低体重児出産の確率を高めます。但し、麻疹が原因の先天奇形はまれとされています。
妊娠中のムンプス(流行性耳下腺炎、おたふくかぜ)の罹患は、先天性奇形と関係ないとされています。しかし、妊娠初期の場合には、流産の確率が高まります。
妊娠中のエンテロウイルスの感染は、流産、死産や先天性奇形と関係ないとされています。しかし、出産の直前の時期に妊婦が感染すると、新生児がエンテロウイルスに感染する恐れがあります。感染した新生児は、通常は軽い症状を起こすだけですが、まれに、肝臓・心臓を含む多くの臓器に感染を起こし死亡する場合もあります。
妊娠中には、風疹、水痘、麻疹(はしか)、ムンプス(流行性耳下腺炎、おたふくかぜ)、サイトメガロウイルス感染症、エンテロウイルス感染症のこどもたちあるいは伝染性紅斑に感染の疑いのこどもたちとは、できるだけ接触しないようにしましょう。接触があったときには、すぐに医師に相談しましょう。
サイトメガロウイルス(CMV)に感染していても、無症状のこどももいます。無症状でもつばや尿の中にサイトメガロウイルス(CMV)が出て来るので、こどもたちのオシメを替えたようなときは、すぐによく手を洗いましょう。
風疹、水痘、麻疹(はしか)とムンプス(流行性耳下腺炎、おたふくかぜ)には予防接種(ワクチン)があります。将来の妊娠を考えている女性は、早めに血液検査(風疹、水痘、麻疹とムンプスに対する抗体検査)を受けて風疹、水痘、麻疹とムンプスに対する免疫の有無を確認し、免疫がない場合には、早めに予防接種(ワクチン)を受けましょう。風疹、水痘、麻疹とムンプスの予防接種(ワクチン)については、妊娠中は接種することができませんし、接種後3ヶ月間は妊娠するのを避ける必要があります。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「風疹について」、「水痘について」、「麻疹(はしか)について」、「ムンプス(流行性耳下腺炎、おたふくかぜ)について」、「伝染性紅斑について」、「サイトメガロウイルス感染症について」、「エンテロウイルスについて」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
性交渉からの病原体
多くの病気が性交渉によって広がります。性交渉によって広がることのある感染症をまとめて、性感染症(STD)ということがあります。性感染症(STD)としては、クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、淋菌感染症(淋病)、梅毒、トリコモナス感染症、B型肝炎、HIV感染症などがあります。妊娠中に性感染症(STD)に感染すると、そのままではおなかの中のこどもが悪影響を受ける場合があります。性感染症(STD)に感染していても、母親が無症状の場合もあるので、まだ生まれて来ないこどものために、性感染症(STD)の検査を妊娠中の母親が受けることもあります。
コンドームは、妊娠を防ぐ目的もありますが、性感染症(STD)を防ぐ目的もあります。性交渉時は、毎回、最初から最後までコンドームを使用しましょう。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「性器クラミジア感染症」、「淋菌感染症(淋病)について」、「性器ヘルペス感染症について」、「梅毒について」、「トリコモナス感染症について」および「HIV感染症について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
その他の病原体
B群連鎖球菌(GBS)は、妊娠女性の5人に1人の割合で、腸や陰部に認められる細菌です。B群連鎖球菌(GBS)が認められても、通常、B群連鎖球菌(GBS)を持っている女性は無症状のことが多いです。しかし、生まれてくるこどもでは、血液・髄液・肺などで重症の感染症を起こすことがあります。B群連鎖球菌(GBS)の検査では、膣や直腸をこすって検体を採取します。妊娠35-37週で検査が行われます。この検査でB群連鎖球菌(GBS)を母親が持っていることが確認されたり、陣痛・分娩時の発熱などの場合に、このB群連鎖球菌(GBS)に赤ちゃんが感染しないように、ペニシリンのような抗生物質が母親に点滴投与されることがあります。
さらに詳しくは、当・横浜市衛生研究所ホームページの「感染症情報」の中の「B群連鎖球菌(GBS)感染症について」をご覧ください(下線部をクリックして下さい)。
2001年4月5日初掲載
2002年1月25日増補
2008年9月2日増補
2009年2月20日増補
2012年5月1日増補