Ⅲ
バルマードがフォルミにてレオクスと会見して、一月後。
残暑厳しい日々の中にも、着実に秋は近付いており、大地は一面、恵みのコパトーンへと染まり、収穫の季節が間近であることを風に揺れる麦の穂先の重さが伝えてくれた。
エグラート大陸の各国は、全てが星の北半球に位置している為、季節が逆に春となる国は存在しない。
これは、かつて五千年もの昔に起こったとされる大戦によって、南半球に存在した大陸が失われたからだと言い伝えられている。
現在、人々はその残された大陸を七分割して国家を形成しているのだが、その盟主である北西大陸の王・ノウエル帝は、スレク公国へ対するフォルミ大公国の行為についての処置に、酷く頭を悩めていた。
大陸間の緊張は日増しに高まり、即時、大同盟によるフォルミ討伐をと叫ぶ国も現れだす次第である。
しかし、皇帝の悩みの種はそんな雑音の類ではなく、彼が最も信頼する王である、ティヴァーテ剣王国・剣王バルマードが、各国の王や諸侯たちの集う会議の最中で、こう言い放ったからである。
「一方的にフォルミ大公国を制裁するには、未だ調査が十分ではない。しかも、かの地で起こった厄災を、見事鎮圧せしめたのはフォルミの戦士リシアである。我らが最大の敵はギーガであり、その為にこそ我らは叡智王・ノウエル皇帝陛下の旗の下、各国の王が集い、エグラート大帝国を形成している。私は一戦士として、フォルミの戦士リシアに敬意を表すと共に、いたずらなフォルミへの武力介入には賛同しない」、と。
バルマードのこの発言に、刹那、一同は言葉を失う。
バルマードほどの大国の王が大同盟に反対すれば、残る国々でそれを強行しても、強戦士リシア有するフォルミ軍への勝算も大きく下がる。
それどころか、もしバルマードがフォルミと組めば、大陸最強の剣王と南大陸全土を敵に回す事になる。ティヴァーテ剣王国の国威はそれほどに強大である。
各国の王たちは、それがバルマードに帝位を、大陸全土をくれてやる愚行である事を即座に悟り、一様に口を閉ざしたのだ。
ノウエル帝は事態を収拾する為に、フォルミ制裁凍結の間、バルマードが一子、ウィルハルトを帝都レトレアへと招く事を、バルマードに提案する。
いわゆる、人質である。
これは、ノウエル帝にとって大きな賭けであったが、会議の中、バルマードがそれを即座に承諾したことにより、事なきを得た。
バルマードがティヴァーテへと帰国したのは、それから間もなくである。
その頃には、ウィルハルトが人質としてノウエル帝の元に送られることは国中の噂となっていたが、バルマードは何事も無かったかのように家庭菜園用の鋤や鎌の手入れをしながら、趣味の土いじりに興じていた。
ティヴァーテの王の居城は、大陸最強の剣王に相応しい荘厳で壮大な造りになっており、『ドーラベルン』の名で知られる天下の名城である。
その防御力は核熱級の攻撃すら無傷で耐え、一度、ドーラベルンが城門を閉ざせば、難攻不落の要塞へとその姿を変える。
築城から五千年以上が経過した今でも城の外観が当時のままに保たれているのは、古代遺産のオーバーテクノロジーのおかげとも言えた。
そんな至高の世界遺産とも言えるドーラベルンの王宮の裏手を、罰当たりにもバルマードは一部、畑へと作り変え、そこで農作業を楽しんでいる。畑ならもっと他の場所にもいくらでもあるのに、近いほうが楽くらいの感覚で、王宮内に違和感ありありの300坪ほどの畑を出現させていたのだ。
「いや、違うんだよ。私はね、アットホームな家庭菜園にこだわりたかったんだよ。家の外にいったら、家庭菜園でもなくなるし、第一、家族とのスキンシップがだね」
白い半袖の肩にタオルをかけて、麦わら帽子の下の汗を拭うヒゲオヤジの独り言には、貴重な文化財である世界遺産の一部を作り変えるほどの説得力は微塵も無い。
単にこのヒゲオヤジは、最愛の我が子とのふれあいの場を作りたかったという理由で、無農薬野菜をひたすらに作り続けていた。究極の美少年、ウィルハルトを王宮の外に出したりしたら、たちまち追っかけどもに囲まれ、スキンシップどころではなくなる。
そんな事を語っていると、やっぱりこのヒゲの思惑どおり、大陸中の少女の憧れの君は、のこのこと、木綿の作業着を着てやって来た。ヒゲオヤジの欲望なのか、その純白のカスタム作業着は、女物のドレスに近い仕上がりになっている。
「パパ、手伝いに来たよ」
「おお、ウィルハルトよ。今日もまた一段と麗しい・・・もとい、生き生きしておるな」
ウィルハルトの後ろにピッタリと張り付いてきたエストの存在が消えてしまうくらいに、ウィルハルトのその姿は神々しく、また可憐である。
その姿はあきれるほど美しく、誰もが彼は『男』であると説明されねば、絶世の美少女と見紛うことだろう。ヒゲが萌え萌えなのもわかるが、後ろに付いてきたエストの方も、その背徳的なほどに美少女したウィルハルトのその容貌に、ムラムラと色気を感じずにはいられなかった。
バルマードとエストの視線が交差した時、互いの叫びが瞳の奥にギラッと映る。
(この子は、私が頂くわッ!!)
(誰にもこの子はやらぬわッ!! ワシの目の黒いうちはな!!!)
互いを凝視し、そして明らかな作り笑いを浮かべたバルマードとエスト。
つられるように微笑むウィルハルトのその紛う事なき純真な笑みに、ついつい二人は癒され、争いの空しさから解放されるように、その天使の微笑に見入ってしまう。
この時、バルマードとエストの間に、即座に無言の停戦協定が結ばれ、互いに出張ることなくこの雰囲気を楽しもうと、瞬きのモールス信号が、二人の視線の間で交わされる。
(く・う・き・よ・め・よ・・・こ・む・す・め・!)
(ひ・げ・・・あ・ん・た・も・な・!・!)
そんなヒゲと小娘のやり取りを、遠巻きに見つめる二つの影があった。
茂みの中から覗く二本の望遠鏡。その片方には、マイオストカスタムと刻印されており、その十万倍率の超高性能携帯望遠鏡にまなこを押し付けるのは、あのアホのためぞうである。くれぐれも太陽は見ないで下さいと、子供向けの注意書きがなされている。その横に、保護者のリリスもいた。
「リリス! あの天使は誰だ!? ほら、ヒゲとガキの真ん中にいる」
「大声出さないで下さいよ、剣王に気付かれたら生きては帰れないですから」
「いいから、知っているなら教えろよ」
せっつくためぞうに、リリスは渋々とポッケの中から定期入れっぽいモノの表紙を飾るウィルハルトの写真を見せてやる。
「なんでお前、あの子の写真なんか持ってんだよ」
「知らないあんたが無知なだけよ。ああ、リアルウィル様を見られるなんて、たまにはバカに付いていくものだわ」
「ウィル? ・・・ウィルハルト王子!? あ、あれ、オトコなのか」
赤毛の天使の正体に愕然とするためぞうを横に、リリスはあれこれ妄想モードに入ったのか、口元からよだれを垂らしては、じゅるりと飲み込む仕草を繰り返している。
するとウィルハルトが小ぶりの鎌を片手に、ティヴァーテ柿の剪定を始めだした。実の糖度を上げる為だ。ウィルハルトは手際よく、不揃いの柿の実を落としていく。
ただ、ウィルハルトは料理も出来る人なので、その落とした実にひと手間加えて、特製のジャムを作る材料にしている。
風が揺らす白地のドレス(風作業着)が、ウィルハルトのその姿を一層華やかに、そして艶やかに見せる。それはまるで、名画の中にいるような光景だ。
あまりに美し過ぎるウィルハルトのその姿に、バルマードもエストも手を止めて見惚れていると、ウィルハルトは二人に向かってこう言った。
「ほら、パパもエストも手が動いてないよ。後で甘い物か何か作ってあげるから、さ、頑張ろう」
ヒゲと小娘はうんうんと頷き、せっせと作業を再開した。
ためぞうは指向性マイクでウィルハルトの声を拾うと、その澄んだ美しい声にさらに驚かされる。
「こ、声もまるで美少女だ。信じられん、ほんとにアレがオトコなのか!?」
驚きを隠せないためぞうに、リリスはやれやれといった感じで自分の聞いている音楽プレイヤーのイヤホンの片方をためぞうの耳に突っ込んだ。
すると、とても美しい歌声のポップミュージックが聞こえてくる。
「これ、聞いたことがあるぞ。馬の絵のエンブレムの付いた荷車のCMのヤツだ」
「まあ、有名ですから。ウィル様のベスト曲は、たいてい大手のCMとかによく使われてるんで」
「リリス・・・後で、コピーしてくれ」
「コピーは違法です! ウィル様ファンとして。ちゃんとショップで買いなさい、売上の印税は、全額慈善団体に寄付されているのよ。ちょっとお金払うだけで、あんたも少しは世の中の役に立てるから」
後日、ためぞうは何処のショップを回っても、全ディスクが次回入荷未定なのを知り、仕方なくマイオストが三枚づつ買い揃えているコレクション(初回版)を一枚譲ってもらうことになる。
相当やな顔をするマイオストだったが、ためぞうにうっとうしく絡まれるくらいならと、その時、泣く泣く手放すのであった。
「しっかし、なんちゅー美少女度やねん。顔はあのセリカちゃんに負けないくらい、いや、オレ的カテゴリーで分けるなら、どちらも究極にして至高。だが、あの子はオトコの子だぞ。オレの偉大なる酒池肉林絶倫計画手帳に、オトコの子の名を入れるのは、果たしていかがなものなのか」
あれこれ難しい顔をするためぞう。
ナメクジ級の思考ルーチンしか持ち合わせていないためぞうに、その答えが出せるわけもなく、横でブツブツうるさいためぞうを黙らせるように、リリスはこう言った。
「嫌なら忘れりゃいいんですよ。アゴに一発、腰の入ったアッパーでも入れてあげましょうか」
「はっ!?」
ためぞうはふと我に返り、いそいそとペンを走らせる。
ためぞうなりに考えたのだ。
ウィルハルトをおんなの子化する、へんなビームの出る謎の古代文明の遺産辺りを、これまた謎い半月状の便利なポケットを見つけ出し、その中から探し出せばいい、と。
なるほど、それを探す旅(アドベンチャー)に出ればよいだけではないかと!
まあ、色々と頭の中で言い訳を考えながらウィルハルトの観察を続けるためぞう。
性を超越して美しいウィルハルト。
その容姿に、ただ見惚れるばかりためぞうとリリスであったが、いくら距離が離れているとはいえ、その二人の存在に気付かないほど、バルマードのバカ親セキュリティーは、ボンクラではなかった。
(うーん、うちの子を見てるのがあそこに二人いるねぇ。戦士レベル93と89といった所か。この組み合わせなら、ためぞう君とリリス君辺りかな。まあ取り合えず無害のようだし、手を出してきたら、お仕置きしてやればいいか)
と、そこに、ふらふらと茶色い作務衣を着た赤茶けた髪にヒゲの、グラサンのオッサンが姿を現した。
そのグラサンに向かってウィルハルトは、とても嬉しそうに、弾む声でこう言った。
「オジサマ!」
っと。
その声を集音マイク越しに聞いていた、ためぞうは一気に噴き出し、リリスの方を見る。オジサマ発言に、一体何者なんだと、ためぞうがおろおろしていると、リリスも同じようにその謎のオジサマの出現に、おろおろとしていた。
その時、うかつにもリリスの目がバルマードと合ってしまう。
ニヤリと微笑むバルマードに、背筋にゾゾッと寒気を覚えたリリスは、ためぞうの手を掴み逃走する!!!
「お、おい、リリス、何なんだ!」
「剣王に睨まれました! 本気(マジ)にさせたら逃がしてもくれないです!! さっさと、ずらからないと!!」
「お、お、お、おう!!」
そうしてバカ二人がその場をスタコラ立ち去ると、今度はエストが不機嫌そうに、何、このオッサンと、グラサン相手にハァン? とガン飛ばしている。
バルマードはエストのその仕草に少し慌てたようで、グラサンとエストの間に割って入ると、グラサンのオヤジをこう呼んだ。
「これは、お久しぶりです、我が師よ」
「まあ、茶菓子の礼にちょっと寄ってみた。ウィルちゃんの顔もみたかったしの」
そのバルマードの言葉に、さすがのエストも空気を読んだ。
何の師匠なのかはわからなかったが、格好からして二流の文化人ぽいので、詩か書辺りの師匠だろうとエストは思う。
ウィルハルトが気を利かして、裏から麦茶入りのステンレスボトルを持ってくると、取り外したボトルのフタをグラサンに手渡し、そこに冷えた麦茶を注いだ。
「悪いね、ウィルちゃん。ウィルちゃん見てると、ネタに困らなくて助かるよ」
そう言ってグラサンは、切り株に腰を下ろすとしみじみと麦茶を味わう。
ウィルハルトの麦茶は、何気に自家栽培の最高品種の麦を丁寧にローストしてあるので、かなり美味い。
グラサンは麦茶片手に、「あ、そうそう」と言って、懐から一冊の本を取り出した。サイン入りのその本の表紙に、エストには見覚えがある。
それはマイオストから借りた大量の本の中の一冊で、特にエストが気に入っているそのキャラクターが、グラサンが手にする本の表紙を飾っていた。
それは、来月発売の新刊、ヤマモト・マリアンヌ作『王子様(プリンス)は眠れない・第三夜』である。
「ありがとう、ヤマモトのオジサマ」
「いやいや、ウィルちゃんに読んでもらえるだけで、オジサン嬉しいよ」
エストはこの時、グラサンの正体を悟った!!! 気がした。
エストはそそくさと部屋からスケッチブックを取ってくると、ヤマモトと呼ばれるグラサンオヤジにこう言い放った。
「し、師匠ぉぉぉおおおおっ!! 私、ねむプリの大ファンです! よかったら、スケブお願いしますッ!!」
「いいよー。んで、キャラの希望とかある?」
「もちろん、プリンスを!!」
ヤマモトは手渡されたスケッチブックにマーカーですらすらとウィルハルト似の王子様を描き上げると、サインの為にエストにその名を尋ねた。
「エ、エスト。あ、いえ、『ストロング天婦羅』でお願いします!」
「ああ!! 最近、良く手紙を書いてくれるストロングさんは、君だったのか。いや、嬉しいよ、熱心なお手紙には毎回、感心させられます。特に、意味不明の『王子様攻略アドバイス』を問われる時なんて、グッとインスピレーションが沸いてくるよ」
ヤマモトはそう言って、エストのペンネームのサインを書き入れたスケッチブックを、にこやかにエストに手渡した。
エストは何やら、感極まった様子で、スケッチブックを抱いて天を仰ぎ感涙している。ヤマモトは気を利かせて、ウィルハルトに手渡したのと同じ本をエストに手渡すと、エストは、ハハーーッ! と土下座して、それを拝領した。まるで、町人とお代官様のやりとりだ。
本来、バルマードに手渡す予定だった本なので、バルマード本人は「エーーーーッ!?」、といった顔で、そのやり取りを切なそうに見つめていた。
ヤマモトは言う。
「ごめんね、バルマード。後で担当に、お前さん宛てに送るように言っとくから」
「助かります、全て初版で集めてありますもので」
バルマードが一礼すると、麦茶を飲み終えたヤマモトは、「ありがとう」とウィルハルトに言って、ボトルのフタを手渡し、すくっと立ち上がった。
バルマードは、立ち上がって腰をポンポンと叩くヤマモトにこう言った。
「せっかく、こんな所までいらしたのですから、久しぶりに私に稽古でもつけてくれませんか、師匠」
「うーん、そうだねぇ、別にいいよ」
軽いノリでそう返事するヤマモトであるが、その稽古とは一体何なのか、気になって仕方ない様子のエストであった。
そんな、もじもじとした微妙に可愛い仕草を見せるエストの姿を見て、バルマードは言う。
「ごめんねぇ。エストちゃんは、ウィルハルトと畑の手入れを頼むよ」
ついで、ウィルハルトも言う。
「そうだよ、エスト。せっかくヤマモトのオジサマが見えられたんだから、さっさと仕事を終わらせて、何か美味しいものでも作らないと!」
バルマードはよしよしとウィルハルトの頭を撫でた。
さすがに剣王とリアルプリンスにそう釘を打たれたら、強情で強欲なエストとしても、それに従うしかない。
エストにしてみれば、ウィルハルトと二人きりになるのもそれはそれでアリなので、問題なかった。
立ち去るバルマードと心の師匠ヤマモトに、エストは、屈託のない笑顔で手を振り、振り返っては、さてどうやって、この鈍感超絶美少年王子の好感度を上げてやろうかと、ニヤける口元に下心を垣間見せる。
バルマードは立ち去り際に、残した二人をチラッと見てこう思った。
(いやね、連れて行きたい気もなくはないんだけど、今のエストちゃんとウィルハルトじゃ、立ってるだけで消し飛んでしまうから。今回は、ごめんね。)
バルマードがフォルミにてレオクスと会見して、一月後。
残暑厳しい日々の中にも、着実に秋は近付いており、大地は一面、恵みのコパトーンへと染まり、収穫の季節が間近であることを風に揺れる麦の穂先の重さが伝えてくれた。
エグラート大陸の各国は、全てが星の北半球に位置している為、季節が逆に春となる国は存在しない。
これは、かつて五千年もの昔に起こったとされる大戦によって、南半球に存在した大陸が失われたからだと言い伝えられている。
現在、人々はその残された大陸を七分割して国家を形成しているのだが、その盟主である北西大陸の王・ノウエル帝は、スレク公国へ対するフォルミ大公国の行為についての処置に、酷く頭を悩めていた。
大陸間の緊張は日増しに高まり、即時、大同盟によるフォルミ討伐をと叫ぶ国も現れだす次第である。
しかし、皇帝の悩みの種はそんな雑音の類ではなく、彼が最も信頼する王である、ティヴァーテ剣王国・剣王バルマードが、各国の王や諸侯たちの集う会議の最中で、こう言い放ったからである。
「一方的にフォルミ大公国を制裁するには、未だ調査が十分ではない。しかも、かの地で起こった厄災を、見事鎮圧せしめたのはフォルミの戦士リシアである。我らが最大の敵はギーガであり、その為にこそ我らは叡智王・ノウエル皇帝陛下の旗の下、各国の王が集い、エグラート大帝国を形成している。私は一戦士として、フォルミの戦士リシアに敬意を表すと共に、いたずらなフォルミへの武力介入には賛同しない」、と。
バルマードのこの発言に、刹那、一同は言葉を失う。
バルマードほどの大国の王が大同盟に反対すれば、残る国々でそれを強行しても、強戦士リシア有するフォルミ軍への勝算も大きく下がる。
それどころか、もしバルマードがフォルミと組めば、大陸最強の剣王と南大陸全土を敵に回す事になる。ティヴァーテ剣王国の国威はそれほどに強大である。
各国の王たちは、それがバルマードに帝位を、大陸全土をくれてやる愚行である事を即座に悟り、一様に口を閉ざしたのだ。
ノウエル帝は事態を収拾する為に、フォルミ制裁凍結の間、バルマードが一子、ウィルハルトを帝都レトレアへと招く事を、バルマードに提案する。
いわゆる、人質である。
これは、ノウエル帝にとって大きな賭けであったが、会議の中、バルマードがそれを即座に承諾したことにより、事なきを得た。
バルマードがティヴァーテへと帰国したのは、それから間もなくである。
その頃には、ウィルハルトが人質としてノウエル帝の元に送られることは国中の噂となっていたが、バルマードは何事も無かったかのように家庭菜園用の鋤や鎌の手入れをしながら、趣味の土いじりに興じていた。
ティヴァーテの王の居城は、大陸最強の剣王に相応しい荘厳で壮大な造りになっており、『ドーラベルン』の名で知られる天下の名城である。
その防御力は核熱級の攻撃すら無傷で耐え、一度、ドーラベルンが城門を閉ざせば、難攻不落の要塞へとその姿を変える。
築城から五千年以上が経過した今でも城の外観が当時のままに保たれているのは、古代遺産のオーバーテクノロジーのおかげとも言えた。
そんな至高の世界遺産とも言えるドーラベルンの王宮の裏手を、罰当たりにもバルマードは一部、畑へと作り変え、そこで農作業を楽しんでいる。畑ならもっと他の場所にもいくらでもあるのに、近いほうが楽くらいの感覚で、王宮内に違和感ありありの300坪ほどの畑を出現させていたのだ。
「いや、違うんだよ。私はね、アットホームな家庭菜園にこだわりたかったんだよ。家の外にいったら、家庭菜園でもなくなるし、第一、家族とのスキンシップがだね」
白い半袖の肩にタオルをかけて、麦わら帽子の下の汗を拭うヒゲオヤジの独り言には、貴重な文化財である世界遺産の一部を作り変えるほどの説得力は微塵も無い。
単にこのヒゲオヤジは、最愛の我が子とのふれあいの場を作りたかったという理由で、無農薬野菜をひたすらに作り続けていた。究極の美少年、ウィルハルトを王宮の外に出したりしたら、たちまち追っかけどもに囲まれ、スキンシップどころではなくなる。
そんな事を語っていると、やっぱりこのヒゲの思惑どおり、大陸中の少女の憧れの君は、のこのこと、木綿の作業着を着てやって来た。ヒゲオヤジの欲望なのか、その純白のカスタム作業着は、女物のドレスに近い仕上がりになっている。
「パパ、手伝いに来たよ」
「おお、ウィルハルトよ。今日もまた一段と麗しい・・・もとい、生き生きしておるな」
ウィルハルトの後ろにピッタリと張り付いてきたエストの存在が消えてしまうくらいに、ウィルハルトのその姿は神々しく、また可憐である。
その姿はあきれるほど美しく、誰もが彼は『男』であると説明されねば、絶世の美少女と見紛うことだろう。ヒゲが萌え萌えなのもわかるが、後ろに付いてきたエストの方も、その背徳的なほどに美少女したウィルハルトのその容貌に、ムラムラと色気を感じずにはいられなかった。
バルマードとエストの視線が交差した時、互いの叫びが瞳の奥にギラッと映る。
(この子は、私が頂くわッ!!)
(誰にもこの子はやらぬわッ!! ワシの目の黒いうちはな!!!)
互いを凝視し、そして明らかな作り笑いを浮かべたバルマードとエスト。
つられるように微笑むウィルハルトのその紛う事なき純真な笑みに、ついつい二人は癒され、争いの空しさから解放されるように、その天使の微笑に見入ってしまう。
この時、バルマードとエストの間に、即座に無言の停戦協定が結ばれ、互いに出張ることなくこの雰囲気を楽しもうと、瞬きのモールス信号が、二人の視線の間で交わされる。
(く・う・き・よ・め・よ・・・こ・む・す・め・!)
(ひ・げ・・・あ・ん・た・も・な・!・!)
そんなヒゲと小娘のやり取りを、遠巻きに見つめる二つの影があった。
茂みの中から覗く二本の望遠鏡。その片方には、マイオストカスタムと刻印されており、その十万倍率の超高性能携帯望遠鏡にまなこを押し付けるのは、あのアホのためぞうである。くれぐれも太陽は見ないで下さいと、子供向けの注意書きがなされている。その横に、保護者のリリスもいた。
「リリス! あの天使は誰だ!? ほら、ヒゲとガキの真ん中にいる」
「大声出さないで下さいよ、剣王に気付かれたら生きては帰れないですから」
「いいから、知っているなら教えろよ」
せっつくためぞうに、リリスは渋々とポッケの中から定期入れっぽいモノの表紙を飾るウィルハルトの写真を見せてやる。
「なんでお前、あの子の写真なんか持ってんだよ」
「知らないあんたが無知なだけよ。ああ、リアルウィル様を見られるなんて、たまにはバカに付いていくものだわ」
「ウィル? ・・・ウィルハルト王子!? あ、あれ、オトコなのか」
赤毛の天使の正体に愕然とするためぞうを横に、リリスはあれこれ妄想モードに入ったのか、口元からよだれを垂らしては、じゅるりと飲み込む仕草を繰り返している。
するとウィルハルトが小ぶりの鎌を片手に、ティヴァーテ柿の剪定を始めだした。実の糖度を上げる為だ。ウィルハルトは手際よく、不揃いの柿の実を落としていく。
ただ、ウィルハルトは料理も出来る人なので、その落とした実にひと手間加えて、特製のジャムを作る材料にしている。
風が揺らす白地のドレス(風作業着)が、ウィルハルトのその姿を一層華やかに、そして艶やかに見せる。それはまるで、名画の中にいるような光景だ。
あまりに美し過ぎるウィルハルトのその姿に、バルマードもエストも手を止めて見惚れていると、ウィルハルトは二人に向かってこう言った。
「ほら、パパもエストも手が動いてないよ。後で甘い物か何か作ってあげるから、さ、頑張ろう」
ヒゲと小娘はうんうんと頷き、せっせと作業を再開した。
ためぞうは指向性マイクでウィルハルトの声を拾うと、その澄んだ美しい声にさらに驚かされる。
「こ、声もまるで美少女だ。信じられん、ほんとにアレがオトコなのか!?」
驚きを隠せないためぞうに、リリスはやれやれといった感じで自分の聞いている音楽プレイヤーのイヤホンの片方をためぞうの耳に突っ込んだ。
すると、とても美しい歌声のポップミュージックが聞こえてくる。
「これ、聞いたことがあるぞ。馬の絵のエンブレムの付いた荷車のCMのヤツだ」
「まあ、有名ですから。ウィル様のベスト曲は、たいてい大手のCMとかによく使われてるんで」
「リリス・・・後で、コピーしてくれ」
「コピーは違法です! ウィル様ファンとして。ちゃんとショップで買いなさい、売上の印税は、全額慈善団体に寄付されているのよ。ちょっとお金払うだけで、あんたも少しは世の中の役に立てるから」
後日、ためぞうは何処のショップを回っても、全ディスクが次回入荷未定なのを知り、仕方なくマイオストが三枚づつ買い揃えているコレクション(初回版)を一枚譲ってもらうことになる。
相当やな顔をするマイオストだったが、ためぞうにうっとうしく絡まれるくらいならと、その時、泣く泣く手放すのであった。
「しっかし、なんちゅー美少女度やねん。顔はあのセリカちゃんに負けないくらい、いや、オレ的カテゴリーで分けるなら、どちらも究極にして至高。だが、あの子はオトコの子だぞ。オレの偉大なる酒池肉林絶倫計画手帳に、オトコの子の名を入れるのは、果たしていかがなものなのか」
あれこれ難しい顔をするためぞう。
ナメクジ級の思考ルーチンしか持ち合わせていないためぞうに、その答えが出せるわけもなく、横でブツブツうるさいためぞうを黙らせるように、リリスはこう言った。
「嫌なら忘れりゃいいんですよ。アゴに一発、腰の入ったアッパーでも入れてあげましょうか」
「はっ!?」
ためぞうはふと我に返り、いそいそとペンを走らせる。
ためぞうなりに考えたのだ。
ウィルハルトをおんなの子化する、へんなビームの出る謎の古代文明の遺産辺りを、これまた謎い半月状の便利なポケットを見つけ出し、その中から探し出せばいい、と。
なるほど、それを探す旅(アドベンチャー)に出ればよいだけではないかと!
まあ、色々と頭の中で言い訳を考えながらウィルハルトの観察を続けるためぞう。
性を超越して美しいウィルハルト。
その容姿に、ただ見惚れるばかりためぞうとリリスであったが、いくら距離が離れているとはいえ、その二人の存在に気付かないほど、バルマードのバカ親セキュリティーは、ボンクラではなかった。
(うーん、うちの子を見てるのがあそこに二人いるねぇ。戦士レベル93と89といった所か。この組み合わせなら、ためぞう君とリリス君辺りかな。まあ取り合えず無害のようだし、手を出してきたら、お仕置きしてやればいいか)
と、そこに、ふらふらと茶色い作務衣を着た赤茶けた髪にヒゲの、グラサンのオッサンが姿を現した。
そのグラサンに向かってウィルハルトは、とても嬉しそうに、弾む声でこう言った。
「オジサマ!」
っと。
その声を集音マイク越しに聞いていた、ためぞうは一気に噴き出し、リリスの方を見る。オジサマ発言に、一体何者なんだと、ためぞうがおろおろしていると、リリスも同じようにその謎のオジサマの出現に、おろおろとしていた。
その時、うかつにもリリスの目がバルマードと合ってしまう。
ニヤリと微笑むバルマードに、背筋にゾゾッと寒気を覚えたリリスは、ためぞうの手を掴み逃走する!!!
「お、おい、リリス、何なんだ!」
「剣王に睨まれました! 本気(マジ)にさせたら逃がしてもくれないです!! さっさと、ずらからないと!!」
「お、お、お、おう!!」
そうしてバカ二人がその場をスタコラ立ち去ると、今度はエストが不機嫌そうに、何、このオッサンと、グラサン相手にハァン? とガン飛ばしている。
バルマードはエストのその仕草に少し慌てたようで、グラサンとエストの間に割って入ると、グラサンのオヤジをこう呼んだ。
「これは、お久しぶりです、我が師よ」
「まあ、茶菓子の礼にちょっと寄ってみた。ウィルちゃんの顔もみたかったしの」
そのバルマードの言葉に、さすがのエストも空気を読んだ。
何の師匠なのかはわからなかったが、格好からして二流の文化人ぽいので、詩か書辺りの師匠だろうとエストは思う。
ウィルハルトが気を利かして、裏から麦茶入りのステンレスボトルを持ってくると、取り外したボトルのフタをグラサンに手渡し、そこに冷えた麦茶を注いだ。
「悪いね、ウィルちゃん。ウィルちゃん見てると、ネタに困らなくて助かるよ」
そう言ってグラサンは、切り株に腰を下ろすとしみじみと麦茶を味わう。
ウィルハルトの麦茶は、何気に自家栽培の最高品種の麦を丁寧にローストしてあるので、かなり美味い。
グラサンは麦茶片手に、「あ、そうそう」と言って、懐から一冊の本を取り出した。サイン入りのその本の表紙に、エストには見覚えがある。
それはマイオストから借りた大量の本の中の一冊で、特にエストが気に入っているそのキャラクターが、グラサンが手にする本の表紙を飾っていた。
それは、来月発売の新刊、ヤマモト・マリアンヌ作『王子様(プリンス)は眠れない・第三夜』である。
「ありがとう、ヤマモトのオジサマ」
「いやいや、ウィルちゃんに読んでもらえるだけで、オジサン嬉しいよ」
エストはこの時、グラサンの正体を悟った!!! 気がした。
エストはそそくさと部屋からスケッチブックを取ってくると、ヤマモトと呼ばれるグラサンオヤジにこう言い放った。
「し、師匠ぉぉぉおおおおっ!! 私、ねむプリの大ファンです! よかったら、スケブお願いしますッ!!」
「いいよー。んで、キャラの希望とかある?」
「もちろん、プリンスを!!」
ヤマモトは手渡されたスケッチブックにマーカーですらすらとウィルハルト似の王子様を描き上げると、サインの為にエストにその名を尋ねた。
「エ、エスト。あ、いえ、『ストロング天婦羅』でお願いします!」
「ああ!! 最近、良く手紙を書いてくれるストロングさんは、君だったのか。いや、嬉しいよ、熱心なお手紙には毎回、感心させられます。特に、意味不明の『王子様攻略アドバイス』を問われる時なんて、グッとインスピレーションが沸いてくるよ」
ヤマモトはそう言って、エストのペンネームのサインを書き入れたスケッチブックを、にこやかにエストに手渡した。
エストは何やら、感極まった様子で、スケッチブックを抱いて天を仰ぎ感涙している。ヤマモトは気を利かせて、ウィルハルトに手渡したのと同じ本をエストに手渡すと、エストは、ハハーーッ! と土下座して、それを拝領した。まるで、町人とお代官様のやりとりだ。
本来、バルマードに手渡す予定だった本なので、バルマード本人は「エーーーーッ!?」、といった顔で、そのやり取りを切なそうに見つめていた。
ヤマモトは言う。
「ごめんね、バルマード。後で担当に、お前さん宛てに送るように言っとくから」
「助かります、全て初版で集めてありますもので」
バルマードが一礼すると、麦茶を飲み終えたヤマモトは、「ありがとう」とウィルハルトに言って、ボトルのフタを手渡し、すくっと立ち上がった。
バルマードは、立ち上がって腰をポンポンと叩くヤマモトにこう言った。
「せっかく、こんな所までいらしたのですから、久しぶりに私に稽古でもつけてくれませんか、師匠」
「うーん、そうだねぇ、別にいいよ」
軽いノリでそう返事するヤマモトであるが、その稽古とは一体何なのか、気になって仕方ない様子のエストであった。
そんな、もじもじとした微妙に可愛い仕草を見せるエストの姿を見て、バルマードは言う。
「ごめんねぇ。エストちゃんは、ウィルハルトと畑の手入れを頼むよ」
ついで、ウィルハルトも言う。
「そうだよ、エスト。せっかくヤマモトのオジサマが見えられたんだから、さっさと仕事を終わらせて、何か美味しいものでも作らないと!」
バルマードはよしよしとウィルハルトの頭を撫でた。
さすがに剣王とリアルプリンスにそう釘を打たれたら、強情で強欲なエストとしても、それに従うしかない。
エストにしてみれば、ウィルハルトと二人きりになるのもそれはそれでアリなので、問題なかった。
立ち去るバルマードと心の師匠ヤマモトに、エストは、屈託のない笑顔で手を振り、振り返っては、さてどうやって、この鈍感超絶美少年王子の好感度を上げてやろうかと、ニヤける口元に下心を垣間見せる。
バルマードは立ち去り際に、残した二人をチラッと見てこう思った。
(いやね、連れて行きたい気もなくはないんだけど、今のエストちゃんとウィルハルトじゃ、立ってるだけで消し飛んでしまうから。今回は、ごめんね。)














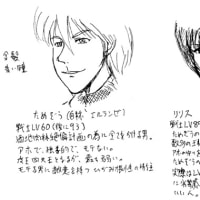

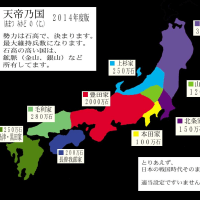



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます