4月18日(木)は茨城県の庄司産婦人科にて
助産師の吉田敦子先生のお話を聞く機会に恵まれました。
2~3歳で、すでに歯並びが悪い、顎が発育していない。
そんなお子さんが現代では非常に多いです。
小児歯科専門医の石田房枝先生は、
生後1か月の授乳の仕方が顎の発育に影響がある、とおっしゃっています。
授乳方法(母乳かミルクか)、からだを動かしているか、離乳食の状態、
指しゃぶりや頬杖、うつぶせ寝など、
顎の大きさ位置、歯並びは生活習慣や習癖など多くの原因が絡みあった結果によるものと思えます。
しかし本日の講義を聞き
さらにさかのぼり、
胎児の時からも不正咬合になる要因はあるのではないかと思いました。
お腹の中の赤ちゃんはお母さんの子宮の中にいます。
妊娠が進むにつれて子宮は大きくなり骨盤の中で守ってもらいます。
しかし骨盤が狭く子宮が膨らみにくかったり、血流が滞り子宮が収縮すると
お腹の赤ちゃんも窮屈になります。
すると、胎児の正常な体位である背中を丸めて手足を折る姿勢が取れなくなり、
左右非対称な状態でお腹の中にいることになります。
例えば顔が横向きになった状態で長くいると筋肉の発育に左右差がでることがあります。
このような事が生まれてからの骨格や筋肉の発育にも関係してくるのです。
これは衝撃でした。
生前から、つまり母親の骨盤や子宮の状態までが生後の発育にも関係しているとは。
でも聞けば聞くほど当然の話です。
私の経験ですと、長男の出産はスムーズでしたが、
次男を妊娠中は育児、家事、仕事をしながらだったので休まる時がありませんでした。
お腹は常時張っていて辛かったのを覚えています。
つまり子宮が収縮していました。
自分自身も辛いのですが、お腹の中の息子も圧迫されて辛かったのではないかな、と思います。
結局35週という早産でした。
今は小学生で順調に成長してくれていますが、赤ちゃんの時から寝るときの体位がいつも顔を横にしたうつぶせ寝です。
私が夜中に何回も仰向けに変えても朝起きては横向きになっています。
もしかしたら、お腹の中で顔が横向きに近い状態であったのかも・・・
と今になって思いました。
そして吉田先生は、そのような場合は
妊娠中はママの体操やマッサージなどのケアで、
産後は赤ちゃんのケアでいい方向に導いていけるとおっしゃっています。
本には、ケアの仕方がのっていますので、
妊娠を考えている方、妊娠中の方、赤ちゃんがいらっしゃる方は是非読んでみて下さいね。
「あぁ。。。もっと早く知っていたかった。10年前に戻りたい!」
と私は思ってしまいましたので。(笑)
正しい口腔育成は胎児から。それにには母親の体幹から。深い話です。

 が、
が、

















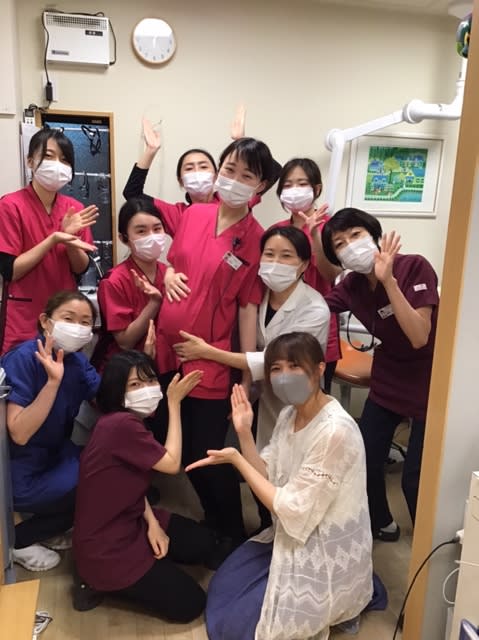


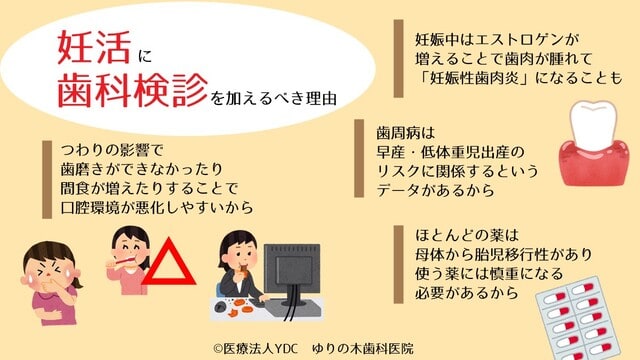


















 と思います。
と思います。






