朝日新聞社の取材を受けました。
小学校での雪の教材化の実践事例の紹介です。
本校の総合的な学習の時間…「Let’s雪タイム」
本時は1時間目で、雪のことについてみんなでいろいろと話し合いました。
大人が思っている以上に子どもは雪が好きです。
「スキーやスノーボードができる」
「楽しいイベントがある」
「雪景色がきれい」など、たくさんの意見がでました。
そこで、子ども達と雪を中心としたウェブマップづくりをしました。
そこから見えてきた視点は
「スポーツ」「遊び」「イベント」「正体」…そして「困るもの」
楽しいものである半面、大人は困っている人が多いという意見も多かったです。


子ども達の話し合いで意見が分かれたのが、雪はいつ誕生するのか?
雲の中でできる…まではいいのですが、「雨から雪へ」、「雪から雨へ」で議論が白熱しました。
そんな中、ある子がつぶやいた「雪の結晶」
「先生、雪ってきれいな結晶なんだよね」
「そうだ!みたことある!」
といった感じで、話は雪の正体を突き止める方向に。
まずは、雪を観察したいということで、雪たんけん館HPで観察の仕方を確認し、
みんなでグラウンドにでました。
そこで、ルーペとベルベット板をもって観察…。

とてもきれいなんですが…
「先生、中には結晶らしいものがあるけど、大部分はくっついて固まっている感じ」
と子ども達。
教室に戻ってから、活動をふり返りました。
結晶を見るためには
「降ってくる雪」「雪の状態」「気温」「湿度」など条件が必要なんだ…
と子どもたちなりに課題を見つけていました。
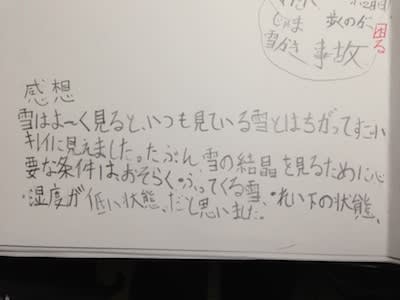

雪の正体をさぐる…
これは3学期の学習になりそうです。
2時間、みんな脳みそフル活用で取り組みました!
私自身も、楽しく授業することができました。
でも、雪をみると、子どもはみんなこうなります。










