あんてぃーく倶楽部 による清の東陵への遠足、続きです。
亡き康熙帝の葬儀を荘厳極まりない規模で終えた雍正帝は、
兄弟の中でも最大のライバル、康熙帝の大本命と言われていた第14皇子・胤[ネ題]に
東陵に残り、父帝の霊魂を守るように命じる。
堂々たる鎮西大将軍から、いきなり墓守りの下っ端役人にまで落とされたのである。
胤[ネ題]については、
清の西陵2、西陵と雍正帝の兄弟争い、康熙帝の皇子らのそれぞれの末路
の中の「十四子)胤[ネ題]場合」を参照にされたし。
(めっさ長い記事です。康熙帝の20人以上いる皇子らの軌跡を延々と書き連ねているので、
途中はとばして、後ろの方にある記述にたどりついてください。)
を参考にされたし。
実質的には、完全な流刑生活である。
東陵での滞在当初は、湯泉行宮(東陵の東)に住んでいたが、
後には、南側の馬庄村にある関帝廟に滞在するようになった。

胤[ネ題]は東陵の界隈で三年の「島流し」生活を送っている。
雍正2年(1724)、雍正帝は、胤[ネ題]が、こっそり頻繁に北京に戻り、
胤[ネ異]らと何か相談していると知り、胤[ネ題]の家族もごっそりと東陵に軟禁するように命じた。
さらには、元々の「郡王」の爵位をはく奪し、格下の爵位「固山貝子(グサン・ベイゼ)」に変更した。
東陵での「流刑」生活の当初、胤[ネ題]は、大酒を煽ってふて腐れるだけの日々だったが、
ある時、廟近くから賑やかな声が聞こえたので、外に見に行った。
そこには、獅子舞の練習をする村の若衆の集団。
「花会」のための練習をしているという。
「花会」、別名「香会」。
中国北方で盛んだった、寺院の縁日や祭日に曲芸を披露して捧げる行事だそうだ。
その演目は多種多彩:
● 龍灯: いわゆる「長崎くんち」、ドラゴンダンス。
長い龍の胴体の途中に棒をつけ、集団で龍がうねり踊る様子を再現するもの。
● 少林: これはわかりやすいですな。少林寺拳法の演舞。
● 中幡: 竿が中央に通った巨大かつ重い旗を使って、体を張った芸をする。

写真: 中国語ブログ: 老房的博客 より
● 獅子舞: ご存じの獅子舞。
● 高[足尭]: いわゆる竹馬ですな。 1m以上もある竹馬を履いたまま、踊ったり、走ったり、さまざまな芸をする。
● 旱船: 船の形をしたぬいぐるみを着て、横に笛吹きなどのはやし役がつき、二人で歌いながら掛け合い漫才のように応酬する。

船の役は、男性が女装することも多い。
写真: ニュース記事 より
花会の特徴は、日本の祭りと同じで、各町内会、力のある企業の社員同好会などが主体となり、
本業の余暇に練習を重ねて晴れ舞台で披露する、という「素人芸」の集団であることだ。
当初は、徒然なるままにただその練習を眺めたり、興が乗ると、自分も練習の輪の中に入って興じたりする程度だったが、
そのうち、側近の一人が「これは軍事演習にもなる」と、物騒なことを耳打ちした。
花会の演目は、どれも体を張った肉体芸ばかりだ。
花会の練習、という名目で屈強な壮丁(成人男子)を集めて肉体を鍛えさせても、立派な大義名分が立つというわけだ。
雍正帝から危険視され、疎まれ、すでに島流しになった今となっては、
もはや圧倒的な実力の差は歴然。
事態を挽回しようにも、現実的には手も足も出ない。
いつ刺客を差し向けられて殺されるかもわからないし、
万が一、時が熟して挽回のチャンスが訪れたとしても、手中にまったく武力勢力がないままでは、身動きもとれない。
・・・と思ったのか。
胤[ネ題]は俄然、やる気を出した。
胤[ネ題]はある日、知州の雷之楡、東陵総管内務府大臣の黄殿邦、馬蘭鎮総兵の範時訳などの現地の高官、
ならびに地元の名士、素封家、豪商を内務府に集めて提案した。
花会を「皇会」と称して、盛り上げて行きたい、と。
つまり皇族の主催する花会・・・。
現代でいえば、競馬の天皇杯のようなものでしょうか?(例がおかしい???)
胤[ネ題]は、今は島流しのような身分とはいえ、数年前までは、康熙帝の覚えめでたき飛ぶ鳥落とす勢いだった皇子。
地方の片田舎の官僚や商人が、その提案に逆らえるはずもなく、皆曖昧な表情をしている間に事はどんどんと決まって行った。
まずは皇子が滞在する関帝廟のある南新城村で11演目の花会を結成することにした。
皇子自らが会の「会頭」になると宣言。
「会旗」も自らが采配して、制作にあたった。
旗の長さは5mもあり、皇帝一家の象徴である黄色の布に
「東陵南新城引善普済老会」と楷書で自ら大きく書き、落款は「固山貝子二十三太王」。
胤[ネ題]は、夭折した兄弟も含めると、第23皇子となるので、そう呼ばれていた。
花会の準備は、伝統的なしきたりに従い、各豪商が一つずつ演目の割り当てを受け、
メンバーの日頃の訓練の世話役として、場所、休憩時間の差し入れ、道具、晴れ舞台の衣装などを用意することになっており、なかなかの出費となる。
二十三太王は、いうことを聞かない隊員の処罰のため、印籠のごとく、「戒尺」を各会頭に渡した。
たぶん、禅寺で座禅が乱れると、後ろからばしっ、と叩かれる、ああいう平たい板のようなものなのかな、と推測するが・・・。
少しは彫刻や彩色が施してあり、二十三太王のお墨付きとわかるような文字や落款もあるのだろう・・・。
ここまで大仰になってくると、割り当てられた地元の名士らも力を入れないわけにいかず、
それぞれの演目がなかなかの仕上がりとなった。
最初のお披露目の場は、旧1月15日、新年最初の満月を祝う「元宵節」の縁日にて。
演技者は総勢500人余り、壮観な図だろう。
それを皮切りに、同月の27、28日にもう一度、南新城で披露した後は、さらに大きな町である馬蘭峪、遵化城にも出かけて披露した。
これに勢いを得た二十三太王の「皇会」は、各地の「縁日荒らし」に乗り込んで行く--。


康熙帝・景陵の隆恩殿(本殿)の内部。
東陵界隈で有名な縁日といえば、景忠山の廟会。
毎年旧4月18日に開かれ、順治帝も康熙帝も座禅に訪れたことがあると言われる古刹。
東陵から東に100里、年に一度の縁日には、大勢の人々で山が埋まるといわれる賑わいとなる。
ここは、今に至るまで、名古刹として残っているようですな。
中国語ブログ 河北遷西景忠山
写真を見るかぎり、かなり山の上にありそう・・・。


そのほかにも、龍山廟会、挟山寺廟会
(調べたが、名前が平凡すぎて全国あちこちの検索結果が出てきて、結局はっきりせず。
要するに500人の演技者をぞろぞろ連れて参加しに行ける程度の近隣の縁日かと思われる。また調べがつく日が来るのを期待して。
今のところは、不明のまま、保留っす)
などの縁日に乗り込んで行った。
花会の行列が、遵化城を通過する時は、五品の州官に至るまですべて出迎えに出た。
何しろ今上皇帝の弟君が、会頭になり、率いて行くのだ。
権力闘争の内部事情がどうあれ、庶民としては、おろそかにするわけにはいかない。
ある時、花会が遵化城を通過するのに、知州の雷之楡は、二十三太王が諸用で今日は来ていないと聞き、
椅子に座ったまま、ぴくりと動こうともしなかった。
知州が自ら迎えに出てきていないことに、会頭が気づいた。
二十三太王がいなくなると、途端に軽んじられたことを悟り、かっとなった頭(かしら)は、
「ふん。小役人め。庶民をなめやがって」
と悪態をついたかと思うと、全隊員に楽器の演奏をやめ、旗の芸もやめるように命じた。
知州府の前でぴたりととまって、数百人の隊列がぴくりとも動かず、やかましいくらいの大音響だった楽器の演奏もぴたりととまり、
突然、しいいんと不気味な静けさが訪れた。
様子の異変を訝しく思って、表に様子を見に来た役人が、はっと事態を呑みこむと、
泡を食って知州の元に駆けこんで大事を告げた。
知州が飛び出して行った頃には、隊列はすでに出発し、先に進んでいた。
知州は馬に飛び乗ると、列の先頭まで必死に駆けて行き、二十三太王が自ら書いたという旗の前に跪くと、
三跪九叩を繰り返して、「王爺(王さま)お許しください。王爺(王さま)お許しください。」と繰り返した。
さらには、会に20両の寄付をして、会頭の機嫌がようやく直り、事なきを得たという。
二十三太王は、足掛け3年を東陵で過ごしたが、
その後、さらに警戒心を強めた雍正帝に紫禁城の裏・景山に軟禁されることとなり、
東陵皇会のテッパンの会頭は去って行ってしまった。
それ以後、往年の勢いを取り戻すことはなかったが、その名声、芸の腕の高さは今に引き継がれているという・・・。


康熙帝・景陵の隆恩殿(本殿)
どういう来歴のものかは、わからないが、少し大仰な椅子が三つ並んでいる。
いつか、「ああ。こういうものだったのか」と調べがつく日も来るかもしれないので、
とりあえず撮影しておこう。古いものなのかなああ・・。それとも新しいものだろうか・・・。


巨大な柱。
こ、この修復の仕方には、何か意図があるのだろうか・・・・。
背の届くところまでは、金の塗料を塗り、その上は放置プレイ・・・・。


ぽちっと押してくださると、励みになります!

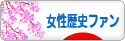
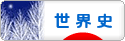
亡き康熙帝の葬儀を荘厳極まりない規模で終えた雍正帝は、
兄弟の中でも最大のライバル、康熙帝の大本命と言われていた第14皇子・胤[ネ題]に
東陵に残り、父帝の霊魂を守るように命じる。
堂々たる鎮西大将軍から、いきなり墓守りの下っ端役人にまで落とされたのである。
胤[ネ題]については、
清の西陵2、西陵と雍正帝の兄弟争い、康熙帝の皇子らのそれぞれの末路
の中の「十四子)胤[ネ題]場合」を参照にされたし。
(めっさ長い記事です。康熙帝の20人以上いる皇子らの軌跡を延々と書き連ねているので、
途中はとばして、後ろの方にある記述にたどりついてください。)
を参考にされたし。
実質的には、完全な流刑生活である。
東陵での滞在当初は、湯泉行宮(東陵の東)に住んでいたが、
後には、南側の馬庄村にある関帝廟に滞在するようになった。

胤[ネ題]は東陵の界隈で三年の「島流し」生活を送っている。
雍正2年(1724)、雍正帝は、胤[ネ題]が、こっそり頻繁に北京に戻り、
胤[ネ異]らと何か相談していると知り、胤[ネ題]の家族もごっそりと東陵に軟禁するように命じた。
さらには、元々の「郡王」の爵位をはく奪し、格下の爵位「固山貝子(グサン・ベイゼ)」に変更した。
東陵での「流刑」生活の当初、胤[ネ題]は、大酒を煽ってふて腐れるだけの日々だったが、
ある時、廟近くから賑やかな声が聞こえたので、外に見に行った。
そこには、獅子舞の練習をする村の若衆の集団。
「花会」のための練習をしているという。
「花会」、別名「香会」。
中国北方で盛んだった、寺院の縁日や祭日に曲芸を披露して捧げる行事だそうだ。
その演目は多種多彩:
● 龍灯: いわゆる「長崎くんち」、ドラゴンダンス。
長い龍の胴体の途中に棒をつけ、集団で龍がうねり踊る様子を再現するもの。
● 少林: これはわかりやすいですな。少林寺拳法の演舞。
● 中幡: 竿が中央に通った巨大かつ重い旗を使って、体を張った芸をする。

写真: 中国語ブログ: 老房的博客 より
● 獅子舞: ご存じの獅子舞。
● 高[足尭]: いわゆる竹馬ですな。 1m以上もある竹馬を履いたまま、踊ったり、走ったり、さまざまな芸をする。
● 旱船: 船の形をしたぬいぐるみを着て、横に笛吹きなどのはやし役がつき、二人で歌いながら掛け合い漫才のように応酬する。

船の役は、男性が女装することも多い。
写真: ニュース記事 より
花会の特徴は、日本の祭りと同じで、各町内会、力のある企業の社員同好会などが主体となり、
本業の余暇に練習を重ねて晴れ舞台で披露する、という「素人芸」の集団であることだ。
当初は、徒然なるままにただその練習を眺めたり、興が乗ると、自分も練習の輪の中に入って興じたりする程度だったが、
そのうち、側近の一人が「これは軍事演習にもなる」と、物騒なことを耳打ちした。
花会の演目は、どれも体を張った肉体芸ばかりだ。
花会の練習、という名目で屈強な壮丁(成人男子)を集めて肉体を鍛えさせても、立派な大義名分が立つというわけだ。
雍正帝から危険視され、疎まれ、すでに島流しになった今となっては、
もはや圧倒的な実力の差は歴然。
事態を挽回しようにも、現実的には手も足も出ない。
いつ刺客を差し向けられて殺されるかもわからないし、
万が一、時が熟して挽回のチャンスが訪れたとしても、手中にまったく武力勢力がないままでは、身動きもとれない。
・・・と思ったのか。
胤[ネ題]は俄然、やる気を出した。
胤[ネ題]はある日、知州の雷之楡、東陵総管内務府大臣の黄殿邦、馬蘭鎮総兵の範時訳などの現地の高官、
ならびに地元の名士、素封家、豪商を内務府に集めて提案した。
花会を「皇会」と称して、盛り上げて行きたい、と。
つまり皇族の主催する花会・・・。
現代でいえば、競馬の天皇杯のようなものでしょうか?(例がおかしい???)
胤[ネ題]は、今は島流しのような身分とはいえ、数年前までは、康熙帝の覚えめでたき飛ぶ鳥落とす勢いだった皇子。
地方の片田舎の官僚や商人が、その提案に逆らえるはずもなく、皆曖昧な表情をしている間に事はどんどんと決まって行った。
まずは皇子が滞在する関帝廟のある南新城村で11演目の花会を結成することにした。
皇子自らが会の「会頭」になると宣言。
「会旗」も自らが采配して、制作にあたった。
旗の長さは5mもあり、皇帝一家の象徴である黄色の布に
「東陵南新城引善普済老会」と楷書で自ら大きく書き、落款は「固山貝子二十三太王」。
胤[ネ題]は、夭折した兄弟も含めると、第23皇子となるので、そう呼ばれていた。
花会の準備は、伝統的なしきたりに従い、各豪商が一つずつ演目の割り当てを受け、
メンバーの日頃の訓練の世話役として、場所、休憩時間の差し入れ、道具、晴れ舞台の衣装などを用意することになっており、なかなかの出費となる。
二十三太王は、いうことを聞かない隊員の処罰のため、印籠のごとく、「戒尺」を各会頭に渡した。
たぶん、禅寺で座禅が乱れると、後ろからばしっ、と叩かれる、ああいう平たい板のようなものなのかな、と推測するが・・・。
少しは彫刻や彩色が施してあり、二十三太王のお墨付きとわかるような文字や落款もあるのだろう・・・。
ここまで大仰になってくると、割り当てられた地元の名士らも力を入れないわけにいかず、
それぞれの演目がなかなかの仕上がりとなった。
最初のお披露目の場は、旧1月15日、新年最初の満月を祝う「元宵節」の縁日にて。
演技者は総勢500人余り、壮観な図だろう。
それを皮切りに、同月の27、28日にもう一度、南新城で披露した後は、さらに大きな町である馬蘭峪、遵化城にも出かけて披露した。
これに勢いを得た二十三太王の「皇会」は、各地の「縁日荒らし」に乗り込んで行く--。


康熙帝・景陵の隆恩殿(本殿)の内部。
東陵界隈で有名な縁日といえば、景忠山の廟会。
毎年旧4月18日に開かれ、順治帝も康熙帝も座禅に訪れたことがあると言われる古刹。
東陵から東に100里、年に一度の縁日には、大勢の人々で山が埋まるといわれる賑わいとなる。
ここは、今に至るまで、名古刹として残っているようですな。
中国語ブログ 河北遷西景忠山
写真を見るかぎり、かなり山の上にありそう・・・。


そのほかにも、龍山廟会、挟山寺廟会
(調べたが、名前が平凡すぎて全国あちこちの検索結果が出てきて、結局はっきりせず。
要するに500人の演技者をぞろぞろ連れて参加しに行ける程度の近隣の縁日かと思われる。また調べがつく日が来るのを期待して。
今のところは、不明のまま、保留っす)
などの縁日に乗り込んで行った。
花会の行列が、遵化城を通過する時は、五品の州官に至るまですべて出迎えに出た。
何しろ今上皇帝の弟君が、会頭になり、率いて行くのだ。
権力闘争の内部事情がどうあれ、庶民としては、おろそかにするわけにはいかない。
ある時、花会が遵化城を通過するのに、知州の雷之楡は、二十三太王が諸用で今日は来ていないと聞き、
椅子に座ったまま、ぴくりと動こうともしなかった。
知州が自ら迎えに出てきていないことに、会頭が気づいた。
二十三太王がいなくなると、途端に軽んじられたことを悟り、かっとなった頭(かしら)は、
「ふん。小役人め。庶民をなめやがって」
と悪態をついたかと思うと、全隊員に楽器の演奏をやめ、旗の芸もやめるように命じた。
知州府の前でぴたりととまって、数百人の隊列がぴくりとも動かず、やかましいくらいの大音響だった楽器の演奏もぴたりととまり、
突然、しいいんと不気味な静けさが訪れた。
様子の異変を訝しく思って、表に様子を見に来た役人が、はっと事態を呑みこむと、
泡を食って知州の元に駆けこんで大事を告げた。
知州が飛び出して行った頃には、隊列はすでに出発し、先に進んでいた。
知州は馬に飛び乗ると、列の先頭まで必死に駆けて行き、二十三太王が自ら書いたという旗の前に跪くと、
三跪九叩を繰り返して、「王爺(王さま)お許しください。王爺(王さま)お許しください。」と繰り返した。
さらには、会に20両の寄付をして、会頭の機嫌がようやく直り、事なきを得たという。
二十三太王は、足掛け3年を東陵で過ごしたが、
その後、さらに警戒心を強めた雍正帝に紫禁城の裏・景山に軟禁されることとなり、
東陵皇会のテッパンの会頭は去って行ってしまった。
それ以後、往年の勢いを取り戻すことはなかったが、その名声、芸の腕の高さは今に引き継がれているという・・・。


康熙帝・景陵の隆恩殿(本殿)
どういう来歴のものかは、わからないが、少し大仰な椅子が三つ並んでいる。
いつか、「ああ。こういうものだったのか」と調べがつく日も来るかもしれないので、
とりあえず撮影しておこう。古いものなのかなああ・・。それとも新しいものだろうか・・・。


巨大な柱。
こ、この修復の仕方には、何か意図があるのだろうか・・・・。
背の届くところまでは、金の塗料を塗り、その上は放置プレイ・・・・。


ぽちっと押してくださると、励みになります!



















サラリーマン社会でも、事実上の流刑はありますからね。
それまでの華やかな場と比べるから
流刑になるんでしょうけど・・・・・。
子供の頃は思いましたよ。
地続きなのに、何で流刑なの?的な疑問。
馬頭をつけたおじさんは、
ノリノリのように見えますが。(笑)
いつも(^_-)-☆ありがとうです!
ノリノリのように見えますが。(笑)
ほんまですね!
癒される絵ですな!