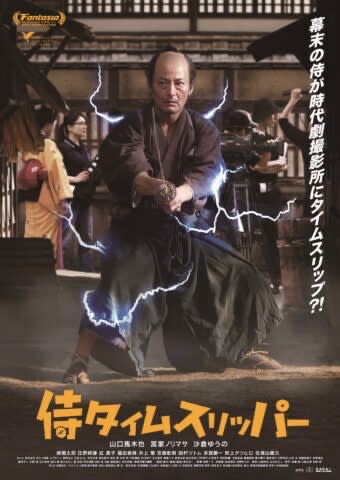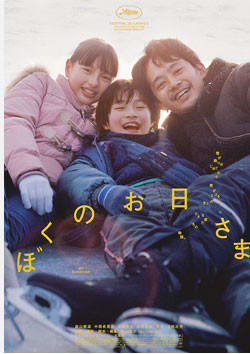原題は「The Great Escaper」。スティーブ・マックイーンが出てきそうなタイトルです。
これを「大脱走者」とか「グレート・エスケーパー」という邦題にしなかったところがまずナイスです。
2014年夏、イギリスの海辺にある老人ホームに住む夫婦の話です。
夫はバーニー90歳。妻はレネ、年齢はたぶんちょっと下だと思います。
二人は仲睦まじく、レネはバーニーのために毎朝化粧をし、バーニーは体が弱ってきているレネに寄り添い、冗談を言いながら車椅子のレナを連れて散歩をします。
こんなふうに歳を取れたら良いなと思わせる理想的な老夫婦で、人生最後の日々を寄り添って生きています。
映画は二人の様子が交互に、そして今と70年前の様子が交互に映し出されて進んでいきます。
二人は第2次世界大戦中に知り合いました。
その頃の二人のキレッキレのダンスシーン、そして現在老人用歩行器と車椅子がないと出歩けないシーンの比較だけで、初老を過ぎ、中老になった私には目頭が熱くなります。
海軍兵となって戦地に赴くバーニー。この時が最初のはなればなれです。
現在に戻ります。
ある日、バーニーは老人ホームを出て行方不明になります。
歩行器を使いながら船に乗り、フランスに向かったのです。
バーニーがかつて戦ったノルマンディー上陸作戦から70年。その式典に向かいました。
これが2度目のはなればなれです。
決して離れないと誓ったバーニーでしたが、どうしても気持ちの整理をつけなければならない理由がありました。
そして妻のレナにもバーニーに秘密にしていることがありました。
老夫婦の愛情と戦争がテーマです。
バーニーが戦友の墓の前で「無駄な死だ」と2回呟いたのがとても印象に残りました。
バーニーは無事、老人ホームに戻りますが、その半年後に亡くなりました。
そしてレナはその7日後に後を追うように亡くなったそうです。
そう、これ実話を元にしているんです。
そしてレナを演じたグレンダ・ジャクソンさんは映画公開前の2023年6月15日にこの世を去りました。
夫役のマイケル・ケインさんは本作が最後の演技。華麗なる俳優人生に幕を下ろしました。
笑える部分と涙する部分と考えさせられる部分がありました。心温まる名作だと思います。