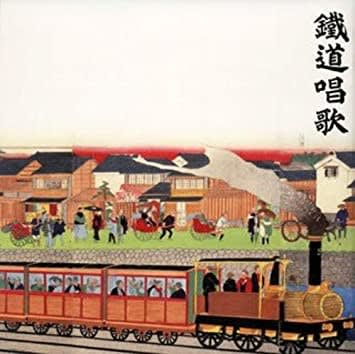令和3年11月2日(火)
十一月 : 霜 月

陽暦の十一月のことで、ほぼ陰暦の十月(神無月)の時期に
相当する。

7日には立冬を迎えるが未だ寒さはそれほど厳しくなく、小春
日和と呼ばれる陽気が続くので行楽等にも適している。

然しそんな日和を挟みながらも、やがて凩が木々の葉を落とし
日の暮れは日毎に早くなり、北国からは初雪の便り届き始め、
万象は厳しい冬への態勢を整えていく。

霜月11月、今年も後2ヵ月、、、、スッカリ晩秋の気配が
漂い、木々の紅葉や落葉も目立ち始めた。 

道行く人達も、早や冬装束が目に付くようになった。
コロナ禍で慌ただしく過ごした日々も、やっと落ち着きを見せ
日々平穏な暮らしが戻る中、「衆議院選挙」が行われた。
下馬評(メデイア)では、「自民苦戦、野党躍進か?」と、、

フタを開ければ、「自民安定多数(「261議席)、公明微増
維新4倍増、立民・共産敗退、野党共闘ならず」
自民党のスキャンダル(一部敗退)も大きな影響もなく、国民
には届かなかった様である。政変を望まぬ人が多かった様だ。
自民党の勝利、強かった、のメデイアの報道、、、、
と言うより、野党が弱かった。 野党に政権を託す物が何も
なかったのだろう。今の野党は文句を言うもののこれといった
目新しい政策が見当たらない。
もう一つ言えるのは野党に若くて目立つ人が居ない様である。
過って、自民党が大敗し野党政権の誕生した折りには皆若さに
溢れ、革新に燃えるエネルギーが漲っていた。
今の野党に任せるよりは自民党の方がマシ、、選挙に行っても
どうせ何も変わらない、と若者達は、、、、

今回の選挙、各党とも「バラマキ選挙」と言われる。
子供支援もよいが一時的なもので、今一番困っているのは若年層
の働き場所のない事であろう。
数年前、失業率低減のため若者の非正規雇用を増大させた。
彼等は昨年から続いたコロナの影響で、真っ先に職場を追われ
其のまま再雇用されぬまま首になって居る。
どうにもならない現状に、そのはけ口は何処へ向けられる?
最近特に多くなった凶悪犯罪、、その犯罪者の低年齢化、、
全てがそれが原因とは言わないが、一端ではないだろうか。
今日の1句(俳人の名句)
物いへば唇寒し秋の空 松尾 芭蕉















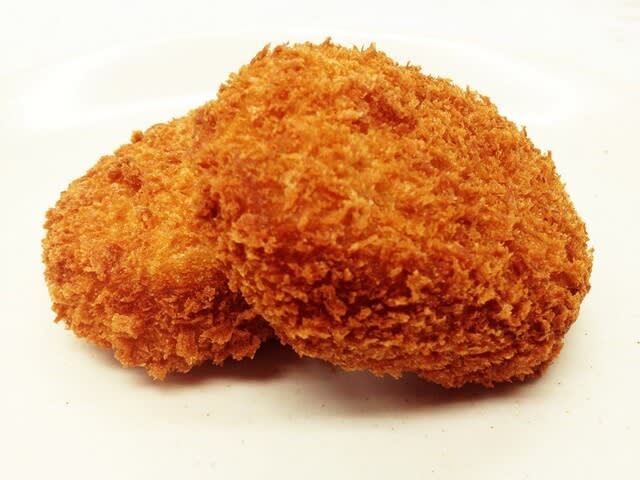














 体験コーナーがあり、子供達は新幹線の運転席に入り係員
体験コーナーがあり、子供達は新幹線の運転席に入り係員