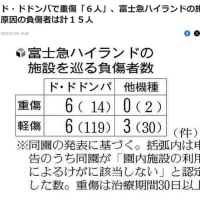工業製品には、素材から完成品に至る訳ですが、その中間に様々な規格化された半製品というのを利用して、製品利用者は完成品を作り上げる訳です。例えば、様々な構築物を作るコンクリート(セメント)という製品がありますが、素材は石灰など鉱物資源を基にしており、作られた微粉末に水を加えることで流動性を得て。型枠などの中に流し込み製品を成型します。なお、セメントは圧縮には強いが、引っ張りには弱いと云う物性がありますから、補強材として鉄筋などを型枠内に適宜配置し、製品は鉄筋コンクリートとして、利用することが一般的です。この例の様に複数以上の素材を利用して求める強度やコストに対応した成型品もしくは半製品などをコンポジットマテリアル(複合材)と呼びます。
ところで、一概にコンクリートと呼ばれる製品でも、その用途などに向けて、高強度コンクリートから一般的な汎用コンクリートまで製品は多種が存在する様です。
ところで、日頃から感心を持って眺めるクルマにも、一般的な鋼板やアルミ板でなく、複合材が使用される場合が、特に少量生産車とか車体重量の軽減を求められるレース様マシンには利用されます。このクルマ用複合材としては、従来FRP(ファイバー、リンホースド、プラステック)が主に使用されてきました。ここでのファイバーとは、極細いガラスの繊維のことを指します。一方、近年、硝子繊維の発展型として炭素繊維を使用したCFRP(カーボン、ファイバー、レインフォースド、プラスチック)というのが、クルマだけでなく飛行機の胴体とか翼などにまで使用される様になって来ました。このCFRPですが、元々人工繊維たるレイヨンとかアクリルなどを高温で焼き固める(炭化)させて作られており、日本メーカーの人工繊維メーカーたる東レとか三菱レイヨンの占める世界シェアが世界の80%以上を占めるというわが国のお家芸となっているものです。炭素繊維の種別としては、アクリル繊維から作られるPAN系とピッチ(石油、石炭、コールタールなどの副生成物)から作られるピッチ系に分かれ、それぞれの用途が分かれる様です。
何れにしても生成された炭素繊維の断面は極細いものですが、同断面積の鋼の10倍近い引っ張り強度を持つと云われています。ただし、この炭素繊維は、鉄筋コンクリートで云うところの鉄筋に相当するもので、これだけでは製品の形状を保つことはできず、適当な樹脂と組み合わせて複合材として使用するものです。ただし、炭素製品の一部にはC/Cコンポジットと呼ばれる副種の炭素繊維を組み合わせて、成型型の中で高温高熱で焼き固めた超高温に耐えられる製品がありますが、その成型自由度の制限とかコストの関係もあり、超高温が求められる特別の部位にのみ用途は限定されます。例として、スペースシャトルの機種戦端とか翼の前縁部、ブレーキディスクローターなどが今まで使用された実用例です。
と云うことで、一般的にCFRPと呼ばれる製品の多くは、カーボン繊維を強度補強材として、その廻りの基剤を樹脂で固めて成型品を作ると云うのが主流となります。なお、単純にCFRP製品と云っても、その使用材料とか成形法により、得られる寸法的な精度だとか強度は異なります。
現在のところ、もっとも寸法精度が良好で、得られる強度も高く、比較的大物製品(中型旅客機の胴体など)までをカバーできる製法は、片面の金型の内側に、予めカーボン繊維のマットに樹脂を含浸させた(プリプレグと呼ぶ)を必要箇所事に積層させ、専用ビニールパックして、内部の空気を真空引きして、金型内面への密着と内部の気泡を除去した状態で、オートクレーブという加熱加圧炉内で焼成させた通称オートクレーブ法と呼ばれる製品です。ただしこの工法は、専用ビニールマットなど、毎回新規使用しなければならない副資材コストを要することや、手作業で張り込む工数が膨大になること、オートクレーブの製造コストやその焼成時間に時間を要するなど、非常に生産性に難点があり製品コストが上昇するという問題があります。
製品がある程度大きくない場合、上下型を使用してプリプレグをプレスする様に挟み込み成型し、そのまま加温し焼成までを行える手法もありますが、金型を使用する関係で製品の大きさに限界がある様です。
ここまでのCFRP成形法では、プリプレグを使用した、長尺カーボン繊維を使用した手法で、高い強度が出せますが、樹脂の射出成形時の材料に比較的短尺繊維を混ぜ込んで、強度を高めるということも、さほどの局部応力が求められない部位には使用されています。
また、高強度のCFRPでは長尺カーボン繊維と熱硬化型樹脂の組み合わせがもっとも強度が出せますが、熱硬化型樹脂はリサイクル不可能もしくは困難という問題があり、ある程度兄弟が犠牲になりますが熱可塑性樹脂と組み合わせた成型品もできつつある様です。
さて、こんな長文を書くつもりもなかったのですが、本論を以下に記します。
CFRP全盛の時代になったとはいえ、空恐ろしくコストは上昇しますので、そのボデーの全体をCFRPとしたクルマは今でも極少ないのが現状でしょう。ある程度安価なスポーツカーなどは、ジャシはアルミ押し出し材を基本として、アッパーボデーは従来のFRPで製造して作り続けているクルマが未だあります。ただし、ファイバーは従来同様のガラス繊維ですが、樹脂が従来はポリエステル樹脂だったのが、昨今は樹脂としての性能が上廻るエポキシ樹脂を使用したものが増えている様です。ですから、同じFRP製品と云えども、強度は高まっているのです。
ところで、つい先日、これらFRPボデーの車両の修理を得意にしている工場へ立ち寄った際、旧型車はポリエステル樹脂のFRPだったものが、最近はエポキシ樹脂のFRPに変わっていますので、修理性はどうなのかをたずねた際、エポキシは例えば20kg入り缶で購入して、一部を使用し、2年ほど経過して再使用しようとしたら、すでに硬化しており使い物にならなかったと難しさを嘆いていました。エポキシの場合、接着剤と同様AB二つの主材を混合することで化学的に硬化反応(重合と呼ぶ)が始まるのですが、時間の経過と共に微量な硬化反応は進行しており、ある程度の製造後の使用可使時間があるということでしょう。つまり、単価を下げるために大量に購入しても、長期間の保存に耐えられないということを知る次第です。
【参考記述】
半製品の寿命 2020-08-28 | 車と乗り物、販売・整備・板金・保険
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/ca78accdda21e2c15d8f12e57d2b6c5b
ところで、一概にコンクリートと呼ばれる製品でも、その用途などに向けて、高強度コンクリートから一般的な汎用コンクリートまで製品は多種が存在する様です。
ところで、日頃から感心を持って眺めるクルマにも、一般的な鋼板やアルミ板でなく、複合材が使用される場合が、特に少量生産車とか車体重量の軽減を求められるレース様マシンには利用されます。このクルマ用複合材としては、従来FRP(ファイバー、リンホースド、プラステック)が主に使用されてきました。ここでのファイバーとは、極細いガラスの繊維のことを指します。一方、近年、硝子繊維の発展型として炭素繊維を使用したCFRP(カーボン、ファイバー、レインフォースド、プラスチック)というのが、クルマだけでなく飛行機の胴体とか翼などにまで使用される様になって来ました。このCFRPですが、元々人工繊維たるレイヨンとかアクリルなどを高温で焼き固める(炭化)させて作られており、日本メーカーの人工繊維メーカーたる東レとか三菱レイヨンの占める世界シェアが世界の80%以上を占めるというわが国のお家芸となっているものです。炭素繊維の種別としては、アクリル繊維から作られるPAN系とピッチ(石油、石炭、コールタールなどの副生成物)から作られるピッチ系に分かれ、それぞれの用途が分かれる様です。
何れにしても生成された炭素繊維の断面は極細いものですが、同断面積の鋼の10倍近い引っ張り強度を持つと云われています。ただし、この炭素繊維は、鉄筋コンクリートで云うところの鉄筋に相当するもので、これだけでは製品の形状を保つことはできず、適当な樹脂と組み合わせて複合材として使用するものです。ただし、炭素製品の一部にはC/Cコンポジットと呼ばれる副種の炭素繊維を組み合わせて、成型型の中で高温高熱で焼き固めた超高温に耐えられる製品がありますが、その成型自由度の制限とかコストの関係もあり、超高温が求められる特別の部位にのみ用途は限定されます。例として、スペースシャトルの機種戦端とか翼の前縁部、ブレーキディスクローターなどが今まで使用された実用例です。
と云うことで、一般的にCFRPと呼ばれる製品の多くは、カーボン繊維を強度補強材として、その廻りの基剤を樹脂で固めて成型品を作ると云うのが主流となります。なお、単純にCFRP製品と云っても、その使用材料とか成形法により、得られる寸法的な精度だとか強度は異なります。
現在のところ、もっとも寸法精度が良好で、得られる強度も高く、比較的大物製品(中型旅客機の胴体など)までをカバーできる製法は、片面の金型の内側に、予めカーボン繊維のマットに樹脂を含浸させた(プリプレグと呼ぶ)を必要箇所事に積層させ、専用ビニールパックして、内部の空気を真空引きして、金型内面への密着と内部の気泡を除去した状態で、オートクレーブという加熱加圧炉内で焼成させた通称オートクレーブ法と呼ばれる製品です。ただしこの工法は、専用ビニールマットなど、毎回新規使用しなければならない副資材コストを要することや、手作業で張り込む工数が膨大になること、オートクレーブの製造コストやその焼成時間に時間を要するなど、非常に生産性に難点があり製品コストが上昇するという問題があります。
製品がある程度大きくない場合、上下型を使用してプリプレグをプレスする様に挟み込み成型し、そのまま加温し焼成までを行える手法もありますが、金型を使用する関係で製品の大きさに限界がある様です。
ここまでのCFRP成形法では、プリプレグを使用した、長尺カーボン繊維を使用した手法で、高い強度が出せますが、樹脂の射出成形時の材料に比較的短尺繊維を混ぜ込んで、強度を高めるということも、さほどの局部応力が求められない部位には使用されています。
また、高強度のCFRPでは長尺カーボン繊維と熱硬化型樹脂の組み合わせがもっとも強度が出せますが、熱硬化型樹脂はリサイクル不可能もしくは困難という問題があり、ある程度兄弟が犠牲になりますが熱可塑性樹脂と組み合わせた成型品もできつつある様です。
さて、こんな長文を書くつもりもなかったのですが、本論を以下に記します。
CFRP全盛の時代になったとはいえ、空恐ろしくコストは上昇しますので、そのボデーの全体をCFRPとしたクルマは今でも極少ないのが現状でしょう。ある程度安価なスポーツカーなどは、ジャシはアルミ押し出し材を基本として、アッパーボデーは従来のFRPで製造して作り続けているクルマが未だあります。ただし、ファイバーは従来同様のガラス繊維ですが、樹脂が従来はポリエステル樹脂だったのが、昨今は樹脂としての性能が上廻るエポキシ樹脂を使用したものが増えている様です。ですから、同じFRP製品と云えども、強度は高まっているのです。
ところで、つい先日、これらFRPボデーの車両の修理を得意にしている工場へ立ち寄った際、旧型車はポリエステル樹脂のFRPだったものが、最近はエポキシ樹脂のFRPに変わっていますので、修理性はどうなのかをたずねた際、エポキシは例えば20kg入り缶で購入して、一部を使用し、2年ほど経過して再使用しようとしたら、すでに硬化しており使い物にならなかったと難しさを嘆いていました。エポキシの場合、接着剤と同様AB二つの主材を混合することで化学的に硬化反応(重合と呼ぶ)が始まるのですが、時間の経過と共に微量な硬化反応は進行しており、ある程度の製造後の使用可使時間があるということでしょう。つまり、単価を下げるために大量に購入しても、長期間の保存に耐えられないということを知る次第です。
【参考記述】
半製品の寿命 2020-08-28 | 車と乗り物、販売・整備・板金・保険
https://blog.goo.ne.jp/wiseman410/e/ca78accdda21e2c15d8f12e57d2b6c5b