▼「誰も取り残さない社会」は全ての人がつながる「共生社会」である。
子どもや高齢者、障害者も活躍できる場である。
子ども食堂
こども食堂とは、無料または安価で栄養のある食事がとれる場所のことです。家族揃ってご飯を食べることが難しい子どもたちに対し、共食の機会などを提供しています。
こども食堂には
・子ども同士、親同士のコミュニケーションが取れる
・アットホームな雰囲気で誰かと食事ができる
こども食堂とは、地域住民や自治体が主体となり、無料または低価格帯で子どもたちに食事を提供するコミュニティの場を指しています。
また、単に「子どもたちの食事提供の場」としてだけではなく、帰りが遅い会社員、家事をする時間のない家族などが集まって食事をとることも可能です。
このように、「人が多く集まる場所」ができたことで、地域住民のコミュニケーションの場としても機能しているのです。
こども食堂は、民間発の自主的、自発的な取り組みから始まりました。
子供食堂と連携した地域における食育の推進
-「子供食堂」とは? -
近年、地域住民等による民間発の取組として無料または安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する子供食堂等が広まっており、家庭における共食が難しい子供たちに対し、共食の機会を提供する取組が増えています。
-食育の推進という観点から見た子供食堂の意義について-
子供食堂の活動は様々ですが、親子で参加する場合も含め、
(a)子供にとっての貴重な共食の機会の確保
(b)地域コミュニティの中での子供の居場所を提供
等の積極的な意義が認められます。
-地域と子供食堂の連携の必要性-
地方自治体は、地域住民、関係機関、関係団体・NPO等と適切に連携して、地域における食育を推進する役割を担っています。
地方自治体が、子供食堂を、そうした連携先の一つとして位置づけ、連携を深める中で、子供食堂の取組に地域ぐるみで協力し、子供食堂の活動遂行に役立つような環境整備を行うことが期待されます。
なお、国や地方自治体は、子供食堂の多くが民間のNPOや個人の善意に基づき、発足、運営されていることに十分留意し、子供食堂の自主的・自発的な取組を最大限尊重し、個人やNPOの善意で行われている子供食堂の活動の趣旨を理解することが必要です。
- 基本的な考え方-
農林水産省においては、子供食堂と連携した地域における食育の推進について、関係府省(注)とともに、以下のような方針により、関係施策を推進します。
(1)地方自治体や地域における食育関係者が、食育推進の観点から、子供食堂の活動の意義を理解し、適切な認識を有することができるよう、全国レベルで情報発信を行うとともに、必要な支援を進めていきます。
また、地方自治体や地域における食育関係者向けに、地域と子供食堂が適切に連携している好事例を収集、整理し、情報提供します。あわせて、子供食堂の抱える様々な課題の解決に役立つような課題ごとの参考情報の提供に積極的に努めます。
食育活動の全国展開をとりまとめている農林水産省が中心となって、関係府省と協力しながら、上記のような情報発信、情報提供に取り組むことといたします。
(2)民間のNPOや個人の善意に基づき、発足、運営されている子供食堂の取組を後押しするためには、政府または地方自治体が実施する表彰制度を活用することが有効です。このため、国の既存の表彰制度を活用するとともに、地方自治体が当該自治体の実施する表彰制度を活用することを奨励します。















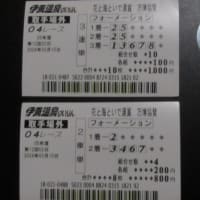
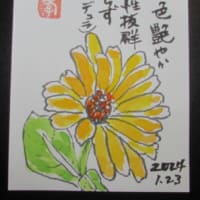








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます