先の第2次世界大戦(1939~1945)ではっきりしたことは、その主役が船から飛行機に移ったこと。 そして陰の主役が、飛行甲板を持ち、航空機を離艦・着艦させると同時に航空機に対する燃料・武器の補給や整備能力を有し、海上において単独で航空戦を継続できる「航空母艦」。 空母が実践で登場したのは第一次世界大戦(1914~1918)だが、それ以前の1910年に米国の巡洋艦に仮設甲板を設け、飛行機の離陸に成功している。 ライト兄弟が初の有人飛行に成功した7年後のことだが、その2ヵ月後には装甲巡洋艦に設置した仮設甲板に、飛行機の原型ともいえるような布張りで、体むき出しのパイロットの操縦する複葉機が、特別に考案されたフックを使って無事着艦している。
1905年(明治38年)日露戦争時に香港からウラジオストクに向かっていた英貨物船「レシントン」を、対馬海峡で捕獲没収し、改装したのが日本海軍初の水上機母艦「若宮」。 前部船倉に航空機格納所や弾火薬庫、後部船倉に兵員室を設け、甲板上にキャンパス製の天蓋をつけた簡単な改装だった。 航空機は前後甲板上に各1機、格納所に分解した2機の計4機を搭載でき、航空機の発進は海上に吊り降ろして行われた。 日英同盟を締結していた当時、第一次世界大戦勃発と同時に日本はドイツに参戦、若宮も「青島攻略戦」に参加しドイツ軍基地を攻撃したのが、洋上を発進した航空機による世界初の実戦活動。
海軍の水上機はそれなりの活躍をしたが、大きなフロートを装備してるため飛行性能では通常の陸上機に比べて劣った。 各国の海軍からは、性能の良い航空機の離発着が可能な母艦が強く望まれ、本格的な航空母艦の開発へと進展していく。 第一次世界大戦での経験から英・日の海軍は、既存艦船の改装によらない本格的航空母艦の建造に着手した。 初めから設計された艦で最初に起工されたのは、イギリスの「ハーミーズ」だったが完成が遅れ、最も早く完成したのは日本の「鳳翔」で1922年の就役。 満載排水量10・500トン、飛行甲板168・5m、重油・石炭ボイラー4基で30・000馬力、航続距離14ノット/10・000海里、最大25ノット、乗員550名、搭載機21機。 第2次大戦の開戦時に海軍に在籍し、無傷で終戦を迎えたのは鳳翔のみ。
「カタパルト」は、航空機を航空母艦の短い滑走路から、瞬時で離陸速度まで加速させる「射出装置」。 大日本帝国海軍では、航空機の連続発射に不可欠なカタパルトの開発に失敗したため、航空母艦ではカタパルトがまったく装備されなかった。 カタパルト未搭載の空母は搭載機の離艦時、風上に向かって高速で航行しなければならず、そのため戦艦並みの大型空母であっても、巡洋艦並みかそれ以上の高速性能が求められ、建造と運用上の大きな制約となった。 一方アメリカ海軍は連続使用が可能な油圧式カタパルトを実用化し、日本の空母に比べ迅速且つ大量の発艦が可能であった。 また小型・低速の空母であってもカタパルトを搭載すれば十分に活用でき、戦局に大きく寄与した。
現代の航空母艦では、第2次世界大戦後にイギリス海軍で考案され,アメリカ空軍において実用化された「蒸気式タパルト」が主流。 蒸気は推進用のボイラーからから圧力タンクに貯めておき、航空機の発進時、一気にシリンダーへ送り込み、カタパルトに連動するピストンを動かすもの。 中国は「大国で空母を保有してないのは中国だけ」と、1988年進水の旧ソ連製空母 「ヴァリヤーグ」(67500トン)を購入し大連造船所で改造中。 完成後は主に練習用空母として離着艦訓練などに利用される見通しだが、別に上海の造船所では初の国産空母を建設中と見られ、最終的には原子力空母2隻を含む5~6隻体制にする見込み。 しかし各国の専門家からこの計画が疑問視されている大きな理由は、「カタパルトの開発が非常に難しいから」。
1905年(明治38年)日露戦争時に香港からウラジオストクに向かっていた英貨物船「レシントン」を、対馬海峡で捕獲没収し、改装したのが日本海軍初の水上機母艦「若宮」。 前部船倉に航空機格納所や弾火薬庫、後部船倉に兵員室を設け、甲板上にキャンパス製の天蓋をつけた簡単な改装だった。 航空機は前後甲板上に各1機、格納所に分解した2機の計4機を搭載でき、航空機の発進は海上に吊り降ろして行われた。 日英同盟を締結していた当時、第一次世界大戦勃発と同時に日本はドイツに参戦、若宮も「青島攻略戦」に参加しドイツ軍基地を攻撃したのが、洋上を発進した航空機による世界初の実戦活動。
海軍の水上機はそれなりの活躍をしたが、大きなフロートを装備してるため飛行性能では通常の陸上機に比べて劣った。 各国の海軍からは、性能の良い航空機の離発着が可能な母艦が強く望まれ、本格的な航空母艦の開発へと進展していく。 第一次世界大戦での経験から英・日の海軍は、既存艦船の改装によらない本格的航空母艦の建造に着手した。 初めから設計された艦で最初に起工されたのは、イギリスの「ハーミーズ」だったが完成が遅れ、最も早く完成したのは日本の「鳳翔」で1922年の就役。 満載排水量10・500トン、飛行甲板168・5m、重油・石炭ボイラー4基で30・000馬力、航続距離14ノット/10・000海里、最大25ノット、乗員550名、搭載機21機。 第2次大戦の開戦時に海軍に在籍し、無傷で終戦を迎えたのは鳳翔のみ。
「カタパルト」は、航空機を航空母艦の短い滑走路から、瞬時で離陸速度まで加速させる「射出装置」。 大日本帝国海軍では、航空機の連続発射に不可欠なカタパルトの開発に失敗したため、航空母艦ではカタパルトがまったく装備されなかった。 カタパルト未搭載の空母は搭載機の離艦時、風上に向かって高速で航行しなければならず、そのため戦艦並みの大型空母であっても、巡洋艦並みかそれ以上の高速性能が求められ、建造と運用上の大きな制約となった。 一方アメリカ海軍は連続使用が可能な油圧式カタパルトを実用化し、日本の空母に比べ迅速且つ大量の発艦が可能であった。 また小型・低速の空母であってもカタパルトを搭載すれば十分に活用でき、戦局に大きく寄与した。
現代の航空母艦では、第2次世界大戦後にイギリス海軍で考案され,アメリカ空軍において実用化された「蒸気式タパルト」が主流。 蒸気は推進用のボイラーからから圧力タンクに貯めておき、航空機の発進時、一気にシリンダーへ送り込み、カタパルトに連動するピストンを動かすもの。 中国は「大国で空母を保有してないのは中国だけ」と、1988年進水の旧ソ連製空母 「ヴァリヤーグ」(67500トン)を購入し大連造船所で改造中。 完成後は主に練習用空母として離着艦訓練などに利用される見通しだが、別に上海の造船所では初の国産空母を建設中と見られ、最終的には原子力空母2隻を含む5~6隻体制にする見込み。 しかし各国の専門家からこの計画が疑問視されている大きな理由は、「カタパルトの開発が非常に難しいから」。



















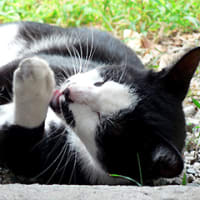
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます