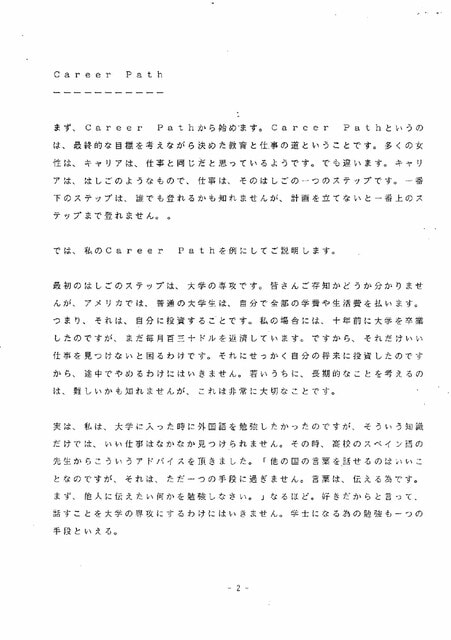英国の大学評価機関QSからQS World University Rankings の雇用者評価の依頼があり、オンラインアンケートに回答しました。QSランキングは、世界で最も広く閲覧されている世界大学ランキングと言われています。
大学ランキングが発表されるようになった経緯は以下の通りです。 2003年英国政府が産学連携の検討を行った際、大学の国際的なランキングの必要性が強調され、タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)とクアクアレリ・シモンズ(QS)と提携し、ランキングが作成されるようになりました。 その後、2009年にTHEは独自のTHE世界大学ランキングを作成することとなり、QSと分離、QSは、教育に関する評価に焦点をおいてランキングを作成し続けています。 QSランキングの評価基準は以下の通りです。
指標 割合 詳細
学術査読 40% 社内グローバル学術調査に基づく
教員・学生比率 20% 教育の取り組みの測定
論文被引用数 20% 研究インパクトの測定
雇用者の評判 10% 新卒採用者へのアンケート調査に基づく
留学生比率 5% 学生コミュニティの多様性の測定
外国人教員比率 5% 教員の多様性の測定
当方に依頼があったのはランキング評価の対象となる大学の卒業生の「雇用者の評判」についてです。
大学教育の質を評価するのは難しいと思いますが、客観性や一貫性を保つ努力はされていると感じました。
翻って日本の大学ランキングは入試難易度主体です。大学が教育機関であるなら、そこで学生をいかに教育したかが大学の質を分けると思います。
もう一つ日本には人事が評価する大学就職力ランキングというものもあります。 これは、私が回答した「雇用者の評判」にあたると思いますが、大学の研究実績や教育の質を客観的に示す評価ではなく、就職後の卒業生の評価と考えられます。
日本でもより客観的に大学の質を評価する大学ランキングが発表されるようになればと思います。