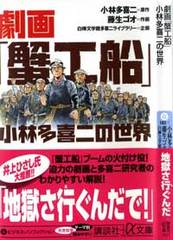
蟹工船から見た日本近代史
/井本三夫著/評者荻野富士夫小樽商科大学教授
周縁・辺境から日本近代史を照射
早くも1913年に1万2000人もの日本人がカムチャツカで漁業に従事していたこと、「蟹缶詰・蟹漁業は植民地的性格の最も強い部門だった」ことなどの指摘をふまえて、企業の競合と国家の統制による「国策的な北洋漁業独占体の形成」の過程が実証的に明らかにされる。それゆえに、「北洋漁業でも遅い時期に成立した蟹工船漁業には、北方植民地化・帝国主義のそれまでの段階で育成された暴力的労働強化の方式が蓄積され、重層的な形で現れたのではないか」という論点は、十分な説得力をもつ。
多喜二は「蟹工船」という「特殊な一つの労働形態」を描いたのであり、発表当時に加えられた、蟹の捕獲や缶詰製造の労働過程が描かれていないという批判は的外れではあったが、それでも本書第三章で扱われる「蟹工船の実態」―人員構成、製造過程、過酷を通り越した労働状況など―を知ることは、多喜二が込めた大きな意図や細部の工夫へのより深い理解につながる。蟹工船が工場法も航海法も適用されないという意味は、労働者が「臨時乗客扱い」とされていたから、だという。
「帝国軍隊―財閥―国際関係―労働者」を全体として描いた『蟹工船』を読む上で、本書は最良の手引きとなるとともに、周縁・辺境から日本近代史を照射する視点を提示する。その点で「北洋漁業」における「帝国軍隊」の存在・かかわりに、まだ論ずべき余地があるように思われる。
いもと・みつお 1930年生まれ。元茨城大学理学部教授。
( 2010年03月21日,「赤旗」)



















そのなかで本書は、"研究"といえるものだ。
本書の礎石は『極める眼』に収録の氏の論文であると思う。
その折にも少し議論したことがあるが、私が強調したいのは「蟹工船」を多喜二が執筆した時期、意識されていた戦争は「対ソ」戦争だということ。
北海道・北方諸島はこの軍事拠点としての位置付けがあるということだ。
「蟹工船」は、内地植民地としてのポストコロニアルとして論じることができる近代文学作品の数少ない成果であると同時に、「日本軍事史」をたどる稀有な作品でもあることを読みとり、浮き彫りにしたいものである。
それだけにこの書評の荻野氏の
「帝国軍隊―財閥―国際関係―労働者」を全体として描いた『蟹工船』…(中略)…その点で「北洋漁業」における「帝国軍隊」の存在・かかわりに、まだ論ずべき余地があるように思われる。」
という指摘は重いだろううと思う。
対ソ戦争は現実とはならなかったとはいえ、その後の帝国日本が中国ばかりか、東南アジアに植民の手を伸ばし、やがて敗北せざるを得なかった全戦争史の序章として「蟹工船」は読む継がれていかなくてはならないだろう。
「希望は戦争!!」などという、歪んだ欲望や利権を、近景とともに遠景でもとらえたいものだ。