近代天皇制のイデオロギー
定価2,860円(本体2,600円)
1998年12月20日
四六判上製 284P
日本近代史上,天皇制の権威はどのように強化されたか。本書は,対外侵略を先導した近代天皇制のイデオロギーを明治憲法や国民意識との関連で解明し,国民支配の構造とイデオロギーを浮き彫りにし,反動的な自由主義史観の根底も批判する。
森熊猛著『マンガ100年 見て聞いて』(A4判 120頁 定価2,500円)は、白樺文学館・多喜二ライブラリーが、2004年8月に主催した「生誕100年記念小林多喜二国際シンポジウム」に併設された「森熊猛作品展」に出品した作品を中心に、新聞各紙に掲載してきた新聞マンガなどを網羅した著者渾身の書き下ろしで、日本マンガ100年の歩みを回顧する内容になっている。
表紙は、ふじ子観音のほほえみ。
また、1932年春の中国への侵略戦争拡大の中で、特高に追われた小林多喜二の地下活動を支えた森熊ふじ子(旧姓伊藤ふじ子・森熊猛の妻)の俳句集『寒椿』も抄録され、多喜二亡き後のふじ子の生活を辿れる内容になっている。
著者の森熊猛氏は、今年9月17日に95歳の生涯を閉じたが、同書の巻頭で、作家澤地久枝さんの「眠りより安らかにー会えなかったふじ子さんへー」が収録されている。
ふじ子の嫁入りの仕度の中にあった多喜二の遺品、いつもふじ子のかたわらにある仏壇にまつられた小さな分骨の包みへの森熊さんの思い。
そして、妻亡きあと、おのれ一人の決心で、多喜二の分骨を妻の遺骨にまぜ埋葬した思いー。尋常に来ることではない。
やるべきことは全てやったと思っていたが、まだ今村についての仕事が残っていた。
どうにかしないとな。
三浦綾子「母」をべースにした映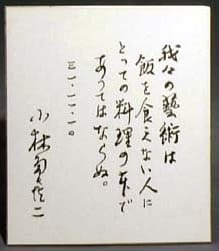
画「母―小林多喜二の母の物語」(主演:寺島しのぶ)が今春から公開される。原作は多喜ニとその恋人タキに焦点を当てたラブストーリーだ。
それはそれで多喜ニの青春である。
しかし、そこで物語は終れない。
多喜ニは革命家とし て日本共産党幹部となり、反戦運動を指導したのだから。
そしてその戦友一伊藤ふじ子を忘れてはならないと思う(三)
●第五章 奴隷―「党生活者」結婚の資格
多喜二は「党生活者」のに「性」の〈犠牲〉を見てはいたが、「家庭生活」の〈犠牲〉は見えていなかったのだろうか――。そうではない。以下に多喜二の回答がある。
―「ヨシちゃんはまだか?」
私は頬杖をしながら、頭を動かさずに眼だけを向けて訊いた。
「何が?」
伊藤は聞きかえしたが、それと分ると、顔の表情を(瞬間だったが)少し動かしたが、
「まだ/\!」
すぐ平気になり、そう云いった。
「革命が来てからだそうだ。わが男の同志たちは結婚すると、三千年来の潜在意識から、マルキストにも拘らず、ヨシ公を奴隷にしてしまうからだと!」
と須山が笑った。
「須山は自分のことを白状している!」
と伊藤はむしろ冷たい顔で云った。
「良き同志が見付からないんだな。」
私は伊藤を見ながら云った。
「俺じゃどうかな?」
――伊藤と互角で一緒になれるような同志はそんなにいまいと思っている。彼女が若し本当に自分の相手を見出したとすれば、それはキット優れた同志であり、そういう二人の生活はお互いの党生活を助成し合う「立派な」ものだろうと思った。――私は今迄こんなに一緒に仕事をして来ながら、伊藤をこういう問題の対象としては一度も考えたことがなかった。だが、それは如何にも伊藤のしっかりしていたことの証拠で、それが知らずに私たちの気持の上にも反映していたからである。
「責任を持って、良い奴を世話してやることにしよう。」
私は冗談のような調子だが、本気を含めて云った。が、伊藤はその時苦い顔を私に向けた……。
ここで多喜二が「わが男の同志たちは結婚すると、三千年来の潜在意識から、マルキストにも拘らず、ヨシ公を奴隷にしてしまう」とマルキストであろうと、「ヨシ公を奴隷」にする旧態依然とした生活態度があることを指摘している。「三・一五」の冒頭での「ローザを知っているか」という問いかけも多喜二の女性への視点を象徴的に示している。ローザとは、虐殺されたドイツ共産党の女性革命家のローザ・ルクセンブルグのことだ。
―私たちは「エンコ」する日を決め伊藤が場所を見付けてくれることにした。いよいよ最後の対策をたてる必要があった。
「あんた未だなす?」
伊藤が立ち上がりながら、そう訊いた。
「あ。」
と云って、私は笑った、「お蔭様で、膝の蝶ちがいがゆるんだ!」
伊藤は一寸帯の間に手をやると、小さく四角に畳んだ紙片を出した。私はレポかと思って、相手の顔を見て、ポケットに入れた。下宿に帰って、それを出してみると、薄いチリ紙に包んだ五円札だった。
〈伊藤〉は綺麗な顔をしていて、経済的に困っている佐々木に五円をみついだり、よごれたシャツをみつけ新しいシャツをプレゼントしてもくれるなど気配りがゆきとどいている。そればかりか、未組織のオルグとして有能な稀有な活動家だ。佐々木の気を惹くには十分な女子力をもっている。佐々木にとっては、その女子力と美貌がオルグとしての能力の前提でもあるらしい。
〈伊藤〉が、「良い奴を世話する」という佐々木に、苦い顔をむけたというのは、〈伊藤〉は〈笠原〉と同じように佐々木に好意以上のものを持っているということを意味する。一度は「俺じゃだめかな?」と〈伊藤〉の気をひきながら、この言葉を「冗談」だととりさげるなど佐々木の告白はズルイ! 佐々木は〈笠原〉より、〈伊藤〉にも男性としての好意を示している。しかし、この小説の範囲では「好意」の告白以上のものではない。
――最近ビラや工新の「マスク」が、女の身体検査がルーズなために女工の手で工場に入っていると見当をつけて、女工の身体検査が急に厳重になり出している。それで当日は伊藤が全責任を持ち、両股がゴムでぴッしりと強く締まるズロースをはいて、その中に入れてはいること。彼女は朝Sの方からビラを手に入れたら、街の共同便所に入って、それをズロースに入れる。工場に入ってからは一定の時間を決めて、やはり便所を使って須山に手渡す方法をとる。ビラは昼休に屋上で撒くこと。それらを決めた。
〈笠原〉は〈伊藤〉になる可能性はあったか?〈笠原〉は想像の産物だったか?〈伊藤〉は想像の産物だったか? 多喜二にとって、女性が自覚的に立ち上がることなくしては、全労働者階級の団結を獲得することも、労働者と農民の同盟を図ることも(「不在地主」の労農同盟の先頭にも女性たちがいた)ないことは、多喜二の作品を少しでも読むものにとっては理解されることだろう。平野謙のように「党生活者」の〈笠原〉への佐々木の態度の一面だけで、「『党生活者』に描かれた〈笠原〉という女性の取り扱いを見よ。目的のためには手段を選ばぬ人間蔑視が「伊藤」という女性とのみよがしの対比のもとに、運動の名において平然と肯定されている。そこには作者のひとかけらの苦悶さえ泛んでいない」(「ひとつの反措定」」『新生活』 四六年四、五月合併号)と批判することは、誤読というだけではなく、多喜二とその作品を誹謗・中傷する目的で意図的に書かれたとしか思えない。
●第四章 〈伊藤〉という名の ふじ子
冒頭で紹介の南(旧姓小沢)路子は多喜二の後に、「藤倉工業」にオルグとして派遣され、多喜二たちの闘争をたどっている。そのレポートは「女工 マツ子」名で「赤旗」に掲載された。
――(大崎労働者クラブ)に集まる「藤倉工業」の皆の不満はひどかった。一人が「プロレタリア小説家の小林さんを知っているからあの人に頼んで来てもらって、皆を集めたらどうだろう?」と提案した。それも未組織の人を大衆的に集める方法なので、早速一人だけ工場を早引きして、小林多喜二に頼みに行った。多喜二は非常に親切に、何から何まで世話を焼いた。馘首が二十日先に迫った時「小林多喜二の小説の話を聞く会」という名目で公然と二十数名余りの男女女工を集めることに成功した。小説の話なんか聞かないうちに、工場長や、重役や組長などの悪口が飛び出したり、既に二回まかれた工場新聞の話が出たり、エロ話に脱線したりした。――「小父さん、あたい達の工場のこと小説に書いてよ」とか男女工が話かけるのに対して、同志小林はニコニコして答えていた。「君達の工場の事を小父さんだって書きたいのだが、何時も監督におどかされて恐々していますだの、大人しく馘になりました、なんて事はみっともなくて書けないじゃないか。今度の首切りなんか、君達がまっさきに起って、反対するんだね、そうすれば小父さんも××の従業員はこんなに偉いんだと大威張りで小説に書くよ」などと答えたりした。多喜二の励ましによって、ほとんど全部が未組織であるにもかかわらず「どんなにして馘首に反対するか」「如何にして従業員大会を開くか」「俺がビラを持ち込む」という元気な青年さえ出てきた。
多喜二は「党生活者」で、この闘争を以下のように描いた。
―太田のあとは伊藤ヨシが最近メキ/\と積極的になった。弾圧の強襲が吹き捲っているときに、積極性を示すものは仲々数少なかったのだ。彼女は高等程度の学校を出ていたが、長い間の(転々としてはいたが)工場生活を繰りかえしてきたために、そういう昔の匂いを何処にも持っていなかった。
―伊藤は警察に捕る度に母親が呼び出され引き渡されたが、半日もしないうちに又家を飛び出し潜ぐって仕事を始めた。母親は、娘が捕かまったから出頭しろという警察の通知が来ると喜んだ。そして警察では何べんもお礼を云って帰ってきた。三度目か四度目に家へ帰ったとき、蔭ながらのお別れと思い、伊藤は久し振りで母親と一緒に銭湯に行った。ところが母親はお湯屋で始めて自分の娘の裸の姿を見て、そこへヘナ/\と坐ってしまった。伊藤の体は度重なる拷問で青黒いアザだらけになっていた。彼女の話によると、そのことがあってから、母親は急に自分の娘に同情し、理解を持つようになったというのである。「娘をこんなにした警察などに頭をさげる必要はいらん!」と怒った。その後、「ただ貧乏人のためにやっているというだけで、罪もない娘をあんなに殴ぐったりするなんてキット警察の方が悪いだろう」と母親は会う人毎にそう云うようになっていた。――自分の母親ぐらいを同じ側に引きつけることが出来ないで、どうして工場の中で種々雑多な沢山の仲間を組織することが出来るものか。
ここは、ふじ子とその母とのエピソードがそのまま生かされているといっていい。ふじ子は検挙され、大崎署に連行された。特高のテロはすさまじいものだった。当時の活動家の証言によると五~六人がかりで帯や着物を引きはぎ素っ裸にして取り囲むと、こわれた肘かけイスの釘の出ている木片で両足を殴りつけ、太ももを靴でけるなどの暴力をくわえ、さらに、うら若き女性にたえ難い野獣のような凌辱をさえもくわえたという。ふじ子が受けたテロも同様なものだったろう。古賀「無名の情熱――伊藤ふじ子」にも、「女であることをもって凌辱的拷問を受けたという。」と書かれている。「党生活者」では、「伊藤も二度ほど警察で、ズロースまで脱ぎとられて真ッ裸にされ、竹刀の先きでコヅキ廻わされたことがあったのだ。」とこのエピソードが描かれている。
〈伊藤〉の下宿の「鏡台を見ると立派で、黄色や赤や緑色のお白粉まで揃っている」という生活を紹介し、
――未組織をつかむ彼女のコツには、私は随分舌を巻いた。少しでも暇があると浅草のレビュウへ行ったり、日本物の映画を見たり、プロレタリア小説などを読んでいた。そして彼女はそれを直ちに巧みに未組織をつかむときに話題を持ち出して利用する。(余談だが、彼女は人眼をひくような綺麗な顔をしている)
―彼女はそれから自分たちのグループを築地小劇場(左翼劇場)の芝居を見に連れて行ったことを話した。労働者だとか女工だとかゞ出てきて、「騒ぎ廻わる」ので吃驚りしてしまったらしかった。終ってから、あれは芝居じゃないわ、と皆が云う。 伊藤が、何気ないように、どうせ俺ら首になるんだ、おとなしくしていれば手当も当らないから、あの芝居みたいに皆で一緒になって、ストライキでもやって、おやじをトッちめてやろうかと云うと、みんなはニヤ/\して、「ウン……」と云う。そしてお互いを見廻しながら、「やったら、面白いわねえ!」と、おやじのとッちめ方をキャッ/\と話し合う。それを聞いていると、築地の芝居と同じような遣り方を知らず識らずに云っていた。
――工場で一寸ちょっと眼につく綺麗な女工だと、大抵監督のオヤジから、係の責任者から、仲間の男工から買物をしてもらったり、松坂屋に連れて行ってもらったり、一緒に「しるこ屋」に行っておごってもらったりする。伊藤は見込のありそうな平職工だと誘われるまゝに出掛けて行ったし、自分からも勿論誘うようにしていた。それで彼女は工場には綺麗に顔を作って行った。
――工場のオルグをやると、どうしても白粉ッ気が多くなるが、細胞の会合のときに伊藤は今まで一度も白粉気のある顔をしてきたことがなかった、又その必要もなかったので。フト見ると、ところが伊藤は今迄になく綺麗な顔をしていた。
この二つのエピソードは、左翼劇場の女優・ふじ子の姿であるだろう。〈伊藤〉もまた、伊藤ふじ子という女性を素材としたものだった。
- 第三章 「党生活者」の家計
佐々木と笠原の生活をさらに追い詰める事態が発生する、〈笠原〉は共産党―赤のシンパとしてデザイン事務所を突然解雇される。解雇の要因は、明らかに、佐々木の党活動に協力したからだ。その責任は佐々木にある。その家計は逼迫する。「党生活者」の家計を多喜二は以下の通り描く
――笠原は別に何もしていなかったのだが、商会では赤いという噂があった。それで主任が保証人である下宿の主人のところに訪ねてきた。ところが、彼女は以前からそこにいないということが分ってしまった。商会ではそれでいよ/\怪しいということになり、早速やめさせたのだった。
「私は今迄笠原の給料で間代や細々した日常の雑費を払い、活動に支障がないように、やっとつじつまを合せてきていた」という言葉があるように、佐々木には収入がなく、笠原のヒモだった。
―私たちはテキ面に困って行った。悪いことには、それが直ぐ下のおばさんに分る。下宿だけはキチンとして信用を得て置かなければ、「危険だった。」それで下宿代だけはどうしても払うことにした。だがそうすると、あと二三円しか残らなかった。
―飯を倹約した。なすが安くて、五銭でも買おうものなら、二三十もくるので、それを下のおばさんのヌカ味噌の中につッこんで貰って、朝、ひる、夜、三回とも、そのなすで済ました。三日もそれを続けると、テキ面に身体にこたえてきた。階段を上がる度に息切れがし、汗が出て困った。
―笠原は何時も私について来ようとしていないところから、為すことのすべてが私の犠牲であるという風にしか考えられなかった。「あなたは偉い人だから、私のような馬鹿が犠牲になるのは当り前だ!」――然し私は全部の個人生活というものを持たない「私」である。私は組織の一メンバーであり、組織を守り、我々の仕事を飽くまでも行くように義務づけられている。
――個人生活しか知らない笠原は、だからひとをも個人的尺度でしか理解出来ない。
佐々木はなんという自己中心主義の人間として描かれているのだろうか。佐々木に協力しなければなに不自由ない生活者だった〈笠原〉は、いまや日陰者の生活を強いられている。その〈犠牲〉を強いたのは佐々木であるのに、佐々木はそのことに心の痛みはないようだ。この主人公は〈笠原〉の寄生虫だ。タイピストの〈笠原〉の安給与が二人の生活を支えていたばかりか、党活動費をも捻出していた。革命のためにという大義を掲げた〈やりがい搾取〉、佐々木への恋情に甘えた〈収奪〉はここにきわまったといえる。これもまた、大きな〈犠牲〉だった。「危険」なのは佐々木だけであり〈笠原〉には危険はなかった。
多喜二は「党生活者」に「性」の〈犠牲〉を見てはいたが、「家庭生活」の〈犠牲〉は見えていなかったのだろうか。そうではない。これは、後の章での「マルキストにも拘らず、女性を奴隷にしてしまう」「党生活者」批判への布石だ。
〈笠原〉は銀座のデザイン事務所のタイピストだという設定だったが、ふじ子が勤めた「銀座図案社」は、前衛日本画家・玉村方久斗の経営で銀座・昭和通りに面する木造三階建ての最上階にあり、衝立に仕切った同じフロアに「キネマ週報社」があった。仕事内容は、東京芝浦電気のグラフ誌のデザインなどを手掛けていて、ふじ子はその使い走りのような仕事をしていた。『キネマ週報』は、戦前の日本映画界で独自の地位を占めた映画界情報誌。『国際映画新聞』の発行元・国際映画通信社の社員であった田中純一郎(『日本映画発達史』の著者)が、片桐槌彌と組んで創刊。トーキー化を経て最初の黄金時代を迎えていた日本の映画業界の内情を知るためにもっとも有効な雑誌として知られる。一階は喫茶店で築地小劇場の劇団員のたまり場でもあった。キネマ週報社に勤める大久保武は共産青年同盟員であったし、このビルに集まった人々は左翼シンパが多かった。そういう文化空間であった。
――笠原は小さい喫茶店に入ることになった。始め下宿から其処へ通った。夜おそく、慣れない気苦労の要る仕事ゆえ、疲れて不機嫌な顔をして帰ってきた。ハンド・バッグを置き捨てにしたまゝ、そこへ横坐りになると、肩をぐッたり落した。ものを云うのさえ大儀そうだった。しばらくして、彼女は私の前に黙ったまゝ足をのばしてよこした。
「――?」
私は笠原の顔を見て、――足に触って見た。膝頭やくるぶしが分らないほど腫くんでいた。彼女はそれを畳の上で折りまげてみた。すると、膝頭の肉がかすかにバリバリと音をたてた。それはイヤな音だった。
「一日じゅう立っているッて、つらいものね。」
と云った。
―笠原のいる喫茶店にはたゞお茶をのんで帰ってゆくという客ではなく、女を相手に馬鹿話をしてゆく連中が多かった。それに一々調子を合わせて行かなければならない。それらが笠原の心に沁みこんでゆくのが分った。
私はそんなに笠原にかゝずり合っていることは出来なかった。仕事の忙がしさが私を引きずッた。倉田工業の情勢が切迫してくるとゝもに、私は笠原のところへはたゞ交通費を貰に行くことゝ、飯を食いに行くことだけになって、彼女と話すことは殆どなくなってしまっていた。気付くと、笠原は時々淋しい顔をしていた。
この場面は、銀座の八丁目「コッテン」に勤めたふじ子の経験が活かされたのだろう。佐々木は〈笠原〉に犠牲を強いている〈笠原〉はそれを享けている。そこに「淋しい顔」をした〈笠原〉がいる。
―私はとにかく笠原のおかげで日常の活動がうまく出来ているのだから、その意味では彼女と雖も仕事の重要な一翼をもっていることになる。私はそのことを笠原に話し、彼女がその自覚をハッキリと持ち、自分の姿勢を崩さないようにするのが必要だと云った。
―私は久し振りに自分の胡坐のなかに、小柄な笠原の身体を抱えこんでやった――彼女は眼をつぶり、そのまゝになっていた……。
さすがのロボット党員佐々木も〈笠原〉を愛しく思ったのだろうか、彼は〈笠原〉をハグした。佐々木は〈笠原〉を失職させたばかりか、夜おそく、慣れない気苦労の要る仕事をさせ、帰ってきてからも炊事や、日曜などには二人分の洗濯などに追われ、それは随分時間のない負担の重い生活を強いているのだ。〈笠原〉の〈犠牲〉のおかげで、日常の活動がうまく出来ているのに。佐々木は、この〈笠原〉の気持ちにどう応えるつもりだろうか?
彼は、その〈犠牲〉に対して感謝をささげるべきだろう。だが佐々木はその〈犠牲〉に一顧だにしてない、このことは非難されてもしかたないだろう。
「彼女と雖も仕事の重要な一翼をもっている」――佐々木はそのことを理解してはいる。だが、「意義と任務」でこの〈犠牲〉を、「左翼の運動に好意は持っていたが別に自分では積極的にやっているわけではな」い〈笠原〉に求めるのは酷だろう。そういう政治性をもった人物として〈笠原〉は設定されていない。多喜二はなぜ、こういう無理を描こうとしているのだろうか――。
それでも「党生活者」最後の場面で、須山が検挙を覚悟して倉田工業の屋上でビラをまく行動に立ち上がる。佐々木、〈伊藤〉との細胞会議で、誰かが大衆の前で公然とやらなくては闘争にならないのだ、と須山が言い、「私(佐々木)」は、「独断」でなく、「納得」によって闘争を進めてゆくべきだと考え、そのやり方で運動が正しい方向に進むように願っているという描写があります。ここで佐々木が〈命令・指示〉によって須山を動かすことを選ばず、あくまで〈納得〉を通じて自覚的に〈犠牲〉的行動に立ち上がることを求めていることにも注目すべきだ。佐々木が〈笠原〉に〈犠牲〉を求める態度も〈命令・指示〉ではなく、〈納得〉であるのだ。
- 第二章 「党生活者」のおんな
―今まで一二度逃げ場所の交渉をして貰った女がいた。その女は私(警察の追及によって地下活動に潜行している―主人公佐々木安治―引用者註)が頼むと必ずそれをやってくれた。女はある商店の三階に間借りして、小さい商会に勤めていた。左翼の運動に好意は持っていたが別に自分では積極的にやっているわけではなかった。
―私は笠原に簡単に事情を話して、何処か家が無いかときいた。
女の友達なら沢山頼めるところがあるのだが、「君、男だから弱る」と笠原は笑った。
「こゝは、どうだろう……?」
私は思いきっていい出した
「…………!」
笠原は私の顔を急に大きな(大きくなった)眼で見はり、一寸息を飲んだ。それから赤くなり、何故かあわてたように今まで横坐りになっていた膝を坐り直した。
しばらくして彼女は覚悟を決め、下(大家さん―引用者)へ降りて行った。S町にいる兄が来たので、泊って行くからとことわって来た。だが、兄というのはどう考えてもおかしかった。彼女は簡素だが、何時でもキチンとした服装をしていて、髪は半断髪(?)だった。そこにナッパを着た兄でもなかった。彼女がそういうと、下のおばさんは子供ッぽいふじ子の上から下を、ものもいわないで見たそうである。
ここは、ふじ子との暮らしを素材としていると思ってもまちがいはない。ふじ子は多喜二の七つ年下「幼い」おもざしの二十歳の女性で、銀座のデザイン事務所に勤める半断髪のモダンガールで、兄もいた。また、実際に活動家をサポートする活動もしていたからだ。
―蒲団は一枚しか無かった。それで私は彼女が掛蒲団だけを私へ寄こすというのを無理に断って、丹前だけで横になった。電燈を消してから、女は室の隅の方へ行って、そこで寝巻に着換るらしかった笠原は朝までたゞの一度も寝がえりを打たなかったし、少しでも身体を動かす音をさせなかったのである。私は、女が最初から朝まで寝ない心積でいたことをハッキリとさとった。
主人公・佐々木安治が〈笠原〉と同居を始めるきっかけは、愛情からではなく、佐々木が帰るべきところを失い、その一夜の宿を求めたことに〈笠原〉が同意したことに始まる。
一つ部屋で一夜を過ごす若い男女。当然、そこには性的欲求の衝動がある。かつて、多喜二は小説「オルグ」でそういう場面を妄想し、描こうとしたことがあった。「オルグ」ノート稿(「小林多喜二草稿ノート・直筆原稿」雄松堂DVD)を検討した解説で、尾西康充は推敲の軌跡をたどり、以下の指摘をしている。
――地下生活者の「愛情の問題」の描写について多喜二が「オルグ」でも試行錯誤していたことは、「中七」の病気を石川に代わってお君がオルグの仕事を引き受けた場面にみられる。「石川は事情があって外の女と一緒に運動しなければならなくなる。すると運動の形態の必然が、外の女と関係させる。その女がお君の友達であり同志である。そうなるとお君は苦しむ。石川はその苦しむお君をケイベツする」とあるが、ペンで上から抹消している。さらに、石川がお君からの愛情に気づく場面で、草稿には「襖を隔てた隣の室で、お君が帯をとき、着物を脱いでいる音を彼は室の中で聞いていた。彼は今晩はまた眠れなく屡屡反そくしなければならないのだなと思った……。」とある。これもペンで上から消されている。また、石川は疲労して帰って床に入ってからも興奮して眠れないときには「まるで狂暴的に」お君の室に入って行くことを考えることもあったが、「しかし、彼はいつでも最後のドタン場でそれを踏みこらえてきた」という文と、「そのために、次の日頭が重いこともあった」という文との間には、草稿では「彼は時々自☓をした。」と書かれていた。これら一連の表現は、作者がどのように「愛情の問題」を描こうとしていたのかを理解する手がかりなる。
「襖を隔てた隣の室で、お君が帯をとき、着物を脱いでいる音を聞いた」その時、多喜二は、前衛としての理性を喪い「まるで狂暴的に」室に入る衝動を意識していた。「オルグ」のなかでは、ドタン場でその欲望をおしとどめたのが多喜二らしいといえる。
小林多喜二とふじ子は、四月二十日頃から麻布の称名寺の境内にある二階の一室を借りてひそかに住んだ。多喜二とふじ子はこの時、”結婚”した。新婚の家は上下一間ずつの小さな家だった。彼らが借りた階下の部屋は隣家の板壁に周りをさえぎられて一日中日光のあたらない陰気な一室での新婚生活であった。多喜二は作家同盟書記長としてばかりか、共産党中央部アジ・プロ部員として、機関紙「赤旗」の文化欄の編集担当者としても多忙を極めていた。新婚としての甘い生活はなかった。
若い男女が一夜をともにすることで生じる性の衝動を、多喜二は小説「オルグ」のなかで自覚していた。その欲求に対してどう理性的に向き合うのかが、多喜二のリアルな課題となって迫った。ふじ子とおなじく、「党生活者」中の女性シンパ〈笠原〉にとっては一夜をともにする決意をするということは、一緒になることをも意味した。
そういう決意をした女と、そういう決意をさせた男。そう決意させておきながら佐々木は〈笠原〉が勤めから帰宅すると、入れ替わるように外出して男女のそういう関係を生じさせないよう、一緒に過ごす時間を持とうとしなかった。それでも〈笠原〉の側は「そうなってはいけない」と自分を抑えてはいたが、佐々木を求めて「一緒に」手をつないで歩きたいという思いでいっぱいになっている――、それは佐々木を愛する存在として〈笠原〉を描いているといえるだろう。その思いを受け止めない佐々木は、〈笠原〉に不機嫌に「当たられても」当然だろう。多喜二とふじ子の生活がそうであったとはいわない。多喜二は佐々木とは異なるからだ。
―彼女は時には矢張り私と一緒に外を歩きたいと考える。が、それがどうにも出来ずにイラ/\するらしかった。それに笠原が昼の勤めを終って帰ってくる頃、何時でも行きちがいに私が外へ出た。私は昼うちにいて、夜ばかり使ったからである。それで一緒に室の中に坐るという事が尠かった。そういう状態が一月し、二月するうちに、笠原は眼に見えて不機嫌になって行った。彼女はそうなってはいけないと自分を抑えているらしいのだが、長いうちには負けて、私に当ってきた。
「あんたは一緒になってから一度も夜うちにいたことも、一度も散歩に出てくれたこともない!」
終には笠原は分り切ったそんな馬鹿なことを云った。
―私はこのギャップを埋めるためには、笠原をも同じ仕事に引き入れることにあると思い、そうしようと幾度か試みた。然し一緒になってから笠原はそれに適する人間でないことが分った。如何にも感情の浅い、粘力のない女だった。私は笠原に「お前は気象台だ」と云った。些細のことで燥いだり、又逆に直すぐ不貞腐れた。こういう性質のものは、とうてい我々のような仕事をやって行くことは出来ない。
―勿論一日の大半をタイピストというような労働者の生活からは離れた仕事で費し、帰ってきてからも炊事や、日曜などには二人分の洗濯などに追われ、それは随分時間のない負担の重い生活をしていたので、可哀相だったが、彼女はそこから自分でグイと一突き抜け出ようとする気力や意識さえもっていなかった。私がそうさせようとしても、それについて来なかった。
しかし、すでに恋心を佐々木に抱いている〈笠原〉、偽装とはいえ「事実婚」に入ることを承認した〈笠原〉にとっては、佐々木はなんとももどかしい感情のないロボットのような男だったろう。
〈笠原〉は佐々木との生活費を負担していた。そればかりか「一日の大半をタイピストというような労働者の生活からは離れた仕事で費し、帰ってきてからも炊事や、日曜などには二人分の洗濯などに追われ、それは随分時間のない負担の重い生活をしていた」。共稼ぎ夫婦の一方が家事労働に従事することだけでも大きな〈犠牲〉だったはずだ。その〈犠牲〉は左翼のシンパとしてのやりがいに甘えた〈やりがい搾取〉、佐々木への恋情に甘えた〈収奪〉でもあった。
佐々木は、〈笠原〉の女心にこたえようとしない。なぜか――、「オルグ」ノート稿には男としての欲求を描きながら、ここではその欲求さえ描こうとしない多喜二だった。
ふじ子は、三一年秋ごろから古賀孝之経営の銀座の八丁目「コッテン」という名の喫茶店を「伊藤まさ子」(-古賀の記憶)と名のり手伝うようになった。遅くなれば店に泊まることもあり、この店から「銀座図案社」というデザイン事務所に勤めに出て行く。そのころ、水島みつこ(後に古賀の妻となる)と知り合う。コッテンに左翼が集まっているという噂が立ち、警察も姿をみせるようになったので古賀は店をたたみ、八丁堀の奥の家に引っ越した。ふじ子も一緒で、高野治郎ともう一人の青年の三人で二階の二帖間にふじ子は住んだ。所持品はほとんどなく、洋服も少なく毎日同じ服をきていた。古賀によると、ふじ子がしばらくして検挙され、女であることをもって凌辱的拷問を受けた。このエピソードは三一年十一月二三日付『帝国大学新聞』に掲載の短編小説「疵」にまとめられた。「疵」とは、特高のテロによってふじ子の身体に刻まれた傷跡のことだ。
同時期、プロレタリア美術家同盟の指導者の一人である岡本唐貴は、杉並・馬橋の多喜二たち一家のそばに引っ越した。細い路地をはさんで、多喜二の家があった。弟の三吾のバイオリンの練習の音が聞こえる距離だったと、『岡本唐貴自伝的回想』で述懐している。岡本は、プロ美第四回展に出品した「電産スト」をテーマに三○○号のキャンパスに向かっていた。多喜二もふじ子もよく遊びにきた、ふじ子は多喜二のことを「ヤツが」「ヤツが」と得意げに語ったと岡本は証言する。すでに多喜二とそういう関係にあったのだ。
翌三二年四月上旬、多喜二が指導するプロレタリア文化連盟は壊滅的な弾圧を受けた。その前から、作家同盟書記長として第五回大会の報告書をまとめるため自宅を離れ、ふじ子に紹介された木崎方にこもっていて検挙を免れ、そのまま地下生活に入った。
古賀孝之「無名の情熱――伊藤ふじ子」(『現象』六九年十一月号)によると、ふじ子は洋裁の出来る水島みつ子を講師に仕立ててグループをつくり、大井町あたりの労働者街でサークル活動をしようとしたそうである。はでな立看板で労働者のおかみさんを集めた。このサークルは「大崎労働者クラブ」にはいっていた。大崎の東京南部地域は、現在も「下町ロケット」などで知られる都下の先進工業地帯で、ここには五反田の藤倉工業の女子労働者らも集まった。藤倉工業は海軍御用達の軍需工場で、中国戦線の毒ガス戦を想定し、防毒マスク、パラシュート、ゴムボート、飛行船の側の製造に従事していた。ここで臨時工解雇反対の争議がまき起こっていたことで、共産党はオルグ対象の重点工場として工作していた。多喜二は、その藤倉工業解雇撤回闘争の経緯を小説「党生活者」(発表時「転換時代」の題名、『中央公論』三三年四月、五月号掲載)で、ドキュメンタリータッチで描いている。同作にはふじ子との暮らしが随所に反映されている。その女性像表現を中心に以下にふじ子の影をたどる。
七沢温泉から届いた多喜二の手紙
ふじ子回想の「ノート原稿の清書」とは、小説「オルグ」(『改造』 三一年五月号)のこと。神奈川県伊勢原市の七沢温泉で逗留中の多喜二から、「伊藤貞助方 伊藤ふじ子様」の封書が届いた。封書の裏の差出人には「七沢の蟹」。中には便箋二枚が入っていた。ふじ子宛の書簡に「七沢の蟹」を名乗ったのは、多喜二がこれまで縁のない七沢温泉に多喜二が逗留していることを明示したものだ。ふじ子が晩年横浜に終の棲家を構えたことを考えても、ふじ子が七沢の温泉宿を紹介したと考えて間違いがないだろう。現物は今に伝えられないが、手紙を盗み見た古賀孝之の記憶に基づいてその文面を再現すると
――君のことをなにかにつけ思い出す。しばらく君とご無沙汰していたのはわけがあるんだ。大阪での戦旗講演で検挙された。その時いっしょに捕まったかわいそうな老人がいたので、それを抱いて寝てやった。そのためにカイセンを移された。それを治療するためにこの温泉にきている。このことは親しい人にも誰にも言っていない。君が誰かに話すとは思わないが、ぼくはそれをちょいと試したくなった。それでこの手紙を書く。帰ったらまた会いたいものだ。
ふじ子と多喜二の交流は、このときすでに始まったのだ。「オルグ」を書き上げた多喜二は一念発起して、東京での暮らしを母と弟を小樽から呼び寄せて一緒に住み始めた。母は猫の額ほどの畑を耕し、弟はヴァイオリン奏者を志望して、斯界の第一人者・橋本国彦のもとで指導を仰いだ。多喜二は元酌婦の恋人・田口タキと別れたばかりだった。ふじ子と出会ったのは、そういう心に空洞ができたころだった。ふじ子は多喜二収監中の同劇団の内紛に巻き込まれて嫌気がさし、七、八名の女優たちと一緒にナップに合流した。多喜二はそのことを知り、ふじ子とその内幕を聞きに何度か築地の左翼劇場をたずね、お茶を一緒に飲む仲になったのだった。多喜二は「文戦の打倒について」(第二文戦打倒同盟『前線』一九三一年七・八月合併号)を書き上げ、続く八月、「都新聞」での連載小説「新女性気質」の掲載を始めた。
ふじ子は、三一年秋ごろから古賀孝之経営の銀座の八丁目「コッテン」という名の喫茶店を「伊藤まさ子」(-古賀の記憶)と名のり手伝うようになった。遅くなれば店に泊まることもあり、この店から「銀座図案社」というデザイン事務所に勤めに出て行く。そのころ、水島みつこ(後に古賀の妻となる)と知り合う。コッテンに左翼が集まっているという噂が立ち、警察も姿をみせるようになったので古賀は店をたたみ、八丁堀の奥の家に引っ越した。ふじ子も一緒で、高野ともう一人の青年の三人で二階の二帖間にふじ子は住んだ。所持品はほとんどなく、洋服も少なく毎日同じ服をきていた。古賀によると、ふじ子がしばらくして検挙され、女であることをもって凌辱的拷問を受けた。このエピソードは一九三一年十一月二三日付『帝国大学新聞』に掲載した短編小説「疵」で作品にまとめられた。「疵」とは、特高のテロによってふじ子の身体に刻まれた傷跡のことだ。
同時期、プロレタリア美術家同盟の指導者の一人である岡本唐貴は、杉並・馬橋の多喜二たち一家のそばに引っ越した。細い路地をはさんで、多喜二の家があった。弟の三吾のバイオリンの練習の音が聞こえる距離だったと、『岡本唐貴自伝的回想』で述懐している。美術同盟第四回展に出品した「電産スト」をテーマに三○○号のキャンパスに向かっていた。多喜二も時々見にきた。岡本は多喜二もふじ子もよく遊びにきた……、ふじ子は多喜二のことを「ヤツが」「ヤツが」と得意げに語った。このころすでに多喜二とそういう関係にあったのだ。
翌一九三二年四月上旬多喜二が指導するプロレタリア文化連盟は壊滅的な弾圧を受けた。その前から、作家同盟書記長として第五回大会の報告書をまとめるため、自宅を離れ伊藤ふじ子を通じて紹介された木崎方にこもっていて検挙を免れ、そのまま地下生活に入った。
古賀孝之「無名の情熱-伊藤ふじ子」(『現象』昭和四十四年十一月号)によると、ふじ子は洋裁の出来る水島みつ子を講師に仕立ててグループをつくり、大井町あたりの労働者街でサークル活動をしようとしたそうである。はでな立看板で労働者のおかみさんを集めた。このサークルは「大崎労働者クラブ」だった。大崎の東京南部地域は、現在も「下町ロケット」などで知られる都下の先進工業地帯で、ここには五反田の藤倉工業の女子労働者らも集まった。藤倉工業は海軍御用達の軍需工場で、中国戦線の毒ガス戦を想定し、防毒マスク、パラシュート、ゴムボート、飛行船の側の製造に従事していた。ここで臨時工解雇反対の争議がまき起こっていたことで、共産党はオルグ対象の重点工場として工作していた。多喜二は、その藤倉工業解雇撤回闘争の経緯を小説「党生活者」(多喜二没後遺作として発表された「党生活者」(「転換時代」として『中央公論』一九三三年四月、五月号掲載)でドキュメンタリータッチで描いている。同作にはふじ子との暮らしが随所に反映されている。その女性像表現を中心に以下にたどる。
小林多喜二は、豊多摩刑務所を一九三一(昭和六)年一月二十二日に保釈出獄したあと、三月中旬、警視庁による拷問の傷や、留置場で感染した疥癬などの治療のため、神奈川県伊勢原市七沢温泉に約一ヶ月間密かに逗留した。その間に、ノート稿から推敲を重ね、作品を四月六日に完成。『改造』五月号に掲載した。多喜二は、「オルグ」を通して、石川とお君の生活、殊にその個人的な生活を、かなりのボリュームで描いている。多喜二は「プロレタリアートを取り扱う場合、何時でもその個人の生活は集団の生活に裏打ちされていなければならない」とし、主人公のオルグ・石川とお君の生活を描くことによって、地下に潜って生活している前衛の生活を、その正しい姿で示すことを大きな眼目とした。
一九三二年の春、前年に多喜二らによって結成したプロレタリア文化連盟(略称コップ)は、前年の秋、日本帝国主義は「満州事変」と称する中国への侵略戦争を開始し、一五年戦争の幕をあけるともに大衆に大きな影響を与える反戦文化活動家に対する大規模な弾圧を受けた。多喜二もその対象の一人だった。
たまたま弾圧を逃れた多喜二の潜行準備は万全というわけではなかった。持ち物は皮のトランク一つ。身を隠すべきあてはなかった。活動家仲間の家はすでに監視下だ。こうなると頼れるのは、ただ、ひとり――。多喜二が向かったのは、一年ほど前の雪の日に、築地の左翼劇場で知り合った女優のたまご。芸名「伊藤一枝」、本名「伊藤ふじ子」。
●第一章 であい――「伊藤」という女
伊藤と知り合ったのは左翼劇場。多喜二は投獄されていた間に、自身原作の「不在地主」が上演されたが、獄中にいて観劇することができなかった。しかし、北海道での労働者と農民が同盟を組んで、勝利したたたかいを描いた同作は、多喜二が勤務先の銀行情報や、組合側から得た情報をもとに書きあげた乾坤一擲の作だった。同作の反応が気になって左翼劇場にむかったのだった。
ふじ子本人が多喜二とのその出会いを記録した一文がある。そこにはこんなことが記されている。
――そもそも私と彼との出会いは、彼が地下の人になる一年程前のことで、あれは彼が上京して東京に住むことになった年の二月だったと思います。ひどく雪の降る日でした。ヤップ(プロレタリア演劇同盟―引用者)の講演会のビラ張りの日で、新宿方面の割り当てが彼と私と京大の学生(中退?)だったM君*の三人だったと思います。彼は大島の対の着物に歯のちびた下駄、帽子はかむっていませんでした。*「M君」とは、芸名・沖圭一郎。本名・鎌原正巳。彼は昭和五年二月の左翼劇場公演「太陽のない街」の前後に演出部に入っている―引用者註。
――雪は私達にとってさいわいして、受持ちのビラを大体貼り終った時は、すっかり日が暮れていました。彼は私達をさそって新宿の角筈の(当時は角筈から若松町行の市電が出ていました)市電の始発の停留所の角に大きな飲食店が有りました。
――名前は忘れましたが、その二階が牛肉を食べさせる座敷になっていました。彼を先頭に、私達はその二階の座敷でスキ焼をごちそうになりました。会計の時、彼は三尺にくるくるまるめた中から小さな蟇口を出して姉さんに金をはらいました。「食べれ、食べれ」と、彼はさかんに私達にすすめて、私達に、にえた牛肉を取ってくれました。その時はそれで何となく別れました。
これが、二十歳のふじ子と二十七歳の多喜二のであいだった。その後のふじ子との交際は 三一年九月の満州事変から「非常時」共産党の大衆的な侵略戦争反対闘争のひろがりと、それに対するプロレタリア文化分野への大規模な弾圧、さらに「大森ギャング事件」の謀略、「熱海党大会弾圧事件」、岩田義道、上田茂樹、野呂栄太郎、小林多喜二など党幹部虐殺という現代史に残る大事件を含む二年にわたる。その進展もまたドラマチックだ。
――それからどう言うきっかけで彼と会うようになったのか、どうしても思い出せないのですが、よくお茶をごちそうになったり、彼の小説*の原稿の清書を私の知人の女性にたのんであげたりしました。当時彼は大学ノートに原稿を書いていました。
伊藤ふじ子(一九一一~一九八一)は山梨県北巨摩郡の出身で、伊藤力治郎・き志の三女として生まれた。父は当時土建業をいとなんだ。甲府第一高女を卒業し、画家を志望した。一九二八年に上京し、アナーキスト・石川三四郎(一八七六~-一九五六)のもとに身を寄せ帝国芸術院会員・小林萬吾指導の洋画塾 ・同舟舎にかよった。ついで上野・松坂屋の美術課に勤めながら造型美術研究所(後のプロレタリア美術研究所)の研究生になった。また、「新興舞台」というアマチュア劇団で舞台に立つようになった。金子洋文が労農芸術連盟の演劇部門として「文戦劇場」を作り、劇団員を募集すると、「伊藤朱美」と名乗って(高野治郎の記憶―引用者註)応募して採用された。この劇団には、戯曲を書き、演出をやる工藤恒と伊藤貞助がいた。創立間もない同劇場は、芝の飛行館で、金子洋文の時代物と、細田民樹作「狂人と偽狂人」の朗読で旗揚げ公演を行った。旗揚げ公演の後、金子洋文の出身地である秋田県下の農民の生活を描いた公演旅行が続いた。秋田はプロレタリア文学の幕開けを告げた『種蒔く人』発祥の地であった。この縁で、ふじ子は、新宿・淀橋の劇作家・伊藤貞助の家に住むこととなったのだった。
中野・沼袋細胞のふじ子――上田耕一郎の森熊猛への弔辞
二○○四年九月に亡くなった政治漫画家の森熊猛をしのぶ会がその年の十一月開催され、上田耕一郎日本共産党副委員長があいさつし、「中野新報」記者だった上田と森熊との戦後直後の中野・江古田沼袋細胞での出会いなどのエピソードを紹介した。上田と森熊は、地元中野の地域細胞での活動仲間だった。その細胞は、戦後ただちに細胞長大沼渉を頭にその妻・松田解子、森熊猛・ふじ子夫婦、南巌・路子夫婦、岡本文弥、橋浦泰男らそうそうたるメンバーで結成、不破哲三も三度ほど細胞会議に出席したこともあるという。上田は、森熊夫人・かつて小林多喜二の”妻”だった旧姓伊藤ふじ子とも旧知だったのだ。















