「利休形 茶道具の神髄ー利休のデザイン」(世界文化社)を読む。読むというか写真集を眺めていた。

利休は単にお茶の作法を定めただけではなく、自らデザインして新しいお茶の造形を作り出した人物と言える。茶道具で言えば、利休自身がデザインをしたものを職人に作らせており、長次郎の樂茶碗、与次郎に釜、盛阿弥に棗を塗らせたり、更には茶室の間合い、寸法、庭、料理を含めて総合的なプロジューサーである。
まさにその神髄ってのはなんなだろう?
特に茶道具について言えば、幾何学的にも寸法的にも極め尽くされている感がある。 利休は「表面に出過ぎるのは駄目」と言っているが、デザインが合目的性のところにあり、過剰な自己表現がない。 のちの光悦などは自意識が過剰な分だけ情緒過多と言われているが、利休は情緒拒否のところで自立していると言える。お茶という厳格な目的に対して必要かつ十分な形を求めていたと思える。
例えば、
利休箸
両細に箸の先端を削っているだけのことであるが、機能美は絶妙と言える。

水指 真塗手桶
実にスッキリしている。整って無駄のない意匠。形のバランスがいい。とくに把手の手のカーブ、まっすぐではない微妙はカーブ。僅かに曲げることで人の手との触れ合いが変わる。 胴にも胴紐のラインを入れることでリズムが生じる。

水指 木地釣瓶
一見素朴な箱型水指。左右対称のようだが、一方は中心部に凹部を持ち手の下側にくいこむように配慮。木釘ではゆるむことを恐れ敢えて金釘を。更には胴の外開き角度。下から順次広がることで真四角な印象を打ち消している。モダン。

黒塗手燭
なんとも優雅でかつ安定性がある。現代のデザイナーが作ったと言われても不思議ではい。

お茶碗、棗、茶杓と上げればキリがないし、むしろここが利休の真骨頂のところ。私が何か言うには全然早い。
それにしても棗の利休形十六器とかの写真を見ていても飽きがこない感じがする。

ともかく、利休はただただ職人の手を通じて人工的に美しいものを作り出そうとしただけではない。よく知られているようにルソンから伝わった水や香料を入れておく何でもない瓶を茶壺として用いたり、漁師が魚を入れていた魚籠(びく)を花入れにしたりとかしている。極めて発想が斬新であり、大変な演出力を持っていたと言える。


そうしてみてみると、利休の美は単に「削ぎ落としただけの」の機能美ではなくて、何かしら芸術的な感動をも持ち合わせているように思えてならない。

利休は単にお茶の作法を定めただけではなく、自らデザインして新しいお茶の造形を作り出した人物と言える。茶道具で言えば、利休自身がデザインをしたものを職人に作らせており、長次郎の樂茶碗、与次郎に釜、盛阿弥に棗を塗らせたり、更には茶室の間合い、寸法、庭、料理を含めて総合的なプロジューサーである。
まさにその神髄ってのはなんなだろう?
特に茶道具について言えば、幾何学的にも寸法的にも極め尽くされている感がある。 利休は「表面に出過ぎるのは駄目」と言っているが、デザインが合目的性のところにあり、過剰な自己表現がない。 のちの光悦などは自意識が過剰な分だけ情緒過多と言われているが、利休は情緒拒否のところで自立していると言える。お茶という厳格な目的に対して必要かつ十分な形を求めていたと思える。
例えば、
利休箸
両細に箸の先端を削っているだけのことであるが、機能美は絶妙と言える。

水指 真塗手桶
実にスッキリしている。整って無駄のない意匠。形のバランスがいい。とくに把手の手のカーブ、まっすぐではない微妙はカーブ。僅かに曲げることで人の手との触れ合いが変わる。 胴にも胴紐のラインを入れることでリズムが生じる。

水指 木地釣瓶
一見素朴な箱型水指。左右対称のようだが、一方は中心部に凹部を持ち手の下側にくいこむように配慮。木釘ではゆるむことを恐れ敢えて金釘を。更には胴の外開き角度。下から順次広がることで真四角な印象を打ち消している。モダン。

黒塗手燭
なんとも優雅でかつ安定性がある。現代のデザイナーが作ったと言われても不思議ではい。

お茶碗、棗、茶杓と上げればキリがないし、むしろここが利休の真骨頂のところ。私が何か言うには全然早い。
それにしても棗の利休形十六器とかの写真を見ていても飽きがこない感じがする。

ともかく、利休はただただ職人の手を通じて人工的に美しいものを作り出そうとしただけではない。よく知られているようにルソンから伝わった水や香料を入れておく何でもない瓶を茶壺として用いたり、漁師が魚を入れていた魚籠(びく)を花入れにしたりとかしている。極めて発想が斬新であり、大変な演出力を持っていたと言える。


そうしてみてみると、利休の美は単に「削ぎ落としただけの」の機能美ではなくて、何かしら芸術的な感動をも持ち合わせているように思えてならない。
















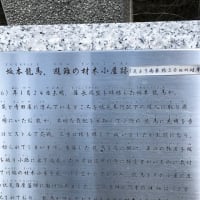



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます