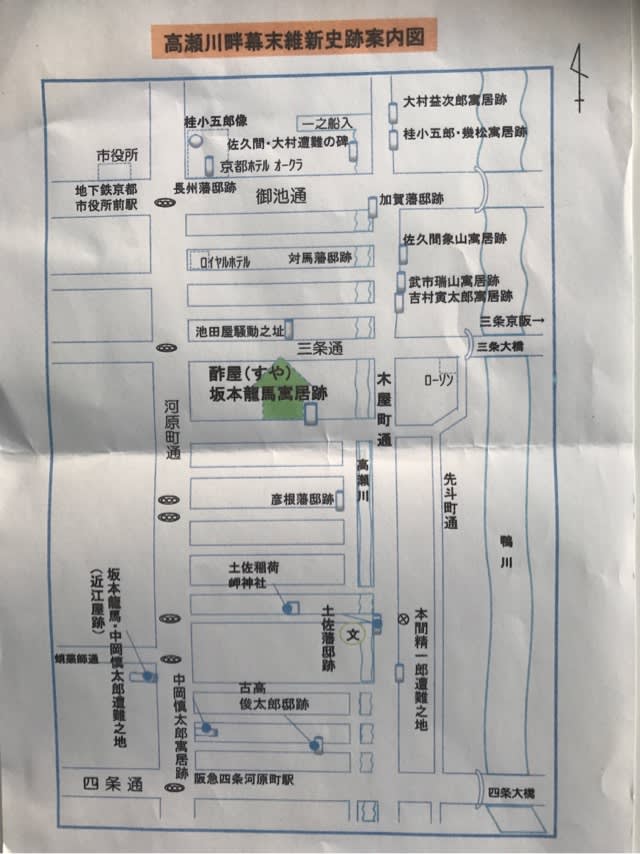スペシャルジャズコンサート@神戸文化ホール
恒例のジャズコン
中高生のバンドからプロのバンドまで。
高校生ともなればそれなりにスウィングの効いた演奏をするのでびっくり。
おっさんもしっかりやらなきゃと反省とまだまだうまくなれるかな?との期待と。
91歳の鍋島さんのビブラフォンが久しぶりに聞けたし、ボーカル たなかりかの「I wish you love 」は染みた。

.
恒例のジャズコン
中高生のバンドからプロのバンドまで。
高校生ともなればそれなりにスウィングの効いた演奏をするのでびっくり。
おっさんもしっかりやらなきゃと反省とまだまだうまくなれるかな?との期待と。
91歳の鍋島さんのビブラフォンが久しぶりに聞けたし、ボーカル たなかりかの「I wish you love 」は染みた。

.