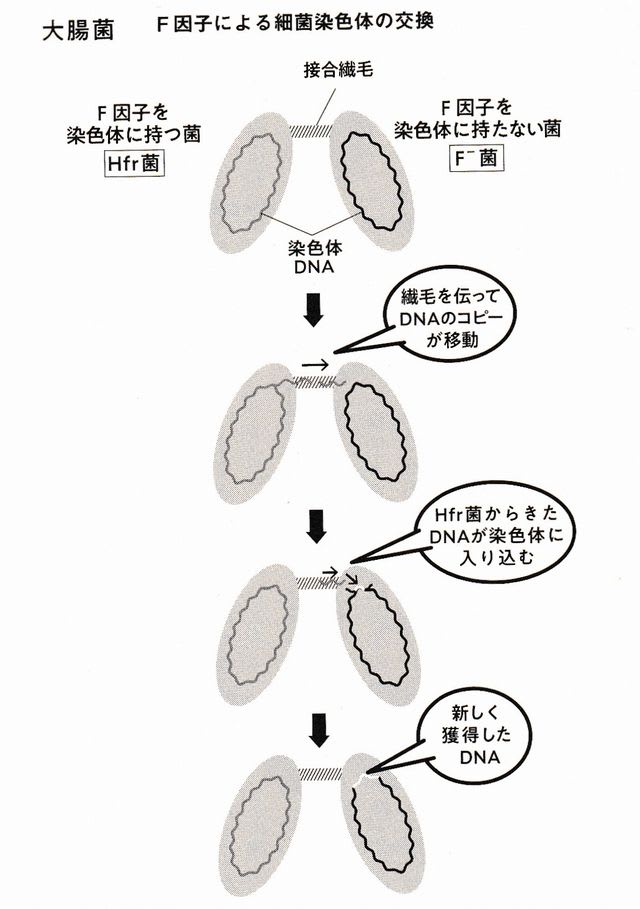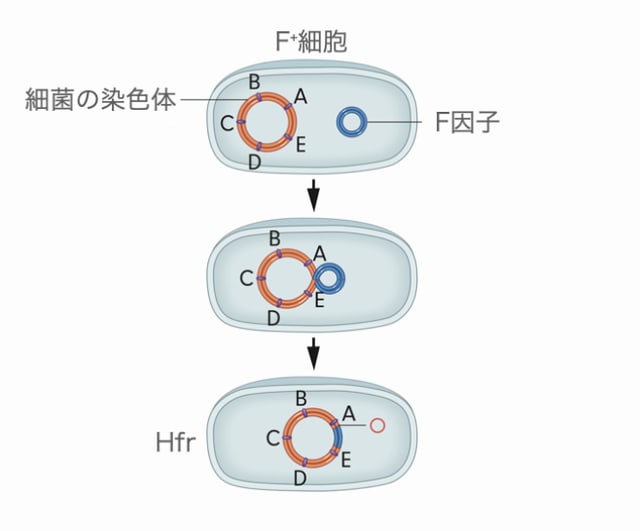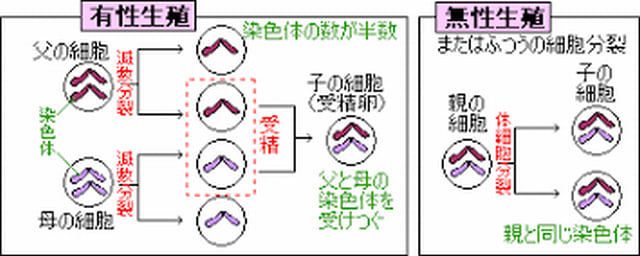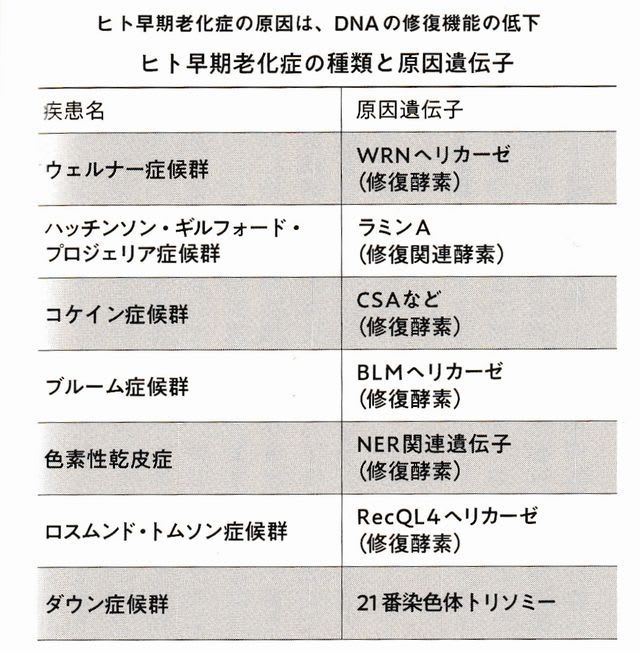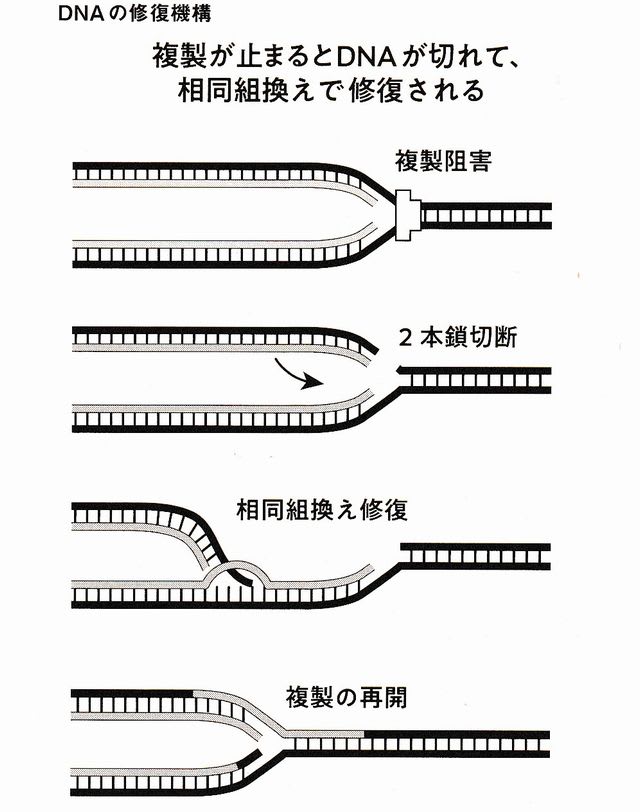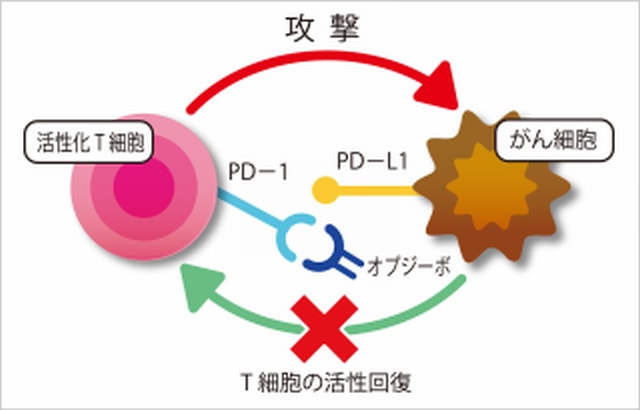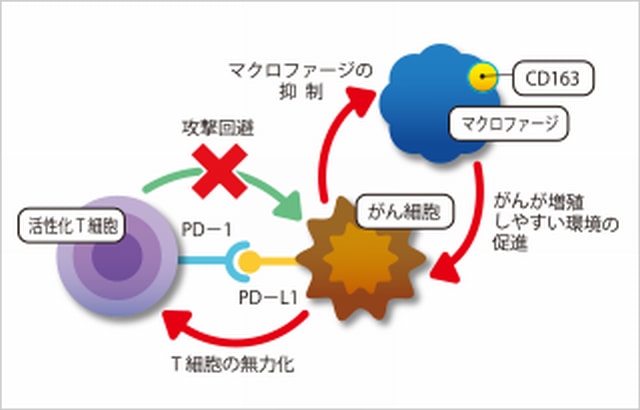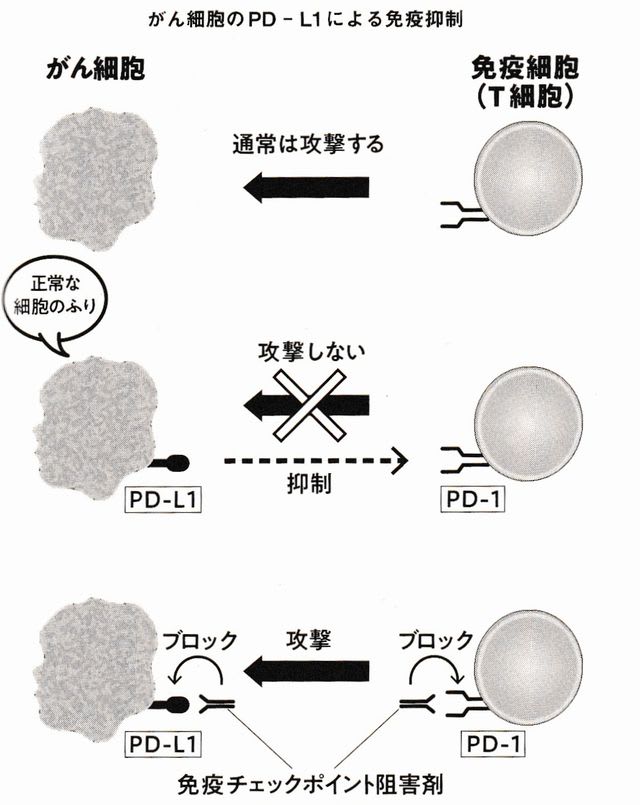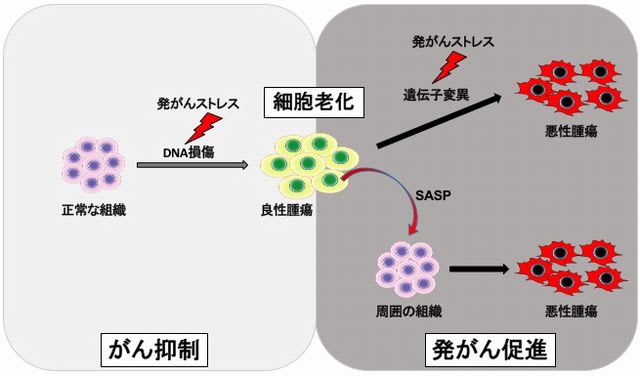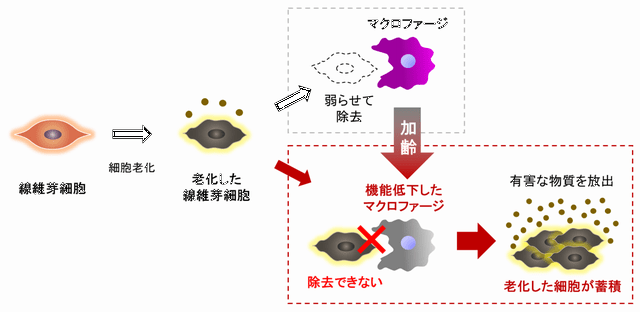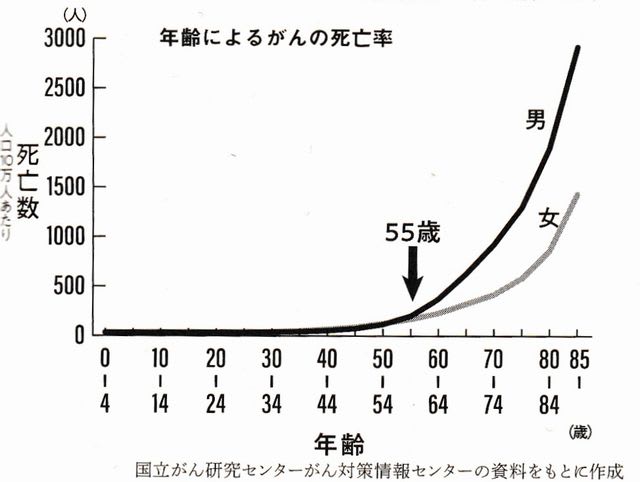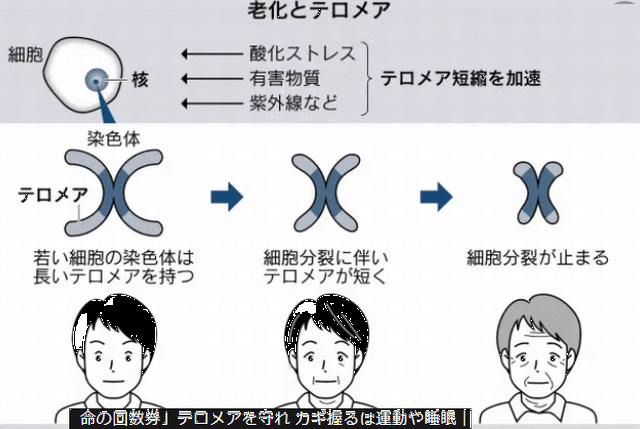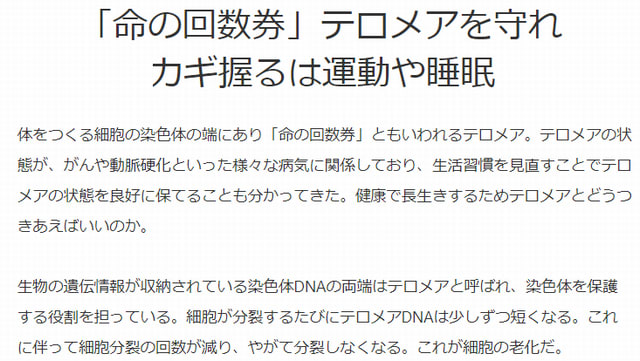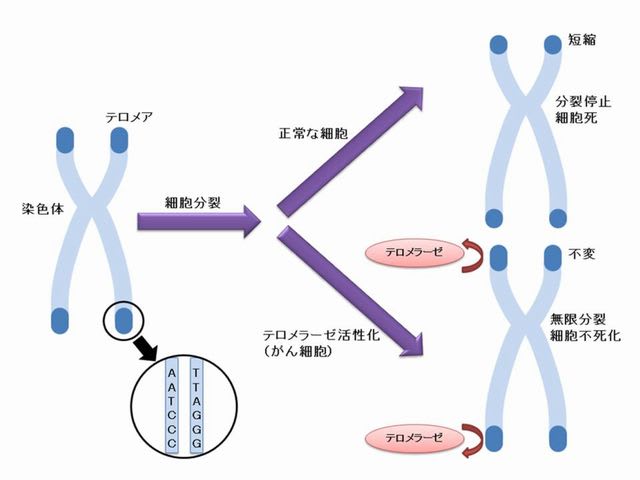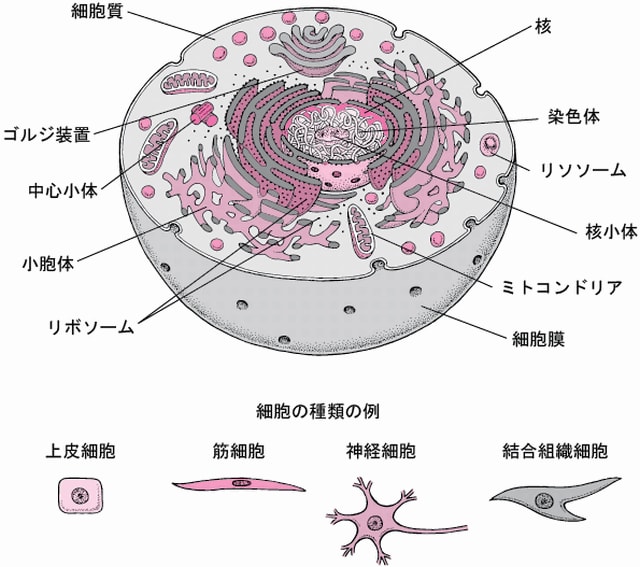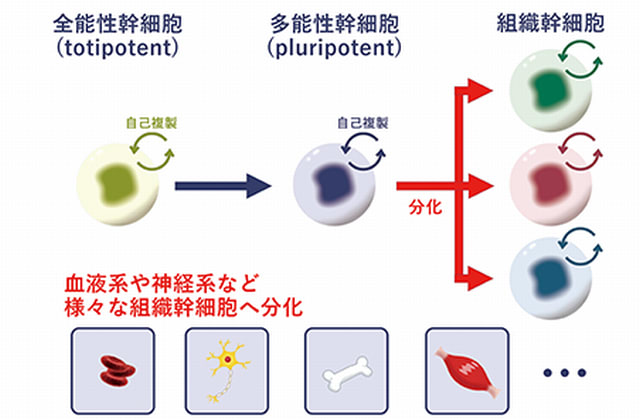🌸生物はなぜ死ぬのか5(リボソームRNA遺伝子)
⛳リボソームRNA遺伝子
☆リボソームとは(復習)
*生物が持つ細胞内でタンパク質を合成する装置
*生物が持つ細胞内でタンパク質を合成する装置
*働きはリボームRNAが担っている
☆寿命に影響がある代表的な遺伝子(お互いに関係があり)
*リボソームRNA遺伝子の安定性に関わる
☆リボソームRNA遺伝子(リボソームRNAを作る遺伝子)
*真核細砲では同じ遺伝子が100コピー以上直列に連なる
*繰り返し返し構造を取っているので、コピー数が多い
*通常の遺伝子に比べて100倍以上の変異が入いる
⛳リボソームRNAのコピーは不安定な領域
(その安定性のメカニズム)
☆変異は正常なリボソームの働きを妨げる
*コピー減少すると、必要量のリボソームRNAを生産できなる
*細胞は正常に生育できない
☆細胞は、進化の過程で
☆細胞は、進化の過程で
*リボソームRNA遺伝子はコピー数を増やす「遺伝子増幅作用」を獲得
☆増幅機構は精巧
*DNAの複製では、細胞が分裂する前に1回だけ起こる
*リボソームRNA遺伝子の増幅、部分的な複製が複数回起こる
☆真核生物は、減ったコピーを元に戻す「遺伝子増幅」能力を獲得し
*リボソームをたくさん作ることが可能になった
*細胞の巨大化に成功し、いろんな機能を持った細胞を
*作れるようになった
☆ヒトの神経細胞は、長いもので1メートル以上のものもある
⛳不安定な遺伝子が寿命を決める
⛳不安定な遺伝子が寿命を決める
☆寿命を変化させる遺伝子
☆複製を止めて組換えを起こす遺伝子FOB1
☆複製を止めて組換えを起こす遺伝子FOB1
*FOB1が壊れると、寿命が60%延長する
☆非コードの転写を抑えて「ずれた」組換えを防ぐSIR2
*SIR2が壊れると寿命が半分に短縮する
☆酵母で見つかった寿命に関わる3つ遺伝子
*GPR1、SIR2、FOB1
⛳FOB1とSIR2の働きが、寿命の決定機構となる詳細
☆ヒトの早期老化症もゲノムの安定性が関わっている
☆ヒトの早期老化症もゲノムの安定性が関わっている
*FOB1が働かないと、複製が止まったりDNAが切れたりしない
*組換えが起こらずリボソームRNA遺伝子は「安定化」する
☆SIR2が壊れると切れたDNAがあつちこつちにずれて
*組換えを起こすため
*リボソームRNA遺伝子のコピー数変動し「不安定化」する
☆リボソームRNA遺伝子以外のゲノム
*複製阻害配列はなく、このような不安定化は起こらない
☆ヒト早期老化症の原因遺伝子
☆ヒト早期老化症の原因遺伝子
*DNAの修復(ゲノムの安定化)に関わる遺伝子です
*ゲノムが不安定化すると、がん化したら困るので
*その前に増殖を止めるべく
*細胞の老化スイツチをオンにして細胞の老化を誘導する
☆リボソームRNA遺伝子
*ゲノムの中でいつもコピー数が減ったり増えたりしている
*もっとも不安定な領域
☆安定性がはじめに悪化して、老化スイツチをオンにしている
☆安定性がはじめに悪化して、老化スイツチをオンにしている
*「メインの老化スイッチ」として働いている
☆酵母のリボソームRNA遺伝子、ゲノム全体の約10%を占める
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『生物はなぜ死ぬ』

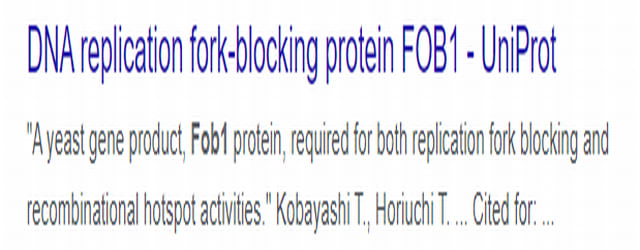

生物はなぜ死ぬのか5(リボソームRNA遺伝子)
(『生物はなぜ死ぬ』記事、ネットより画像引用)