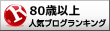10月26日(土)朝 9時雨脚が強くなる中、自宅を出発、伊東市で行なわれた指導者講習会を台風が迎えてくれる。
10月26日(土)朝 9時雨脚が強くなる中、自宅を出発、伊東市で行なわれた指導者講習会を台風が迎えてくれる。
台風の中、宗家の墓詣り後、岳雲荘での稽古に入る、玄制流(玄守会)指導者達。
道場の雑巾掛けからはじまり、後屈立ちの重要性と七減三加の理論から実技、腰内弦のインナーマッスルの神経を目覚めさせるトレーニングを合わせ、後屈立ちからの変化技に繋げる。
指導者の皆さん普段稽古しているので理解が早い、内容を理解した正確な後屈立ちを、行なって頂きたいと思います。
尚、構えで必要な起発起体と運足運身には重要な要因と繋がりを持っている事を、躰道会員の皆さんにも知って頂きたい。
夜は伊東園ホテルで一泊し脇屋夫妻と指導者の皆さん、齋藤夫妻と多田君そして私とで夕食を頂く、その後齋藤夫妻は湯河原に帰宅。
27日(日)伊東市の合宿から朝帰り 2時から行なう壮行会に間に合う。二週間後に行われる第47回全日本躰道選手權大会に向けての、最終稽古と壮行会を埼玉県城西大学武道館で行なった。
県を代表する選手諸君も楽しみながらの稽古で気負いが無い。
最後は、起発起体を備えた構えで、120%の実力を発揮出来るよう理解させ、競技に臨むよう話をする。
2時間余りで全行程を、県事務局長小林 学君の進行で終了、最後は円陣を組み気合を入れて無事閉会。
埼玉県(武州)の近年の目標は、審判員が決める 1 ,2, 3位の評価ではなく。武道(躰道)に対しての姿勢であり理念の実践と考えております。