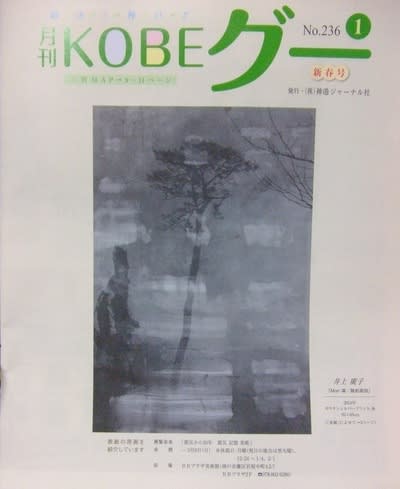戸田勝久さんの個展を見てきました。
JRの元町駅近くに出来た新しい画廊「ギャラリーロイユ」(galerie L'oeil)で16日まで開かれています。
精緻(せいち)このうえない作品です。
そこから深い幻想が立ち上がってくるのです。
題して「六月の夜の神戸の空」。
都市神戸の幻想です。
神戸に生まれ、神戸で育ち、神戸で制作を続けている作家です。
神戸を深く愛している作家です。
神戸を愛するものたちには、一つの共通項があるようです。
たいがいのひとが二つの神戸を生きてます。
一つは、現在ここにあるこの21世紀の現実の神戸です。
そしてもう一つは、かつてここにあって、今はもうないけれど、想像力の中でいきいきと生きている幻想の神戸です。
こういえば、それはどの都市でも同じことではないか、と反論されるかもしれません。
けれど、神戸の場合は他都市とちょっと違うのです。
首都東京の100メートル先を走っていたといわれるかつての神戸(映画評論家の故淀川長治さんの言葉です)は、1945年の空襲で火の中に消えました。
灰燼(かいじん)に帰しました。
しかしそこで奇跡が起こったようです。
アヴァン・ゲールのその神戸はそこで断絶しませんでした。
場所を現実の空間から、一転ひとびとの心の空間へ移したのです。
ひとびとの体にもぐりこんだともいえるでしょう。
もぐりこんだどころか、そこで再び強い成長を始めました。
いま、神戸港を歩きます。
するとひとはここでは大型のコンテナ船が入ってくる今の港と、大小の客船や貨物船でにぎわっていた昔の港を同時に歩くことになるのです。
いま、北野のあたりを歩きます。
するとひとはここでは商業施設が並んでいる今の坂道と、たくさんの西洋館(異人館)が建っていた昔の坂道を歩くことになるのです。
現実の神戸と幻想の神戸。
そして、特筆すべきは、その双方がいっそう美しい姿へと現在進行形で変化を続けているということです。
戸田さんの個展の表題作品「六月の夜の神戸の空」は、そのような幻想の中で成長している神戸の壮麗な景色です。
空には鎌のような大きな月がかかっています。
月の下は深い影に包まれた六甲連山の一角です。
そしてその山の斜面には、今まさに夜へ包まれようとして、たくさんの西洋館が建ち並んでいるのです。
いくつもの尖塔が月へ向かって歌うように伸びてます。
今わたしたちがしばしばたたずんでいる山裾の高台からかつての神戸港へまっすぐに出ていくような、そのような時間を超えた美しい坂も出てきます。
神戸の中心部を山から海へ急な勾配で一気に下るトアロードの景色です。
スエズ以東で最も美しいホテルといわれた「トアホテル」が建っていた坂道です。
稲垣足穂(いながき・たるほ)があの不思議な小説「星を売る店」を幻視した坂道です。
西東三鬼が戦時下を過ごした「国際ホテル」(実はトア・アパートメント・ホテル)、あの抱腹絶倒のホテルがあった坂道です。
それらはむろん、巨大なコンテナ船が入ってくる今の神戸、西洋館が観光装置に変身した今の神戸、ハイセンスな老舗の店が多く絶えてしまった今の神戸にはないものです。
しかし、だからといって、どこにもないというわけではないのです。
ひとびとの心のなかにありありとあるのです。
むしろ、火の中に消えたときからいっそういきいきと生を得て、新しい進化を続けているのです。
おそらくもとあった神戸よりもっと美しい第二の神戸が、現実の神戸と並行して、形成されているのです。
戸田さんはその幻想神戸の司祭です。
わたしたちの中で潜在的に進行している神戸の奇跡に、目の覚めるような色と形を与えます。
わたしたちを、わたしたちの心の底と出合わせます。
戸田さんのこの個展は、もう一つの神戸がこの都市の奥に厳然と存在する、そのみごとな証しにほかなりません。
ギャラリーロイユは
http://g-loeil.com/