先日ストレングスについて綴ったが、多くの皆さんからコメントを頂いた。特に、千葉のOさんからは、ストレングスに関する大学院の授業の後で、教育出身の学生が、教育学では当たり前のことであるといった意見に、学部から社会福祉であった自分が、ハッとしたコメントを頂いた。具体的には、以下の通りである。
「ストレングスと言えば,印象に残っている大学院授業での1コマがありました.
ストレングスを学んだ授業の終わりに,各自がコメントを述べた場面です.教育学部を卒業して大学院に来たある院生が,「教育の分野では,生徒の長所(ストレングス)を見つけて伸ばすという考えは普通のことであるのに,社会福祉の分野では,ストレングスに焦点を当てるという考えが比較的新しいと知って,意外な感じを受けた」という旨のコメントをされた場面です.
おそらく,教育は「伸ばす」,社会福祉援助は「足りていない(貧困等)ところを充足する」といった歴史的な出発点の違いがあるからかと思っています.
おっしゃる通りで、アメリカの教科書でも、ストレングスが教育学から引用している部分が多いことが書かれています。
私も娘が子どもを出産するに当たって、当時育児書としてアメリカや日本を含めた世界22か国でも愛読されているベストセラーであるドロッシー・ドーノルドとレイチャル・ハリス著『子ども育つ魔法の言葉』(PHP文庫)をプレゼントしたことがある。この本もストレングスを活用することが子育てで重要であることをいっている。「見つめてあげれば、子どもは頑張り屋になる」「認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる」といったことである。
また、 こうした視点で支援をすれば、受容や共感ということは実感として感じられることであるが、これを理論的に実証してみたいものである。但し、アメリカの論文でも、その実証は量的な調査というよりは、事例分析といった質的調査がほとんどであり、日本でもまずはそうした質的調査を積み重ねが大切である。
こうしたことを考えると、社会福祉は「問題解決型」志向が強かったが、「成長・発展型」志向を加味していこうとしていると思える。
「ストレングスと言えば,印象に残っている大学院授業での1コマがありました.
ストレングスを学んだ授業の終わりに,各自がコメントを述べた場面です.教育学部を卒業して大学院に来たある院生が,「教育の分野では,生徒の長所(ストレングス)を見つけて伸ばすという考えは普通のことであるのに,社会福祉の分野では,ストレングスに焦点を当てるという考えが比較的新しいと知って,意外な感じを受けた」という旨のコメントをされた場面です.
おそらく,教育は「伸ばす」,社会福祉援助は「足りていない(貧困等)ところを充足する」といった歴史的な出発点の違いがあるからかと思っています.
おっしゃる通りで、アメリカの教科書でも、ストレングスが教育学から引用している部分が多いことが書かれています。
私も娘が子どもを出産するに当たって、当時育児書としてアメリカや日本を含めた世界22か国でも愛読されているベストセラーであるドロッシー・ドーノルドとレイチャル・ハリス著『子ども育つ魔法の言葉』(PHP文庫)をプレゼントしたことがある。この本もストレングスを活用することが子育てで重要であることをいっている。「見つめてあげれば、子どもは頑張り屋になる」「認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる」といったことである。
また、 こうした視点で支援をすれば、受容や共感ということは実感として感じられることであるが、これを理論的に実証してみたいものである。但し、アメリカの論文でも、その実証は量的な調査というよりは、事例分析といった質的調査がほとんどであり、日本でもまずはそうした質的調査を積み重ねが大切である。
こうしたことを考えると、社会福祉は「問題解決型」志向が強かったが、「成長・発展型」志向を加味していこうとしていると思える。










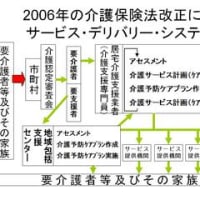
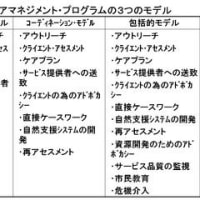
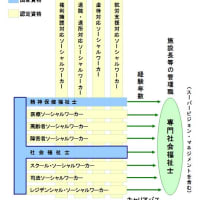


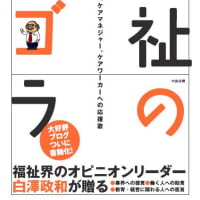
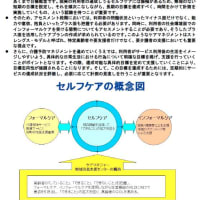
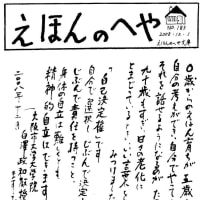
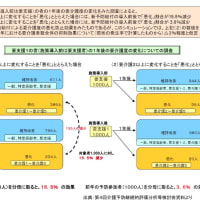

その通りだと思います。くわえて、現代福祉はその歴史が短く、教育や心理学、社会学から多くの理論・技法を取り入れてはいますが、まだまだひとつの「学」として確立されていないと思います。しかし、間違いなく必要性の高い領域になるので、発展させていかなければならないと痛感しています。